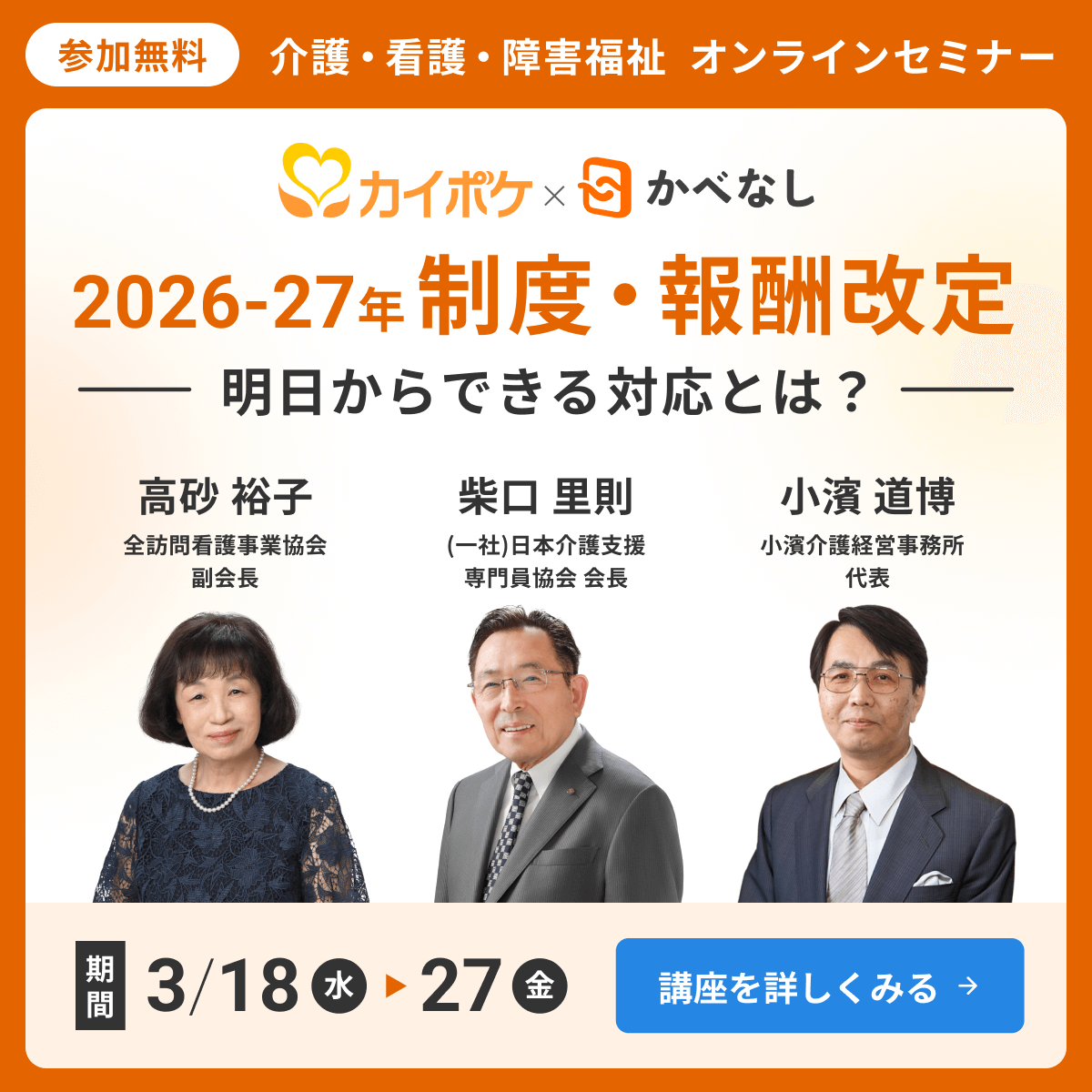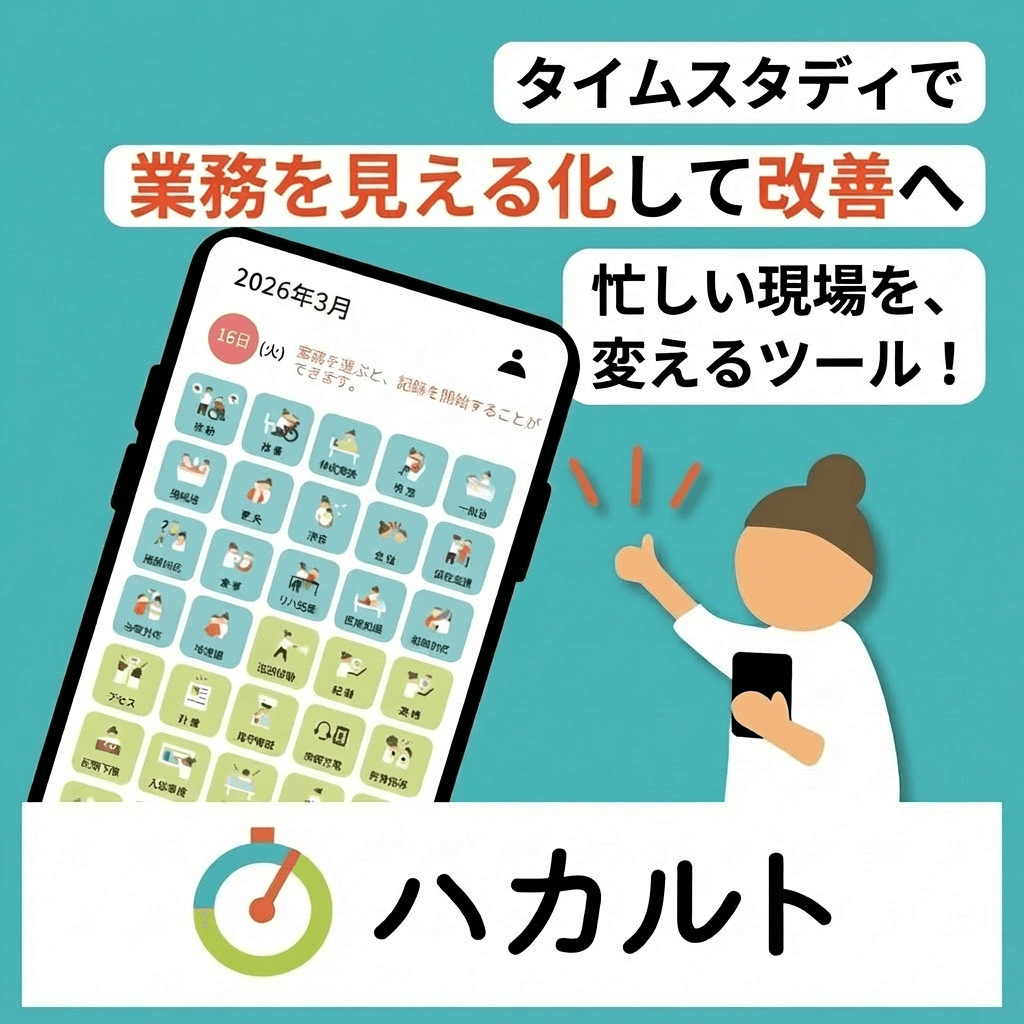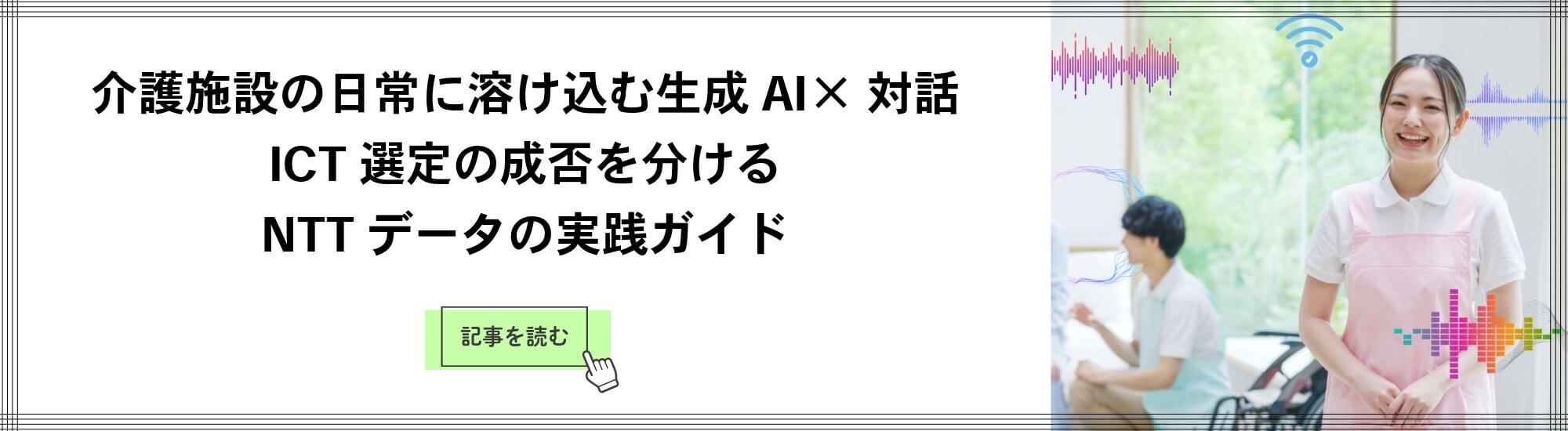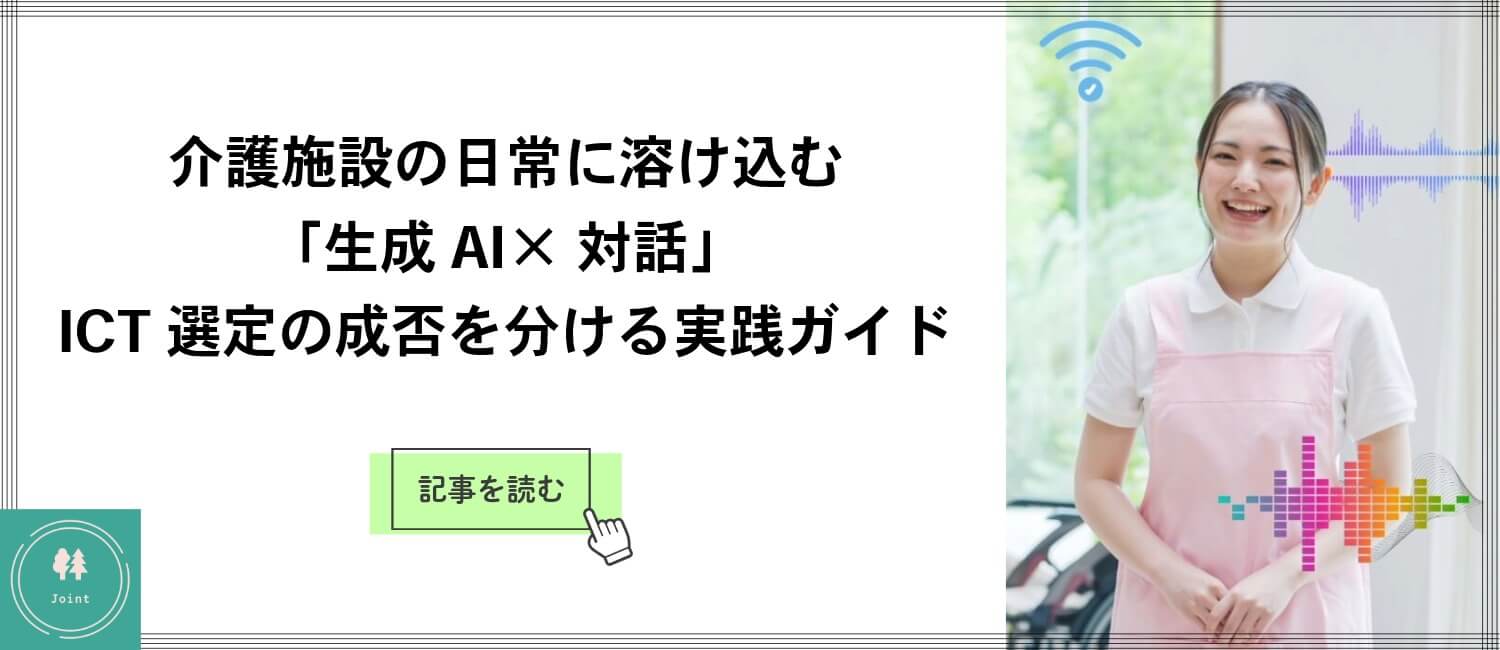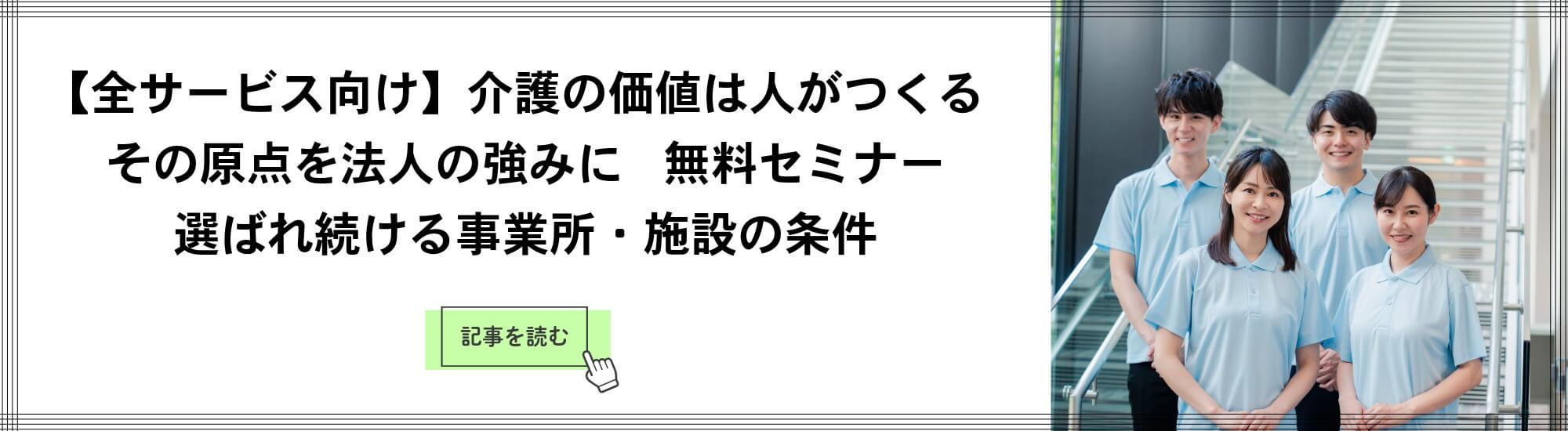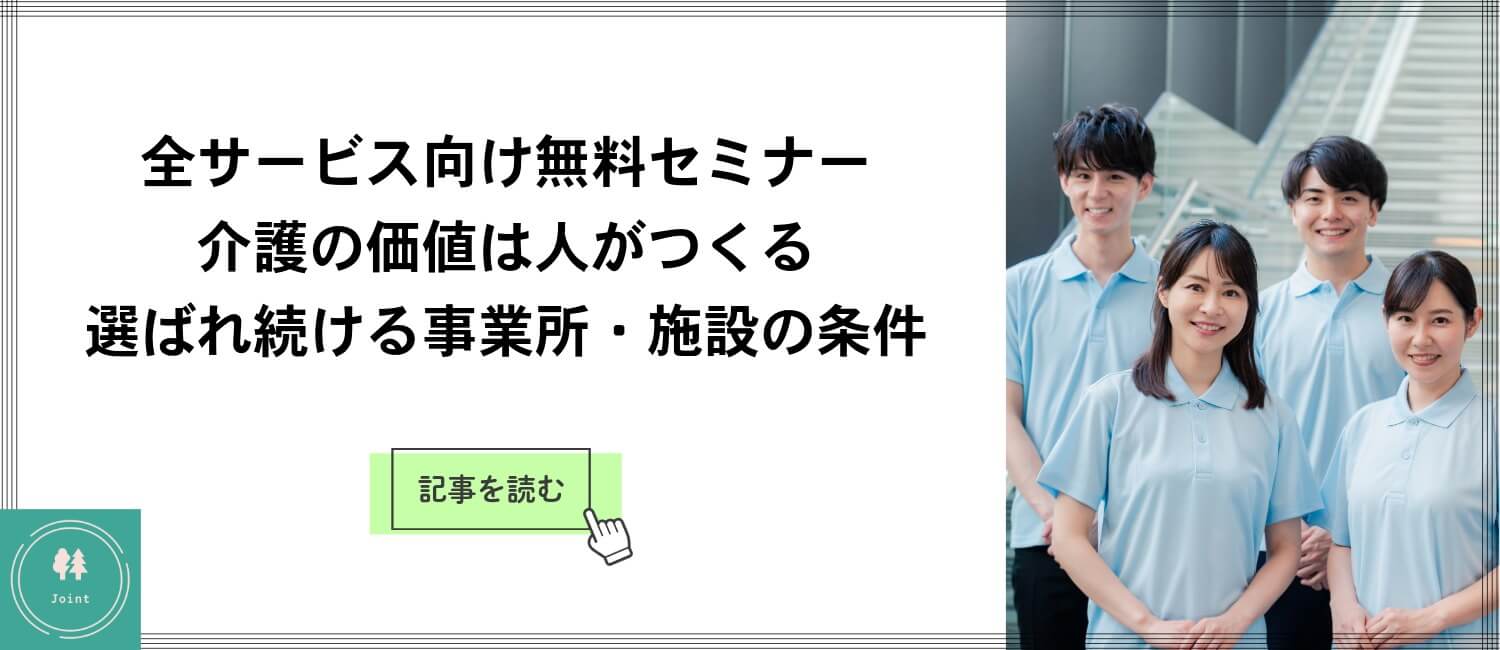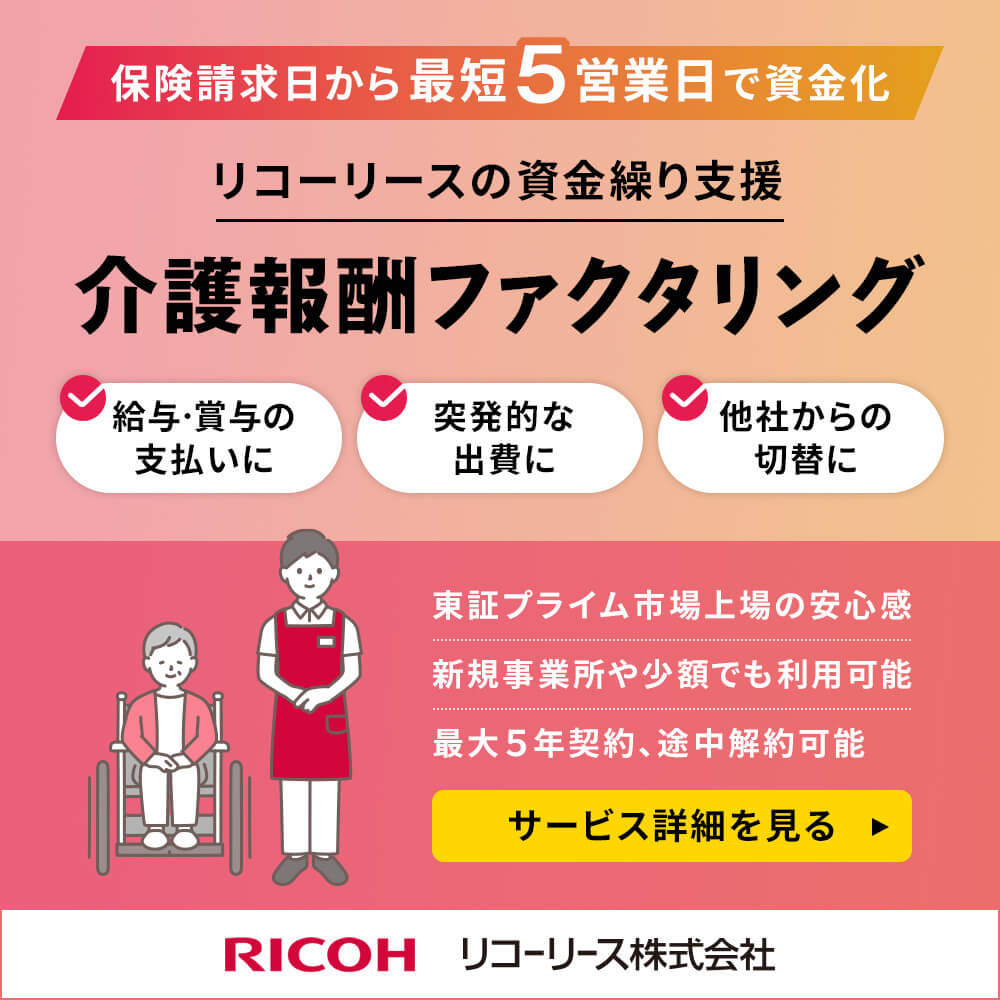若手確保へ本気の伴走 多様な人材と向き合う介護現場発の人間力 採用・定着で確かな成果


「本気で取り組めばきっと人は来てくれると思ったんです」。
そう語るのは、社会福祉法人泉陽会(東京都)で人材対策室を率いる平本穣さん。5年前、自らの提案で新設した同室は、今や法人の人材確保を牽引する存在だ。
豊富な資金力や広報力を武器に、民間大手が人材確保を優位に進める時代。熾烈な採用競争の最前線で、社会福祉法人が劣勢に立たされるケースも少なくないなか、どう難局を打開しようとしているのか。平本さんに話を聞いた。【Joint編集部】
◆「人を採る」に専念を直談判
きっかけは、新卒採用の難しさへの強い危機感だった。法人全体の年齢構成が高まりつつあるなか、若手人材をどう確保するかは喫緊の課題。現場の声と自らの問題意識を重ね合わせ、「自分が人を採る。専念させてほしい」と当時の上司に直談判した。
「高度な採用スキルがあったわけではありません。でも、やってみれば道は拓けるという直感がありました」。最初はデイサービスの所長職と兼務で動き出し、翌年からは専任に。現場経験を生かした地道なアプローチが本格的に始まった。
当初から注力したのは地方での採用活動だ。法人の知名度では大手に敵わない。そこで都内での競争にこだわらず、自ら地方へ足を運んで福祉系大学や専門学校の教員に直接アプローチ。業界で培った人脈をたどって紹介を受け、授業やゼミの場で法人の魅力を伝える機会を設けてもらってきた。
「就職先の選択肢のひとつとして見てもらえれば、まずは十分だと思っています。大切なのは、丁寧に顔を合わせて話すこと。関心を持ってくれる人は必ず出てきます」

◆ 上京後も丁寧に寄り添う
採用の成果も着実に現れている。たとえば愛媛県の専門学校では、主任教員に思いを伝えたところ、東京への就職を希望していた学生に声をかけてもらい、リモートで説明・選考を実施。結果として採用につながり、今も現場で戦力として活躍している。
平本さんは、採用後の「伴走支援」にも余念がない。地方から上京する場合、4年間の家賃補助を用意。引っ越しの初期費用も法人が支援している。住まいの確保も平本さんら人材対策室がサポート。本人の希望や予算を聞いて反映するほか、一緒に内見にも同行する。
「東京で暮らし始められる、ということを1つの武器にしています。知らない土地での暮らしは誰でも不安なもの。物件の立地や設備まで一緒に確認しながら、納得して新生活を始められるようにしています」
◆ 学びと仕事、生活をトータル支援
今年度からは外国人材の確保でも新たな一歩を踏み出した。十文字学園女子大学(埼玉県)と連携し、外国人留学生を対象とした長期育成プログラムをスタート。4年間の学費を泉陽会が共同で負担し、在学中は介護現場でのアルバイト勤務も受け入れている。
「将来的に現場をリードできる人材を育てていくことが目的です。バイトで働きながら学校で学び、卒業後にはうちの職員として就職する。生活継続の見通しを立てられることが、外国人の学生にとって安心材料になっていると思います」
住まいの手配、生活支援も法人が担う。日用品の買い出しや地域の案内なども含め、生活立ち上げの不安を和らげるサポートを柔軟に提供している。
◆ 法人の枠を越えた挑戦
他法人との連携の輪も広げている。平本さんは現在、同じ志を持つ10の法人と共に人材確保の協働チームを結成。合同で就職フェアを開催しているほか、若手職員のネットワーク形成にも取り組んでいる。
「コストを抑えながら、法人の枠を超えて介護現場の魅力を発信したいという思いで始めました」
就職フェアでは介護食の試食体験や講演会も企画。若手職員が福祉の魅力や課題を率直に語り合う場も設けている。法人の垣根を越えた交流が、業界全体の魅力や働き続けるモチベーションの向上につながるという。
「業界内の情報交換は、自分の職場を理解するうえでもやっぱり重要。“友達の友達は友達”という気持ちで、横のつながりを大事にしています」

人材確保のハードルが年々高まる中でも、平本さんは「本気で取り組めば必ず道は開ける」と前を向く。
「仕事を探している人は皆、多かれ少なかれ不安を抱えています。だからこそ細やかに寄り添い、安定するまで一緒に歩む。そこに本気で向き合えれば、必ず信頼が生まれて定着につながります。この業界に人を呼び込む責任を、一人ひとりが自覚して行動していくことが大切だと思っています」
すべては現場の問題意識から始まった。それが今、確かな手応えとともに人をつなぐ力を生んでいる。