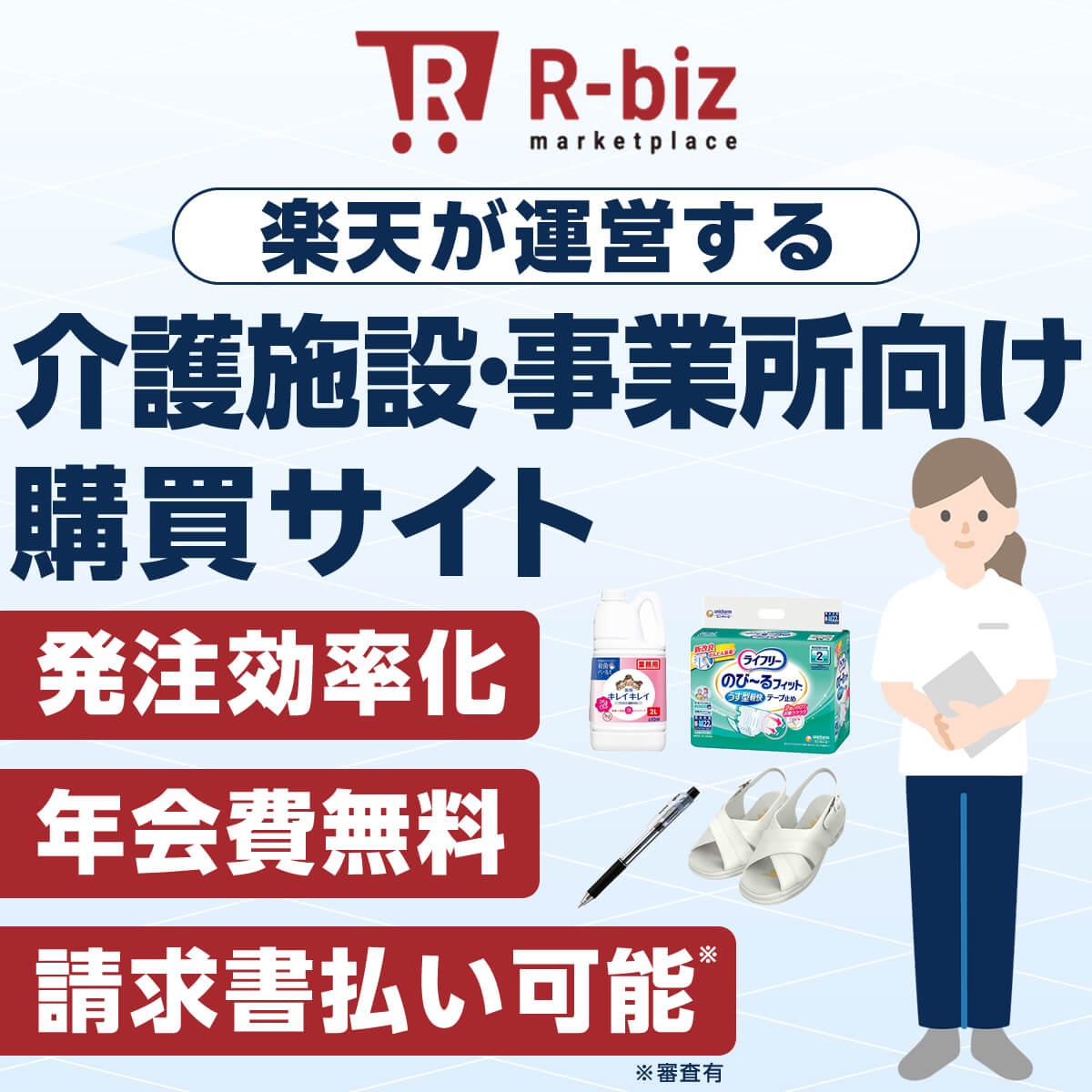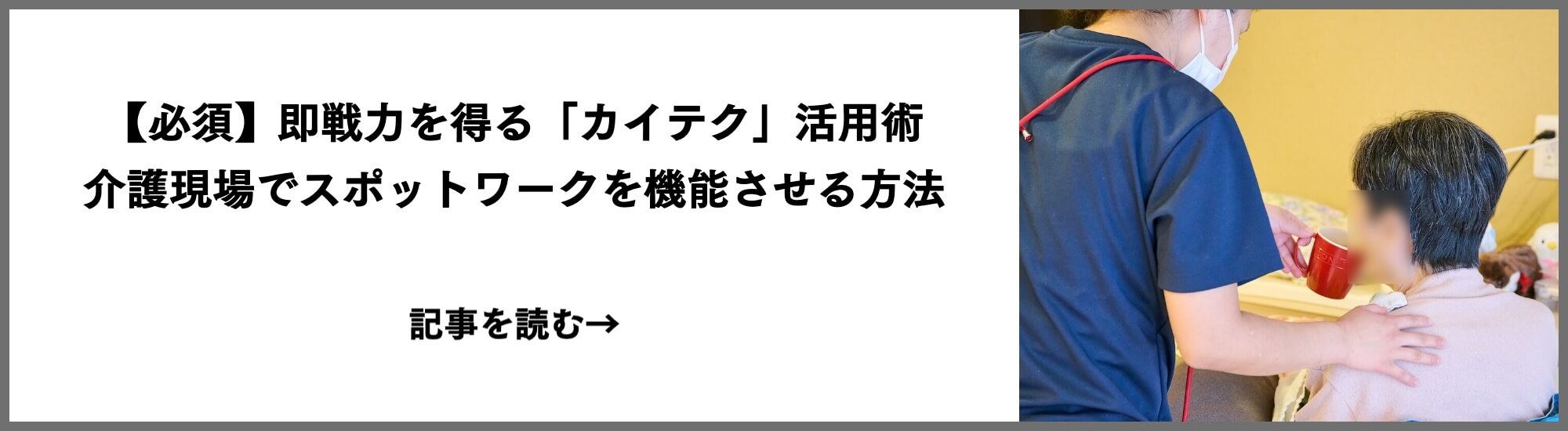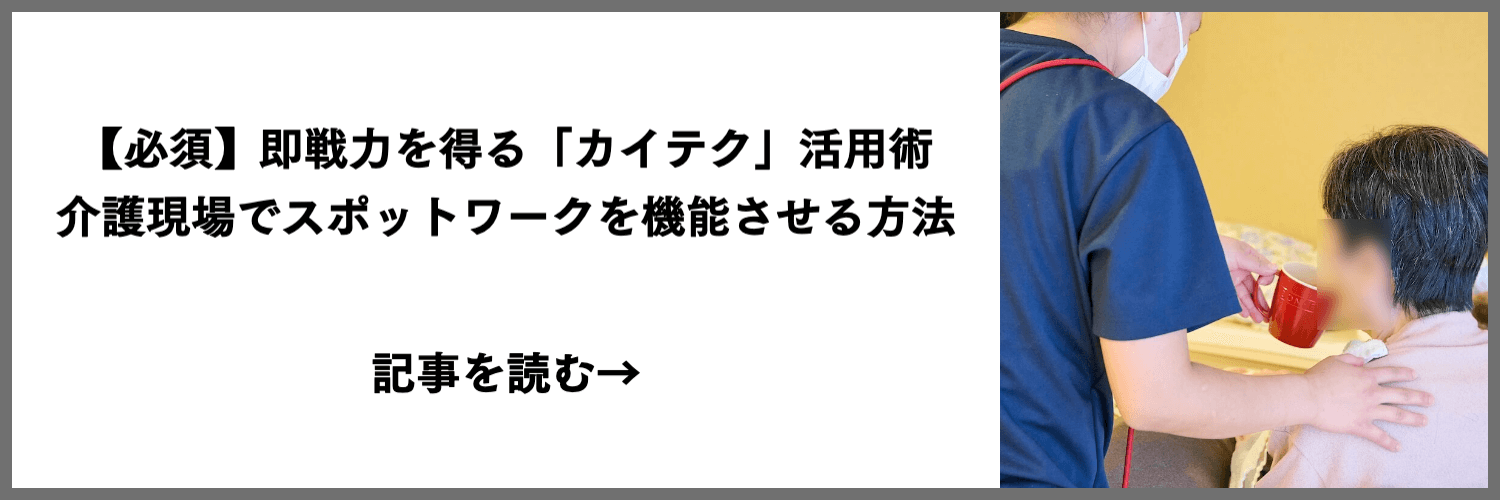ケアマネ協会、カスハラは「対策に決め手がない。事業所だけの対応では厳しい」
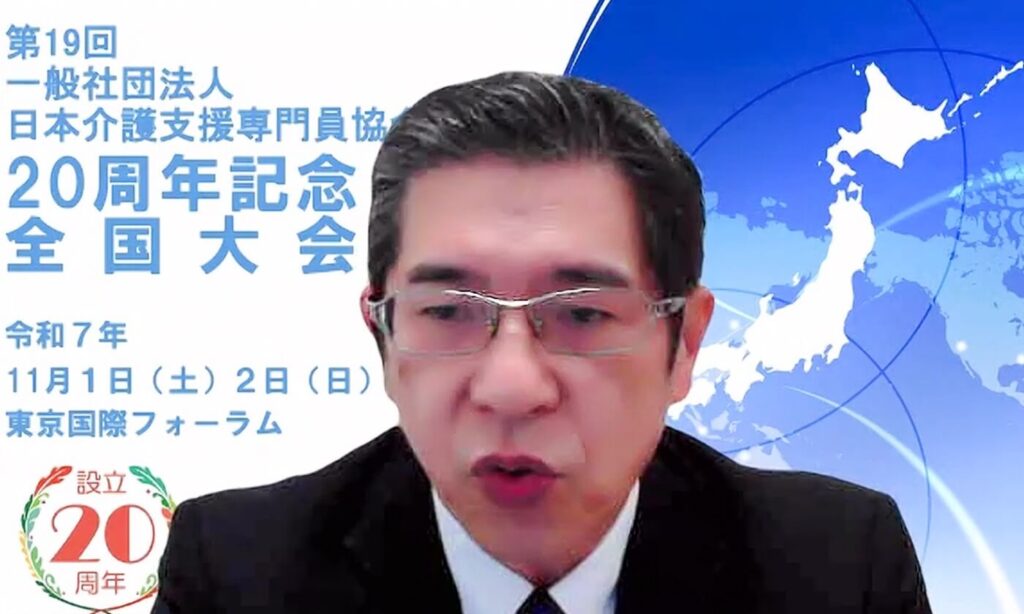

日本介護支援専門員協会は23日に記者会見をオンラインで開き、ケアマネジャーへのカスタマーハラスメントに関する調査の最新の結果を報告した。【Joint編集部】
過去1年間にカスハラを受けたケアマネジャーは3割を超えている。カスハラを誰かに相談したケアマネジャーのうち、「解決した」と答えた割合が23.2%にとどまることも明らかになった。
協会はこうした状況を踏まえ、「今は対策にこれといった決め手がない」と説明。「現在の様々な対策を、より実効性の高いものにしていくことが重要」と提言した。
協会の七種秀樹副会長は会見で、「個々の事業所の取り組みだけでカスハラを解決するのは現実的に厳しい」と問題を提起。「事業所だけに対応を任せるのではなく、国や自治体、地域などの連携で対応していける仕組みが必要。現場の介護支援専門員がもっと働きやすい環境を作るために、厚生労働省ともしっかり協議していきたい」と述べた。
この調査は、協会のシンクタンク部門が昨年11月から12月にかけて行ったもの。およそ2000人の会員が対象で、1293人から有効な回答を得た。
それによると、カスハラを受けたケアマネジャーは管理者や上司、同僚に相談することが多く、地域包括支援センターに相談するケースも一定数あった。一方で「解決した」は2割強にとどまり、「解決までは至らないが改善した」が約3割、「解決しなかった」が約2割となっていた(*)。
* 残りは無回答や「その後を把握していない」など。
協会の七種副会長は会見で、「まずは誰かに相談できる環境をしっかり整えることが大切。加えて、相談を受けた人が解決に向けて動ける仕組みが非常に重要ではないか」との見解を示した。
事前の十分な説明を前提として、やむを得ない措置として契約を解除することの効果については、「ケースによっては1つの方法になる。カスハラの抑止力にはなる」と説明。ただ現場の判断は難しく、仮に契約を解除したとしても迷惑行為が続く場合もあるとした(*)。
* 追記:4月23日16時39分
会見の最後は、改めて次のように強調して締めくくった。
「カスハラはごく一部。多くのご利用者・ご家族は、介護支援専門員の立場を理解してくださっている。そうした皆さまを支えることに、我々は日々大きなやりがいを感じている。これからもご利用者・ご家族との良好な関係づくりに注力していきたい」