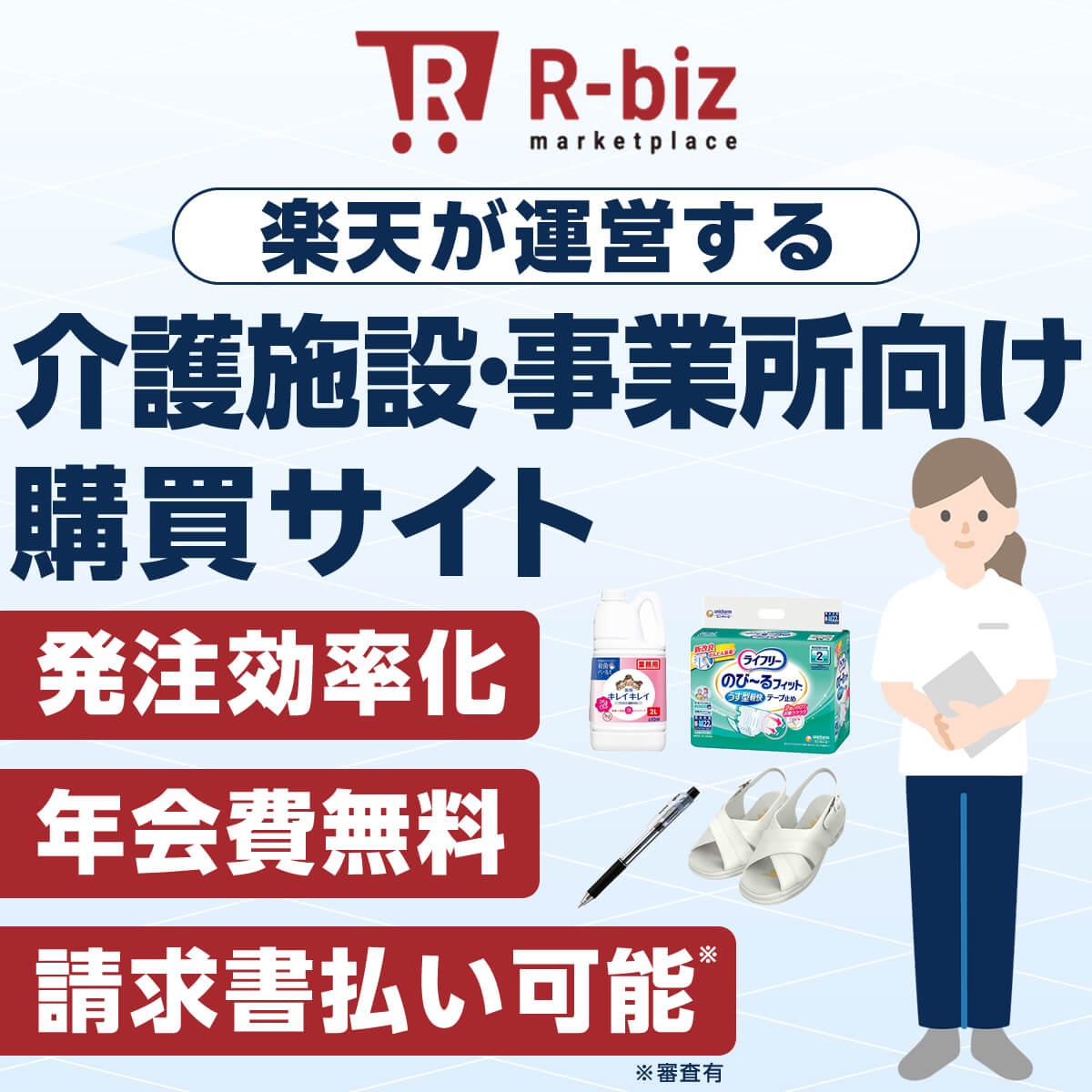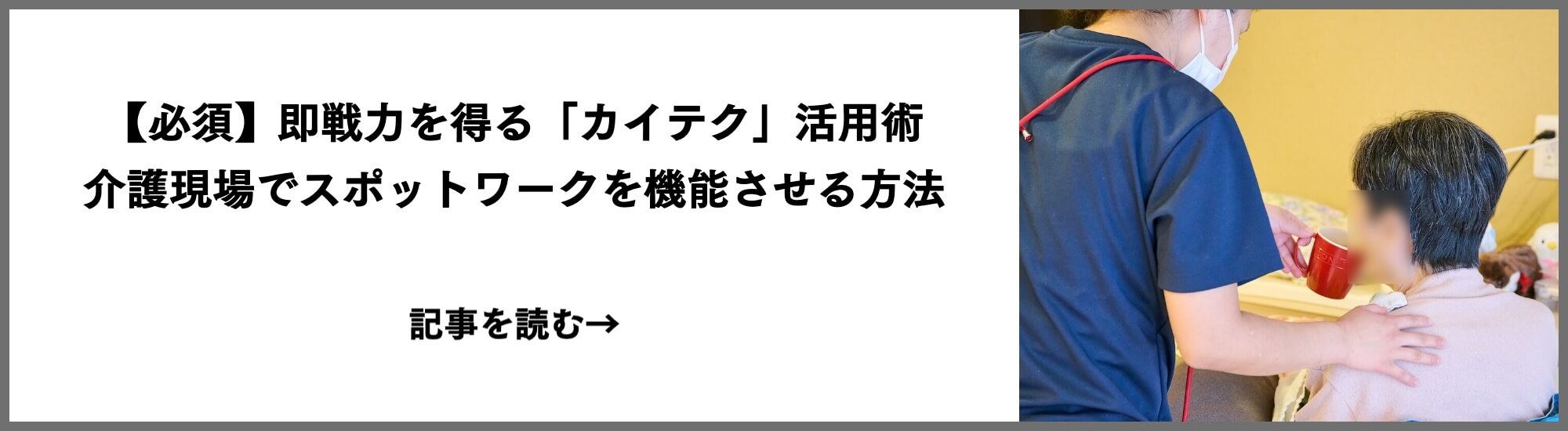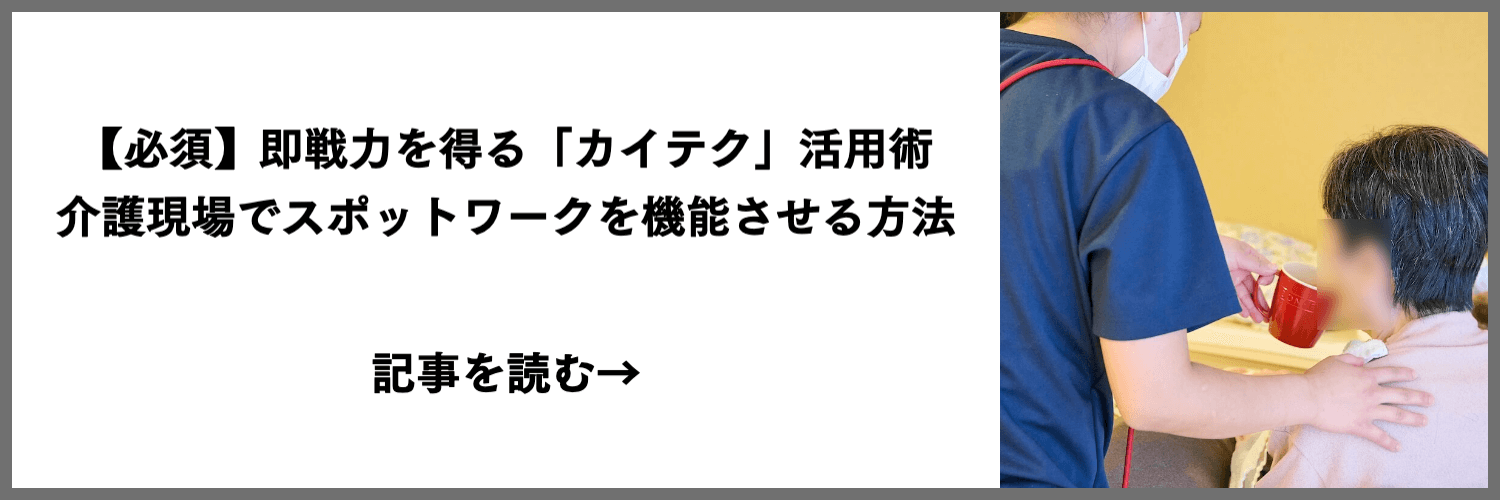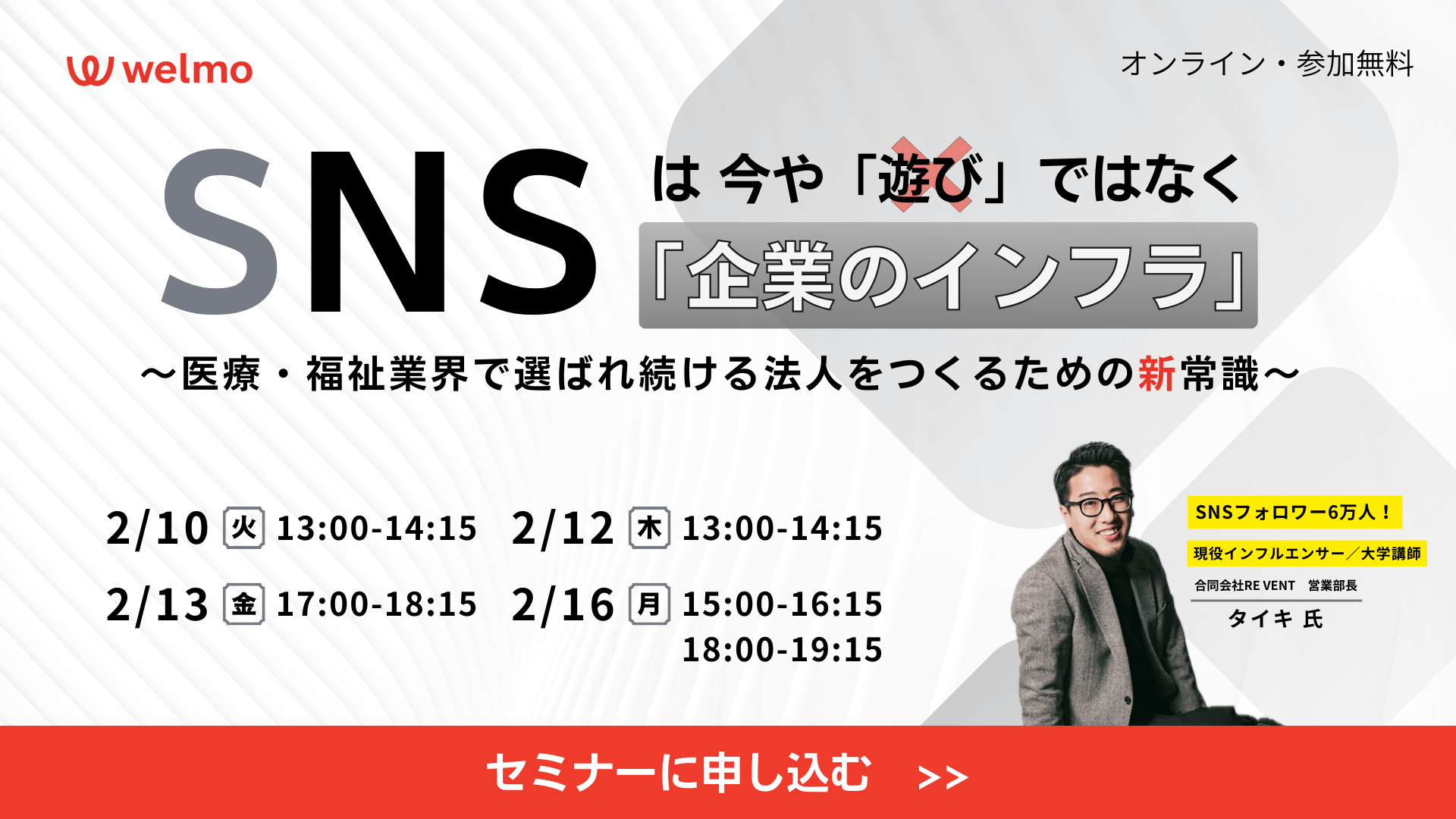ケアプラン作成の職種拡大を 人材難の自治体が提案 専門職の柔軟なシェアも


今後の介護サービス提供体制のあり方が、28日に開催された政府の「規制改革推進会議」のワーキング・グループで取り上げられた。【Joint編集部】
中山間地域や離島などの自治体の関係者が出席し、介護サービスを維持していくために必要な施策を提案した。
介護ニーズの縮小や人材確保の難しさなどを背景として、事業所・施設の人員配置基準の弾力化を求める声が続出。ケアプランを作成できる専門職を拡大したり、人材の複数現場での兼務・シェアを柔軟に認めたりするなど、思い切った手を打つべきと促す意見が相次いだ。
厚生労働省は4月10日に公表した検討会の報告書に、中山間地域を中心として人員配置基準の弾力化を検討していく方針を盛り込んでいる。体制の効率化と介護サービスの質の確保をバランスさせることが大きな課題。今後、具体策をめぐる議論がさらに活発化していきそうだ。
「介護職員だけでなく、あらゆる職種の確保が困難になってきている」
こう危機感をあらわにしたのは、ワーキング・グループのヒアリングに参加した長崎県五島市の担当者だ。「人材確保の取り組みと並行して、少ない人数でも必要な支援を行っていくための仕組みも考えていく必要がある」と呼びかけた。
あわせて、「ケアマネジャー離れが加速している」とも説明。更新研修の負担が重かったり、独居の高齢者などから求められる役割が増大したりして、資格を持っている人が他の職種を選ぶ傾向にあると報告した。
五島市の担当者はそのうえで、介護予防支援のルールにも触れつつケアプランを作成できる専門職の拡大を提案。ケアマネ資格の更新制度の見直し、人材の確保が困難な地域での簡易なケアプランの導入、訪問介護の移動時間・待機時間を考慮した加算の創設、介護施設のサテライト化の基準緩和なども要請した。
このほか、同じくヒアリングに参加した島根県邑南町の担当者は、オンラインを適切に活用しつつ、通所介護の看護師ら専門職が事業所を兼務できるようにすることを提案。例えば介護施設と併設の通所介護などで、専門職のシェアを柔軟に認めていく案も提示した。