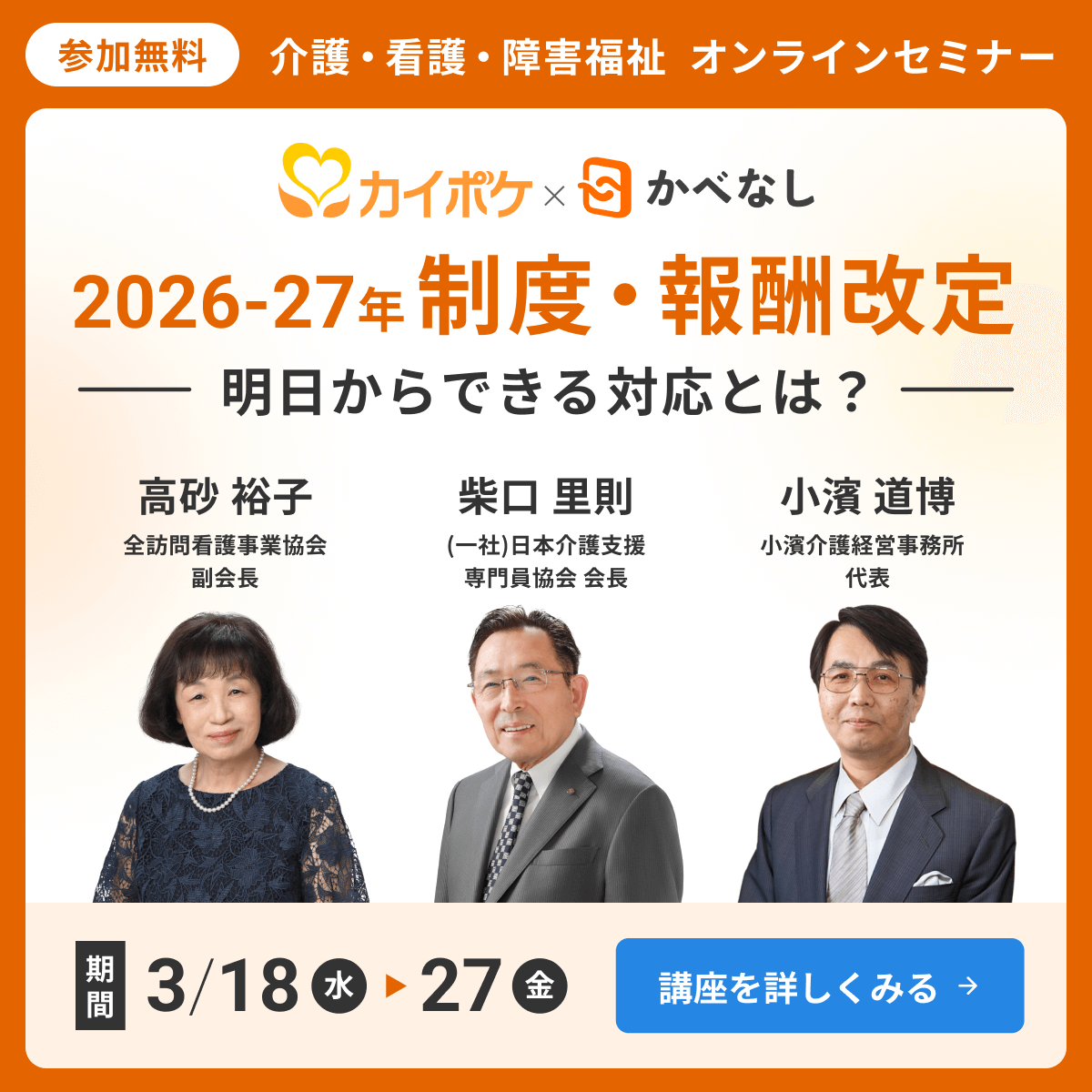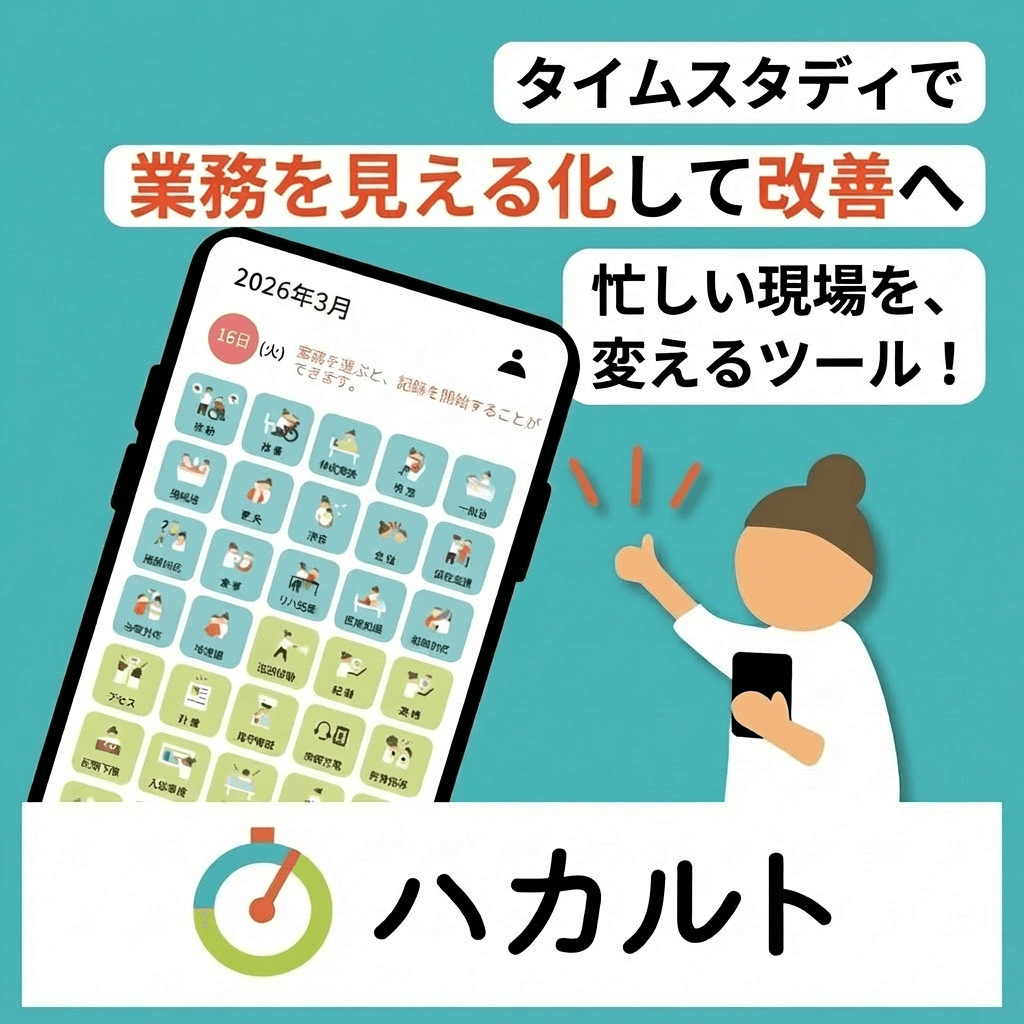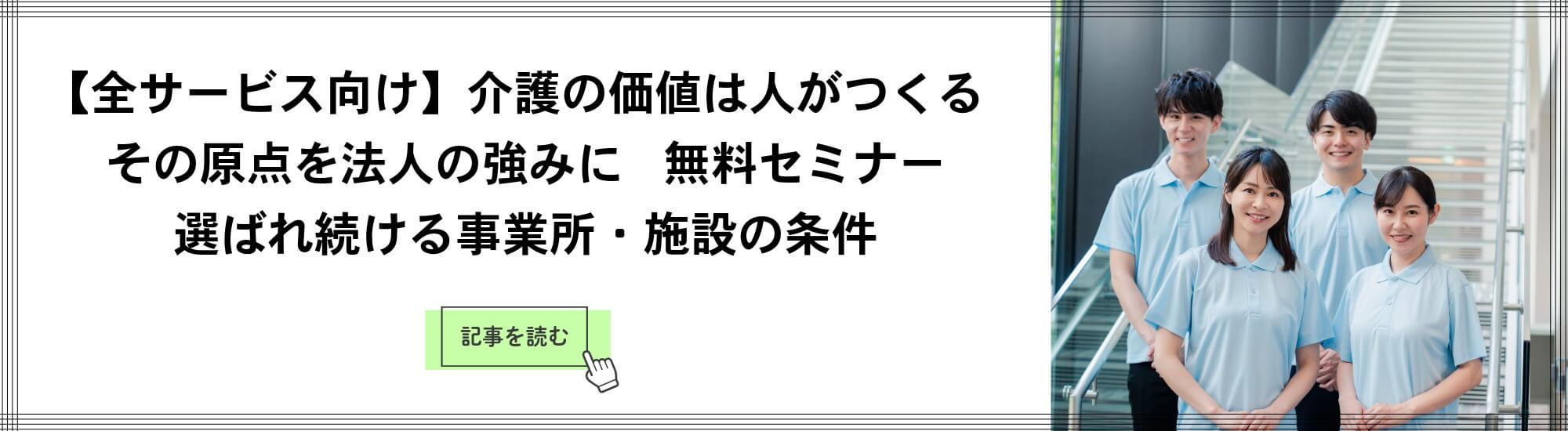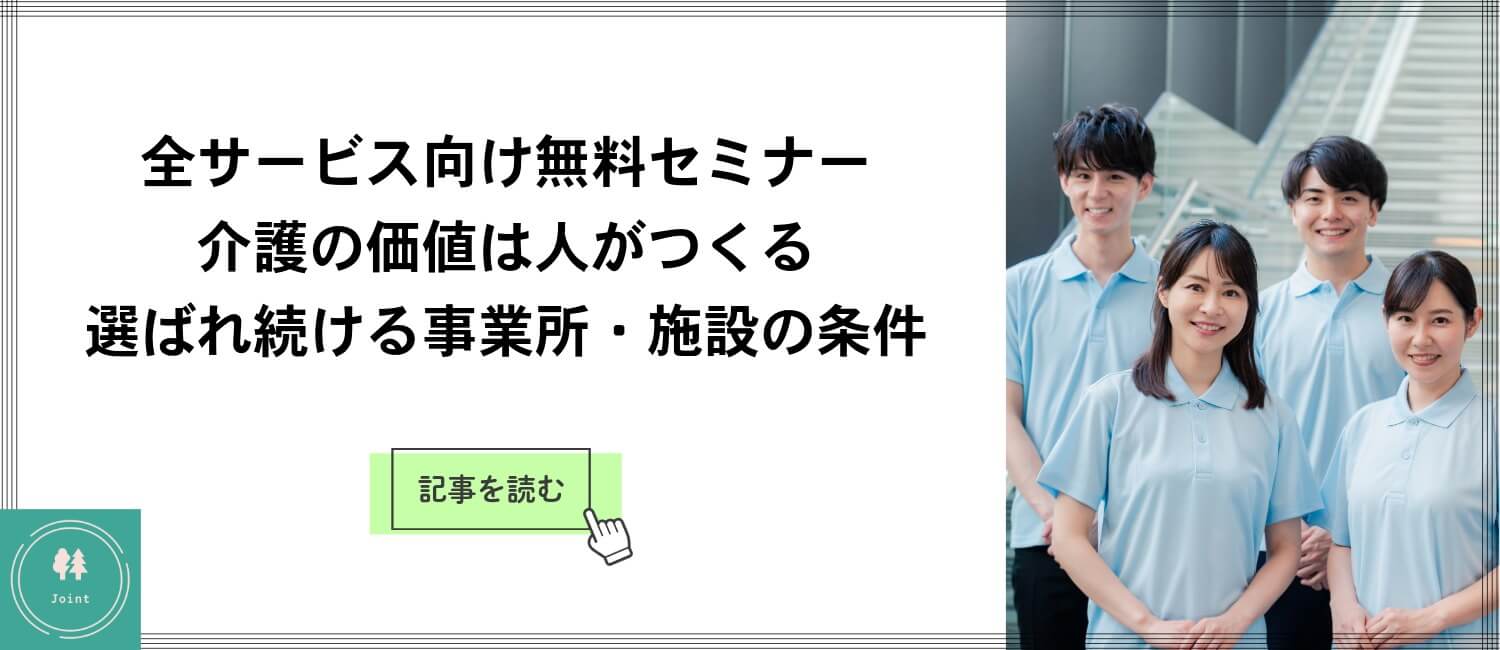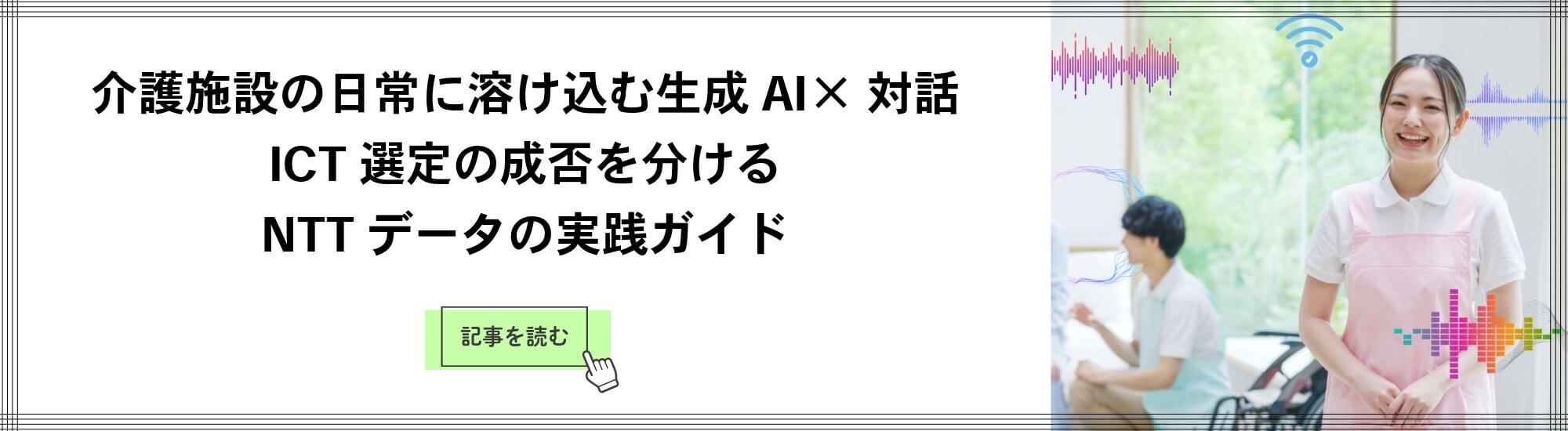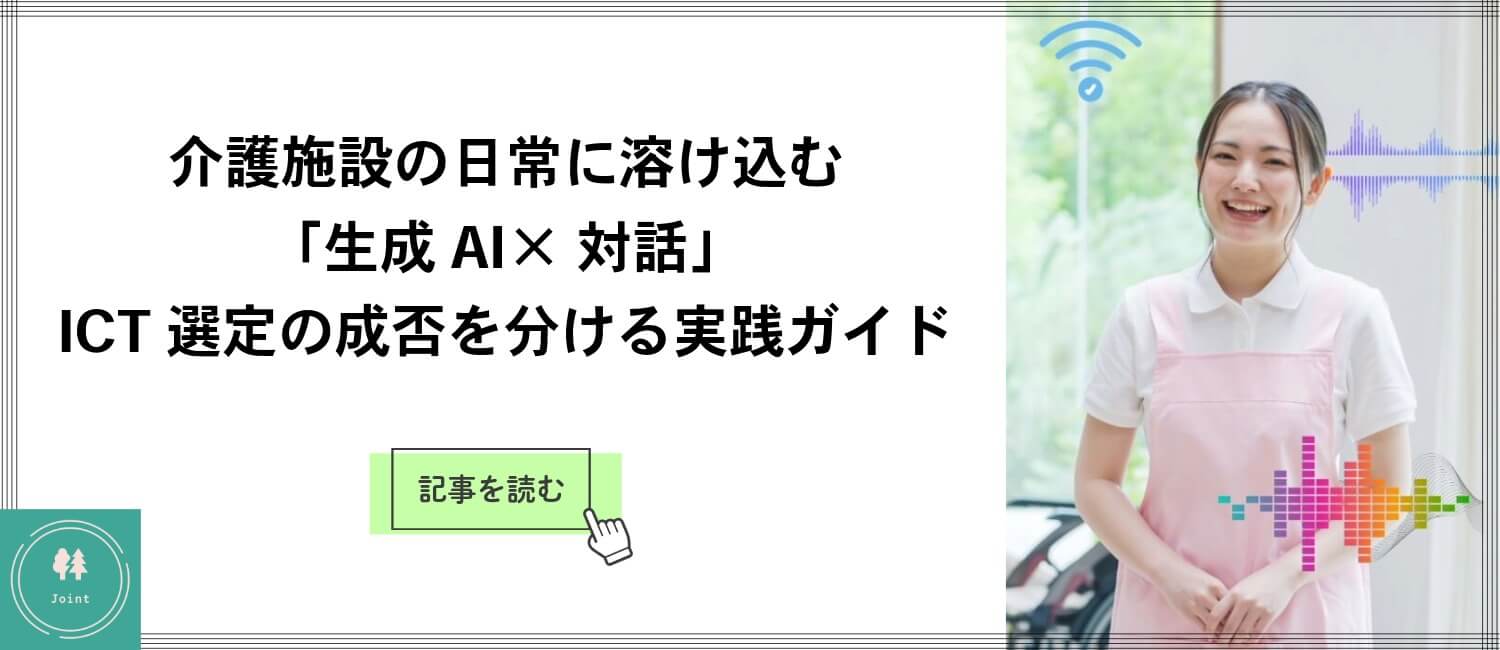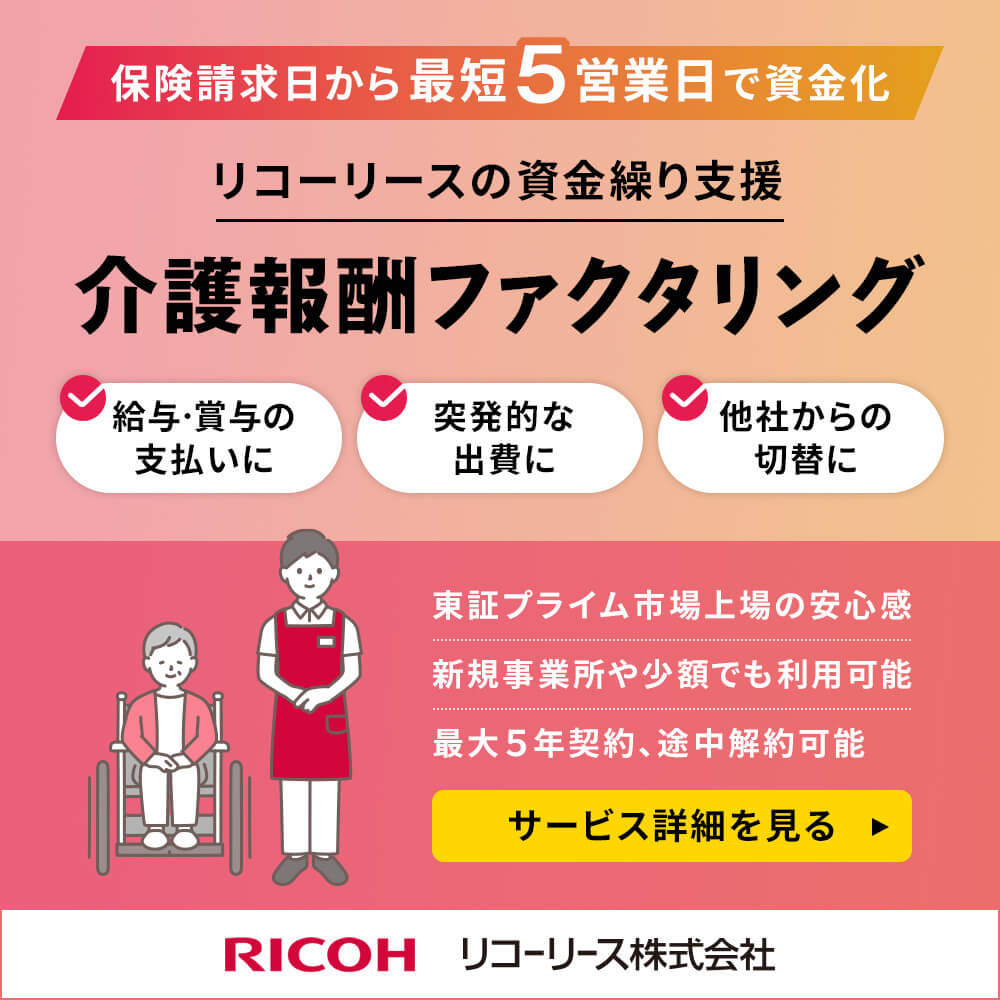自虐のネガキャン、もうやめよう 介護職の過度な負のイメージ 塗り替える足がかりは“外部との接続”


自分自身の仕事を、周囲にどんな言葉で説明しているだろうか。
これは決して軽視できない問いだ。日々の業務に追われるなかで、我々はしばしば自分の職責の意味や範囲、真価の言語化を後回しにする。「大変」「地味」「取るに足らない」などと吐き捨てることもある。
もちろん謙遜や恥じらいはあるが、時にはもっと正面から語ってもいいのではないだろうか。私たちは日々かけがえのない仕事をしている。少なくとも介護職にとって、それは紛れもない事実だ。【Joint編集部】
「介護職自身がネガティブキャンペーンをしていることも少なくない」
こう指摘するのは、株式会社Salud(サルー)の代表取締役で介護福祉士、ケアマネジャーの中浜崇之氏。介護職員から施設長、デイサービスの立ち上げなど、およそ17年間にわたって現場の第一線に従事してきた。

現在は独立・起業し、地元地域の障害者向けの訪問介護やグループホームの運営、各種研修の講師、講演、広報など活躍の幅を広げた。業界の内外をつなぐ実践にも力を入れており、介護職の多様な可能性を体現するロールモデルの1人だ。
中浜氏が焦点を当てているのは、意識の高いキャリア論ではない。介護職が持っている本来の価値や魅力は、どうすれば社会に響き渡るのか。そして、業界をもっと良くするために現場のひとりひとりに何ができるのか。その答えの手がかりを探して、中浜氏の言葉に耳を傾けた。
◆ ネガティブな語りが印象を下げる

−− 介護や福祉の仕事に対して「大変そう」「つらそう」といったイメージが根強いことについて、どう感じていらっしゃいますか?
そうですね。たしかに現場は忙しいし、体力的にも精神的にも負担がかかることは否めません。でも、そればかりを強調して語られてしまうのは、すごくもったいないことだと思っています。
実際には、人の人生に深く関わって「ありがとう」と感謝されることも多いですし、自分の仕事が誰かの暮らしを豊かにしているという実感が得られやすい仕事です。それが本質だし、普通に誇るべきことではないでしょうか。
−− 現場の魅力が外に伝わっていない、ということでしょうか?
やっぱりそう言わざるを得ないと思います。特に、現場で働く私たち自身が、「きつい」「しんどい」「職場はダメな人ばかり」などと言ってしまっているケースも少なくありません。いわゆる“ネガティブキャンペーン”を、自分たちでしてしまっているというか…。
でも、それって業界全体の印象をすごく悪くしてしまうんです。家族や友人との会話で前向きな言葉を発するだけでも、周りのイメージは大きく変わるのではないでしょうか。「福祉の仕事って面白いよ」「利用者さんをこう支えた」「こんな価値を生み出した」。どれも事実で大切なことなんですから、ありのままを伝えればいいのではないでしょうか。
◆「外とつながる」ことで気づく価値
−− 確かに、身近な人のリアルな声の影響って大きいですよね。
そうなんです。テレビやネットで見るネガティブな情報よりも、家族や友達などの話の方がずっと信頼されるんですよね。重みが違うというか、みんなが理解してくれる。だから、業界の外にいる人たちに向けて、自分たちの言葉で語ることが本当に大切だと感じています。
−− そうした「外とのつながり」が重要だということでしょうか?
そこを強調したいんです。もちろん他分野も似たところがあると思いますが、介護・福祉の現場ってどうしても内向きになりやすい面があると思うんです。職場と家の往復だけで1日が終わってしまう。人間関係も施設内だけに閉じてしまいがちです。だからこそ、あえて“外に出る”ことが重要ではないでしょうか。
異業種の人たちと話したり、業界外のネットワークに関わったりすることで、自分の仕事の価値や強みに改めて気づけることがたくさんあります。
−− どのような気づきがあるのでしょうか?
現場で当たり前だと思っていたことが、実は他の人にとっては「すごいこと」だったりするんです。たとえば、どんな相手でも尊重してじっくり話を聞く力や、相手の表情や行動から気持ちを読み取る力などがそうです。
そういうスキルってどこでも重要で、例えば接客業や営業・販売など他の仕事でもすごく活かせるんですよね。実際に、福祉の経験をもとに飲食店や一般企業で働いている人、独立している人も少なくありません。「あのお店は接客が丁寧で安心できる」と評判になっていたら、実は店長が元介護職だったみたいな話もあるんです。

◆ 経験を「出口」に活かせるキャリア観を
−− 福祉の現場で積んだ経験は、別の場所でも通用するということですね。
はい。これは人材確保の課題と関わることだと思います。「現場でキャリアを終える」のではなく、そこを出発点として捉える考え方も大事ではないでしょうか。現場での経験を土台に、地域の産業に関わることもできるし、講師や研修などの分野で活躍することもできる。他の業界へ行ったり会社を立ち上げたりすることも可能なんです。
福祉・介護の仕事って、もっと自由に、自分の興味や特技を活かしながら、広く展開していける仕事ではないでしょうか。私はそこも魅力だと捉えていますし、今後も引き続き実践していきたいと思っています。
−− 若い世代へのアピールにもつながりそうですね。
その通りです。若い人たちは、「この仕事を続けた先にどんな未来があるのか」をとても気にしています。だからこそ、介護の現場が“多様なキャリアの入口”でもあることを、もっと伝えていかなければならないと思います。
もちろん、いったん介護を辞めたらそれで終わり、ではありません。いつでも出入りできる、しかも経験が他の世界でも活かせる、と伝えることで、関心を持ってくれる人はきっと増えるはずです。
◆ 前向きな語りが力になる
−− 人材不足などをめぐっては、給与の低さが諸悪の根源だという声もあがりそうです…。
確かにそうですが、それだけで終わらせてはいけないと思います。もちろん、制度の問題や待遇面の課題が大きいことは否めません。処遇改善は不可欠です。
でも、だからといって私たちが自分自信の仕事をいつも卑下していたら、誰もこの業界に魅力を感じてくれません。この分野に財源を投じることの重要性も分かってくれません。
もっとも、きちんと経験を積んでキャリアを重ねていけば、介護職の給与は決して極端に低いわけではありません。他のサービス業と比べて大きく見劣りするものではなく、全国どこでも安定的に働けるという点でも魅力があります。
一部の悪いイメージだけが独り歩きしてしまっている現状があるのは、やはり現場の声が十分に届いていないからではないでしょうか。
だからこそ、自信と誇りを持って、今の仕事の魅力を語っていくことが必要なんです。胸を張ってそれができる人が増えれば、業界全体のイメージも少しずつ確実に変わっていくはずです。

◆ 業界を外側に開いていく
−− 最後に、今後の介護・福祉の現場に必要な視点とは?
私は、もっと「開かれた業界」にしていくことが何より大事だと思っています。外とつながることで、互いに刺激を与え合い、自分の価値に気づき、同時にその価値を周囲に伝えることもでき、更に自信をつけられるのではないでしょうか。
介護・福祉の業界は、決して夢のない世界ではありません。地域の最前線で臨機応変に動き、人の暮らしを支える想像力と行動力が求められる仕事です。いつでも入ってこれて、いつでも出て行けて、いつでも戻ってこれます。他の業界と同じ様に、頑張れば独自のキャリアを切り開くことも全然できます。
その価値を、私たち自身が信じて普段から自然に伝えていく。たった1人の“前向きな一言”が、業界のイメージを変える原動力になる。私はそう信じて、今後も行動を続けていきたいと思います。