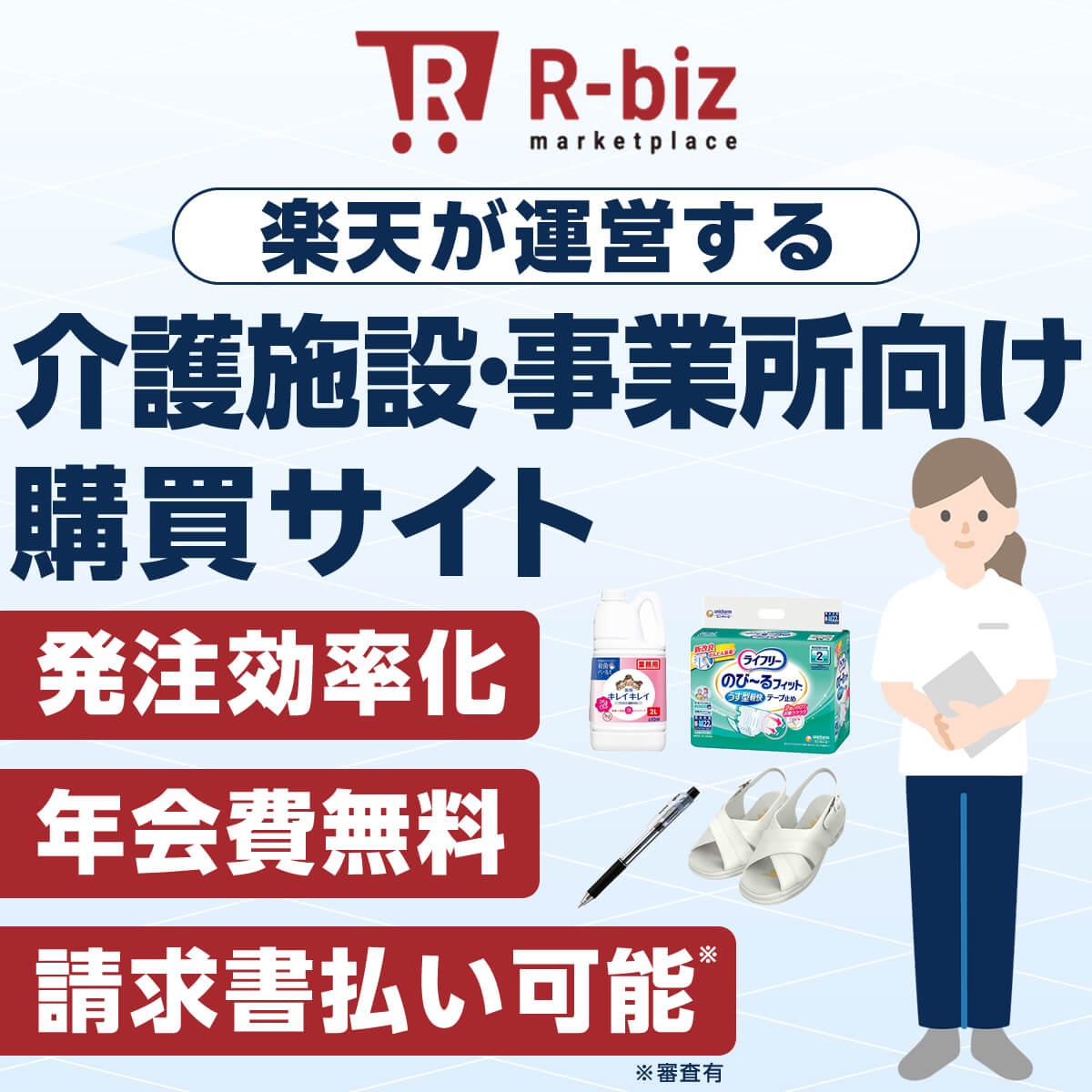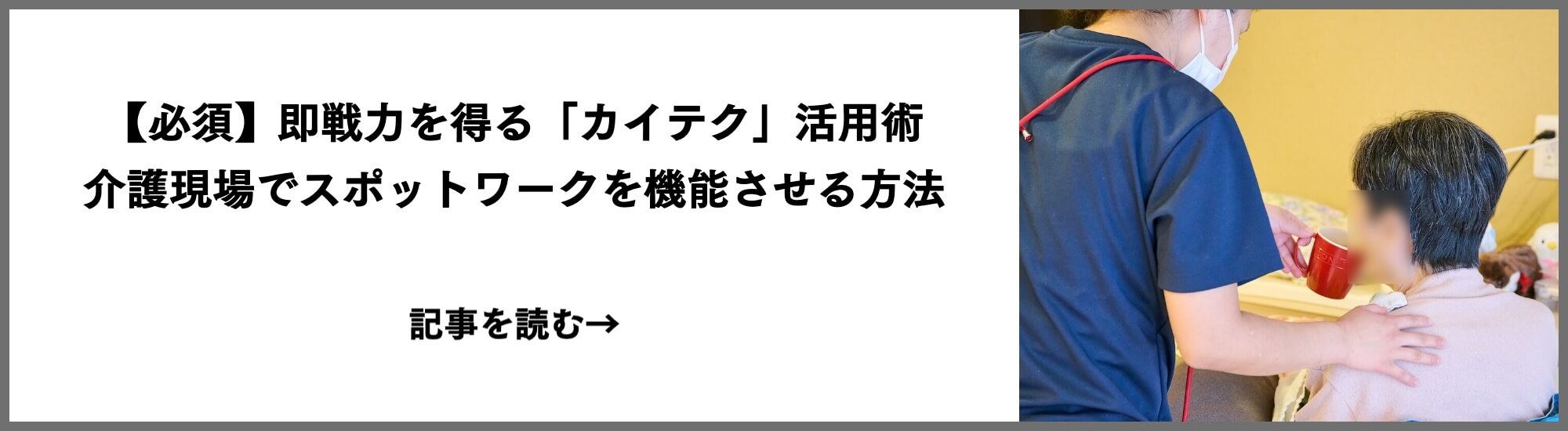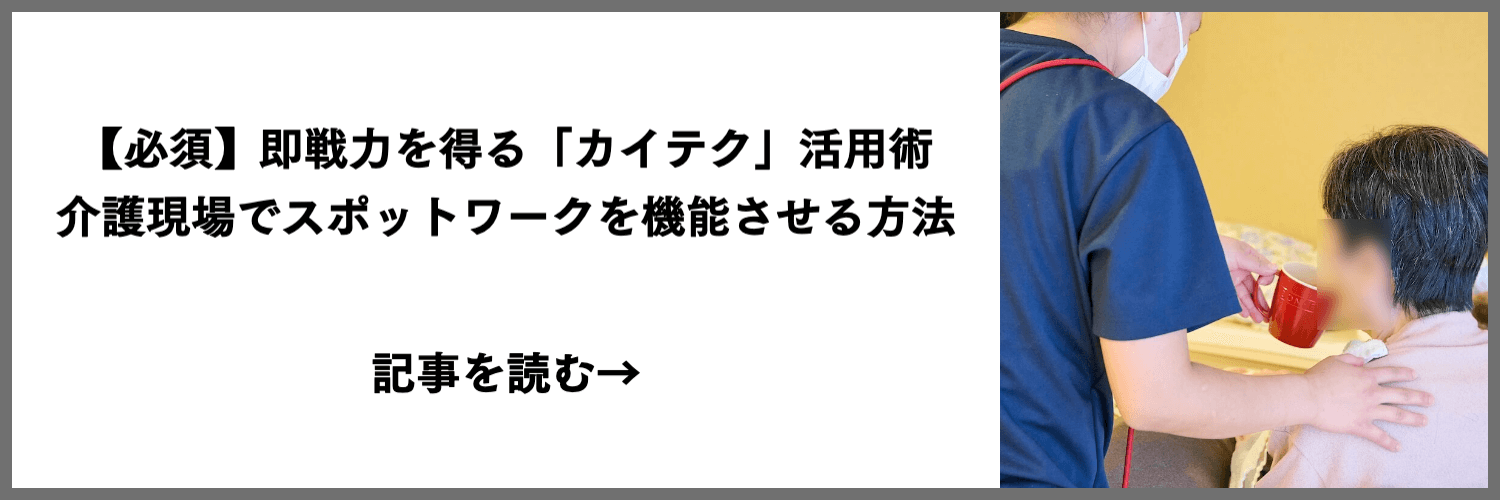2025年7月23日
「ALP」の普及へ東大でシンポジウム開催 自分らしい老後を実現する新たな備えのプロセスを考える


東京大学高齢社会総合研究機構(IOG)は22日、人生100年時代に対応した老後の備えのプロセス「Advance Life Planning(ALP)」の普及・浸透を目的としたシンポジウムを開催した。【Joint編集部】
資産や住まい、介護など将来の暮らしの重要な要素について、本人が主体的に考えて選択できるようにするアプローチを社会に根付かせる狙いがある。
背景には、人生の終盤に起きがちな“後手の対応”がある。多くの人が面倒なことを先送り、成り行き任せにしがちで、身体機能や認知機能が衰えてからようやく、資産管理や介護の問題を考え出す。ただ、その時点では既に本人の意思を反映しにくい状況に至っており、周囲の人が限られた選択肢の中で仕方なく対応を決めるケースが少なくない。
ALPはこうした状況を変えるためのアプローチだ。将来を自ら能動的に設計し、関係者とともにあらかじめ、繰り返しの対話を通じて、本人の希望を軸に、資産・住まい・介護など生活基盤に関する意思決定を先手先手で行っていくプロセスを指す。
IOGは現在、ALPの考え方を社会に広げるとともに、相談支援にあたる専門人材「ALPアドバイザー」の資格創設も含め、ALPアドバイス事業という新たな社会システムの実装に向けた取り組みを進めている。
シンポジウムの開会の挨拶に立った東京大学名誉教授の樋口範雄氏は、「高齢期のあり方は人それぞれ大きく異なる。自分らしい年の重ね方を支える仕組みが必要だ」と述べた。講演した元厚生労働事務次官の蒲原基道氏は、「本人が自分の意思で選択し、自分らしく生きることこそが支援の出発点」と強調。医療・介護にとどまらず、暮らし全体を視野に入れた備えこそが重要であるとして、ALPの意義を訴えた。