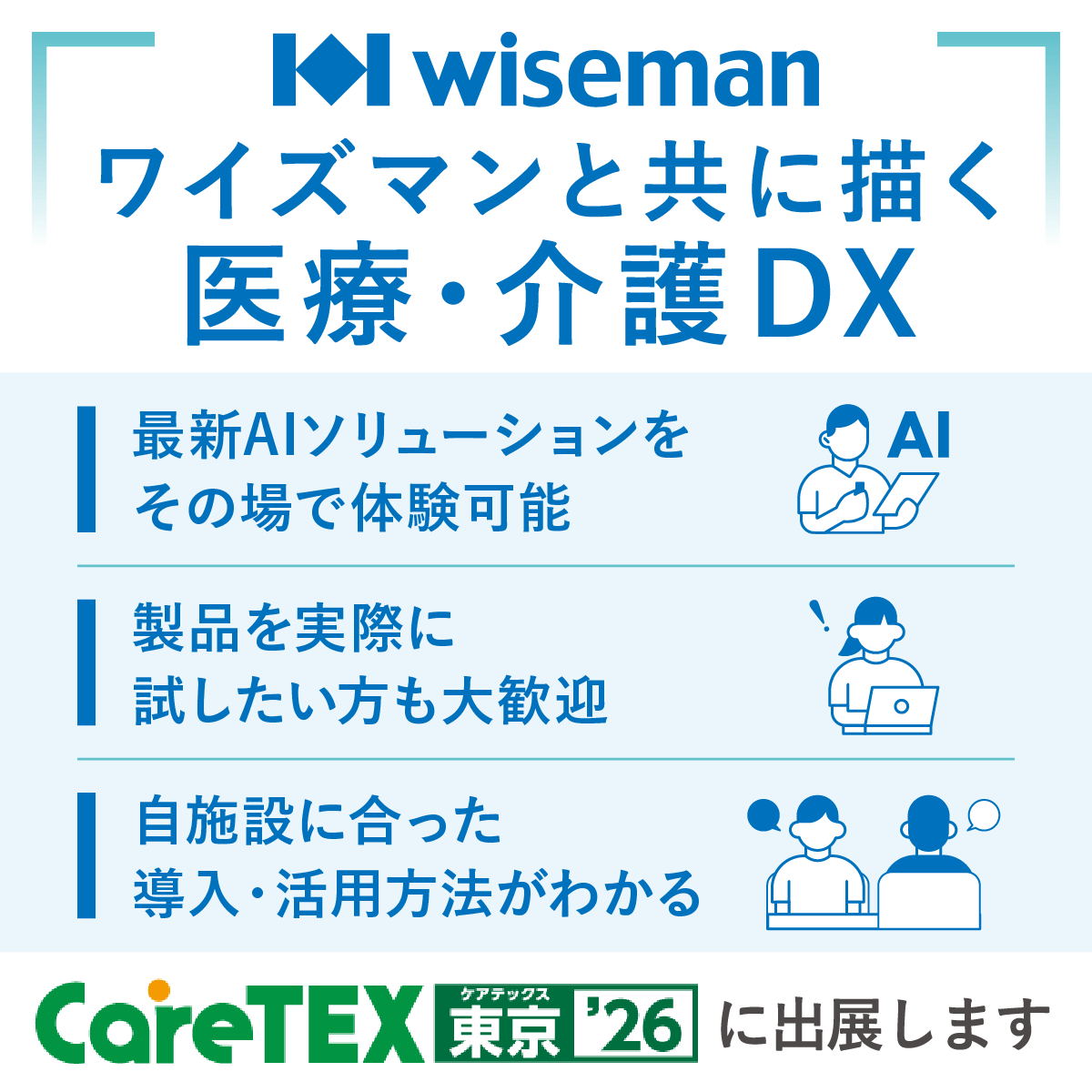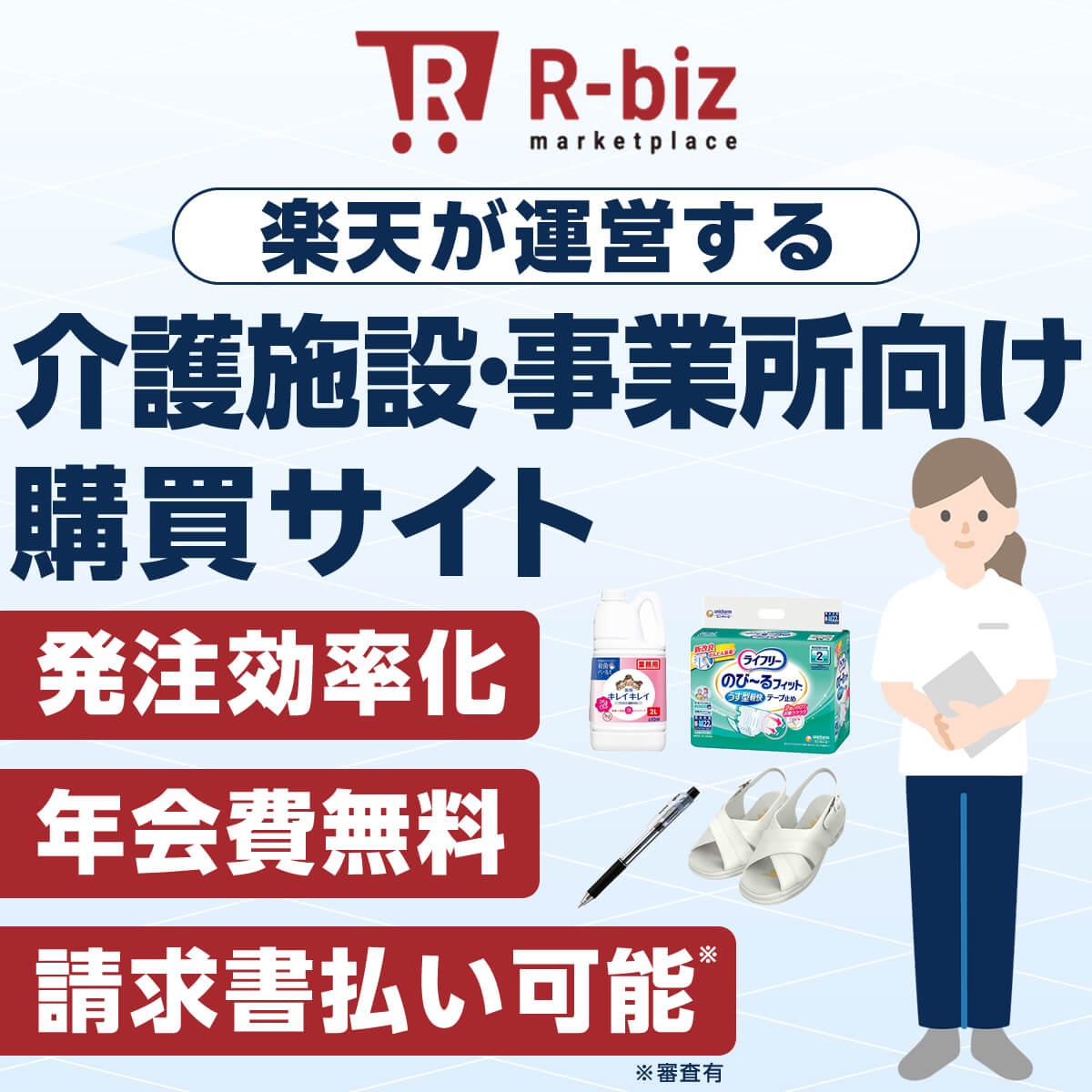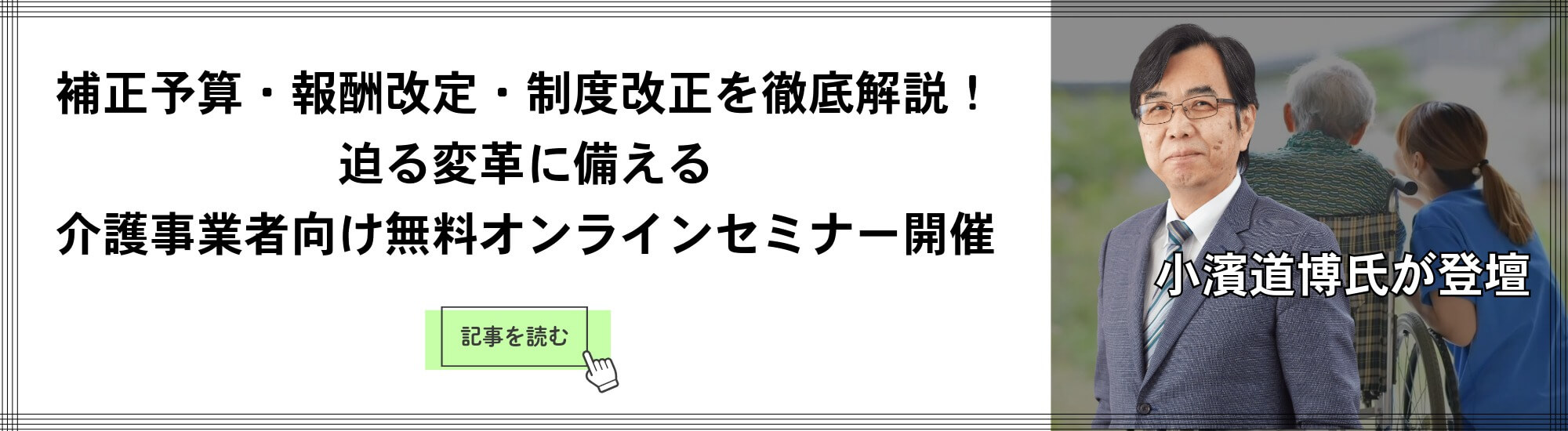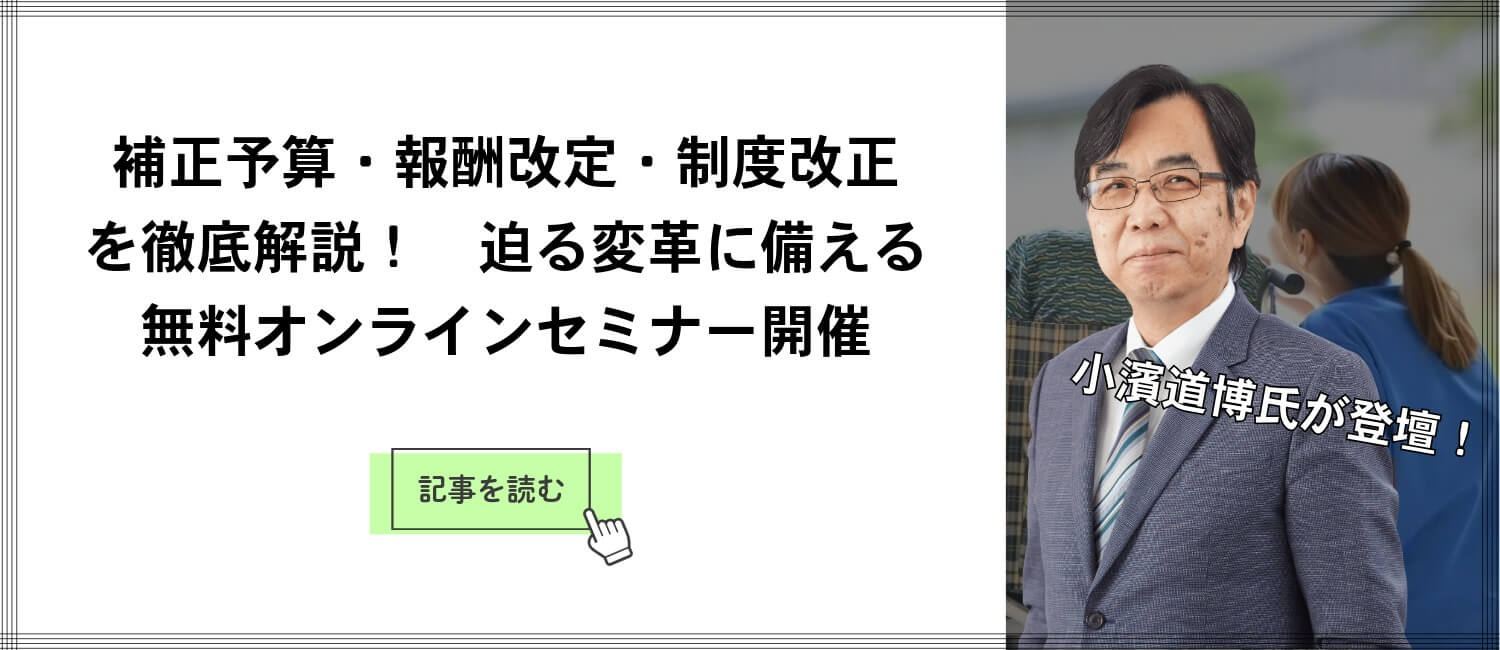長崎県、ケアプランデータ連携システムの活用に本腰 離島を含む在宅介護の業務の効率化に向けて


長崎県は今年度、介護現場のICT化を一層進めるため「ケアプランデータ連携システム活用促進モデル事業」に注力する。【Joint編集部】
離島や過疎地が多く、慢性化した人手不足を根本的に解消しにくい地域特性と向き合い、在宅介護の持続可能性を確保する道を探る。昨年度に続く取り組みで、導入効果の数値化や課題の洗い出し、ノウハウの確立を図り、県全体への成果の普及につなげていく。
長崎県は全国で最も多くの離島を抱え、業界全体で人材確保が難しい中でも特に切実な状況に直面している。求人を出しても応募がない状況は珍しくなく、外国人材の受け入れを進めても人手不足の解消には至らないのが実情だ。
県福祉保健部長寿社会課の担当者は、「介護人材の確保には県、市町、関係機関と介護事業所が連携して支え合う仕組みが不可欠。ICTを活用し、生産性を高めていくことが安定的な介護サービスの提供につながる」との認識を示す。
そこで、国の「ケアプランデータ連携システム」に目を向けた。在宅介護に欠かせない情報連携を効率化し、現場の負担を和らげるインフラのフル活用が欠かせないことは明らかだ。
◆ 今年度は五島市などで実施
長崎県は昨年度、諫早市内の10事業所を対象にモデル事業を実施した。
ケアプランやサービス提供票、実績報告書などのやり取りをオンライン化し、タイムスタディ調査で効果を検証。結果として、これまで2人で2日かかっていた実績配布の時間が1人で3~4時間で済むなど業務時間の削減に加え、ガソリン代や人件費、印刷にかかる費用の削減にもつながることが分かり、アンケート調査でも67%の事業所が「効率化できた」と答えた。
一方で課題も浮かび上がった。
例えば、現場ではその有用性を実感する一方で、経営層には費用面の不安から導入に慎重な姿勢があったり、逆に、経営層が積極的でも、現場では多忙から導入に消極的な事例もあるという。
また、高齢のケアマネジャーなどはパソコン操作が不慣れなことが多く、それが導入に消極的となる大きな理由であることも分かった。
長崎県の担当者は、「分かりやすい動画教材を用意することも含め、関係者への丁寧な説明・サポートを心がけないといけない」と振り返った。
今年度のモデル事業は、昨年度と同様に事業運営を長崎県介護支援専門員協会に委託し、対象を諫早市や五島市など3地域に拡大。各地域で10事業所ずつ、おおむね30事業所が参加する予定だ。
昨年度に作成したマニュアルや導入手順を補強し、各地で説明会や報告会も開催。諫早市のモデル事業所が他地域の助言役として関わるなど、県内の横展開の仕組みも並行して整えていく。
また、導入効果を再びタイムスタディで数値化し、実証的なデータを更に強化する。キャンペーンでケアプランデータ連携システムを無料で導入できる今は好機。長崎県介護支援専門員協会の七種秀樹会長は、次のように意欲をみせた。
「長崎県の人手不足は深刻。その危機感は担当課とも共有しており、連携を密にして取り組んでいる。日々の業務で忙しく、デジタル化を躊躇する声も現場にあるが、今やらなければ他産業との格差は広がるばかりで猶予はない。県や協会の関係者も趣旨を理解してくれており、思いを一つに生産性向上を実現したい」
◆ モデル事業の成果を全県へ
長崎県は今後、モデル事業で得られた知見を県内全域に広げる方針だ。事業所間の横のつながりを活かし、導入経験を持つ事業所が未導入の事業所を支援する「伴走型の展開」を視野に入れる。業務の効率化による余力を利用者へのケア、アセスメントの充実に振り向ける効果も期待している。
担当者は「人手不足は待ってくれない。在宅介護を守るためには、ICTによる生産性向上が不可欠。実施を“義務”ではなく“必要な投資”と捉えてもらえれば」と語る。全国最多の離島を含むユニークで豊かな地域、文化、産業、自然を持つ長崎県だからこそ、独自の取り組みで苦境を打開しようという意思は強い。
長崎県の挑戦は、全国の介護現場にとっても共通する示唆を含む。介護業界は今年から、2040年を視野に入れて体制づくりに取り組む新たな時代に入った。ICT化、DX、AXによる業務効率化を前向きに捉え、未来に向けて確かな一歩を踏み出す視点が広く問われている。