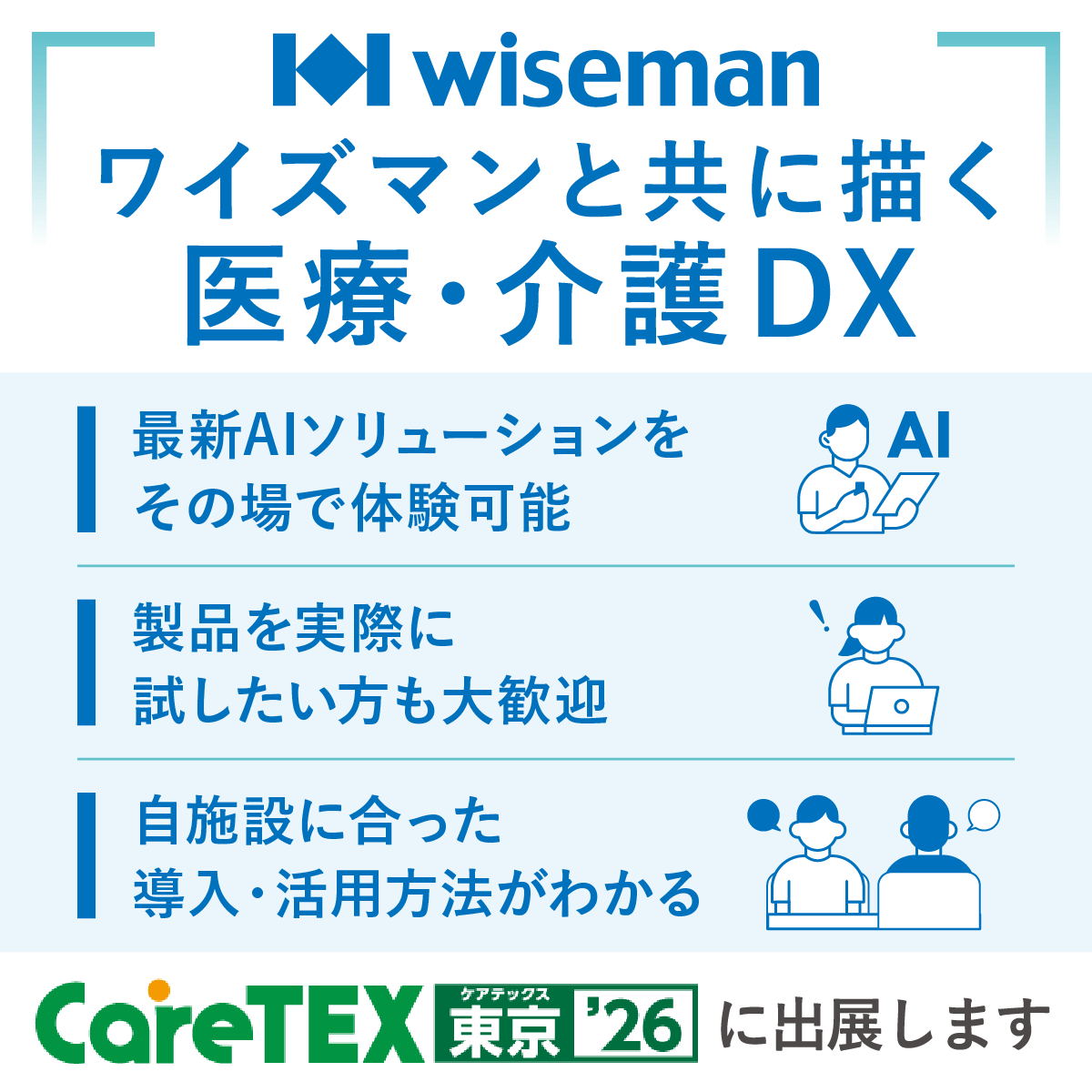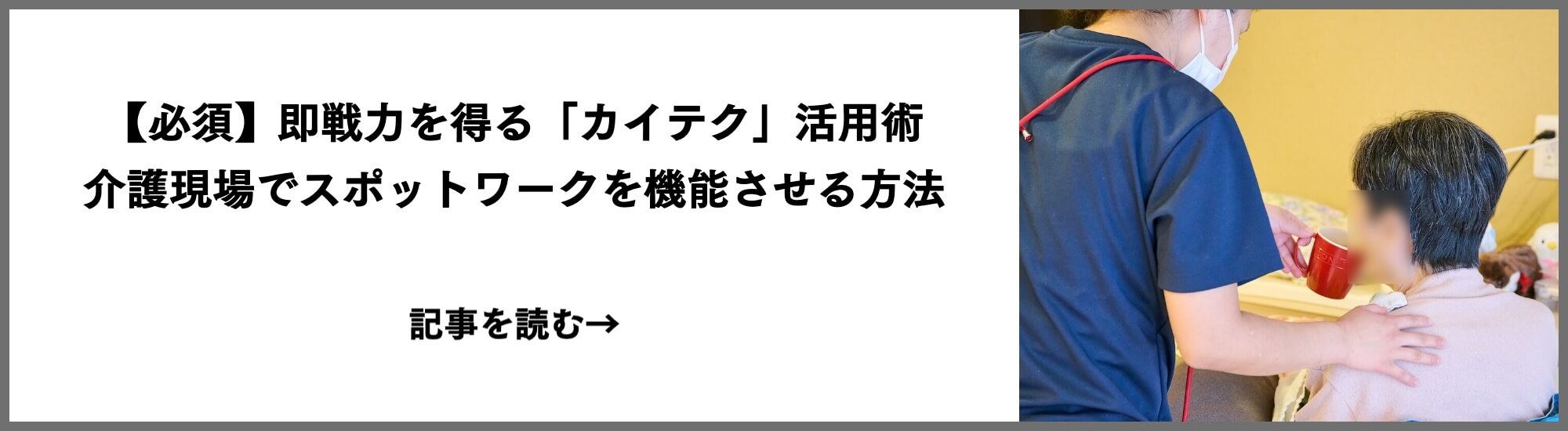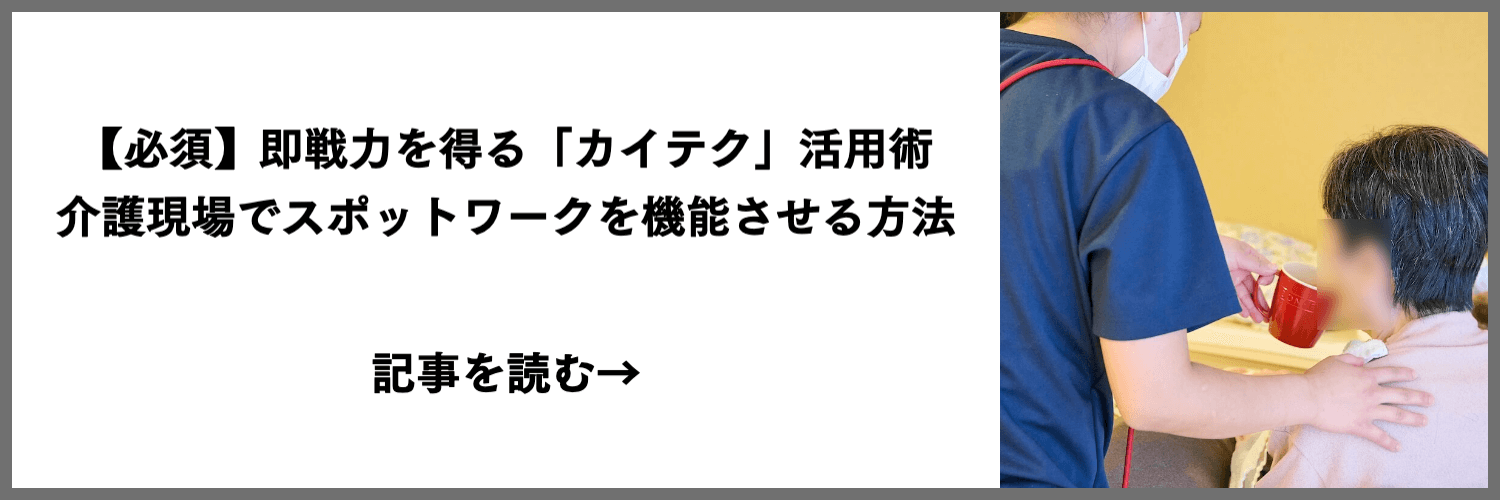田中滋氏「地域包括ケアシステムは永遠に完成しない」 社会変化に応じて「常に構築中」


埼玉県立大学の田中滋理事長は、今月21日に開催された「特別オープンセミナー」で講演した。地域包括ケアシステムの性格について、「永遠に完成することはない」と語った。【Joint編集部】
介護報酬を議論する国の審議会の会長など、これまで数多くの要職を務め、医療・介護政策の議論をリードしてきた田中氏は、「2025年になって地域包括ケアシステムは完成したのか、と聞かれることがある」と切り出した。
続けて、「完成なんかしない。永遠に完成することはない」と明言。人口動態や医学の発展、社会環境の変化などに応じて、常に姿を変えていくべきものだと強調した。
安全保障や防災、教育などが不断に見直されるのと同じように、地域包括ケアシステムにも「終わりがない」と説明。むしろ重要なのは、社会環境の変化を見極めながら継続的に更新し、一段と進化させていく姿勢だと訴え、「地域包括ケアシステムは常に構築中」との認識を示した。
◆ 時代とともにニーズも変わる
田中氏が足元の重要な変化の1つとしてあげたのが、1人暮らしの高齢者が急速に増えているという地域の現実だ。
かつて、介護保険制度が誕生して歩き始めた時代、多くの高齢者は配偶者や子どもと共に暮らし、家庭内の介護負担も当然のものと受け止められていた。
しかし現在は、三親等以内の親族がいない高齢者が年々増加している。内閣府の推計によれば、昨年1年間に孤立死に至ったのは2万1856人。家族の支えを前提とした制度設計は、もはや時代にそぐわなくなっている。
家族介護を前提とした発想はもはや通用しない。田中氏は講演でそう指摘し、孤独・孤立の問題は介護や医療だけでは必ずしも解決できないと述べた。
今後、85歳以上の高齢者や1人暮らしの世帯がさらに増加するとの見通しを示し、「時代が変わった。ニーズも変わる」と指摘。掃除や洗濯、買い物、移動といった日常生活の支援、地域とのつながりをどう確保するかが課題になるとした。