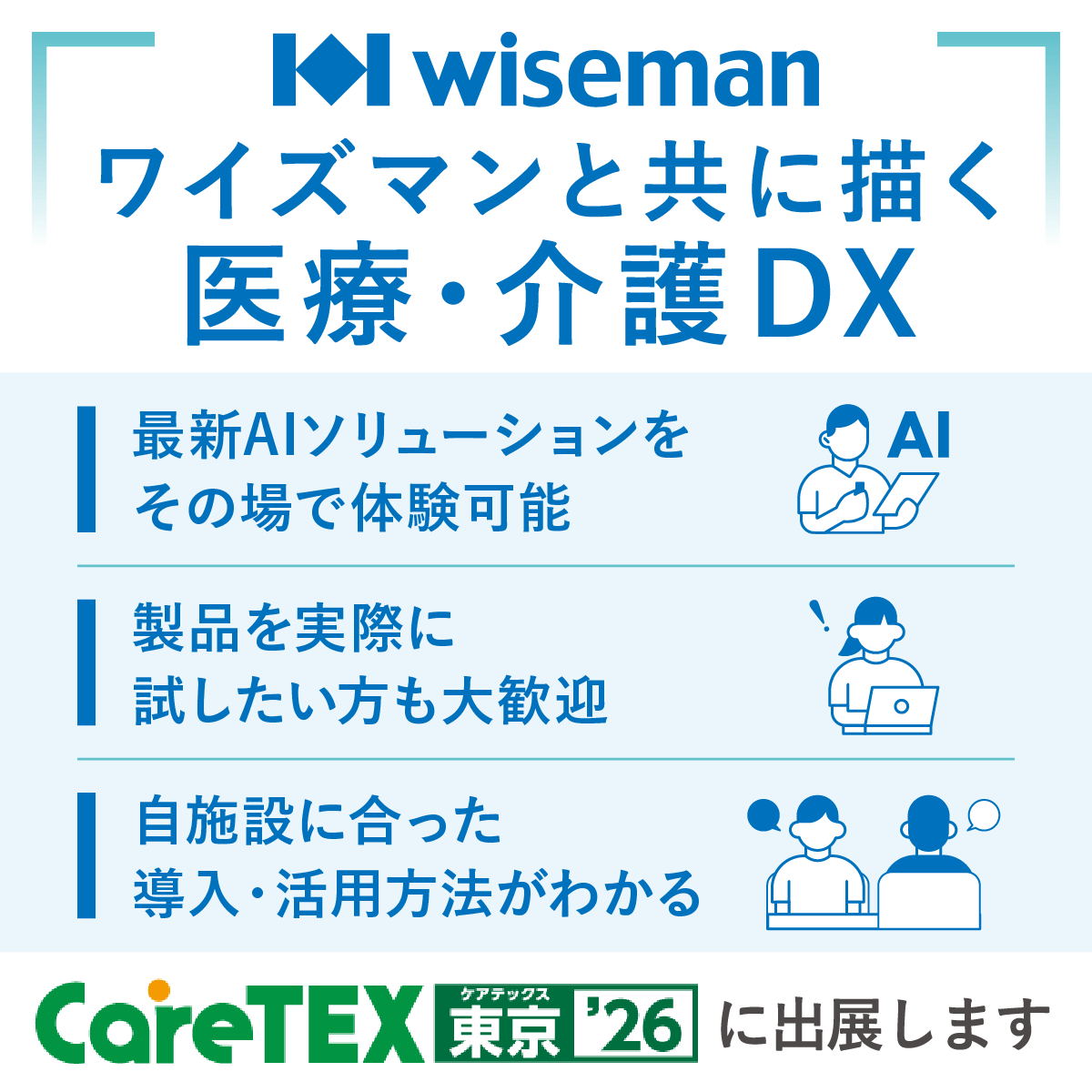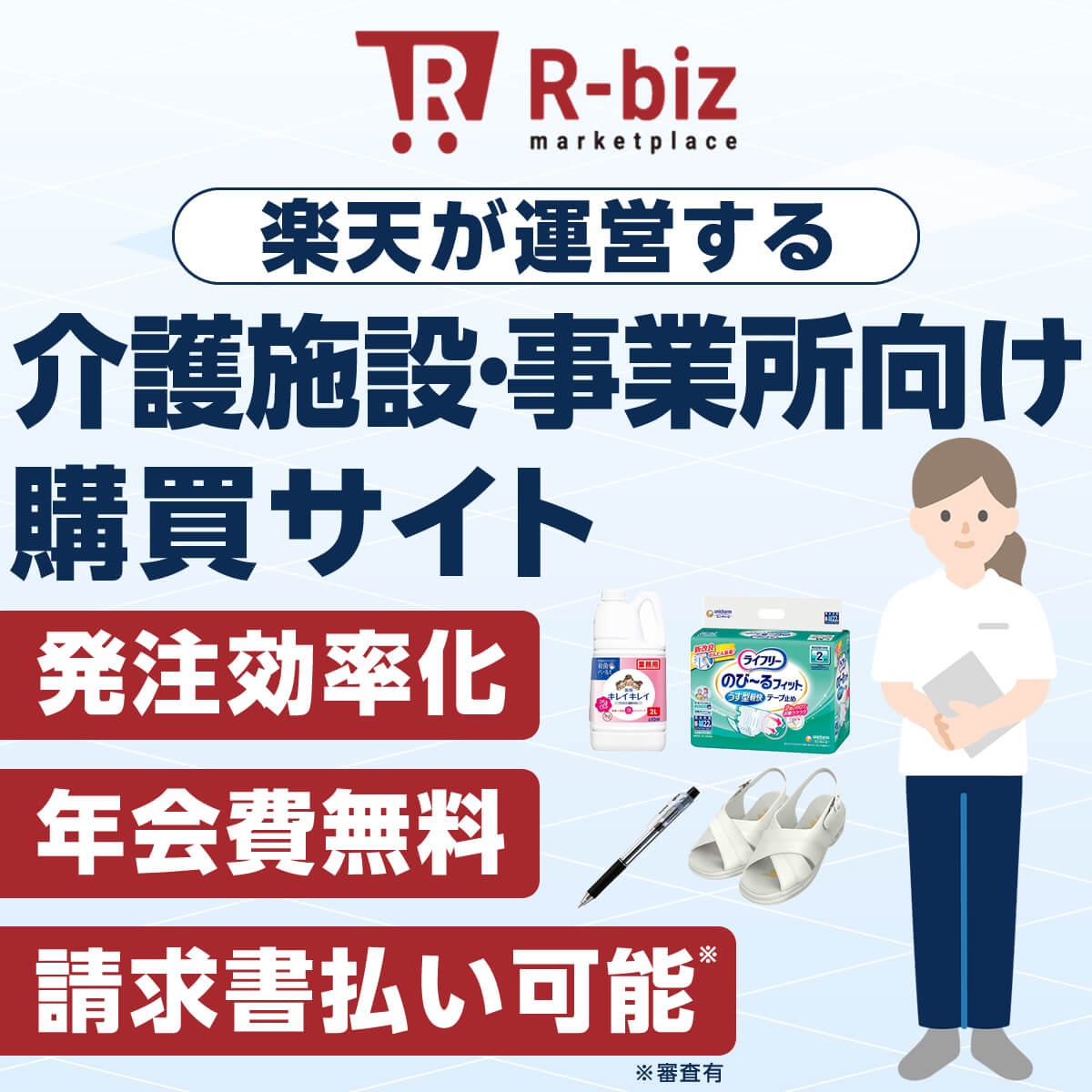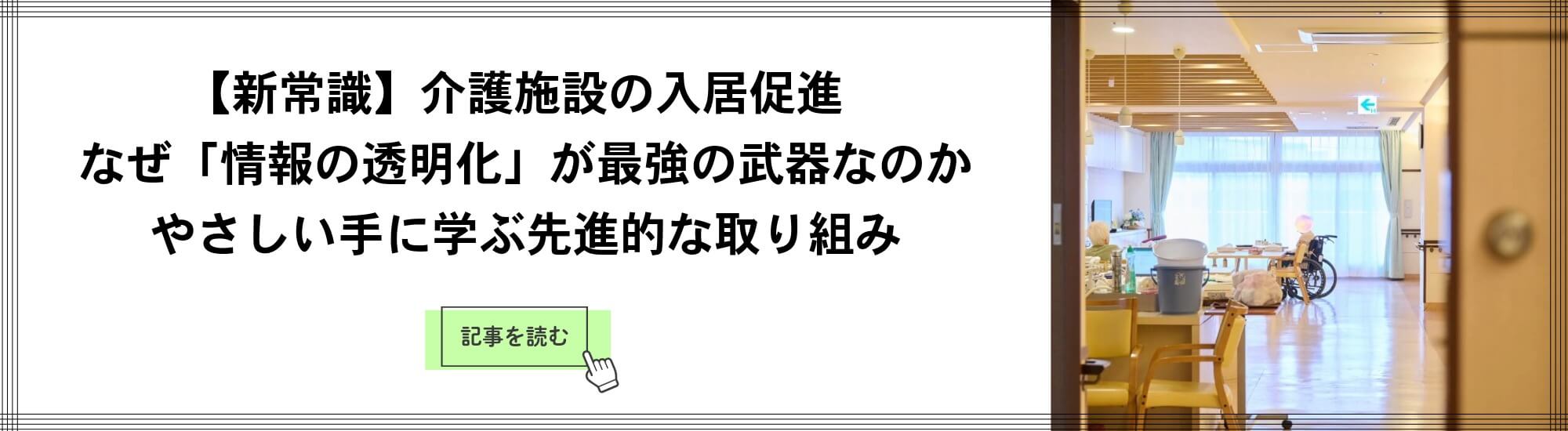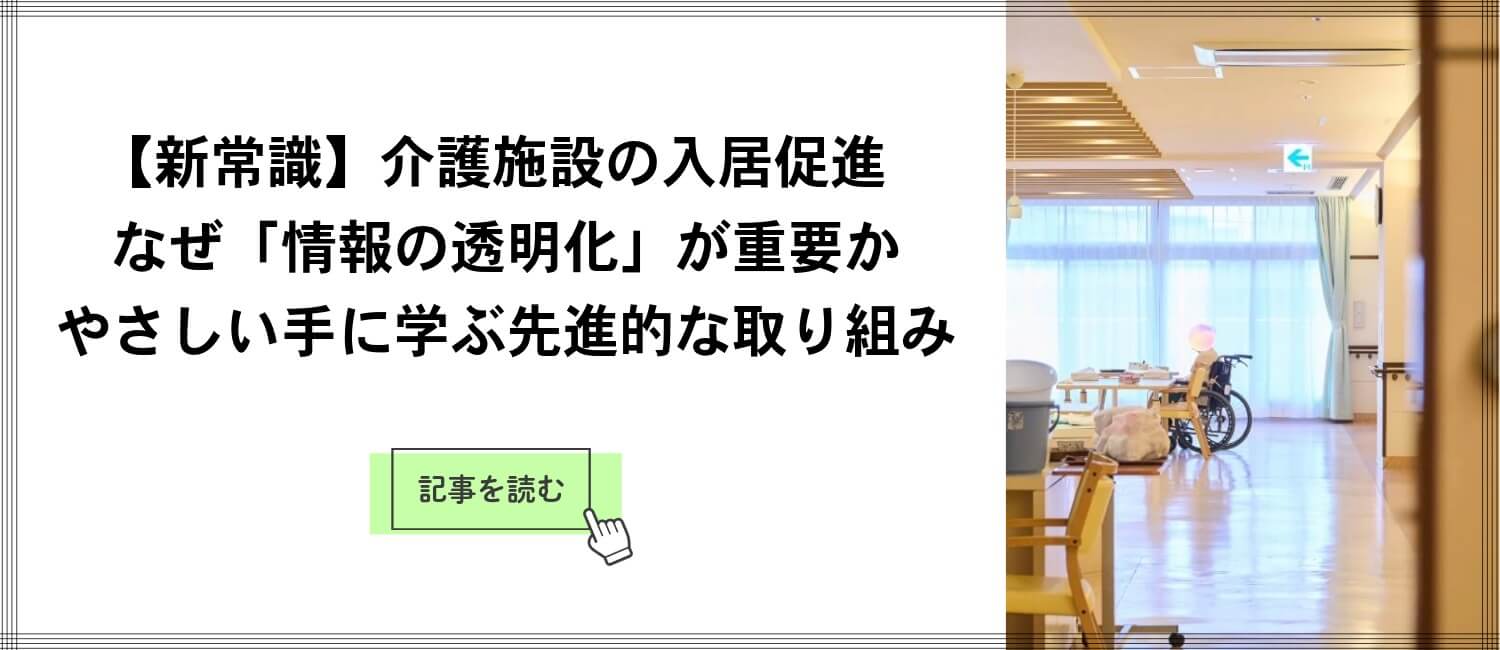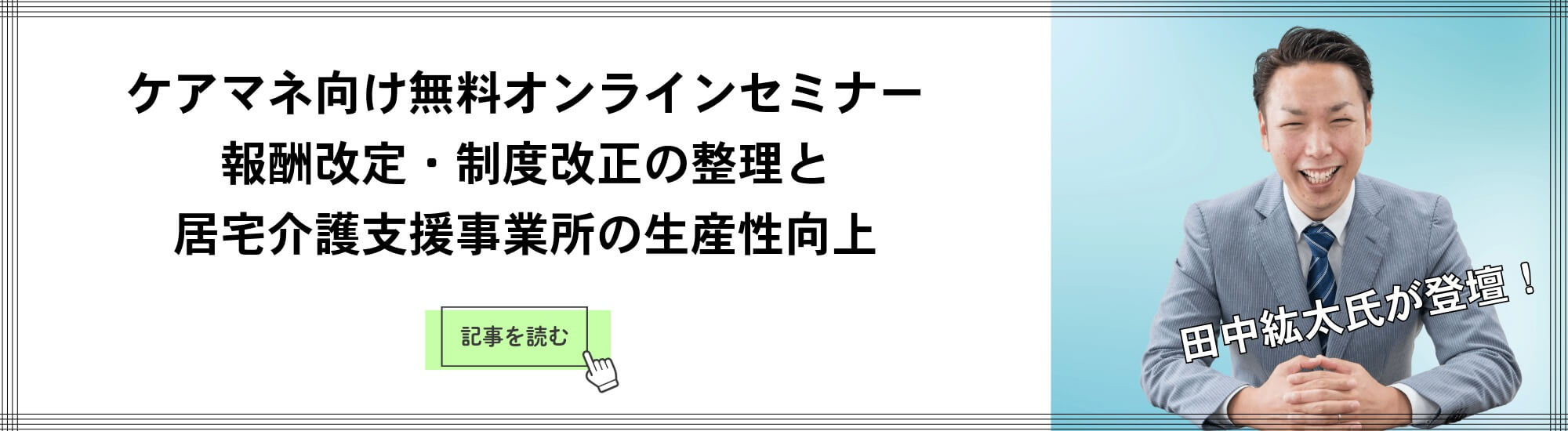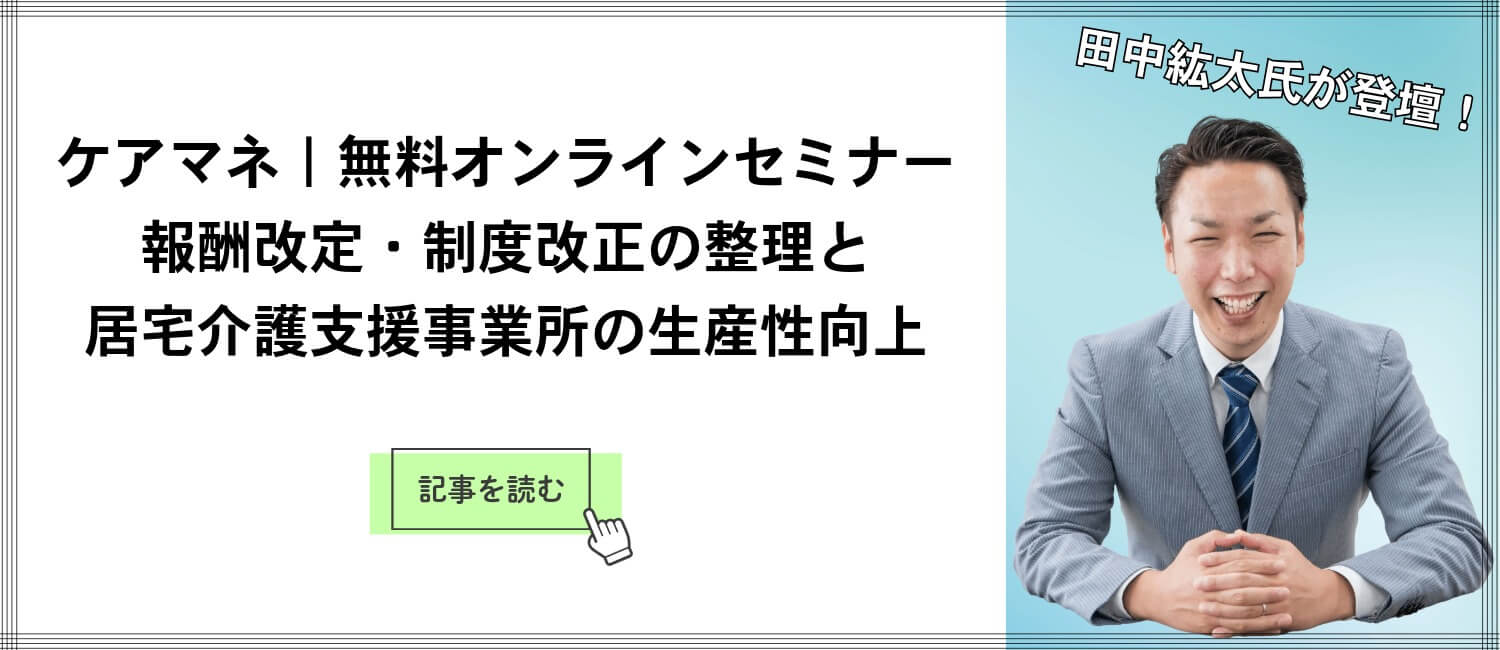【田中紘太】ケアマネ支援で新展開 厚労省が新規3事業を予算要求 カギを握る運用設計の妙


厚生労働省が来年度予算の概算要求で、居宅介護支援事業所やケアマネジャーを後押しする新規事業を3本打ち出しました。【田中紘太】
人材確保や負担軽減、経営支援、法定研修の見直しなど、いずれも現場のニーズに即した重要なテーマに焦点を当てたものです。昨年末にまとめられた検討会(ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会)の報告書も反映した中身で、厚労省が一連の議論の流れに沿って具体的な施策を新たに講じる構えをみせたことを、まずは率直に評価したいと考えています。
◆ 画期的な新しい補助メニュー
3本の新規事業の1つは、居宅介護支援事業所などを対象とする新たな補助制度の創設です。既存の基金(地域医療介護総合確保基金)の使途を拡充して具体化するもので、対象経費は例えば、人口減少地域での採用活動の支援、潜在ケアマネジャーの復職・定着支援、事務職員の採用・研修の支援、過度なシャドウワークの解消など多岐にわたります。
中でも私は、利用者確保のための広報活動の支援、コンサルタントの派遣による加算の新規取得、処遇改善、大規模化・共同化の支援に注目したいと思います。
この広報活動の支援は、一見すると「人手が足りないと言っているのにPRか」と否定的に受け止められがちですが、実は地域差を踏まえた現実的な施策だと考えられます。
現状では、ケアマネジャー不足が非常に深刻な地域が多くある一方で、依然として営業活動が欠かせない地域も少なからず存在します。そうした地域の事業所にとっては、やはり“入り口”の強化が不可欠です。
利用者獲得は経営の根幹で、事業を安定させる効果が非常に大きい。この点を政策メニューとして明示したことは評価に値します。これまであまりなかった切り口ですし、画期的と言っても過言ではないかもしれません。
一方で課題は、広報が「単発の制作費」にとどまりがちな点です。その後の運用や改善の仕組みまでを視野に入れないと、十分な成果につなげることは難しいでしょう。
コンサルタントの派遣についても効果が大きい反面、「誰が来るのか」で成果が大きく分かれがちです。現場や地域の実情に疎い助言は逆効果になりかねません。
したがって、派遣するコンサルタントの人選、成果指標、不適切な助言の是正フローを明確化し、しっかり結果にこだわる伴走支援として設計することが、より現場に根づく条件になるのではないでしょうか。
◆ 法定研修、焦点は今後の制度運用
もう1つの新規事業は、法定研修の効率化、ケアマネジャーの負担軽減です。厚労省は来年度から、法定研修に用いる全国統一的な講義動画や教材の作成に着手する方針を示し、これを今後のオンデマンド化につなげる構想を描いています。
全国統一的な講義動画・教材を国が整備することは、研修の質や内容の“ばらつき”を是正し、受講コストや運営負担を軽減する有効な一手となります。講師の質の差、都道府県の類似教材の重複制作といった非効率も解消されるでしょう。
焦点となるのは、これから法定研修がどうなっていくかという具体像です。国が統一的なコンテンツを整備する一方で、運用は引き続き都道府県が担っていくと見込まれます。どの科目を全国統一的な動画で代替するのか、オンデマンド化をどのように実装するのかといった制度設計は、まだ今後の議論次第です。移行スケジュール、個々の研修の受講可能期間なども重要になるでしょう。
オンデマンド化は学びやすさを高める一方、視聴のみの“消費”にとどまらない仕組みづくりも問われます。演習や実地との接続、評価基準の統一なども含め、引き続き具体化の動向を注視していく必要があるでしょう。
3つめの新規事業は、ケアマネジャーの魅力を広く伝えるための広報です。厚労省は特に若年層、潜在ケアマネジャーへの情報発信を強化するため、動画コンテンツ、漫画、パンフレット、ポスターなどを作成するようです。
どこまで成果が出るのかなかなか判断しづらい面がありますが、これは「やらないよりはやった方がいい」という領域ではないでしょうか。専門職の密着動画、職業理解のコンテンツなどが一定の効果を生み出した例もあります。
こうした広報は概して地道な取り組みになりがちですが、現場で奮闘しているケアマネジャーの姿や生の声、仕事の本来的な魅力が1人でも多くの方に伝わり、新たな仲間が増えることを期待しています。
◆ 成果は実装力と現場の知恵にかかる
国の財源に余裕がない中で、厚労省がこうした3つの新規事業に踏み出す構えを見せたことは歓迎すべきです。昨年の検討会で重ねられた議論を具体的な施策に落とし込んだ点も、意義が大きいと言えるでしょう。
共通する課題は、やはり成果をどこまで上げられるかという点です。トライアンドエラーを重ね、現場の声を丁寧にすくい上げながらチューニングしていけば、やがて効果を発揮する事業も生まれてくるはずです。
地域差の大きな現実を直視し、取り組みの改善の迅速化や成功パターンの横展開を徹底できれば、ケアマネが誇りを持って働き続けられる基盤の整備に必ずつながります。今回の概算要求は新たな動きの幕開けで、次の局面の扉を開くものです。実装段階での丁寧な設計、現場の知恵の反映に強く期待したいと思います。