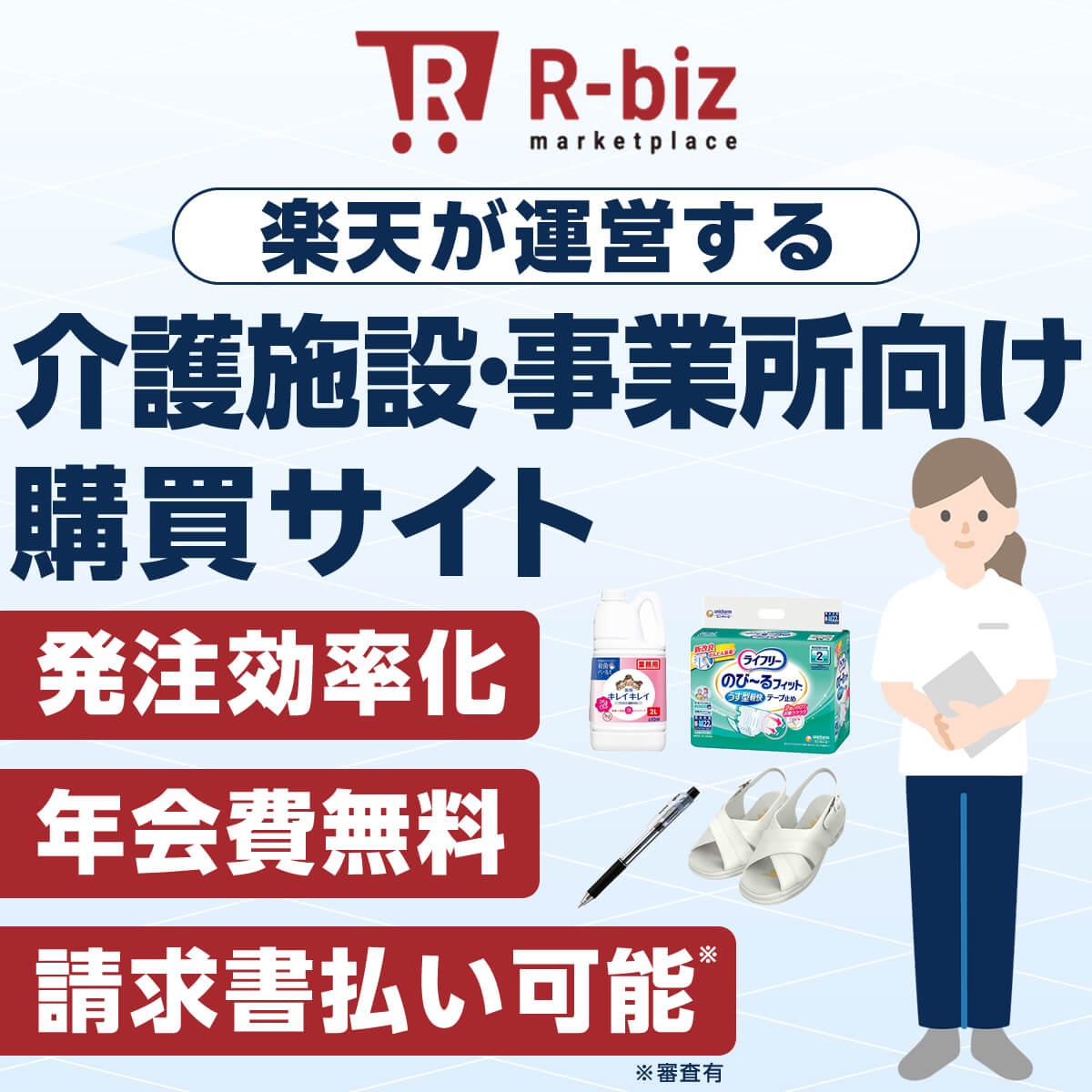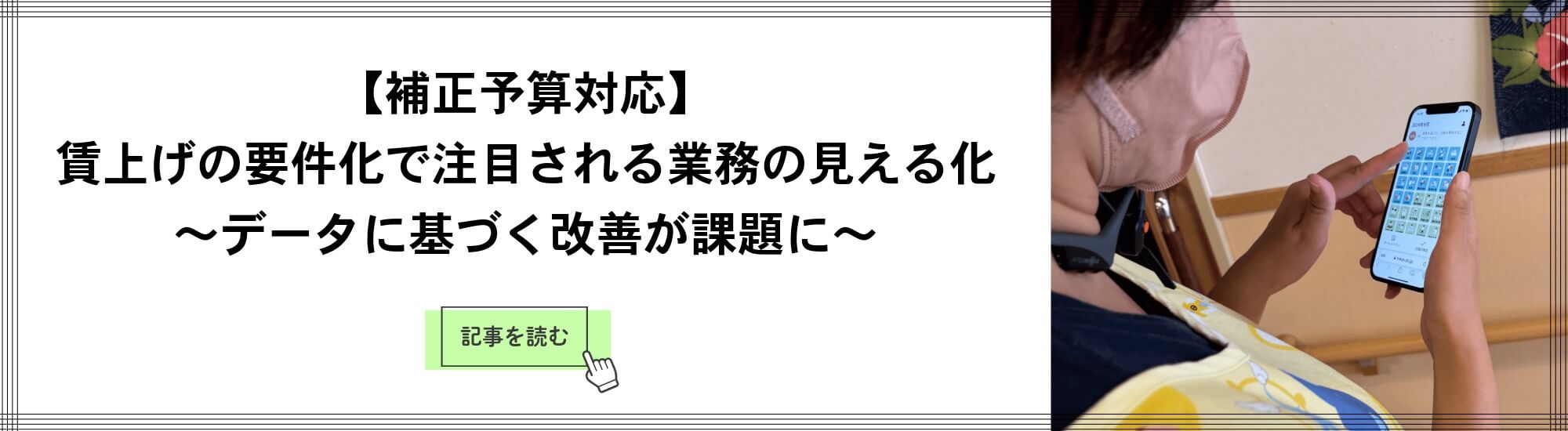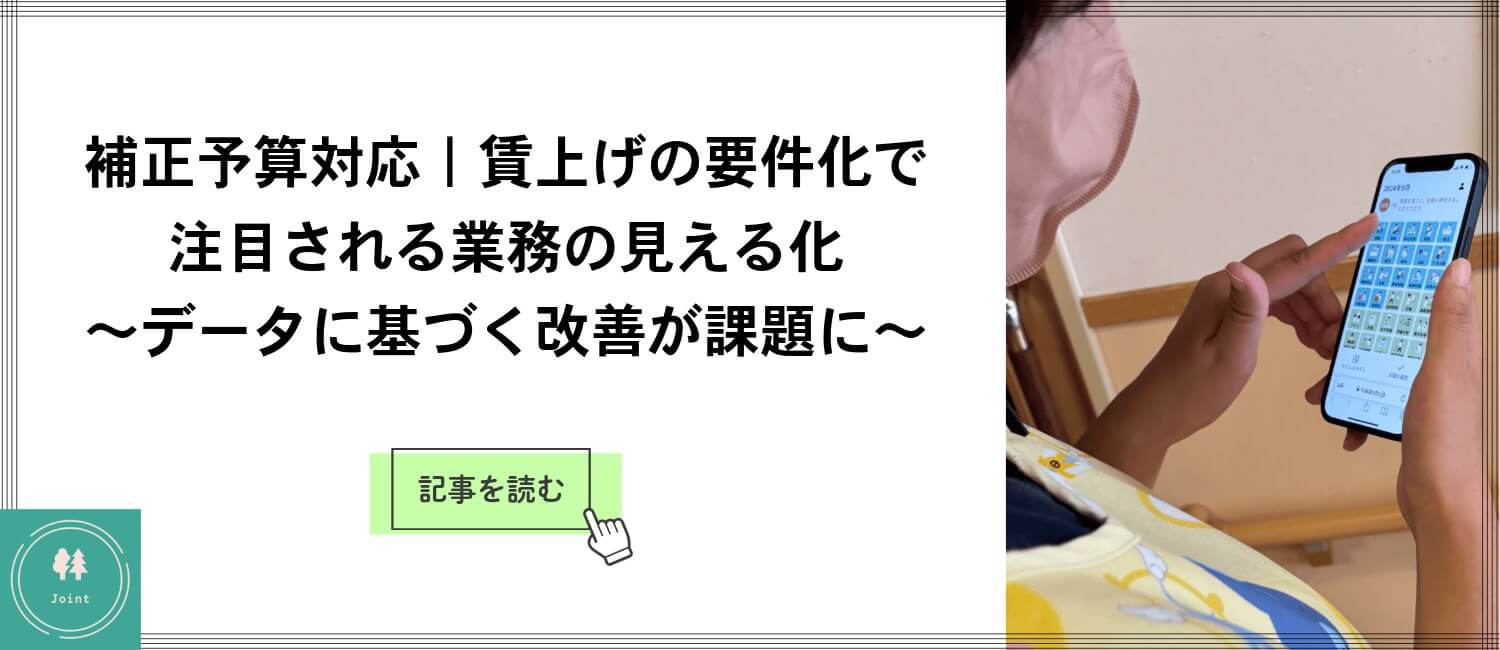厚労省、処遇改善加算の見直しへ検討開始 年末に方向性 介護現場からは「賃上げ実現」の大合唱


厚生労働省は今月から、介護報酬の「処遇改善加算」の見直しに向けた具体的な議論を開始した。【Joint編集部】
来年度の期中改定を見据えた動き。介護職の賃上げを前に進めるために何をすべきか、5日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で委員から意見を聴取した。
賃上げを本当に実施するのか、その規模、幅、財源のあり方などの根幹部分は、今秋に誕生する新たな政権の枠組みが年末までに決めることになるが、今のうちからディテールの議論を重ねていく狙いがある。
政府が見せている前向きな姿勢が後退しないかどうかが焦点だ。
石破政権は今年の「骨太の方針」に、「介護・障害福祉職員の他職種と遜色のない処遇改善に取り組むとともに、これまでの処遇改善の実態を把握・検証し、今年末までに結論が得られるよう検討する」と書き込んでいた。厚労省は今回、こうした「骨太の方針」の記載内容を踏襲する形で、次のような認識を明示した。
「介護など公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある」
◆「過去に類のない異次元の賃上げを」
この日の意見交換は、早期の十分な賃上げの実現を求める委員の大合唱となった。
日本医師会の江澤和彦常任理事は、「来年度は過去に類を見ない異次元の力強い処遇改善が不可欠」と強調。「介護職員がいなくなれば我が国の介護は消滅してしまう。処遇改善の財源が必要不可欠であることは、全員で共有すべきこと」と呼びかけた。
全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「介護業界を崩壊させないためにも、少なくとも他産業に引けを取らない賃上げが必要。来年度からではなく、補正予算などによる今年度内の賃上げ対応も必須」と主張した。
日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長は、「介護職員の処遇改善が図られるのであれば、介護支援専門員については少なくとも同等か、これまで処遇改善加算の対象でなかったことも考慮した対応を強く要望する」と訴えた。
このほか、健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「利用者負担や保険料負担とのバランス、あるいはそれぞれの納得感も非常に大切」とクギを刺した。今後、厚労省は政局の行方も横目に見つつ具体策の議論を進めていく考えだ。