「専門職の集まりである介護事業所でスポットワーカーを活用することは困難ではないか」という過度な思い込みは、もはや時代遅れだ。【Joint編集部】
加速度的な生産年齢人口の減少に伴う人材獲得競争の激化という有事に対し、新たな機運であるスポットワーカーを単なる短期的な労働力としてだけでなく、生産性向上のための中核人材として位置付けることができた介護事業者が生き残る時代になるだろう。
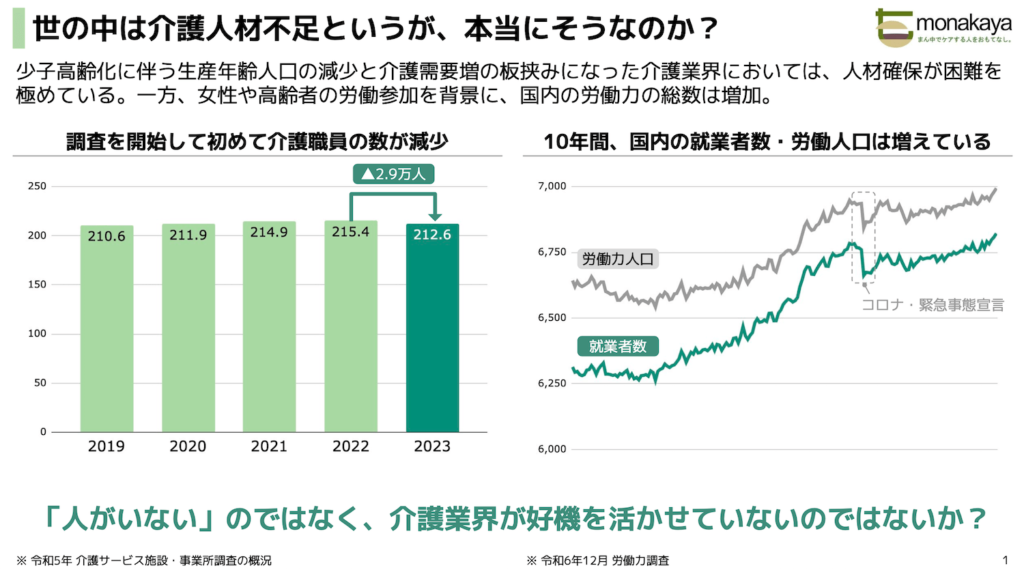
◆ 浸透するスポットワーク
介護現場における人材確保の手法として、スポットワークの活用が急速な広がりをみせている。現に、スポットワーク仲介業者も次々と増え、スポットワーカーとして働く介護有資格者の数も増加の一途を辿る。例えばタイミー。上場を果たした昨年7月時点で、有資格者が前年の1.7倍、2年前の4.2倍にあたる28万5千人に増えたと報告している。
スポットワークとは継続した雇用関係のない働き方で、求職者の働きたい時間と事業者の働いてほしい時間をマッチングするサービス。求職者にとっては、面接なく申し込んだ段階で仕事が確定する手軽さ、都合の良い時間・場所に合わせて働くことができる働き方の柔軟性、給与が原則即払いである利便性が受け入れられ、日本国内におけるスポットワークサービスへの登録者は2200万人を突破した(昨年5月末時点。スポットワーク協会調べ)。
スポットワーク仲介業者が展開するサービスには多少機能差分はあれど、ミスマッチを防ぐ仕組みが基本的に搭載されている。
《スポットワークサービスの基本機能例》
◯ 応募条件の設定によりピンポイントで必要な人材を集めることができる。
◯ 事業者と求職者が勤務後に相互評価を行う。評価結果に基づいた自浄作用が働く仕組みが構築されている。
◯ 無断欠勤や申し込んだ仕事をキャンセルするなどの事業者への迷惑行為を繰り返すと求職者の信用スコアが下がり、働きにくくなる。
◯ 働きぶりがよかった求職者に限って仕事を依頼することができ、中長期に教育コストが下がるメリットを享受できる。
加えて、人材派遣とは異なり、時給や交通費は事業者自ら設定できること、1時間単位から仕事を依頼できることから、人件費コストの最適化も叶う仕組みだ。
◆ 求められる受け入れ環境の整備
ただし、「スポットワークを導入さえすれば全てが上手くいくというものではない」ことに事業者は注意を払う必要がある。また、介護業界にも人材確保の手段としてマッチングサービスが参入・多様化している。事業者自身も、手段に惑わされず、その時々の自分たちの課題に照らし、各スポットワークサービスのメリット・デメットの双方に目を向けたうえで、何が最適解か取捨選択できるようになることが重要だ。
また、スポットワークという働き方の特性上、「いつ、誰が行っても、同じ手順で、無駄なく、求める品質で業務を遂行できる」環境を整える必要がある。スポットワークサービスが複数ある中、どのサービスを選ぶのかという手段の検討から入るのではなく、受け入れるための環境整備を行うことが本質的な効果創出のために重要となる。
スポットワークサービスで掲載されている求人を実際に見てみると、「介護業務全般」としか書かれていなかったり、「入浴介助、食事介助、排泄介助、更衣介助、移動介助、移乗介助…」のように介護業務が羅列されただけの求人が目立つ。
これでは、スポットワークの導入によってシフトの穴埋めという短期的なメリットを享受できたとしても、スポットワークサービスを使えば使うほど業務の属人性が増し、自社スタッフには何も分からない状態になってしまうリスクを孕んでしまう。さらに、仲介業者に支払う手数料の増加や生産性悪化という悪循環に陥るだろう。
◆ 簡単になったタイムスタディが力の源泉に
では、介護事業者は何を行えば良いのか。アプローチはいくつか考えられるが、最もシンプルな方法が「業務の切り出し」だ。従前より国策レベルでタスクシフト/シェアが推進され、業務切り出しについても国や自治体からガイドラインが提示されてきたが、現場レベルで成功した事例は少ないのが実態としてある。
そこで、業務切り出しを加速させる手段としてタイムスタディの実施を提案したい。タイムスタディと聞くと、ストップウォッチを片手に持った職員が別の職員につきっきりで調査を行う絵を思い浮かべる人もいるだろうが、現在はタイムスタディを簡易的に実施できるツールが存在している。
※ タイムスタディアプリ「ハカルト」の詳細はこちら↓
ガイドラインなどに沿って、専門性の有無を軸として行う業務の切り出しも一定の効果はあるが、あくまでも机上で行う静的なものだ。一方、タイムスタディでは人の流れ、オペレーションを動的に把握することができる。タイムスタディを通じて得られた「実際に現場で起こっている事実」をスタート地点に、現場や管理者が一体となって、業務切り出しやその先のスポットワークの活用余地を検討することが、本来求められる生産性向上の姿ではないか。
「専門職の集まりである介護事業所でスポットワーカーを活用することは困難ではないか」という過度な思い込みは捨てる必要はあるが、介護に関わる人材が人間の形をしていれば誰でも良いというわけでは決してない。
現場実態を可視化したうえで、現場の本質的な課題に向き合い、環境改善・小さな工夫を積み重ねた結果として、求職者から見て働きたいと思われる介護事業所になること。そして、生産性向上の成果として、利用者が元気になるケアを提供でき、それを見た求職者が自然と集まってくるような介護事業所になる好循環を生み出せるか否かが、超人材難の時代を乗り越える切り札になりそうだ。
Sponsored by 株式会社最中屋

