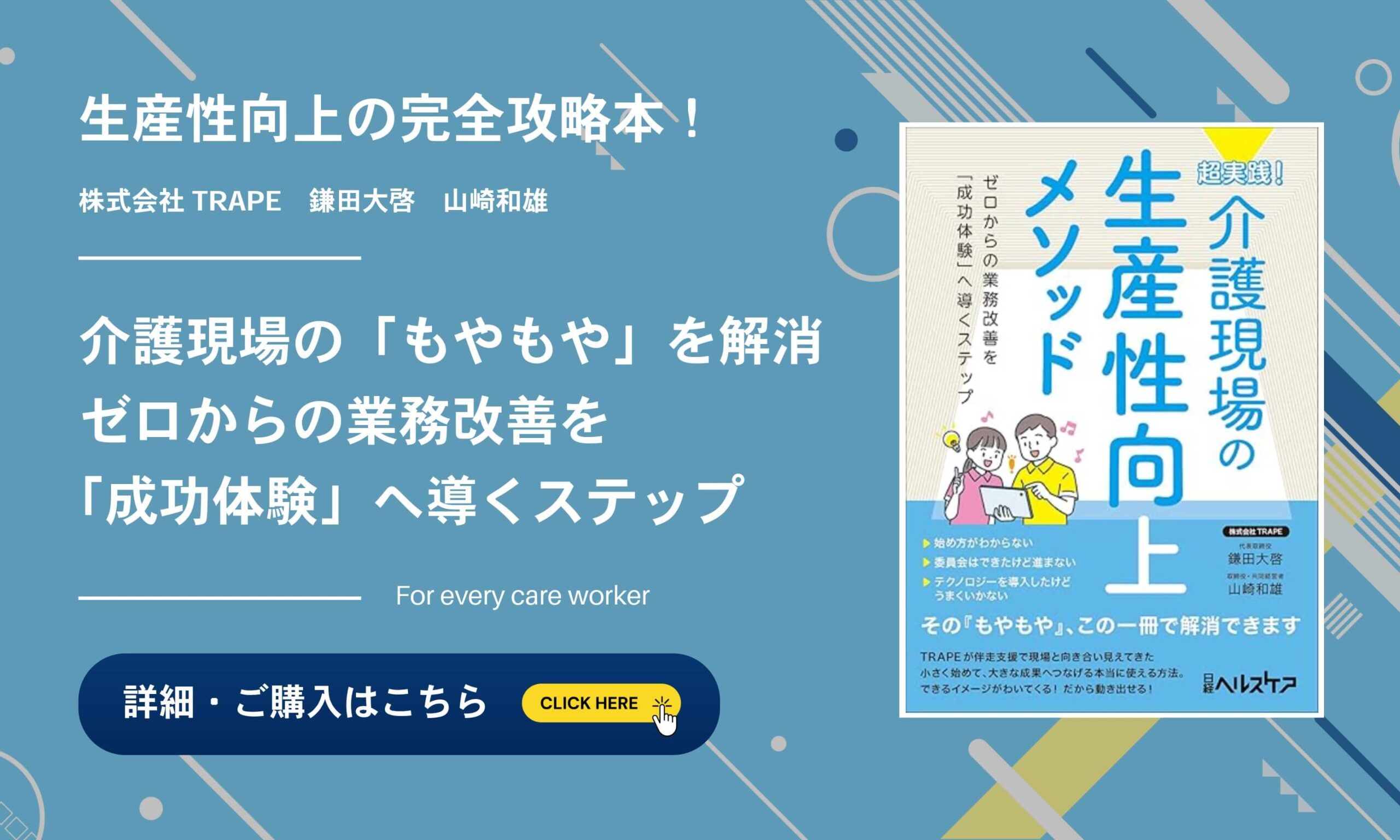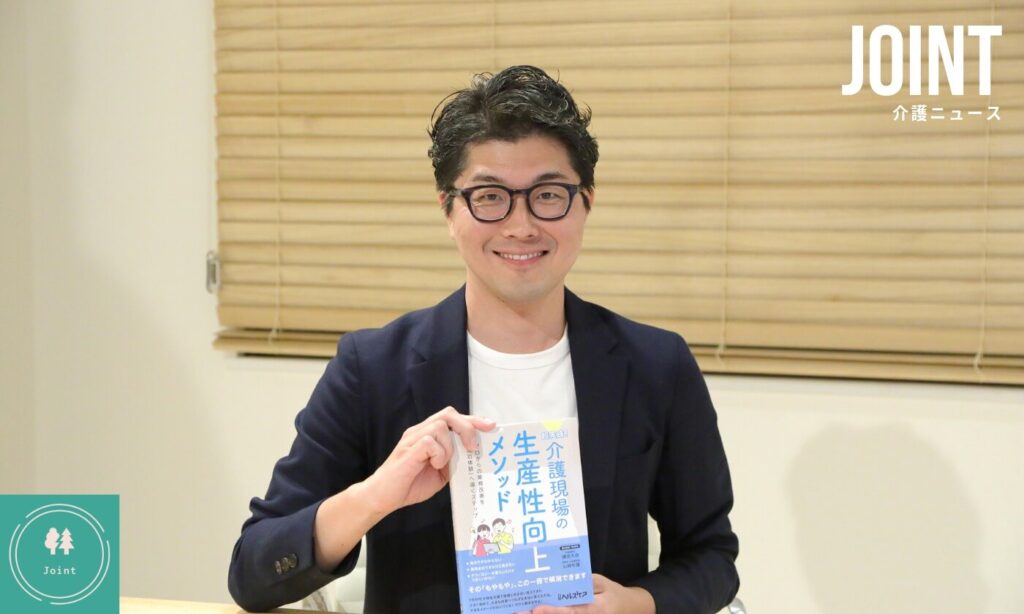
特に難しく考える必要はない。介護現場の生産性向上には、全国各地の積み重ねから確立された体系的な進め方がある。【Joint編集部】
そのノウハウとコツを1冊に凝縮した最強の攻略本が登場した。株式会社TRAPE(トラピ)代表の鎌田大啓氏による新刊「超実践! 介護現場の生産性向上メソッド」だ。
※ 本書の詳細・ご購入はこちら↓から
これは、自宅やカフェでじっくり読み込んで学習する本ではない。介護現場で迷った時に開き、その場面に合ったページを直ちに活用する。そんな極めて実用的な一冊だ。
各ステップの取り組みは流れに沿って整理され、「何から始めればいいか」「自分たちは今どの段階にいるか」「次に何をすべきか」がひと目で分かる。イラストや図解も豊富で、視覚的にすぐ理解できるよう丁寧に作り込まれている。
生産性向上にまだ取り組んだことのない人でも、手に取れば「あ、これならできそう」と感じられるはずだ。介護現場の“あるある”や、多くの人がぶつかる課題・つまずきに寄り添っているため、その時々で必要なアプローチだけを自然に吸収できる。
本書の流れに沿って一歩ずつ取り組めば、誰もがまず小さな成功体験を掴める。その積み重ねが、介護現場をどう変えていくべきかという視界を切り開いていく。
◆ 言葉は広がったけど…

鎌田氏は2017年度から厚生労働省の生産性向上事業に携わり、これまで全国でセミナーや伴走支援を続けてきた。「生産性向上やDXといった言葉はだいぶ浸透した」と語る一方で、手応えは決して十分ではないという。
「自分たちには関係ない」「お金も人も乏しいから無理」。そんな風に最初から距離を置く事業所が多いほか、「やってみたけど成果が得られない」「続かない」「浸透しない」といった声もあまり減っていない。
「だからこそ、そうした事業所・施設の助けになる本、使いやすいツールを作りたかった」。介護現場の良い変化を実感できる成功体験が広がらないまま、「生産性向上」という言葉だけが先行している現状を変えたい ー 。それが執筆の原点だという。
◆「生産性向上」という言葉をいったん忘れよう

本書が最初に提案しているのは、「生産性向上」や「DX」といった言葉をいったん脇に置くことだ。まず最初に、「自分たちは本当はどうありたいのか」を考えることが何より大切だという。
「そもそも、生産性向上は自分たちにとって大きなメリットがある取り組みです。介護現場の皆さんはもっと、自分たちが今より楽になることを考えていいはず」。鎌田氏はこう語る。
動機はシンプルでいい。「もっとゆとりを持ちたい」「働きやすい環境にしたい」「職員の負担を軽くしたい」「ケアに力を注ぎたい」「地域づくりにも関わりたい」。そんな“ありたい姿”を描き、その実現を妨げるムリ・ムダ・ムラ(3M)を見つけ、一つひとつやめていく。必要であれば、テクノロジーもうまく使っていく。
職員がテクノロジーを導入する意味を“自分ごと化”できることで、結果として生産性は上がり、自然にDXへとつながっていく。本書では、個々の事業所・施設が踏み出しやすい一歩から歩き始めることを強く勧めている。
◆「急がば回れ。土台をしっかり」

本書が重要なポイントとして強調していることを、もう1つあげたい。それは「成功のカギは準備が8割」という合言葉だ。
人手不足や業務の肥大化などもあり、少なからぬ介護現場が「頑張るほど糸がこんがらがっていく状況」に陥りがちだ。「準備が8割」とは、そのこんがらがった糸をまず丁寧にほぐすプロセスの大切さを表す。
鎌田氏はこう語る。「介護現場の皆さんは本当に忙しいので、どうしても“すぐ効きそうな解決策”に飛びつきがちなんです。でも、必要な準備をしないで打ち手だけ並べても、ほとんどの場合うまくいきません」。
ここでいう準備とは、チームをつくってありたい姿を共有すること、課題をしっかり整理・分析して話し合うことなどを指す。「急がば回れ。土台がしっかりしているほど、高いところまで登れる」。本書ではこう解説されている。

◆ すべての現場に通じる王道
もっとも、こうした進め方は決して特殊なものではない。介護保険のどのサービスでも、あるいは他の業界でも通用する生産性向上の普遍原理だ。
鎌田氏は「在宅系か施設系かで取り組みの本質が変わるわけではない。特に、最終的な発展段階に至るまでの道程はどのサービスもまったく同じ」と明言した。
この共通性は、厚労省の指し示す方向性とも一致している。国の「生産性向上ガイドライン」は、これまで施設向け、在宅向け、医療系向けと3種類に分かれていたが、今年夏に1冊の共通版に統合された。基本的にどのサービスも同じノウハウで進めるべきことが、改めて明確にされた形だ。
※ 本書の詳細・ご購入はこちら↓から
本書もこの流れを踏まえ、サービス種別や事業所の規模を問わず、どこでも使えるように作られた。誰もが進むべき王道の歩き方が、介護現場に最適化された形で、介護現場の言葉で分かりやすく記されている。
本書は実践書として、国のガイドラインの理解をさらに深める一助となる。全編を通じて、TRAPEがこれまで積み重ねてきた事業所・施設の伴走支援のノウハウが盛り込まれた。例えば課題の言語化、合意形成の工夫、実行計画の立て方、テクノロジーの導入フローなど、様々なポイントについて「どの順番で」「何を話し合い」「どこに気をつけるか」がきめ細かく整理されている。
これは生産性向上の攻略本だが、“伴走支援の教科書”と言ってもいい。事業所・施設のリーダーや経営層だけでなく、外部の支援者にとっても役に立つ。介護現場で多くの成功体験を積み上げてきたTRAPEならではの視点が、要所要所で読者を後押ししてくれる。
◆「今からでも決して遅くない」

鎌田氏は、「もはや生産性向上に取り組まないと生き残れない」と断言する。業界横断的な人材の獲得競争が激化する中で、「変わろうとする事業所・施設には人が集まり、そうでないところからは人が離れていく。今はその差が開いていく局面」とみている。
一方で、「今から始めても決して遅くはない」と強調する。「これまで生産性向上に取り組んでこなかった事業所・施設でも、『変わろう』と決めてできることからコツコツ進めれば、数年で追いつき、追い越せる」と語気を強めた。さらに、「テクノロジーを導入してもうまくいかない事業所・施設も、正しく取り組むことで必ず成果が出せるようになる」と呼びかけた。
重要なのは、いきなり大きなことをやろうとしたり、問題を一気に解決しようとしたりしないことだという。
介護業界では本当にテクノロジーに長けた人は少ない。もしテクノロジーに苦手意識がある場合は、アナログな業務の一部を変えるだけで初手としては十分。ささいな改善が生じれば、周囲も自然に「次はどうする?」という声をかけてくる。
本書は、こうした小さな成功体験をどうすれば安定的に積み重ねていけるのかを、極めて具体的なノウハウ・ステップで導く一冊だ。
「変化するって案外いいものだよね。そんな風に多くの人に感じてもらえたら」。鎌田氏の言葉通り、本書は前に進もうとする介護現場に寄り添う確かな伴走者となるはずだ。
※ 本書の詳細・ご購入はこちら↓から
Sponsored by 株式会社TRAPE