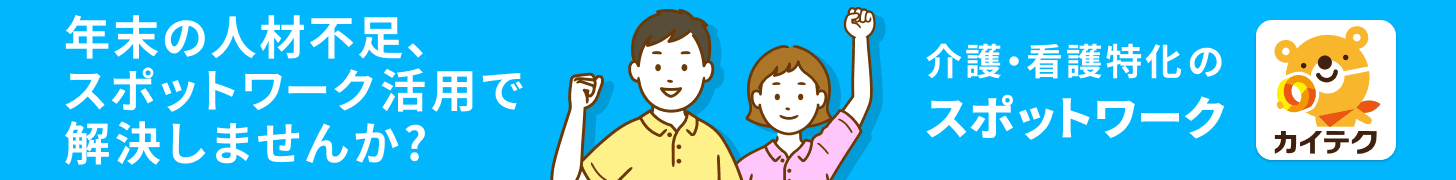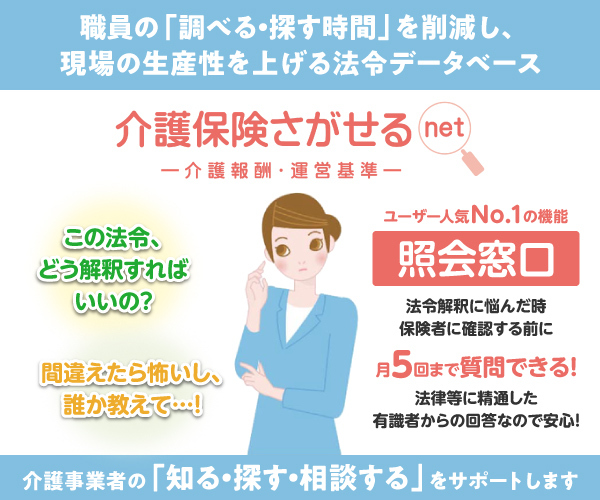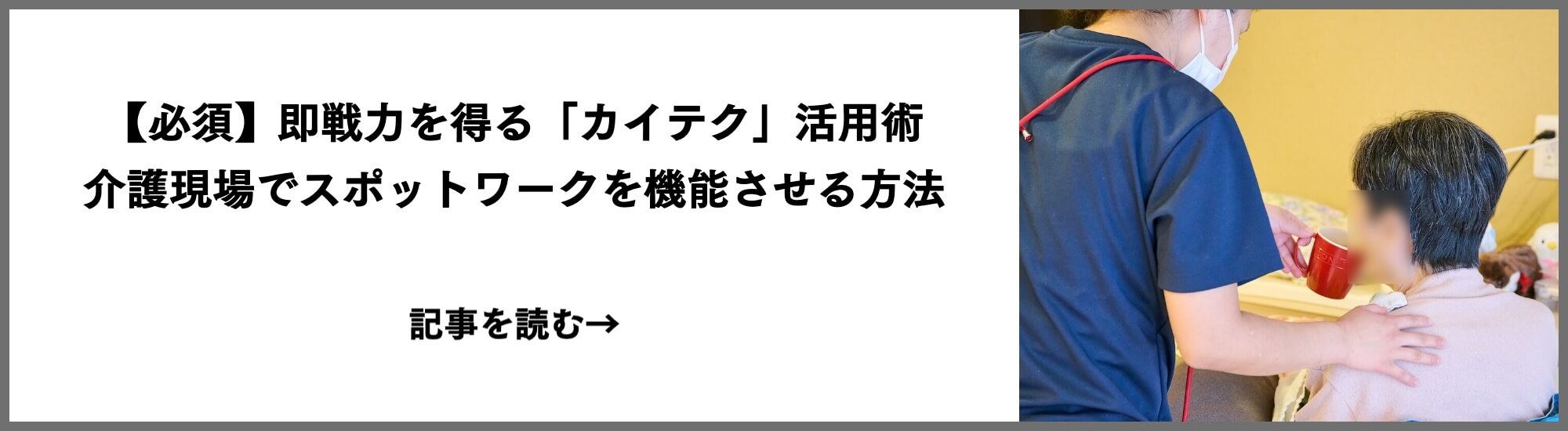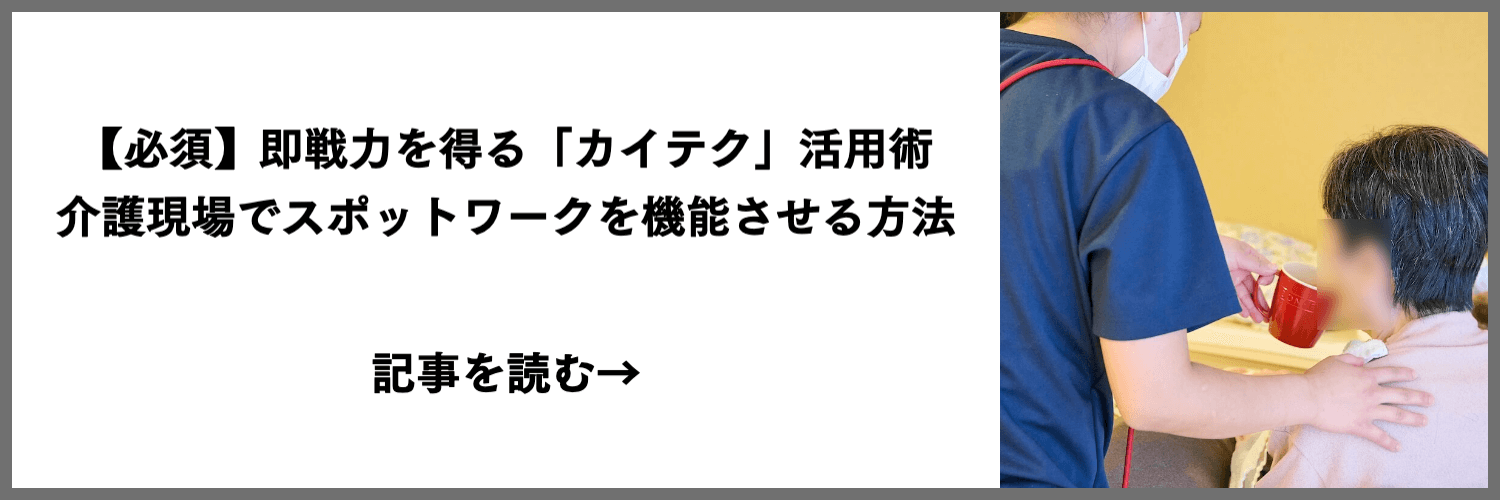数々の現場で積み上げられた豊かな経験も、言葉にしなければ活かしきることはできません。いま、その知を広く共有するための専門職の挑戦が始まっています。【山田剛】
日本介護支援専門員協会では、2022年度から「介護支援専門員の実践知の言語化事業」を開始し、今年度からは教材化を含む本格的な展開を予定しています。
この取り組みは、介護支援専門員の専門性向上と人材育成を目的とするもので、介護保険がスタートしてからの20年以上にわたる実践の中で蓄積された知識・技術・思考を体系的に整理し、共有することを目指しています。
この事業に取り組み始めた背景には、介護支援専門員の社会的地位や専門職としての質の向上を図る中で、実践知の継承が十分に行われていないという課題に直面したことがあります。特に、ケアマネジメントの思考プロセスや判断の根拠は暗黙知として個人に留まりがちで、教育やスーパービジョンの場でも共有が困難でした。
◆ 暗黙知を見える化し、次代へつなぐ
そこで協会では、熟練者の実践を「見える化」することで、学習困難な領域の理解を促進し、後進の育成に資する仕組みを構築しようとしています。
具体的には、全国のベテラン介護支援専門員100名以上に依頼し、その人たちを16グループに分けて、インテークやアセスメントなど7つのテーマに基づき、約120時間に及ぶグループミーティングを実施しました。
そして、全ミーティングを逐語録化し、その膨大な逐語録から、実践知の抽出・分類・統合・整理を行いました。抽出された実践知は、文言の修正やカテゴライズのチェックを経て、現在、解説を加えた形での整理を進めている段階です。
このように構造化された実践知は、日々のケアマネジメント業務で活かせるだけでなく、教育コンテンツとしての活用も可能となり、介護支援専門員の養成や生涯学習体系の中で、実践的な学習内容を強化することにつながります。また、ケアマネジメントの質の評価指標を作成するためのデータベースとしても活用される予定です。
さらに協会では、これらの実践知の「書籍化」や「AIを活用したアプリケーション化」も検討しています。これにより、個人では学びにくい領域や、人に聞きづらい内容についても、先輩たちの成功例や考え方をいつでも、より簡単に知ることができるようになるでしょう。
これは、介護支援専門員の基本的姿勢の明示や専門性のさらなる向上にもつながります。実践知の言語化は、未来への知の継承を可能にするとともに、専門職としてのアイデンティティの再構築にも結びつく取り組みで、極めて意義の大きな挑戦だと考えています。
今後も是非、多くの関係者の皆さまにご関心を持っていただきたいと思います。