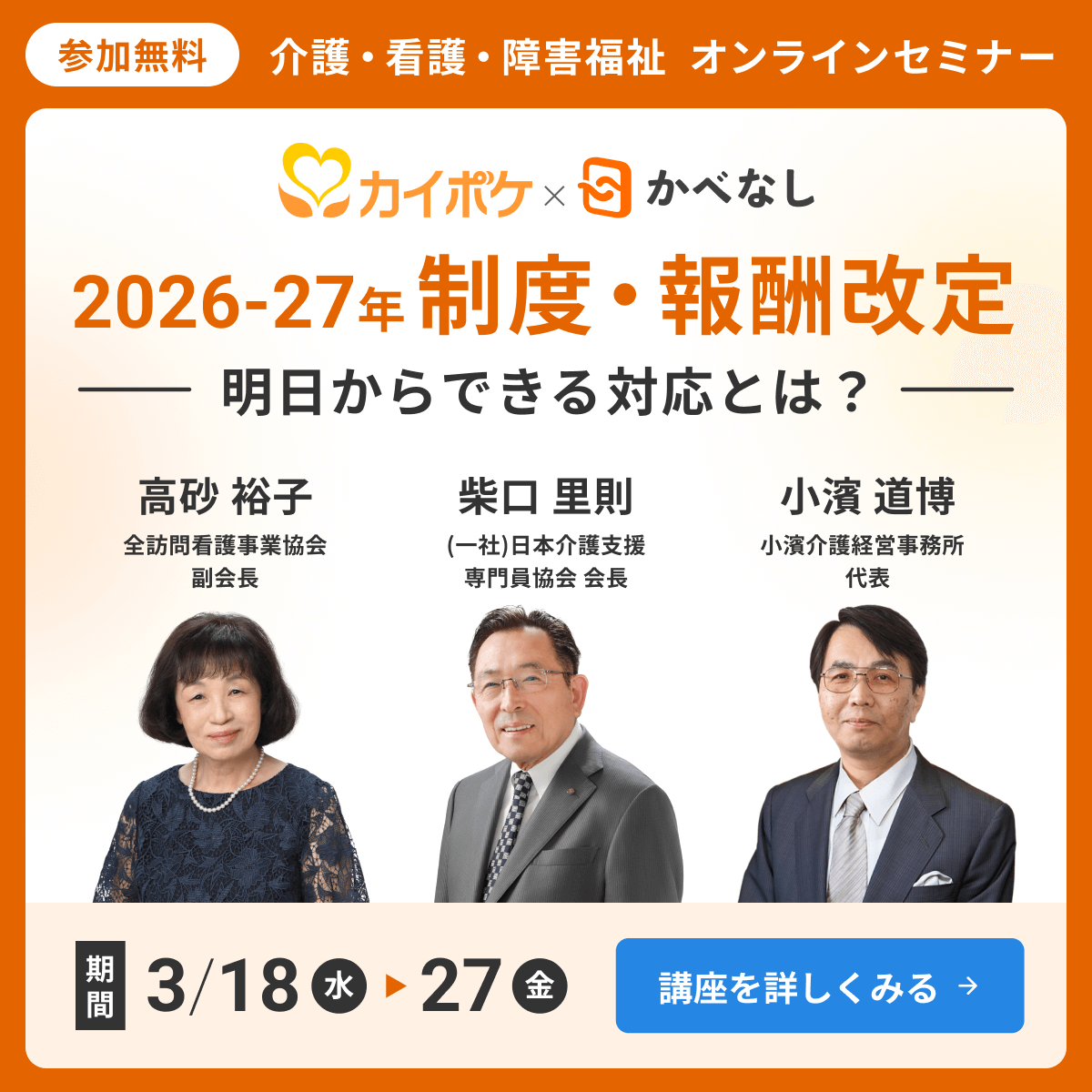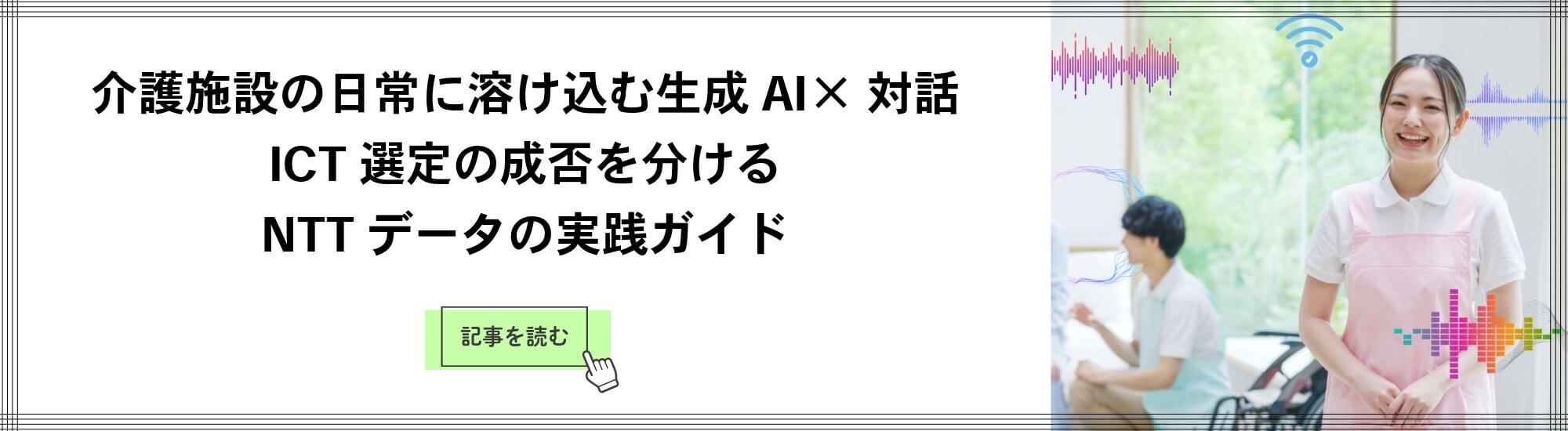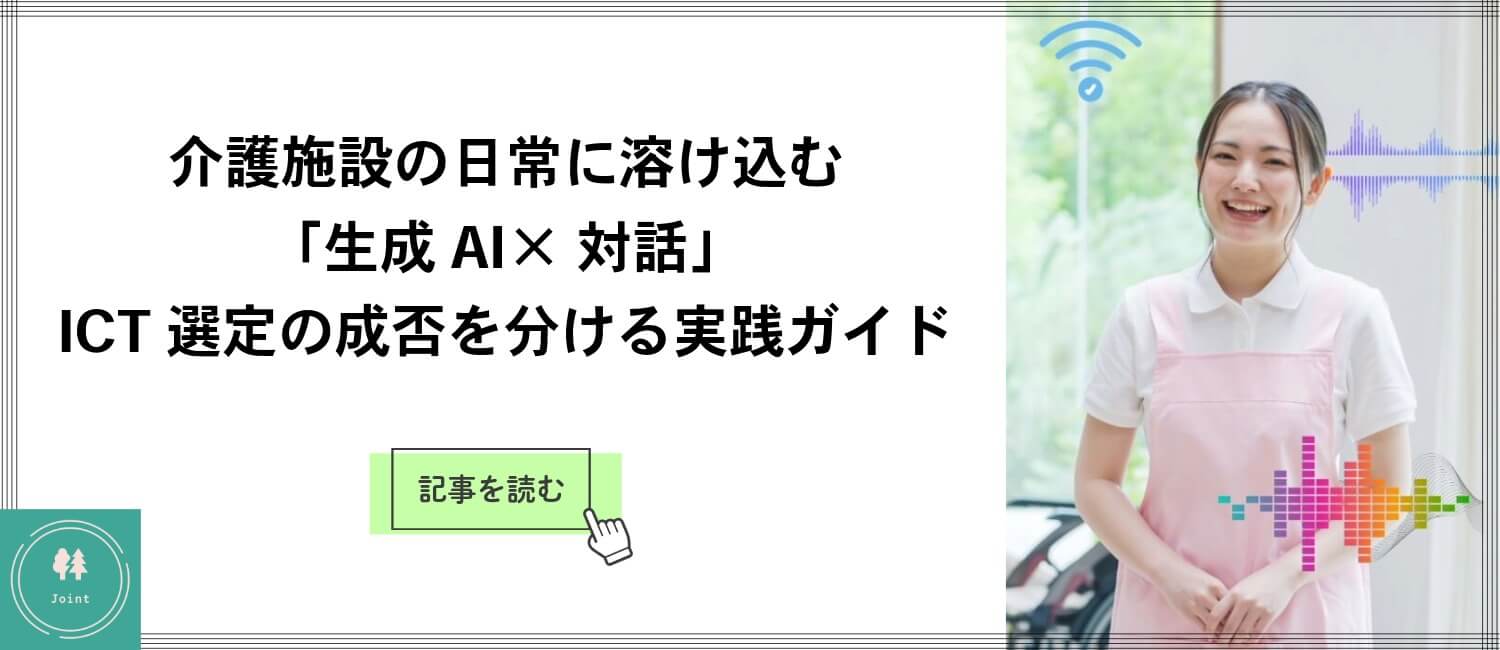【青柳直樹】夏も要警戒! 広がる新型コロナ感染 新株「ニンバス」の特徴と介護現場に必要な備え


この夏、新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。8月17日までの1週間に全国の定点医療機関から報告された患者数は、1医療機関あたり6.3人。9週連続で前週から増加しています。【青柳直樹】
感染者の多くは軽症ですが、介護施設を中心に注意が必要な状況です。特に今夏は、新しい変異株「ニンバス(NB.1.8.1)」の出現が報じられ、現場には不安が広がっています。

青柳直樹|医師。2017年にドクターメイト株式会社を創設。日本ケアテック協会の理事も務める。介護施設が直面する医療課題に対応すべく、オンラインの医療相談や夜間のオンコール代行などのサービスを展開中。介護職の負担を減らすこと、利用者の不要な重症化、入院を減らすことなどに注力している。
◆ 新株「ニンバス」の特徴
ニンバスは全く新しいウイルスではなく、以前からあるオミクロン株の一種です。特徴としては、従来株に比べて伝播性が高いこと、より広がりやすいことが指摘されています。
重症度が顕著に高まっているわけではありません。ただし、死亡例の大半は依然として体の衰えた高齢者です。介護現場にとっては、引き続きリスクの高い感染症であることに変わりはありません。
また、今回の流行で目立つのは「強い咽頭痛」です。唾を飲み込めないほどの痛みを訴える例も報告されており、これまでの「発熱中心」の症状から変化がみられます。喉の痛みを訴える利用者が出た場合に、早期に検査などの対応をとる体制を整えておくことが求められます。
これまで、感染症の流行は冬場を中心に語られてきましたが、新型コロナには夏と冬の2度の流行期があります。インフルエンザやノロウイルスと異なり、夏も警戒すべき感染症である点も特徴です。
「夏は感染症が少ない」。そんな従来の意識も残る中で、この時期に感染対策への注意が緩みやすい傾向があることも懸念されます。介護現場では夏を「第2の流行期」として認識し、十分に備えることが重要になるでしょう。
◆ 求められる対策
まず、最も基本的で有効な対策は、利用者に免疫をつけてもらうことです。特に、非常に高齢の利用者、透析を行っているなど基礎疾患のある利用者に対して、ワクチン接種を優先的に進めていくことが欠かせません。ワクチンは感染そのものの予防に加え、発症しても症状を軽くする効果があることが、各国の保健機関から報告されています。
また、介護施設などで見落とされがちな対策は「換気」です。夏場は暑さを避けるため、どうしても窓を閉め切る時間が長くなりますが、空気が滞留する環境は感染を広げやすくします。
このため、CO2濃度1000ppm以下を目安に、定期的に換気を行うことが推奨されています。エアコンを使用していても、定期的に窓を開けて空気を入れ替える工夫が必要です。
このほか、職員教育の徹底も欠かせません。手指消毒、ゾーニング、清掃物品の取り扱いなどは基本的な感染対策ですが、時間の経過とともに意識が薄れがちです。
厚労省や自治体が提供する教材・動画を活用し、年2回程度は全職員で再確認する機会を設けることが望ましいでしょう。職員の入れ替わりも多い介護現場では、繰り返し教育することがリスクを減らします。
予防と並んで大切なのは、発生時の対応フローをあらかじめ整備しておくことです。発熱や低酸素に加え、今回のように「強い咽頭痛」が見られた際の対応を明確にし、迅速な検査・ゾーニングにつなげることが必要です。また、協力医療機関との連携を事前に確認しておくことも欠かせません。
◆ 再度の意識づけを
介護施設には既に、一定の感染対策の実施が運営基準として組み込まれています。しかし、日々の業務に追われる中で、どうしても形骸化してしまう場面もあります。今夏の感染拡大は、改めて意識を引き締めるよい機会と捉えるべきでしょう。
特に、冬の流行期を前にした今の時期に対応を徹底しておけば、次の流行に備える大きな力となります。感染症は常に新しい変化を伴いますが、「夏も油断しない」「基本を徹底する」という姿勢こそが、介護現場を守る第一歩です。
高齢者の命と生活を守るため、再度のあの頃の警告を胸に刻み、運用を徹底していく必要があります。