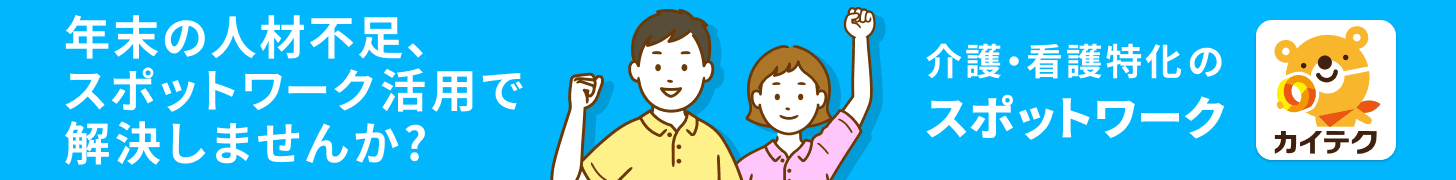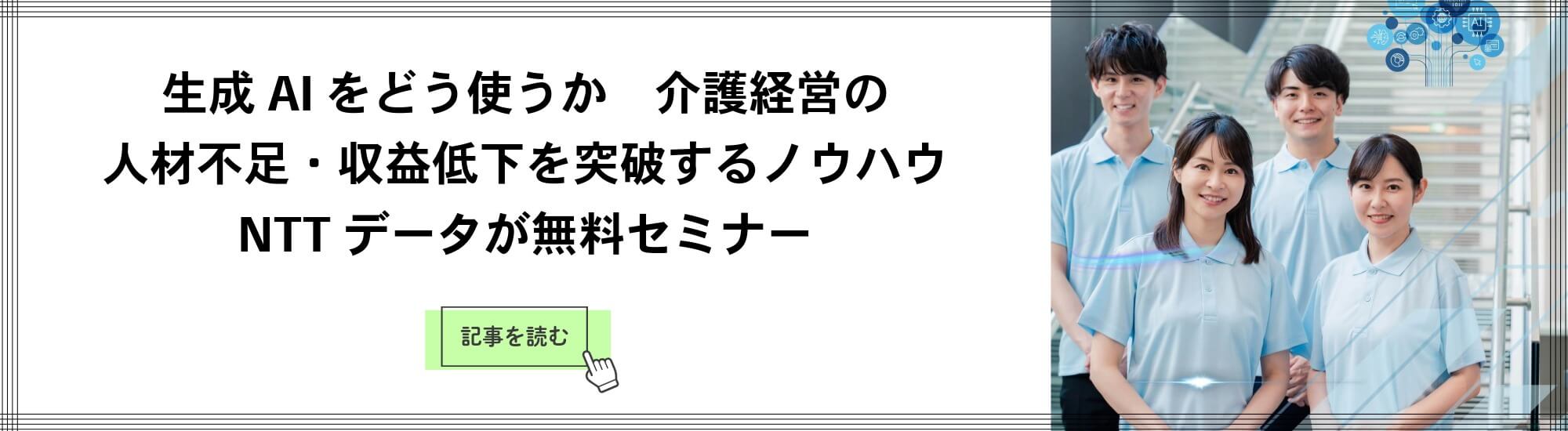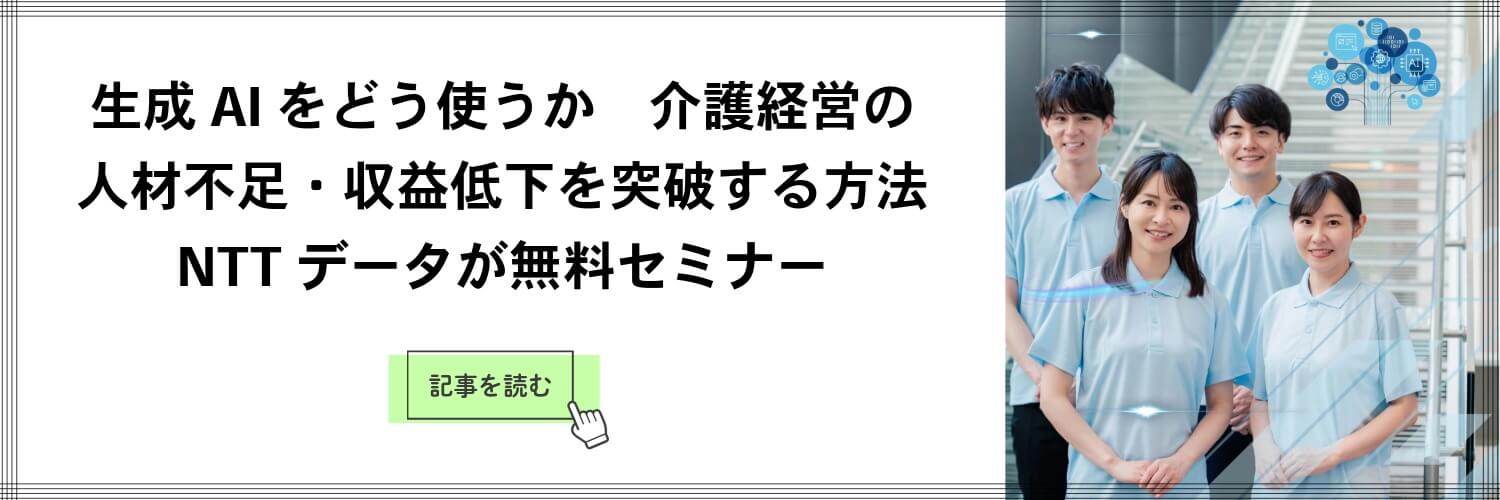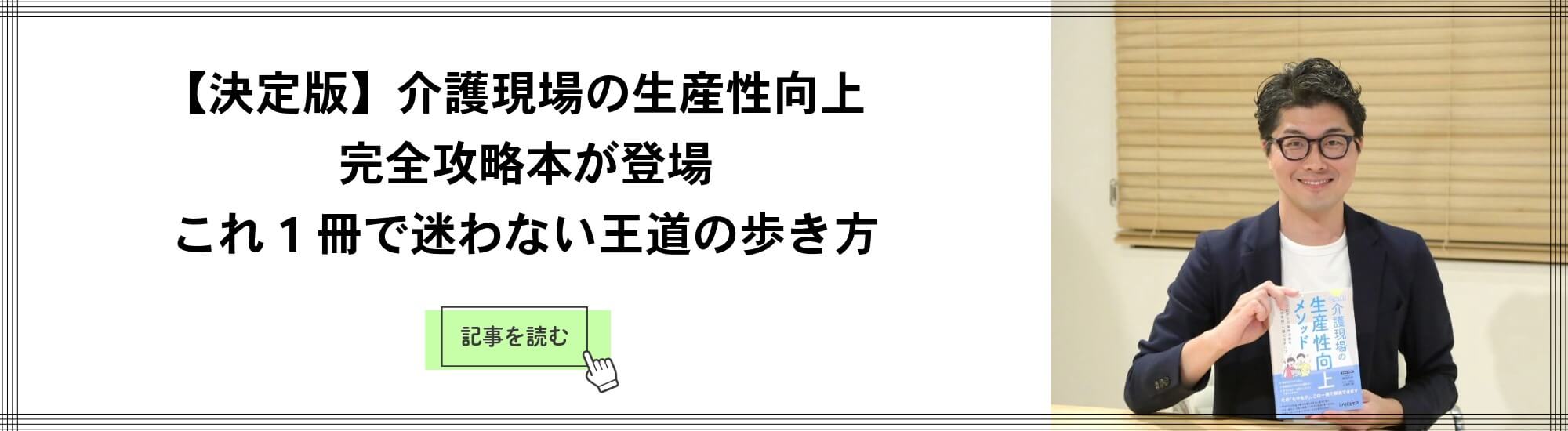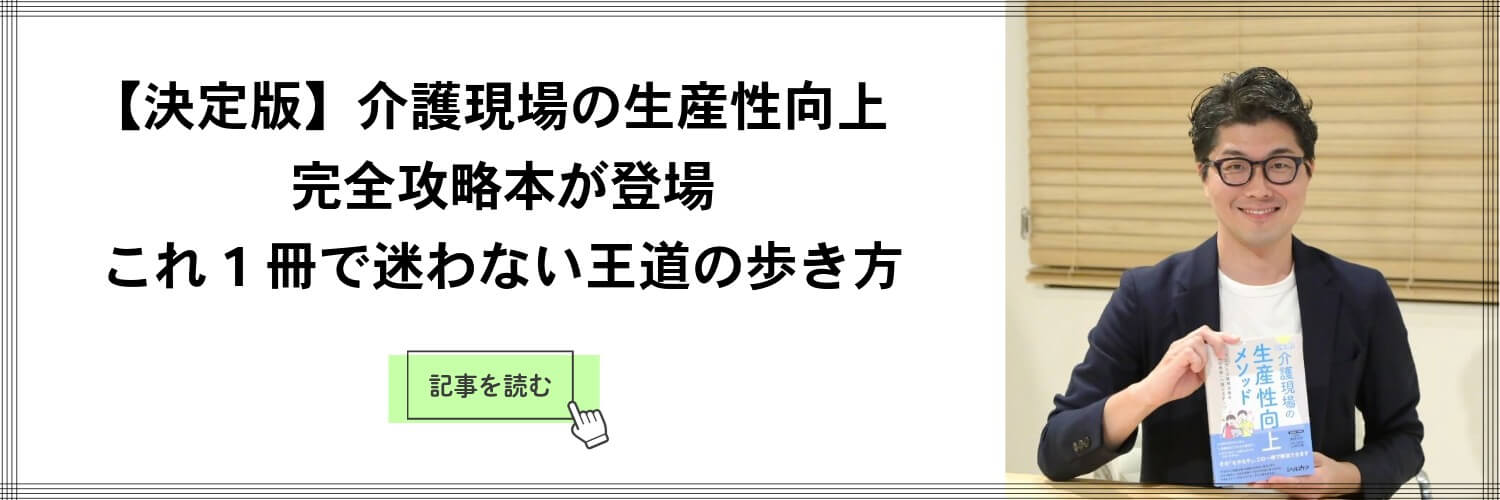【片岡眞一郎】介護現場の生産性向上は次のステージへ 業務効率化の先に広がる新たな展望


今年6月、厚生労働省は介護分野の「省力化投資促進プラン」を公表した。
このプランは、最低賃金の引き上げによる影響が大きい業種を対象に、生産性向上の目標や支援策を定めたものである。介護分野では、2029年までにICT・介護ロボットなどの導入事業者の割合を90%に引き上げるといったKPI(重要業績評価指標)が設定されている。【片岡眞一郎】
本プランでは、これまでの実証事業の成果に基づき、介護記録ソフトやケアプランデータ連携システムによる事務作業の効率化、見守り支援機器を活用した夜間巡視の最適化などが有効であると記載されている。
しかし、本プランが特に重視しているのは、単なるテクノロジーの導入に留まらず、その活用を通じて「業務時間の削減やケアの質の向上」といった具体的な成果に結びつけることだ。
「ケアの質の向上」の定義をどう考えるかという点はあるが、介護保険法の第1条が示す「高齢者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む」という基本理念に立ち返ることが、より重要になってくるだろう。
◆「効率化」から「ケアの質」へ
施設系サービスを中心に、テクノロジーの導入による業務改善は進みつつあり、職員の負担軽減や残業時間の削減といった成果も見受けられる。しかし、「業務効率化」の事例に比べ、「ケアの質の向上」にまで踏み込んだ事例はまだ多くはないように感じる。
生産性向上の議論においては、職員の業務負担の軽減に焦点が当たりがちだが、生産性向上ガイドラインでは、「介護の価値を高めていく」ことが謳われている。本来目指すべきは、生産性向上により創出された時間を活用し、利用者一人ひとりと向き合う時間を増やすなど、より質の高いケアの提供につなげることだ。
「質の高いケア」とは、介護保険法の理念が示す通り、利用者の有する能力が一人ひとり異なることを踏まえ、その人らしさを尊重した「個別ケア」を追求することではないだろうか。
こうした中、ケアの質の向上に力を入れ始めた先進的な動きも出てきている。
例えば東京都では、科学的知見に基づき、高齢者が“自分らしく生きる”ためのケアを行う介護サービス事業者を支援する「自立支援に向けた事業者の取り組み促進」事業を開始している。これは、高齢者の自立支援に向けた取り組みを行う介護事業所や施設に対する研修などの支援、成果の評価分析、都へのフィードバックができる事業者を対象としている。
◆ ケアの質の向上を実現するテクノロジーの活用
テクノロジーの活用も「ケアの質の向上」に寄与することができるだろう。
今年度の内閣総理大臣表彰を受けた特別養護老人ホーム「もくせい」では、シートセンサー型見守り機器の活用により、巡視時の訪室回数を減らすことで、業務効率化を図っている。さらに、利用者が覚醒しているタイミングで排泄介助を行うことで、従来の夜間排泄定時介助を廃止し、個別ケアへと転換した。
また、レクリエーションを実施した日は、シートセンサー型見守り機器のデータから夜間の覚醒がほとんど見られないことが確認されている。こうしたデータを活用することで、レクリエーションが単なる「楽しみ活動」にとどまらず、身体機能や活動状態にまで影響を与えることが明らかになった。
また、特別養護老人ホーム「高寿園」では、夜間の定時おむつ交換について、職員にとっては効率的な業務である一方、利用者の睡眠を妨げる一因にもなり得ると捉え、改善に取り組んでいる。利用者一人ひとりの排泄リズムをデータで把握し、高性能な紙おむつを一部の利用者に導入した。
その結果、夜間のおむつ交換回数が減り、職員の負担が軽減されただけでなく、利用者の睡眠が安定し、日中の活動性が向上するという効果も得られている。
昨年度に内閣総理大臣表彰を受けた特別養護老人ホーム「六甲の館」では、全居室・浴室・トイレ・静養室に天井リフトを導入し、「寝かせきり」にしない介護に取り組んでいる。
リフトの活用は、職員の腰痛予防に役立つだけでなく、利用者の離床機会を増やす効果もある。職員が腰痛を恐れて移乗介助をためらうことがなくなれば、より積極的に利用者をベッドから起こし、リビングでの時間や活動を促すことができる。その結果、利用者の心身機能の維持・向上や重度化の防止につながる。
重度の利用者に対してもリフトのメリットは大きい。人力での移乗介助では2~3人を呼んで集まる時間が必要となるが、リフトなら1人で安全に行うことができる。
また、人力で抱える場合は利用者の足元が見えず、移乗時に内出血や皮膚剥離などの事故が起こりやすいが、リフトを使うことでそのリスクを大幅に減らせる。移乗時の事故報告件数が減少したことは、利用者にとって安心につながるだけでなく、職員にとっても事故報告書の作成に費やしていた時間をレクリエーションやコミュニケーションに充てられるという効果を生んでいる。
◆ 生産性向上の新たなステージ
生産性向上が進むと「直接介護時間を増やすこと」につながるが、究極的には、質の高いケアが進み、ADLが向上し、利用者が自身の力でできることが増えれば、結果として「直接介護時間は減っていく」のかもしれない。
施設サービスにおける生産性向上の取り組みは、一つの段階を終え、次なる進化の時期を迎えている気がしてならない。
これからは、単なる業務効率化に留まらず、自法人の強みや理念に基づき、「いかにして利用者の尊厳を保持し、その人らしい生活を支援するか」というケアの質の向上の視点から、テクノロジー活用とケアのあり方を再構築していくことが、これまで以上に重要になってくるだろう。