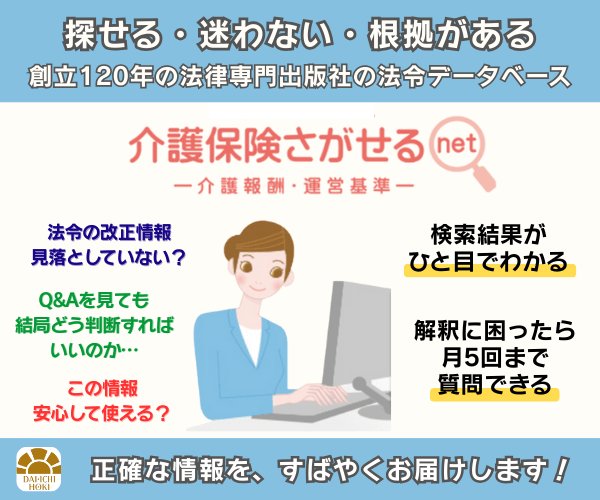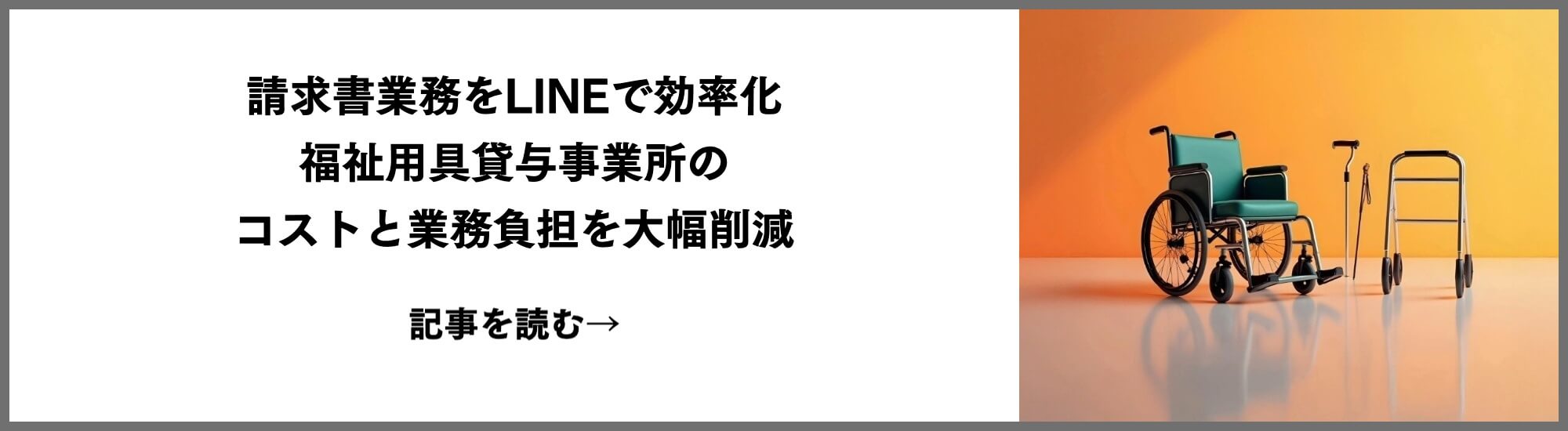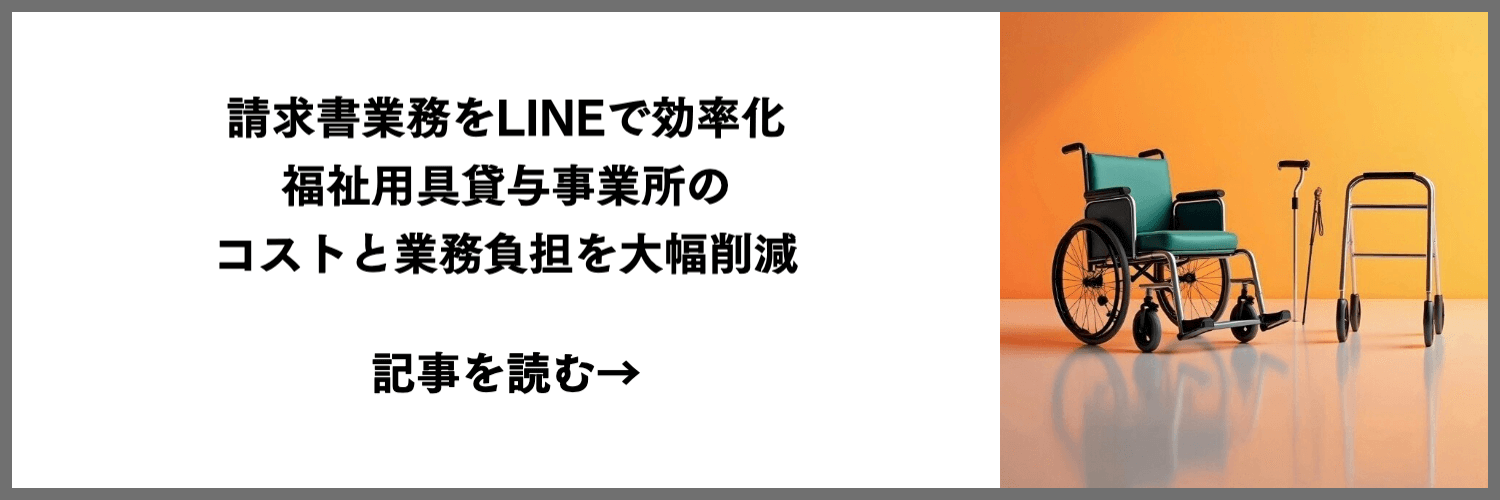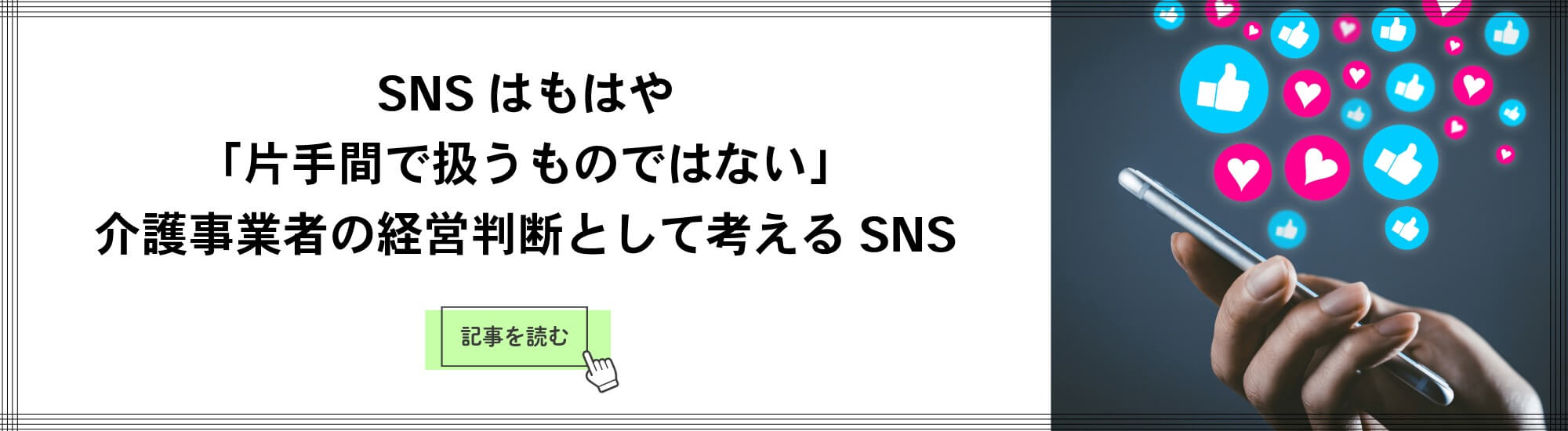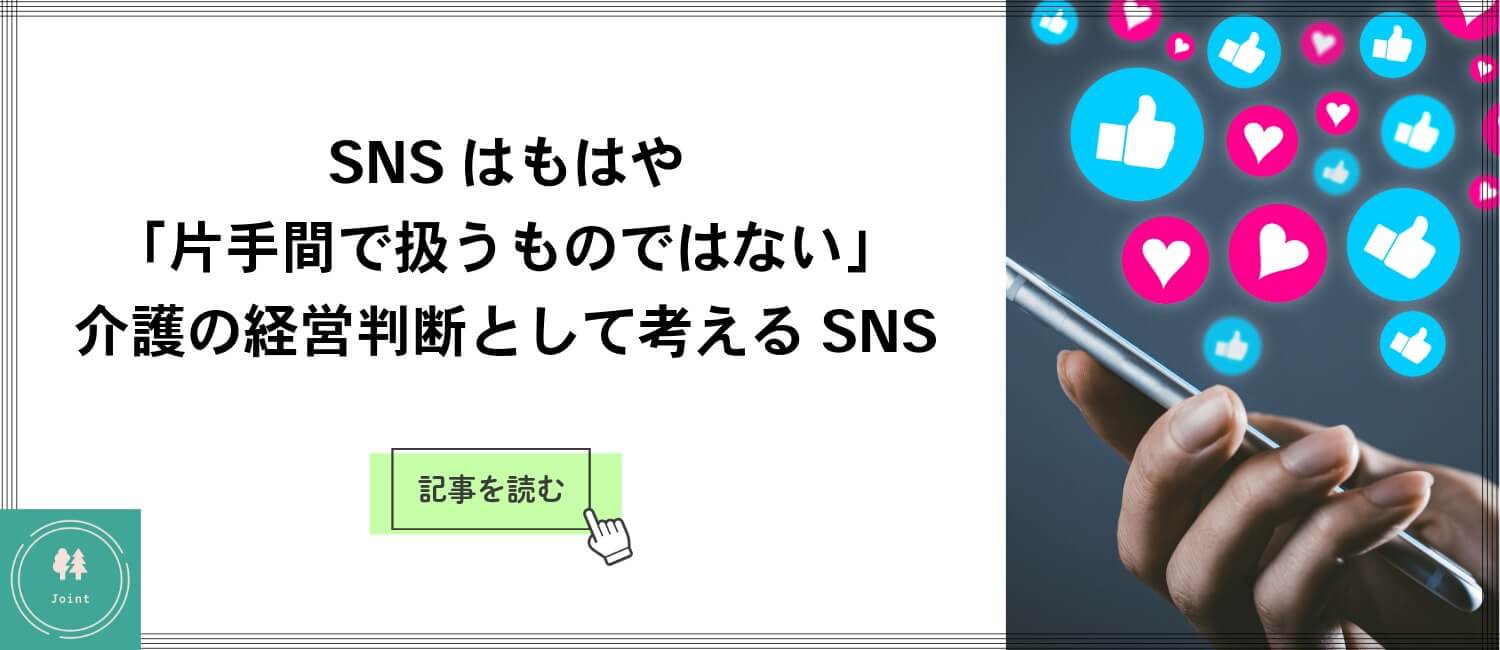介護費どう支える? 利用者負担の引き上げに賛否 給付と負担、難しい選択のとき


厚生労働省は29日、次の2027年度の介護保険制度改正に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で、給付と負担のあり方を俎上に載せた。介護職の賃上げや事業所の支援が急がれるなか、膨張を続ける介護費を社会でどのように賄っていけばいいのか、という本丸の議題だ。【Joint編集部】
「最近、社会保障の負担をめぐる世論は大きく変わった。現役世代が支えきれる制度にしていかないといけない」
委員を務める一橋大学国際・公共政策大学院の佐藤主光教授はこう述べた。続けて、「年齢で考えるのではなく、個々の負担能力に応じて適切に負担していただくということが筋ではないか」と投げかけた。
厚労省は具体的な論点として、例えば利用者負担を引き上げることの是非をあげている。利用者の9割超が1割負担となっている現状(*)を改め、2割負担、3割負担の対象者を拡大するか否かを検討していく構えだ。
* 厚労省の提出資料によると、利用者に占める3割負担の人の割合は3.6%、2割負担の人の割合は4.6%にとどまっている。
政府は今年の「骨太の方針」に、この懸案の結論を今年末までに得ると明記している。最終的な判断は、今秋に生まれる新たな政権の枠組みが年の瀬に下す見通しだ。
◆「断じて容認できない」
今回のディスカッションでは、所得に応じた利用者負担の引き上げを断行すべきという声があがった。
日本経団連の井上隆専務理事は、「日本経済全体のバランスで見て、やはり現役世代の負担が非常に重くなり、これが成長を阻害しているという大きな問題意識がある」と持論を展開。健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「現役世代の負担は既に限界に達している。利用者負担の見直しを確実に実施していただければ」と求めた。
一方で強い反対意見も出た。
認知症の人と家族の会の和田誠代表理事は、「利用者負担の引き上げは、物価高などで生活が苦しい高齢者の家計を直撃し、必要な介護サービスの利用控えに直結する」と問題を提起。「断じて容認できない」と強調した。
また、民間介護事業推進委員会の山際淳代表委員は、「介護サービスは長期にわたり利用し続けるもの。利用者負担を引き上げると利用控えが起こり、状態の悪化を招き、結果的に費用が増加するという懸念が拭えない。高齢者の生活実態を踏まえた丁寧な議論を」と促した。
このほか、UAゼンセン日本介護クラフトユニオンの染川朗会長は、「金融資産の保有状況なども含め、負担能力を総合的に判断することが必要」と主張。連合の小林司総合政策推進局生活福祉局長は、「受給者と被保険者の範囲を拡大する検討も中長期的な視点から重要」と提言した。
また、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「事業所の経営、介護職の処遇、利用者負担、保険料負担、どれも厳しい。制度自体が揺らいでおり、公費を含む新たな財源の投入が避けられない」と訴えた。