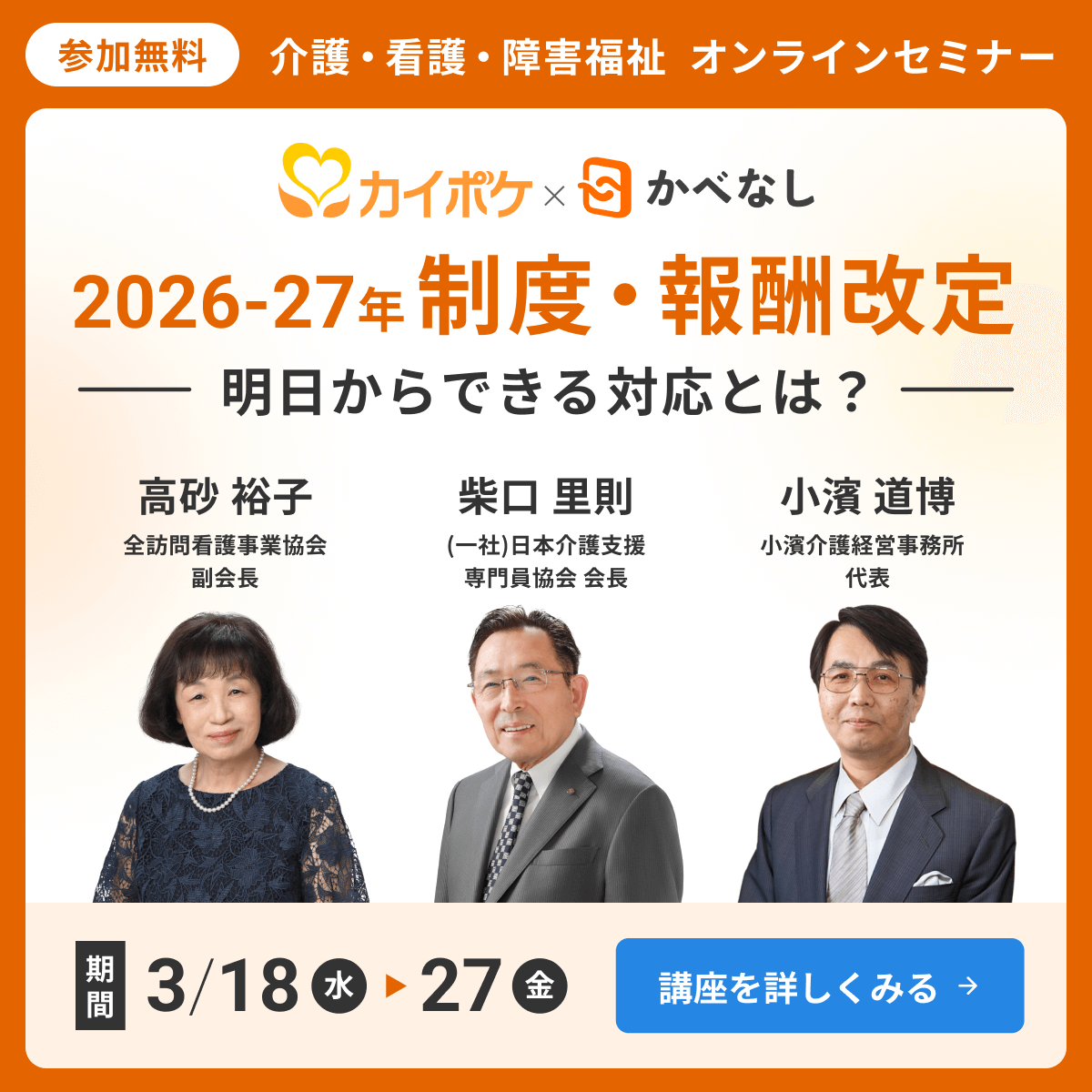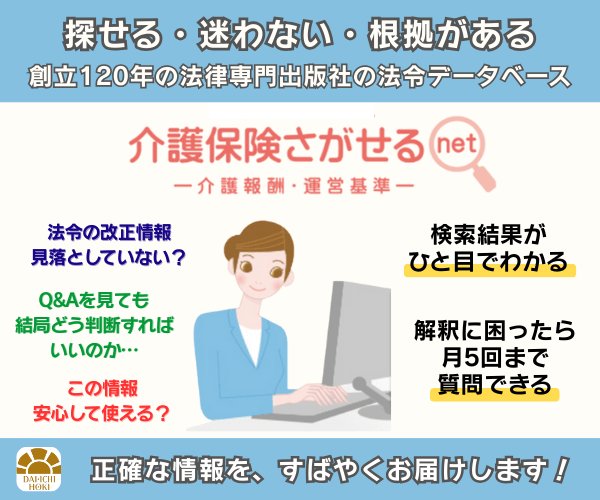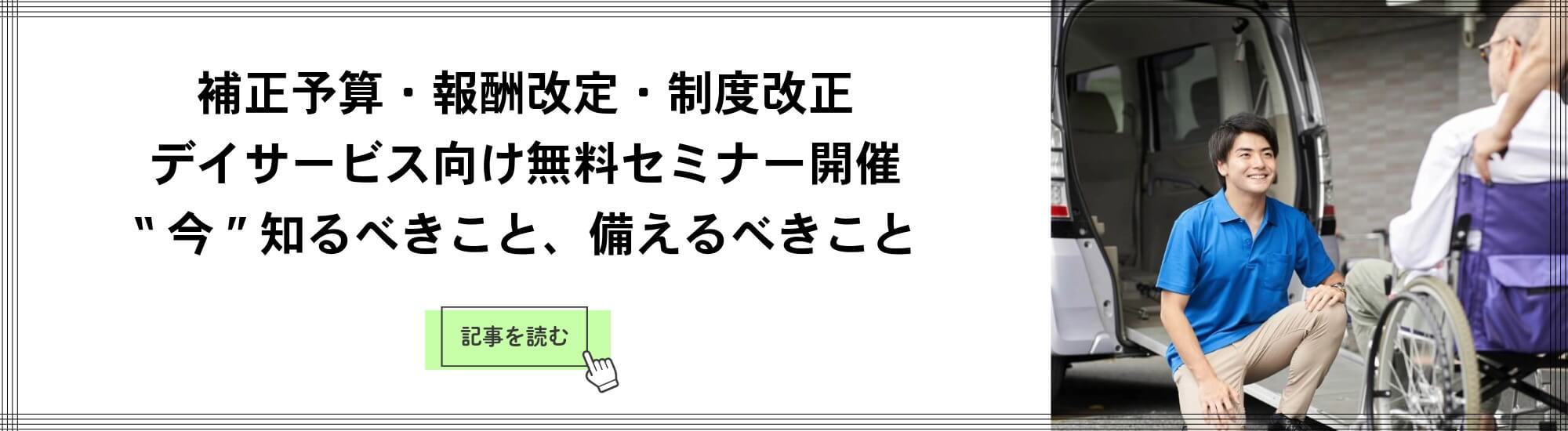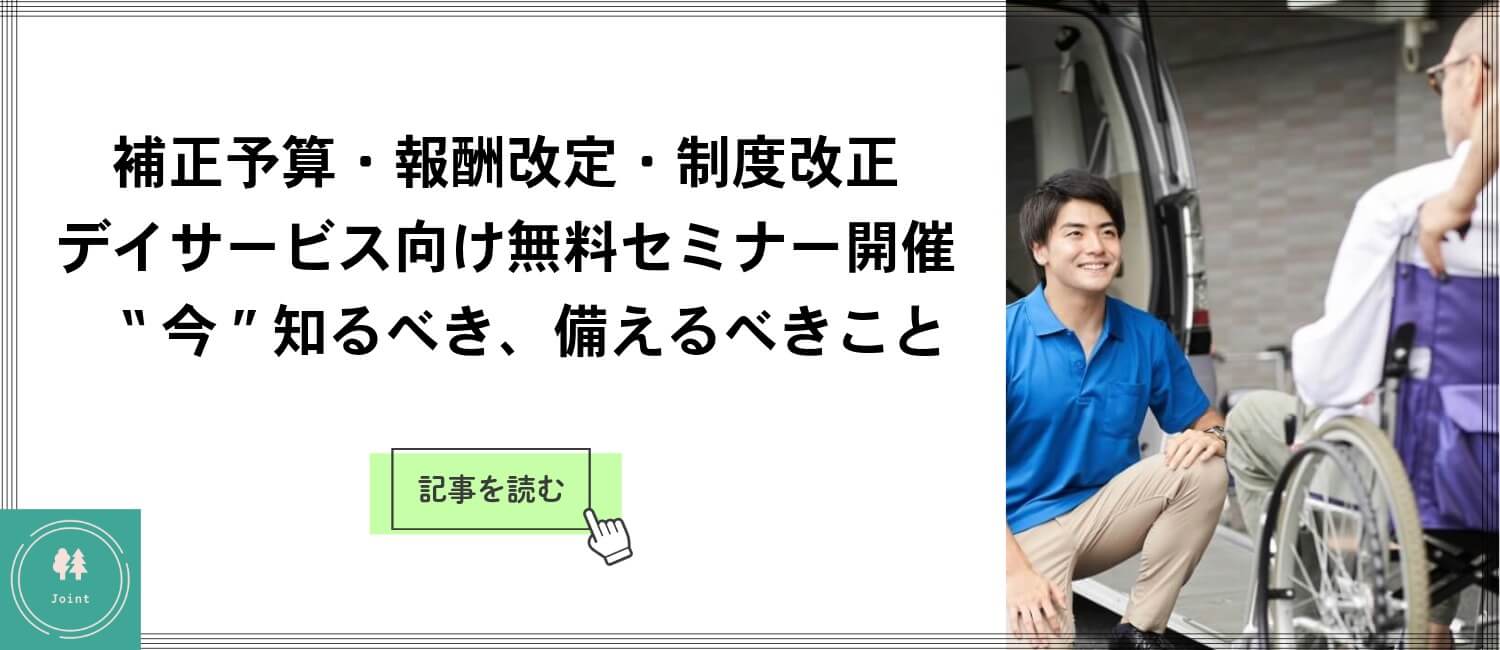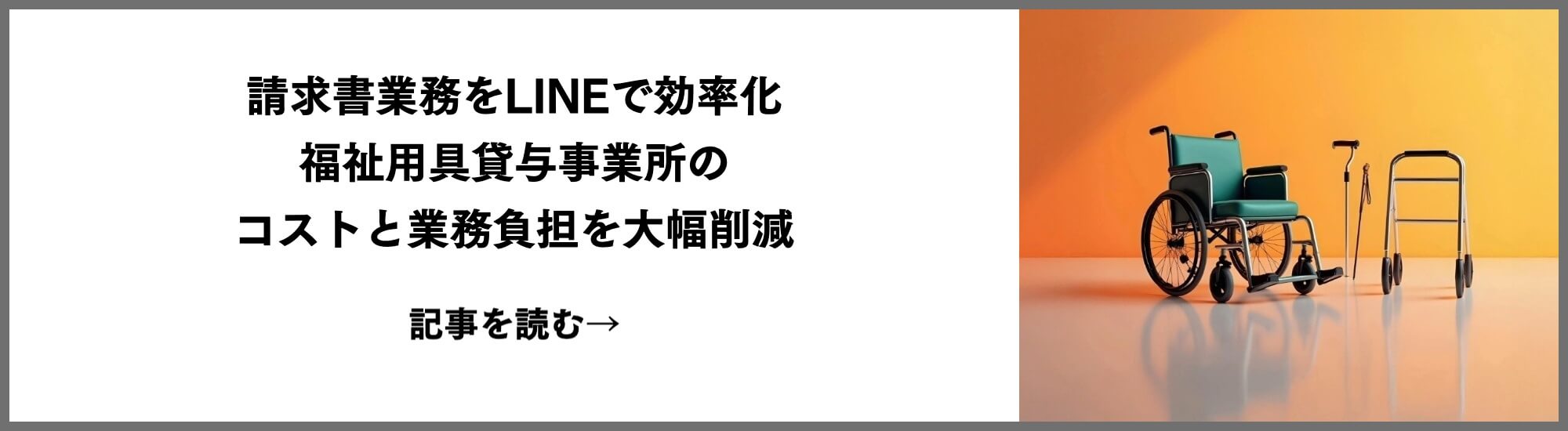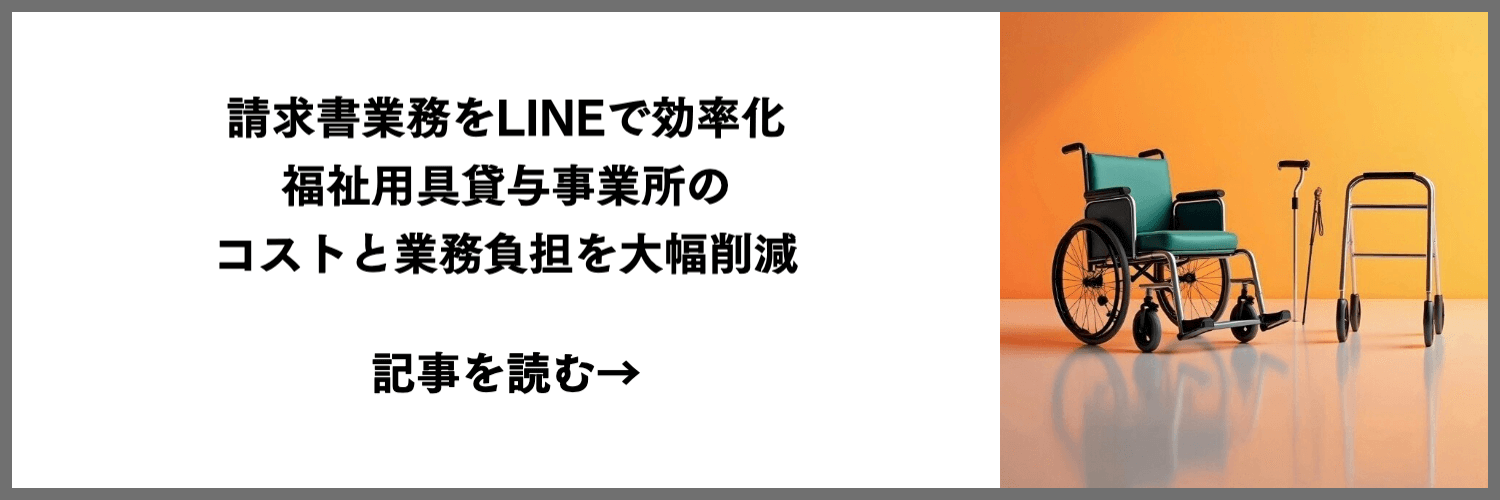【小濱道博】住まいを制する者が介護経営を制す 改正住宅セーフティネット法の核心と進むべき道
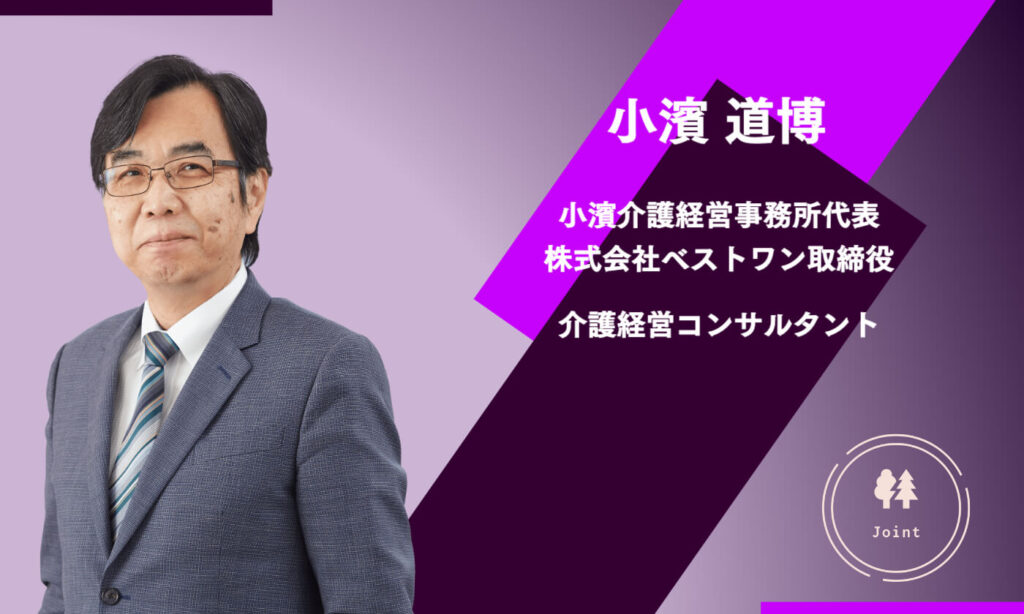
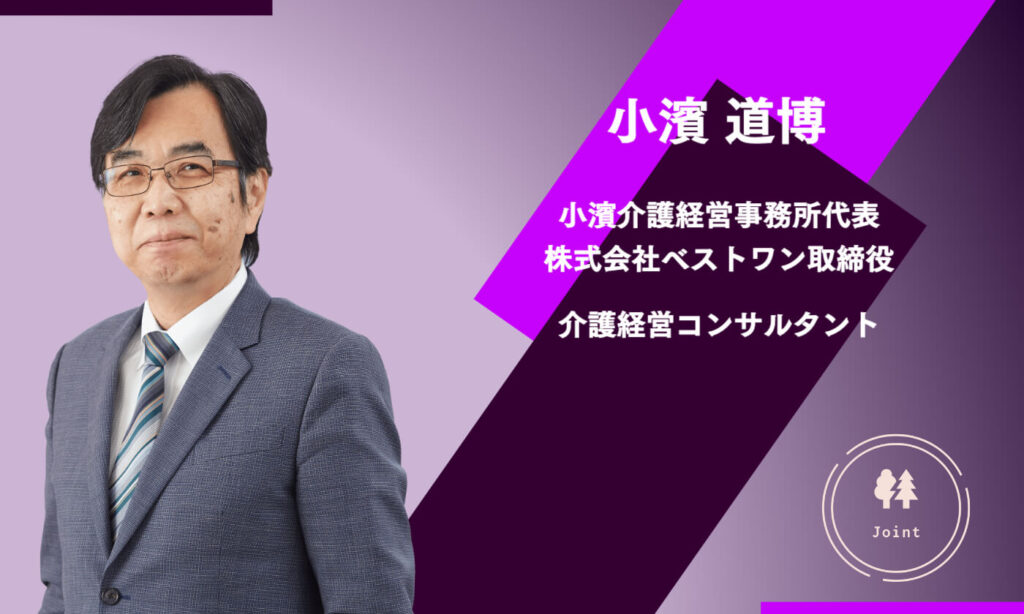
1,10月1日、介護と住宅が交差する
改正住宅セーフティネット法が10月1日に施行された。【小濱道博】
この改正は単なる住宅政策の枠組み変更にとどまらず、介護事業経営の根幹に直結する制度的転換である。地域包括ケアシステムの最大の弱点とされてきた「住まい」の不安定さに対し、国が本格的な制度基盤を整備する点に最大の意義がある。
特に注目すべきは、今年4月に訪問介護で外国人材の受け入れが解禁されたばかりであり、同一年度内に「人材の確保」と「住まいの安定」という介護事業の持続可能性を左右する2つの要素が、制度的に同時に動き出すことである。
2,改正の3本柱と経営リスクの低減
改正の第1の柱は、居住サポート住宅の創設である。居住支援法人などが大家と連携し、高齢者らの安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを行う住宅制度が新設される。
従来の「住むだけ」から「住み続ける」支援への転換は、介護事業にとって画期的である。利用者が家賃滞納や孤独死への不安から入居・継続を拒否され、サービス提供が中断される事例は少なくなかった。居住サポート住宅の普及により、こうした住宅リスクが制度的に吸収される。
第2の柱は、認定家賃債務保証業者制度の創設である。住宅金融支援機構の保証保険を活用し、家賃滞納リスクを低減する仕組みが整備される。
生活保護受給者が居住サポート住宅に入居する場合、住宅扶助費の代理納付が原則化されることで、大家の不安は大幅に軽減される。利用者の住まいの安定は、在宅介護の継続性の確保に直結する。
第3の柱は、残置物処理と契約終了手続きの明確化である。孤独死の発生時、遺族不在や権利関係の不明確さからトラブルが頻発していた。
改正により、居住支援法人が残置物処理を業務として担えるようになり、終身建物賃貸借の認可手続きも簡素化される。これらは介護事業者にとって、「利用者の死後のリスク」に伴う経営不安を低減する重要な制度改正である。
3,介護事業者が取るべき3つの戦略
第1の戦略は、居住支援法人との連携強化である。全国で700を超える法人が指定されており、住宅確保から生活支援までを担う地域資源として機能している。
ケアマネジャーはこれを踏まえ、住宅支援を介護計画に組み込み、地域包括支援センターや居住支援法人との情報共有体制を整備すべきである。利用者が住まいを喪失するリスクを早期に察知し、住宅支援につなげる体制の構築が、サービス継続性の確保に直結する。
第2の戦略は、外国人介護人材の住居確保支援である。訪問介護の外国人材の受け入れ解禁により、住宅確保が喫緊の経営課題となっている。
セーフティネット住宅を活用することで、自前の社員寮の整備コストを抑制できる。居住支援法人と連携し、言語・文化面の生活支援を充実させることで、外国人材の定着率向上と採用コスト削減を同時に実現できる。
第3の戦略は、介護と住宅を一体化したサービスモデルの構築である。介護事業者自身が居住サポート住宅を運営し、小規模多機能型居宅介護と組み合わせれば、365日24時間の見守り体制を実現できる。訪問介護、通所介護、住まいを統合したパッケージモデルは、新たな収益源となるだけでなく、地域包括ケアシステムの中核的役割を担うことにもつながる。
4,地域福祉の新たな基盤として
改正法では、市区町村による居住支援協議会の設置が努力義務化され、住宅部局と福祉部局の連携が制度的に促進される。介護事業者は協議会に積極的に参画し、地域の住まいと福祉の連携基盤を築く主体となるべきである。見守りや安否確認を通じた問題の早期発見・早期対応は、要介護状態の重度化予防につながる。
改正住宅セーフティネット法は、介護事業における「住まいの不安」を大幅に解消する制度である。利用者の住居が安定すれば、サービスの継続性が担保され、経営リスクは低減する。外国人材の受け入れや単身高齢者の増加に直面する現場において、「住まいと介護の一体化」を経営戦略に組み込むことが、事業の持続可能性を左右する分岐点となる。
2025年は、介護と住宅が真に統合される元年である。この制度改正を単なる政策動向として傍観するのではなく、積極的に経営戦略に活かす姿勢が求められている。