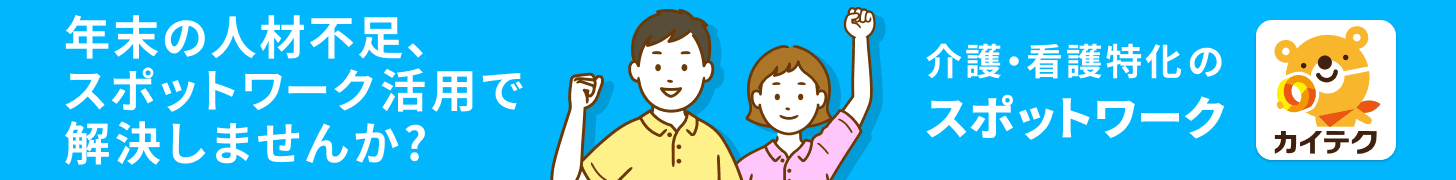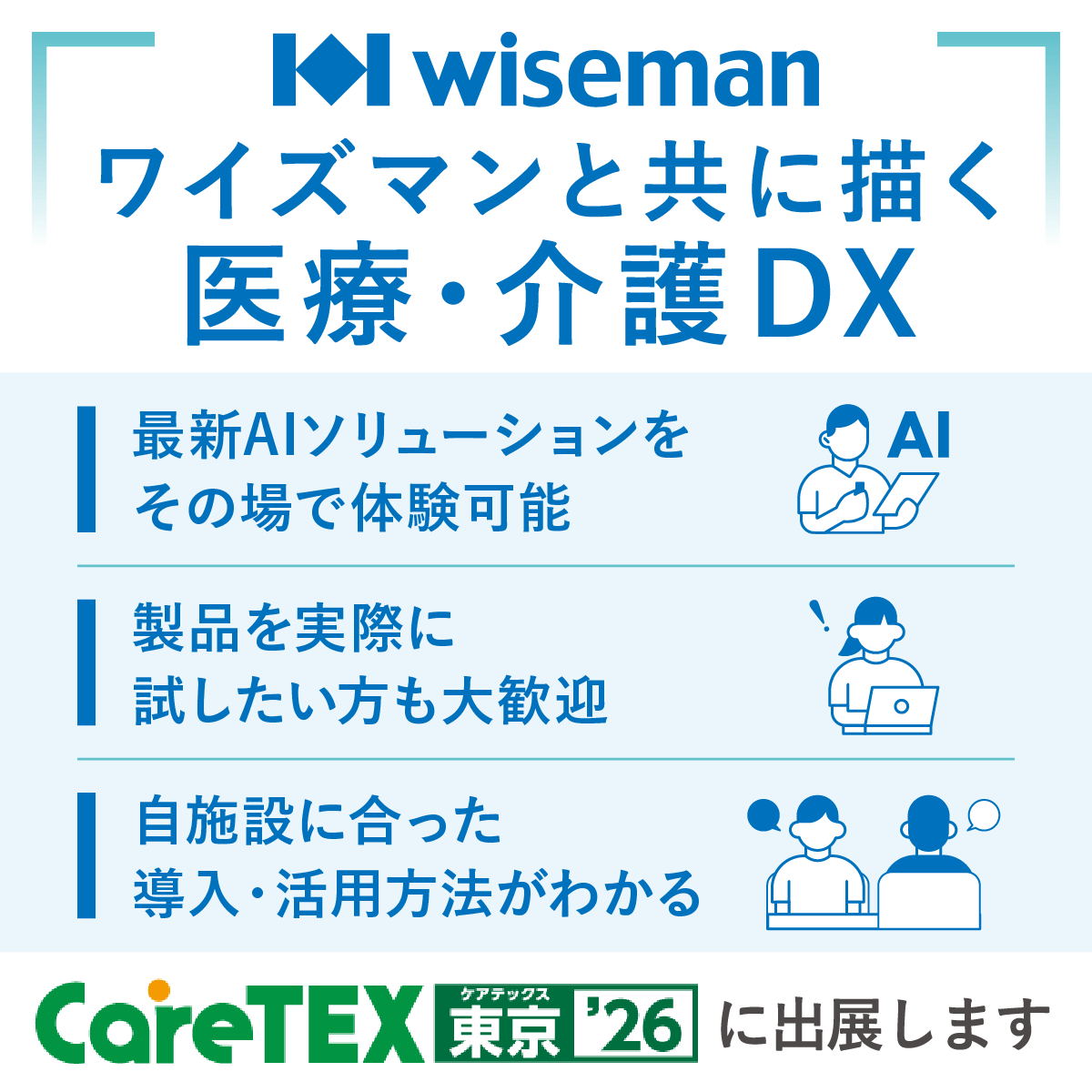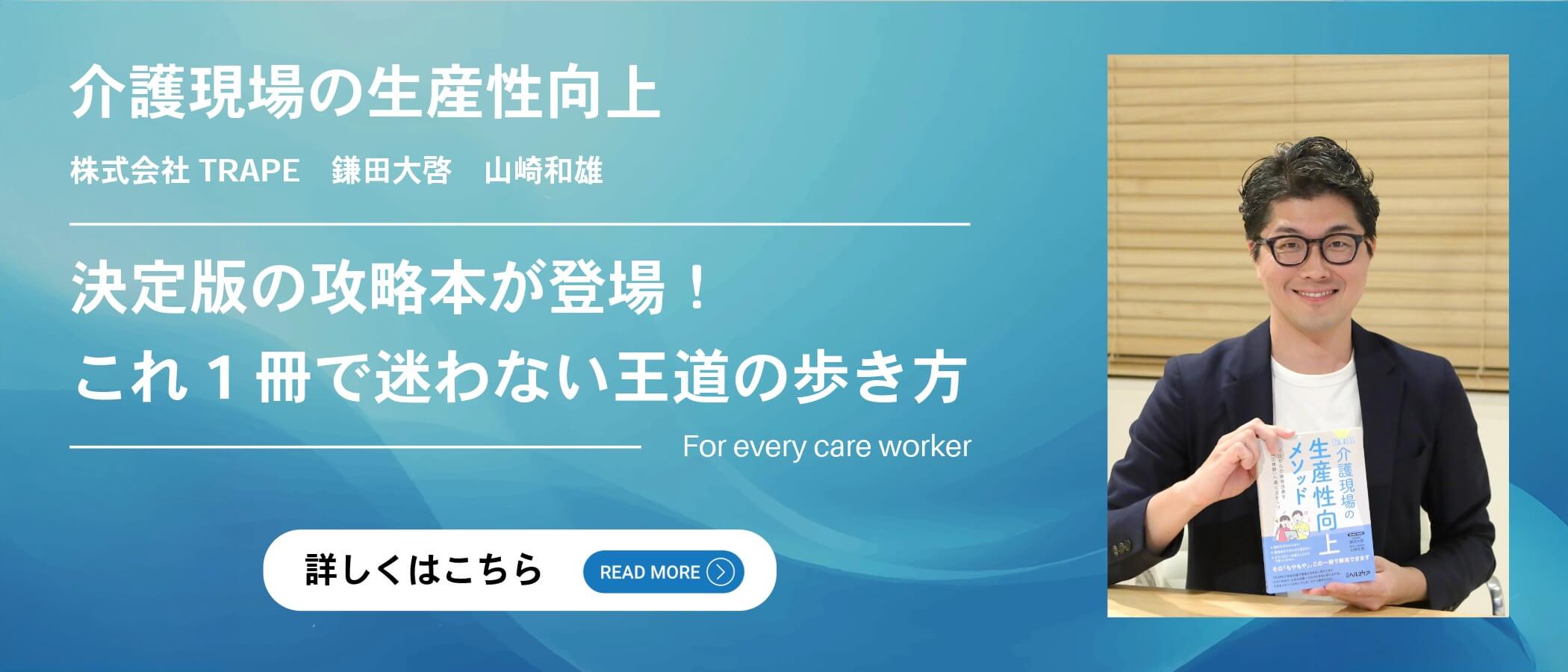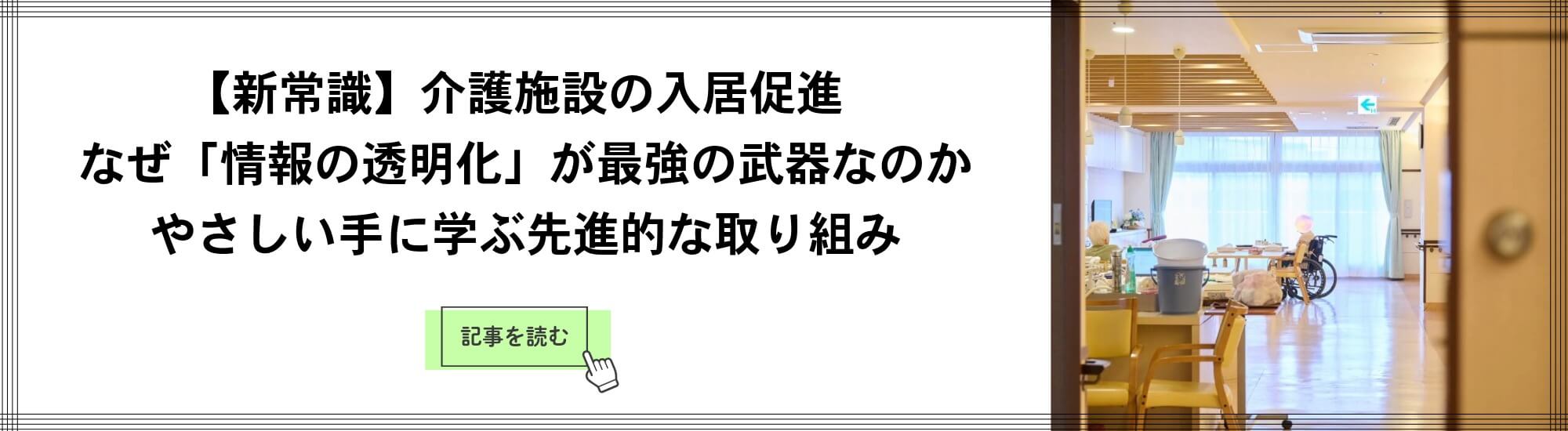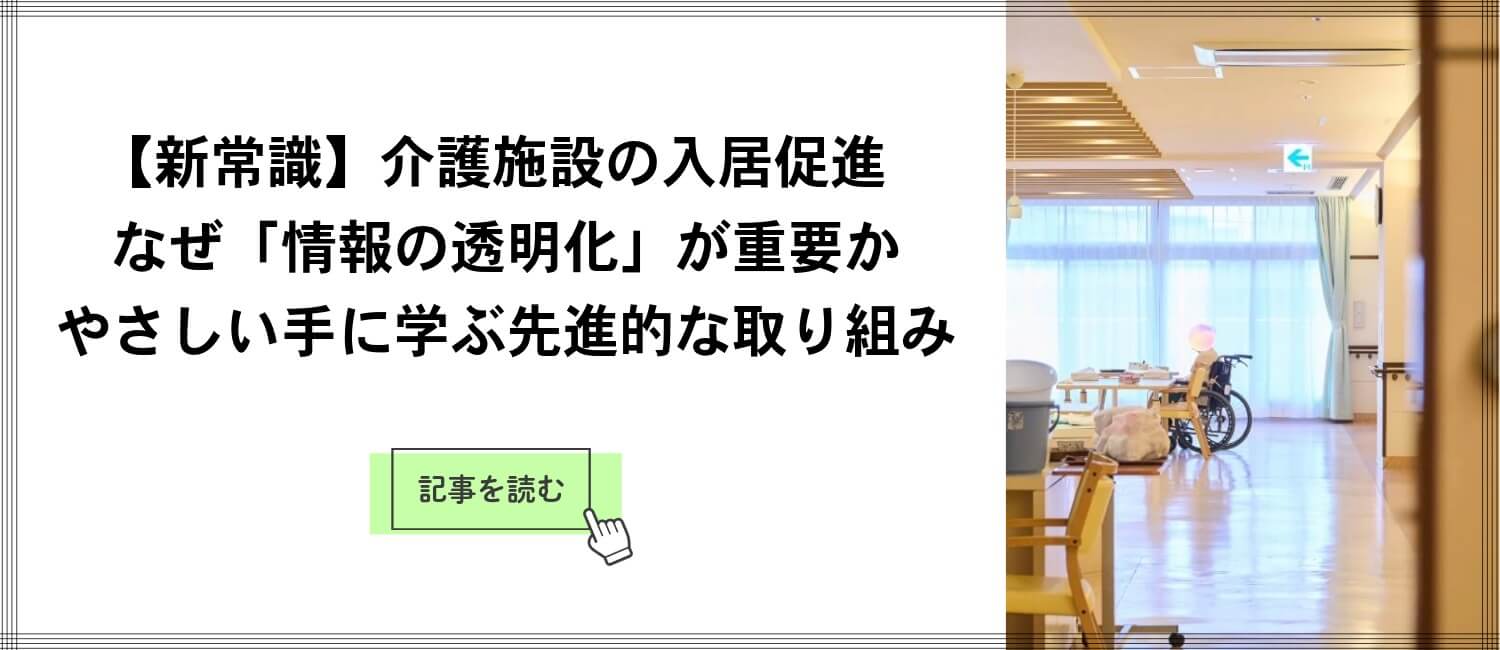【足立圭司】テクノロジー活用、地域に根ざした伴走支援者をどう育てるか 介護・障害の体制強化のカギ


介護分野では、人手不足を背景に、テクノロジーの導入や業務改善など、生産性向上の取り組みが加速している。【足立圭司】
◆ 伴走支援者育成の課題
厚生労働省は今年度、「生産性向上の取り組みに関する中央管理事業」の一環として、介護現場を伴走的に支援する企業などを対象にオンラインセミナーを開催した。本セミナーでは、国の政策動向に加え、テクノロジー活用の支援事例などが紹介され、参加者が支援の方法を体系的に学ぶ機会となった。
伴走支援者とは、介護事業所がテクノロジーの導入や業務改善を進める際に、現場に寄り添って課題分析から実践、評価に至るまでを継続的に支援する人材を指す。
課題は人材確保だ。各都道府県で設置が進む「生産性向上ワンストップ窓口」からは、「支援を担える人材を地域で見つけるのが難しい」という声が多く上がっている。
こうした状況を受け、すでに一部の窓口では、伴走支援者の養成研修や実地指導を独自に行う動きが始まっている。窓口として相談対応だけでなく、育成機能を兼ね備える試みである。
本セミナー参加者(約600名)の分析結果では、「支援経験がある」または「支援予定がある」と答えた人が全体の約4割に上った。この伴走支援者の担い手候補は、コンサルタントや介護テクノロジー開発企業の所属者が一定の割合を占めており、すでに支援ノウハウを持つ人材が中核を担う可能性が高い。一方、介護事業所や業界団体の関係者も学びの意欲が高く、将来的な伴走支援者として重要である。
ただし地域別では、東京都・福岡県・大阪府・神奈川県に担い手候補が集中。都市圏では民間支援者が主導する一方、地方では介護事業者の職員や自治体の担当者が中心であり、地域間の偏在が課題と言える。都市部の専門人材を広域的に活用するとともに、地域内での人材育成と連携強化を進めることが求められる。
◆ 支援者を支える仕組みづくりを
今後、障害福祉分野でも生産性向上の関連政策が始動し、介護分野で培われた伴走支援の枠組みが参考となる。こうした分野横断的な動きを見据えると、担い手を単に増やすだけでなく、「伴走支援とは何か」を明確に定義し、その目的と手法など基本的な考え方を整備することが喫緊の課題となる。支援者が共通の考え方と目線を持つことで、支援の質や信頼性、再現性を高められるだろう。
伴走支援者は、データ活用・人材育成・組織開発を統合的に支える「現場変革のファシリテーター」である。各自治体やワンストップ窓口が、こうした人材を地域で育て、支援を必要とする現場とつなぎ、活躍の場を創出していくことが、今後の介護・福祉現場の持続可能性を左右する。支援者を支える仕組みの確立こそが、業界全体の生産性向上を進めるための土台となる。
最後に、介護現場の生産性向上や伴走支援に取り組む読者におすすめしたい一冊が『超実践! 介護現場の生産性向上メソッド』(日経BP刊)である。
本書は、現場で使える具体的手法を豊富な事例とともに解説した実践書であり、著者の一人は本セミナーでも講師を務めた実践家。現場支援の豊富な経験に基づき、生産性向上を段階的に進めるための視点がわかりやすくまとめられている。