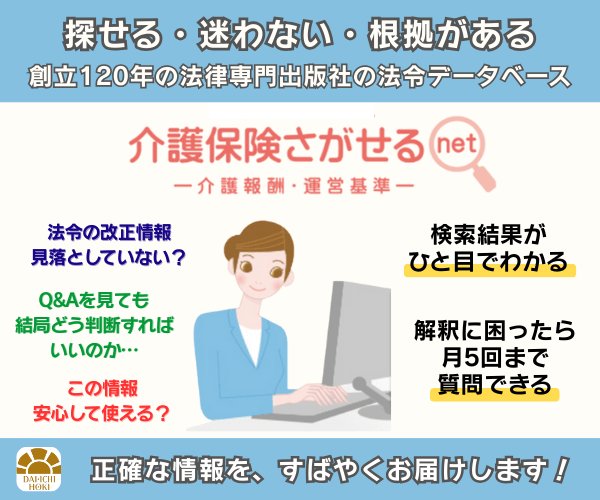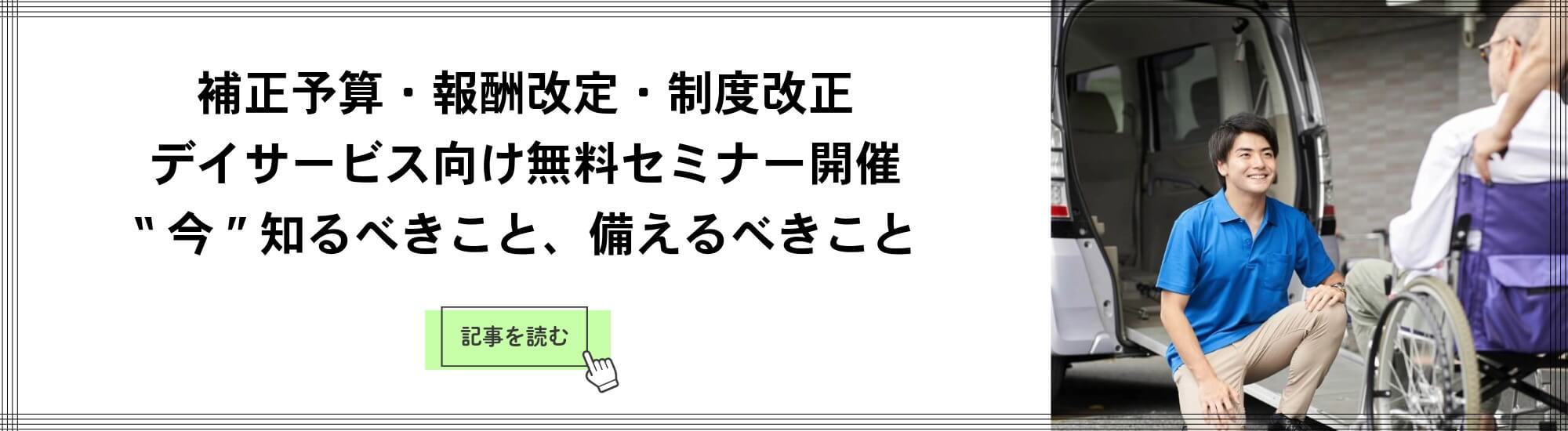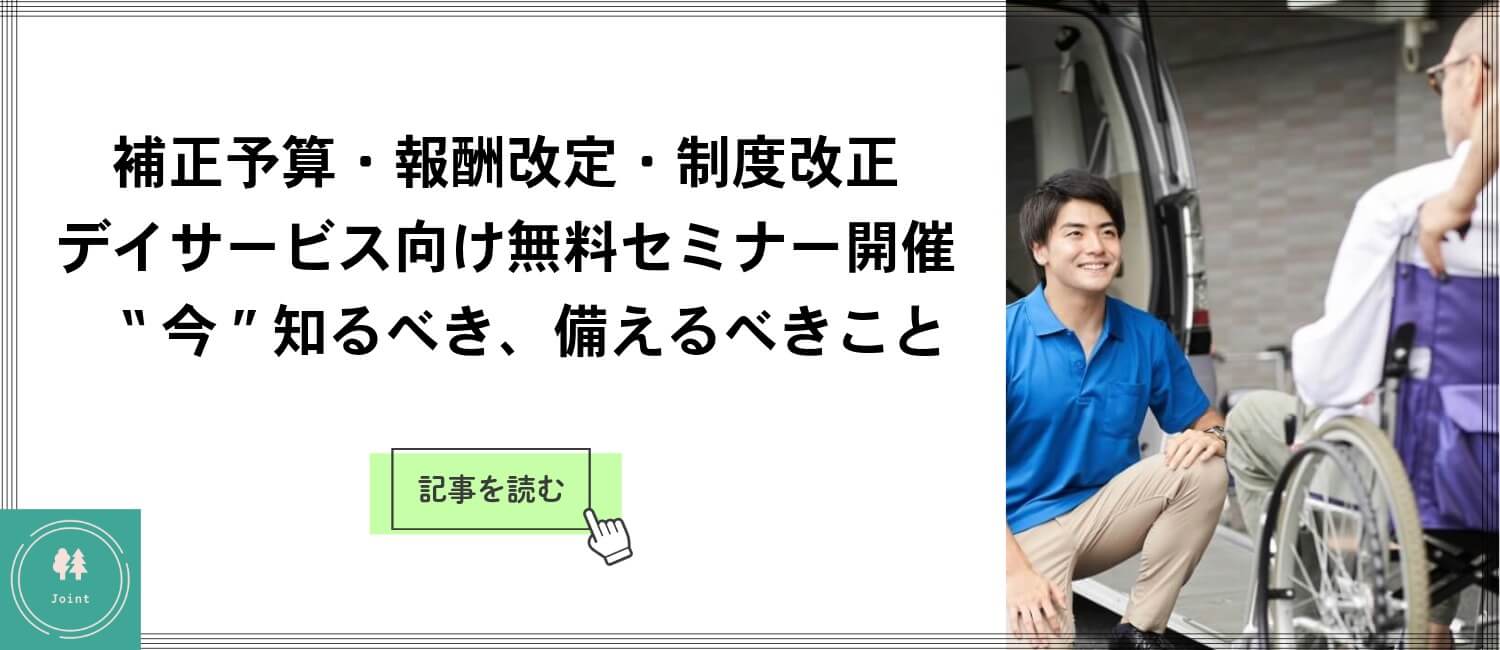介護サービスを給付ではなく事業で 中山間地域に新たな制度 厚労省方針


厚生労働省は中山間・人口減少地域に限った特例として、市町村が介護サービスを給付ではなく事業として実施できる新たな仕組みを創設する方針を固めた。【Joint編集部】
2027年度の制度改正に向けた議論を重ねている審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で今月10日に提案し、大筋で了承を得ていた経緯がある。
利用者の減少や事業者の撤退、リソースの縮小が急速に進む中山間・人口減少地域では、既存の給付の枠組みだけでは在宅サービスの提供体制を維持できないケースが増えている。厚労省はこうした課題に対応し、サービスの空白が一段と広がってしまうことのないよう、市町村が介護保険財源を活用し、事業としてサービスを実施できる仕組みを設ける構想を打ち出した。
新たな事業は、利用者ごとの出来高払いではなく、市町村が事業者に委託費を支払う形が基本となる。利用者数が限られる地域でも、事業者が安定してサービスを提供できるようにすることが狙い。市町村内に事業所がない場合は、周辺自治体の事業所に委託すること、複数のサービスを組み合わせて委託することなども想定されている。
提供できるサービスは、訪問介護、通所介護、ショートステイといった居宅サービス、またはそれらの組み合わせで、利用者との契約やケアマネジメントを適切に実施する点は従来と大きく変わらない。サービスの質を確保するため、事業者が守るべき基準について国が標準的なひな型を示し、市町村が適切に関与・確認する仕組みが考えられている。
厚労省は今後、関係者の意見を丁寧に聞きながら新たな事業の具体的な制度設計を進める方針だ。
これまでの審議会では、「サービスを維持するための新たな選択肢として意義がある」といった前向きな評価とともに、今後の丁寧な制度設計を求める意見が多かった。
一方で、「出来高払いの給付ではなくなると、自治体や事業者の都合で必要なサービスが抑制されるのではないか」「地域間の不公平が生じる」「市町村の事務負担が大きい」「委託先を確保できるのか」といった懸念の声もあがっており、こうした声にどう応えていくかが今後の課題となりそうだ。