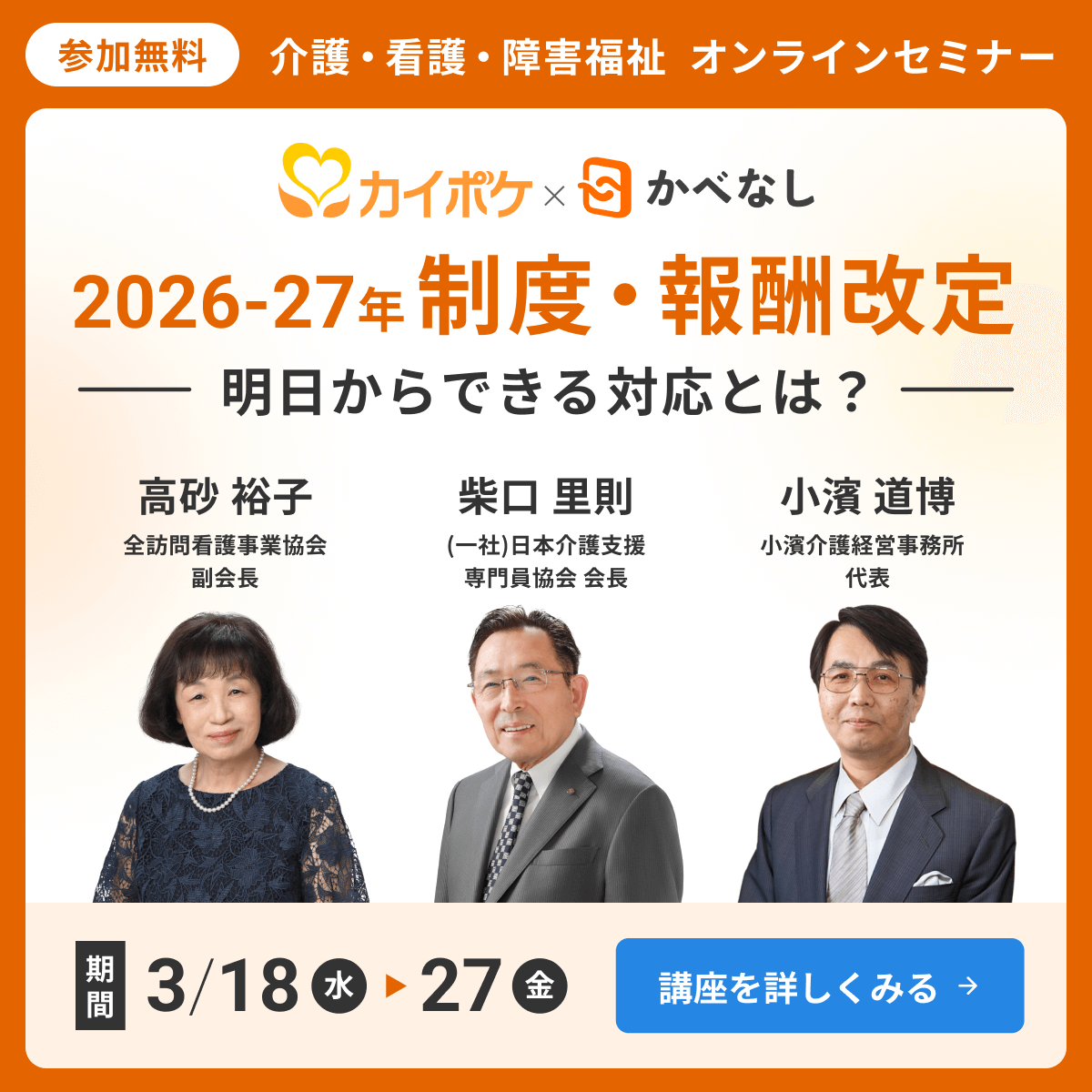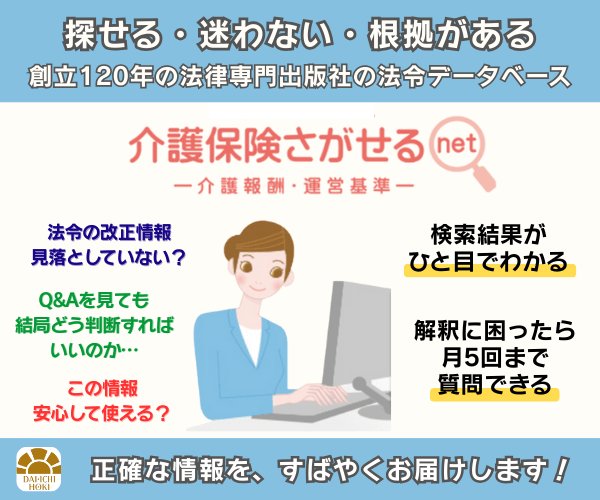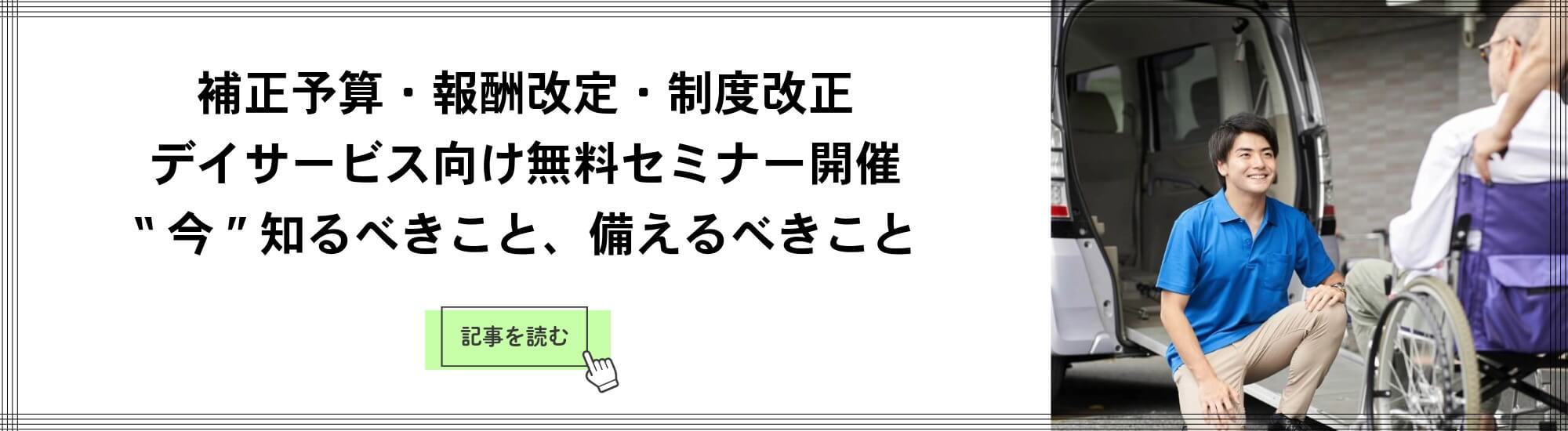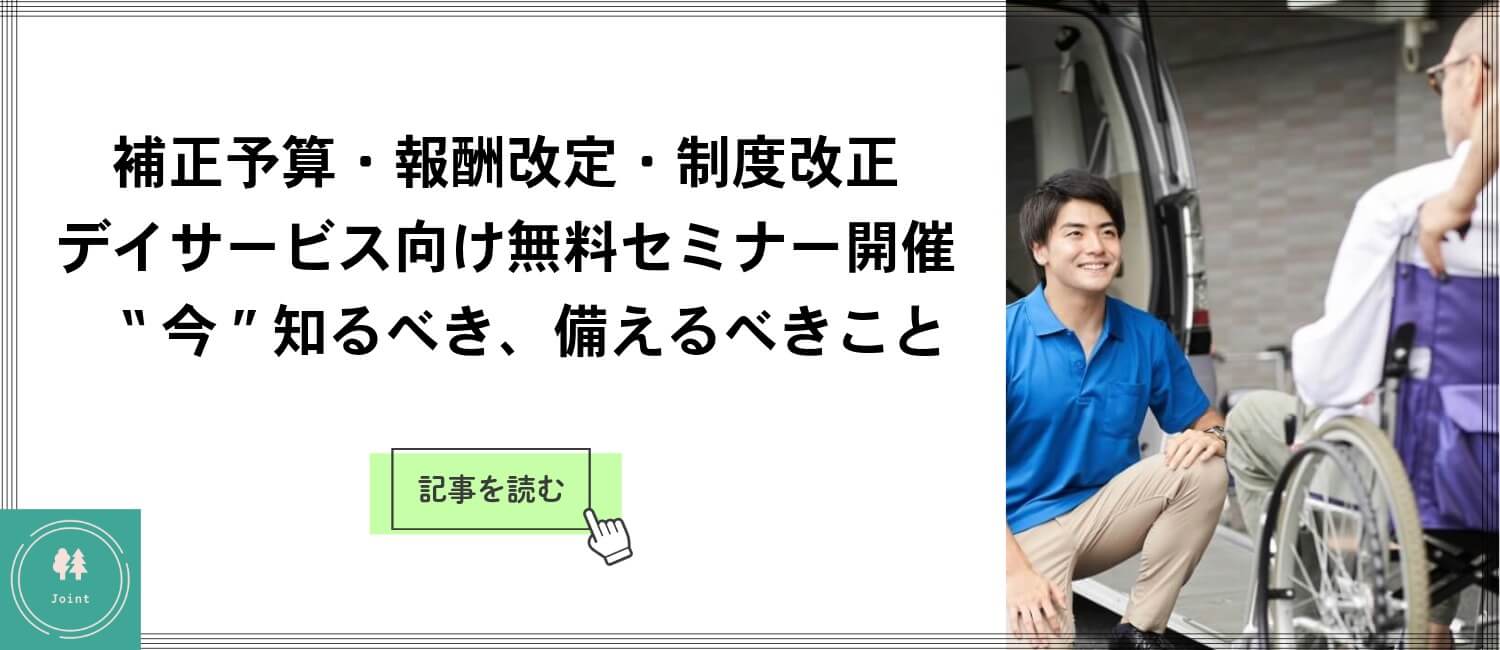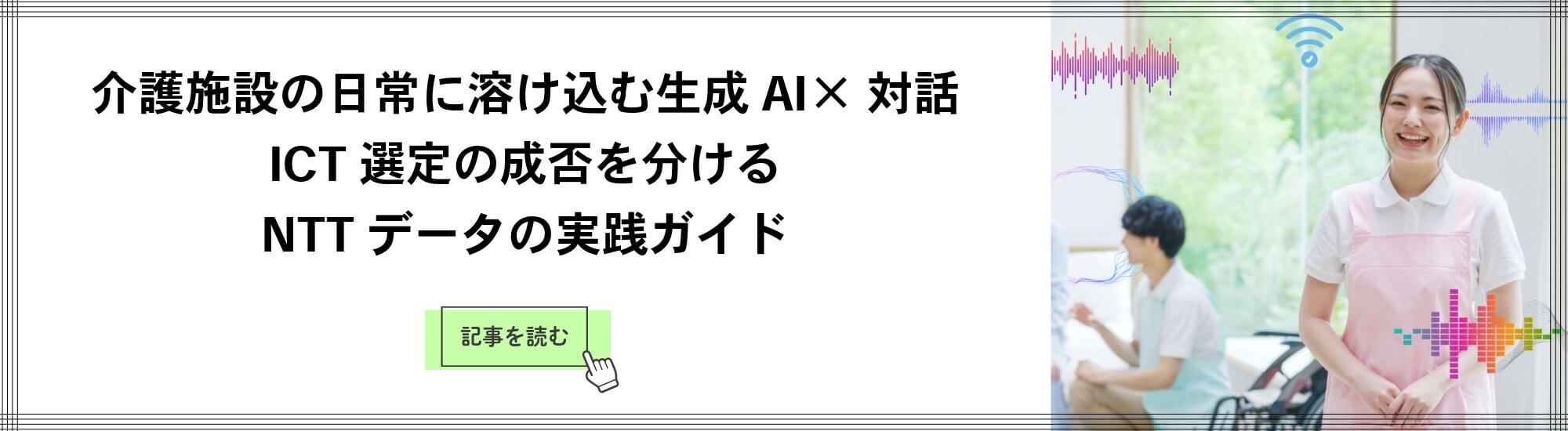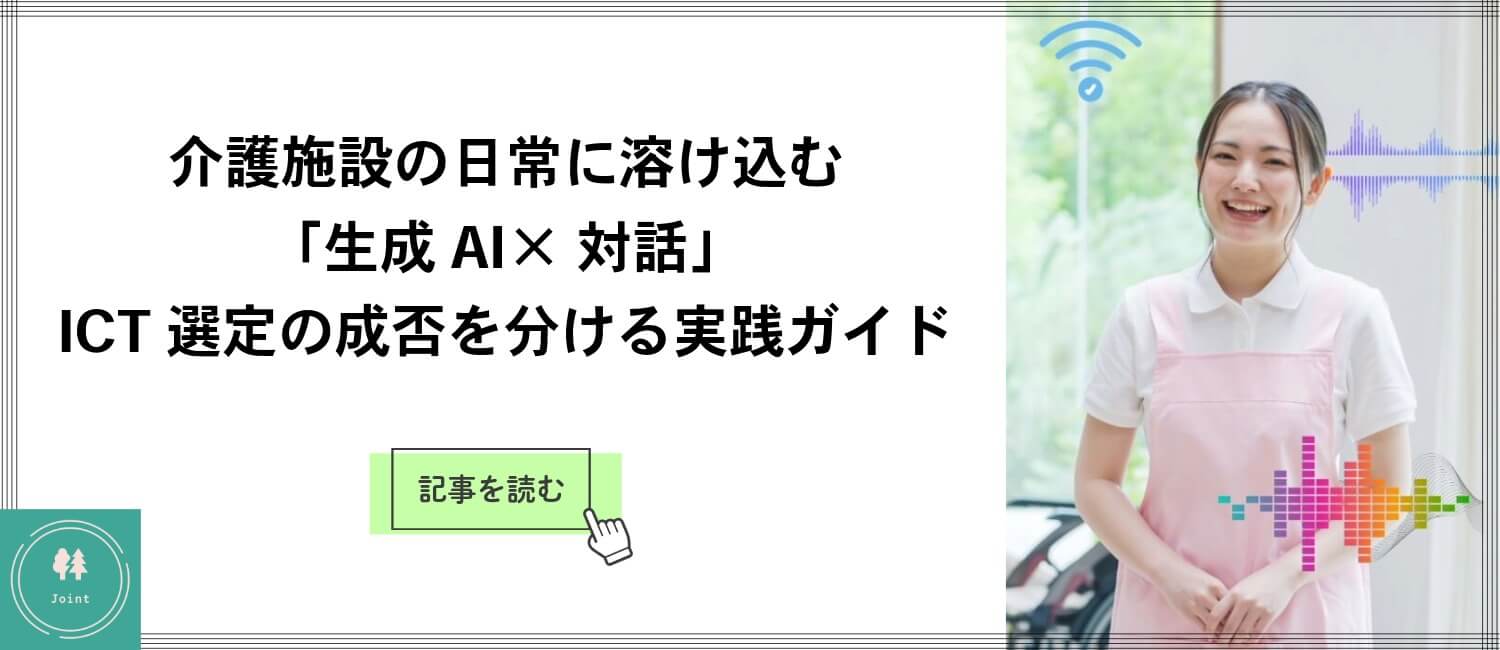【奈良夕貴】条件不利地域の介護の現実と課題 「地域の実情に応じたサービス」はなぜ重要か


介護現場を支える若手職員はもはや外国人材だけ、という地域があります。そうした地域での介護サービスの仕組み、提供体制などの見直しは、いたずらに質を下げるために行われるものではありません。住民の生活を守るための前向きな判断です。地域の状況に合わせ、サービスの提供を現場が無理なく続けられる仕組みが求められています。【奈良夕貴】
離島や中山間地域などの条件不利地域では、新卒採用がほぼ途絶え、若手職員の多くを外国人材が支えている現実があります。職員の半数以上が65歳を超え、新卒が10年以上入っていないという話も珍しくありません。地域に入所施設が1つしかないことも多く、その施設が“生活インフラ”として高齢者の暮らしを支えています。
いま、厚生労働省の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)では、例えば特例的な人員配置基準の弾力化や訪問介護の定額報酬の新設など、「地域の実情に応じたサービス」のあり方が検討されています。これは、地域の持続可能性を考えるうえで極めて重要なテーマです。
◆ 質の低下ではない
人員が限られる地域では、介護サービスの「支援回数の調整」や「方法の変更」を判断せざるを得ない場面があります。
こうした変化だけを捉えると、サービスの質の低下に見えることがありますが、実際の現場では、利用者の状態やリスク、生活の流れを踏まえながら、地域の介護インフラを維持するために「何を守り、どこを見直すか」を慎重に判断しています。
例えば、夜勤を最低限の人数で行っている地域では、利用者の状態変化があれば、安全を最優先に支援の順番や方法を組み替える必要が生じます。これは“支援を減らす”のではなく、命に関わる支援を確実に行うための、現場だからできる判断です。
また、職員が疲弊した状態では本来の質を発揮できず、それこそが最大のリスクとなります。だからこそ、ときには入所定員を見直す必要が出てくることもあります。現場はサービスの質を守るために、必要に応じて「見直す」勇気を持っていると感じます。
一方で、こうした判断の背景が誤解されないよう、支援内容が変わる理由を根拠とともに丁寧に伝えることが、これまで以上に重要になっています。
◆ 外国人材に頼る地域の脆さ
日本人の採用が極めて難しい地域では、特定技能や技能実習(今後の育成就労)が実質的に唯一の若手確保の手段です。しかし、委託費や監理費、育成体制の不足、転職リスクなど、長期的な受け入れには課題が多くあります。
一方で、外国人職員を継続的に受け入れ、先輩が後輩を支えられる“循環型”の仕組みが生まれれば、地域は大きな力を得ます。ただ、職員数が少ない地域では、日本人職員の急な退職や外国人同士の関係性の変化など、些細な出来事が全体の安定性に影響する脆さもあります。
地域を支える介護が継続できるよう、制度(受け入れの仕組み)と現場(育成・定着)の両方から、人材基盤を補強する視点が欠かせません。
◆ 地域を支えるというキャリア
条件不利地域では、少人数ゆえに法人内で役職の階段を整えにくく、研修機会も都市部ほど多くはありません。
一方で、技能実習修了後も地域に残る外国人職員に話を聞くと、中には「育ててもらった恩を返したい」「人が足りないことが分かっているので役に立ちたい」と語り、地域の暮らしを支えることそのものに価値を見い出していると感じます。肩書や昇進だけでは測れない、“地域を支えることがキャリアになる”という新たな価値観が、現場から生まれているのではないでしょうか。
地域を支えるという経験そのものをどう評価し、どう成長機会につなぐのか。これからの地域介護にとって大切な視点です。
◆ 地域で選べる無理のない制度へ
離島や中山間地域は一括りにされがちですが、人口規模、施設数、交通手段、生活動線などは地域によって大きく異なります。行政上の定義も省庁によって微妙に異なり、一律の枠組みでは地域の実情に合わない場合があります。
だからこそ、「地域の実情に応じたサービス」という考え方は必要です。ただし、制度が複雑になりすぎれば、現場の負担が増えてしまいます。
重要なのは、地域が自分たちで選べて、無理なく使える制度にすること。今後の議論が、地域の状況に合わせ、サービスの提供を現場が無理なく続けられる仕組みになることを期待しています。