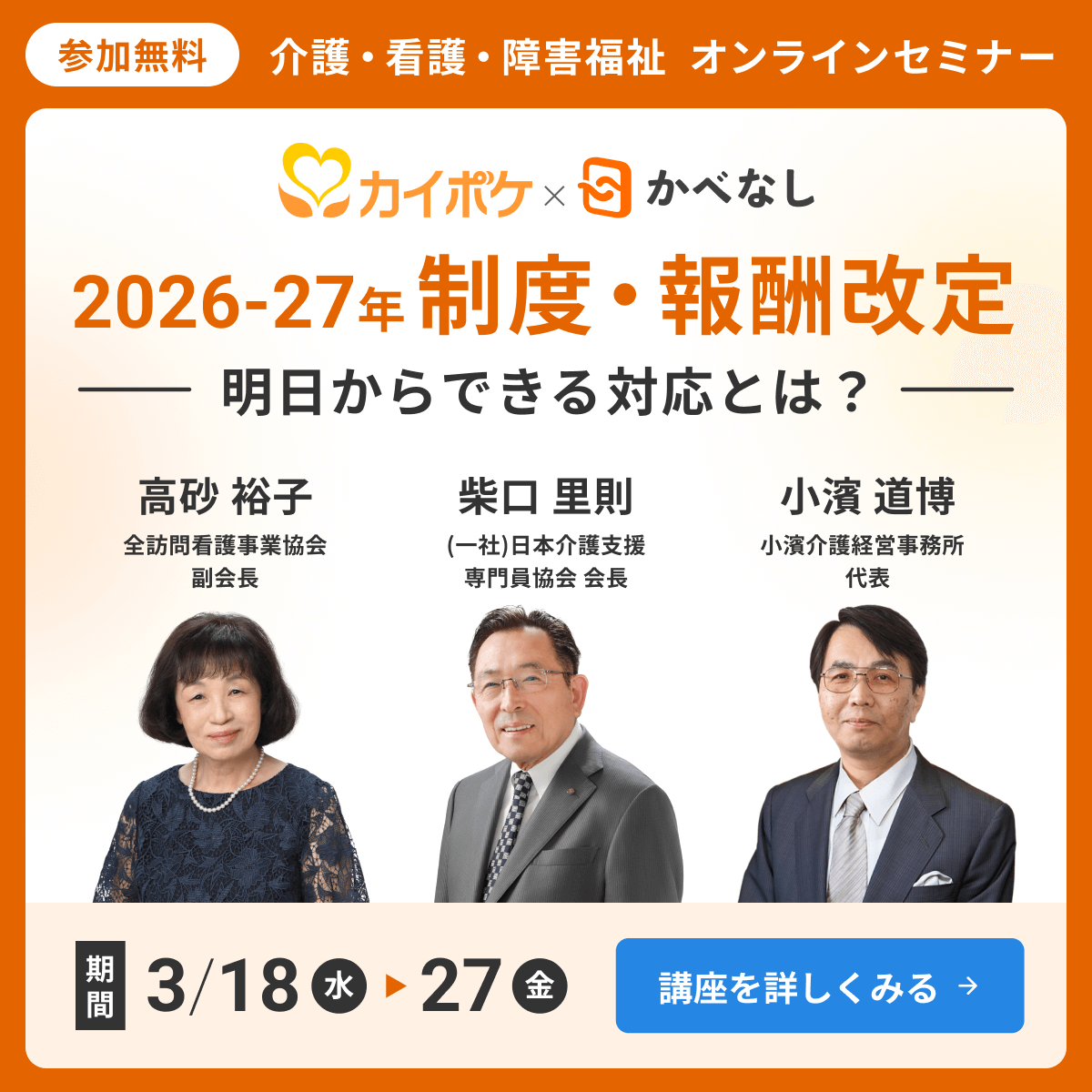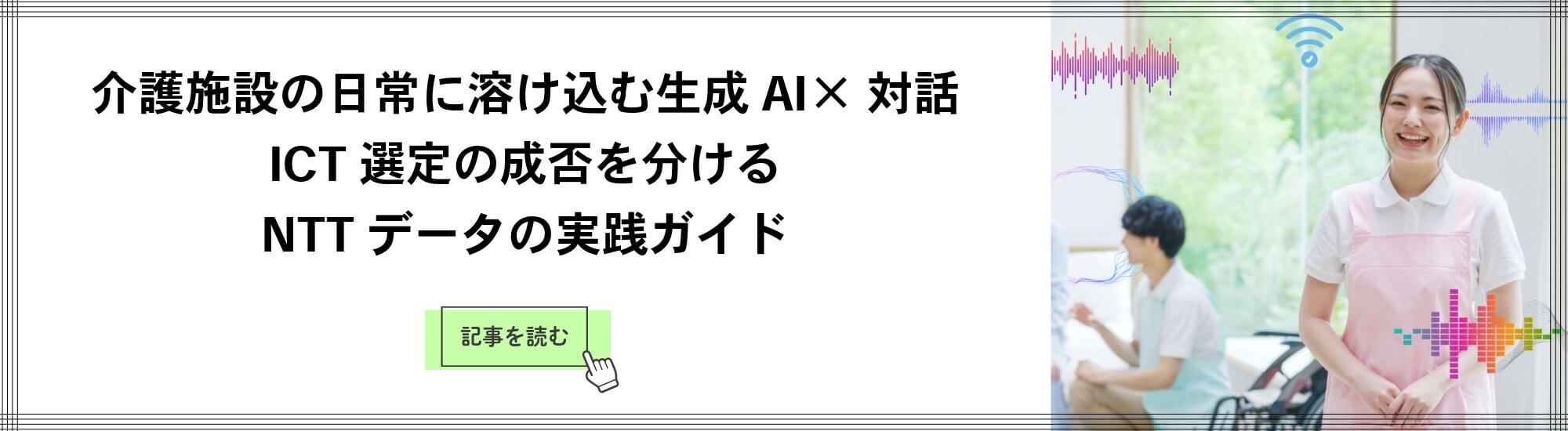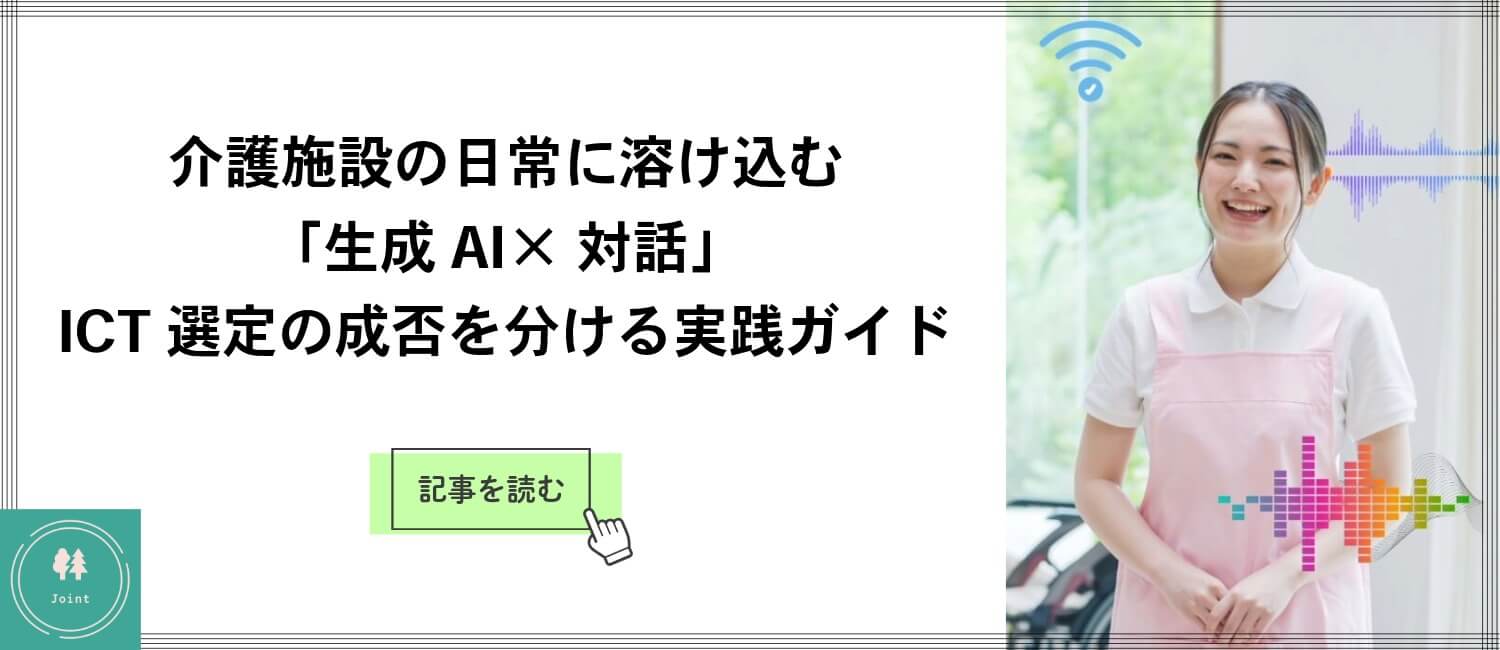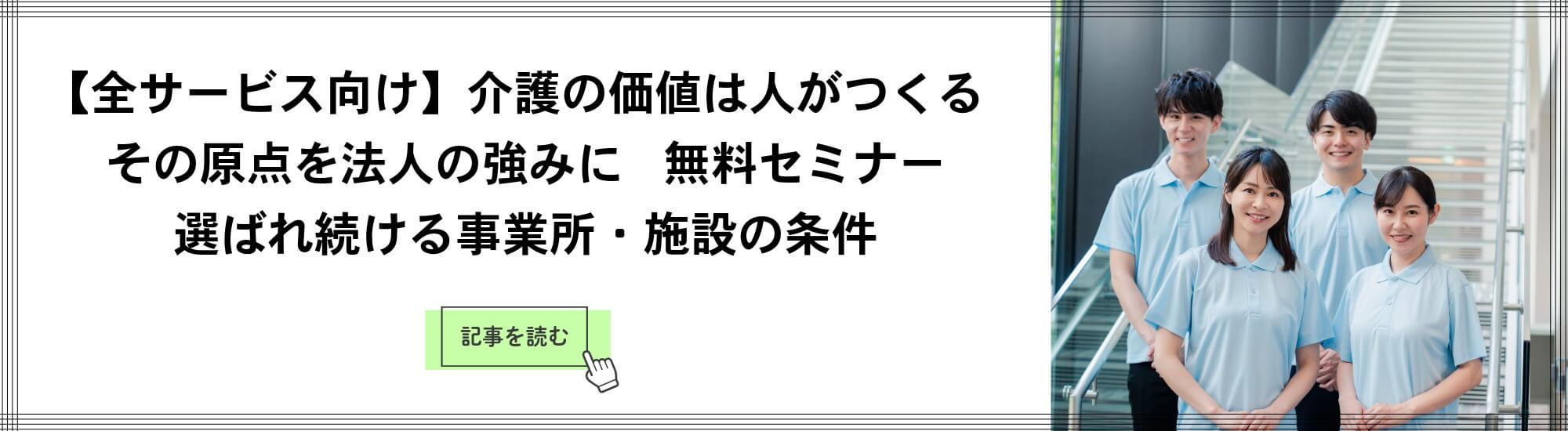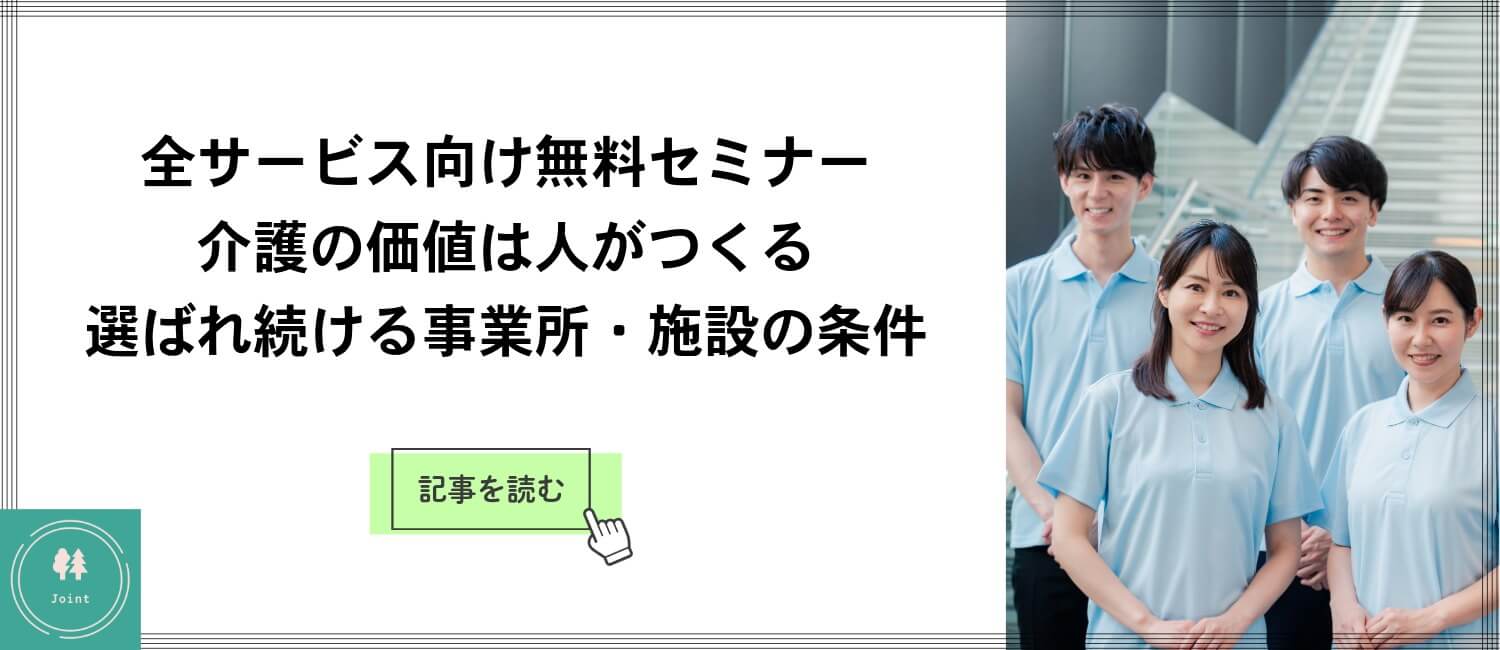【高野龍昭】徹底解説|運用開始迫る「介護情報基盤」 介護現場はどう向き合うべきか


1.はじめに
現行の介護保険法のなかで、未施行であった「介護情報基盤の整備」(介護保険法第115条の45第2項など)が、いよいよ2026年4月から施行されます。
私はかねてから「2024年度の介護保険制度改正で最も重要なポイントは『介護情報基盤の整備』だ」「この事業の施行日がいつになるか注目しておくべき」「これが今後の医療・介護DXや生産性向上施策の命運を左右する」と指摘していました。
しかし、この事業について、いまだに介護サービスの実践者と事業者の関心が高まっていないことに大きな懸念を抱いています。【高野龍昭】
2.「介護情報基盤の整備」とは何か
(1)事業の趣旨
①介護DXとは
「介護情報基盤の整備」の事業は地域支援事業の1つです。この施行によって、保険者と介護サービス事業者は、“介護DX”を強力に推し進める必要性に直面することになります。
DX(Digital Transformation)とは、単に業務をICT化(Information and Communication Technology=情報通信技術の活用)することを指すわけではなく、“デジタル化により生成されたデータを利活用して、サービス提供のモデルや働き方を改革すること”を指します。そのうえで、“介護DX”とは“デジタル化とデータ利活用により、サービス提供のプロセスを変革し、サービスの質の向上(自立支援・重度化防止)や専門的業務の標準化を図ること”と言えます。
②隣接領域でのDX
わが国の介護分野は、官民ともにDXが大きく立ち遅れている実態にあります。とりわけ隣接領域である医療・公衆衛生などと比べると、その差は歴然としています。
たとえば、公衆衛生分野においては、戦後の保健所法の施行(1948年)、そして老人保健法の施行(1983年)や地域保健法の施行(1997年)以降、都道府県・市町村が主体となって、住民の健康状態、疾患、その原因、栄養、生活環境などに関するデータを収集・分析し続けています。
それに基づいて、地域ごとの状況に応じた保健施策を展開し、いわゆる「5疾患」(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)などの予防のアウトカムを問う事業を実施してきました。その結果のひとつが、世界トップの平均寿命となって現れています。
また、医療においては、おそらく医制の施行(1874年)以降、さらに言えばヒポクラテスの時代(紀元前400年代)以降、現実的には医療機関での電子カルテ化などが進んだ1980年代以降、患者の疾患・状態と治療的介入(薬剤や処置、術式など)との関連をデータで縦断的に可視化するなどして、そこから標準治療やEBM(Evidence-Based Medicine)を体系化してきました。
その結果、標準治療が国内どこでも行われるようになるとともに、わが国の医療水準は世界トップクラスとされるようになりました。加えて、医療に対する社会的評価と信頼が高まったのです。
医療保険制度において2012年度から各医療機関が取り組んでいる「データ提出事業」(介護保険制度における“LIFE”と同様のもの)により、その精度はさらに高まっています。
看護も同様です。F.ナイチンゲール(1820-1910)は「近代看護の母」という功績だけでなく、「近代看護統計学の始祖」とも称されています。すでに19世紀に「データと根拠に基づく看護」の体系化に努め、現在の看護の体系化・標準化にも大きな影響を及ぼしています。
わが国の看護では、前述の医療でのデータ活用の手法を取り入れたEBN(Evidence-Based Nursing)の発展や、それに即した看護教育の体系化、それを習得した看護師の増加によって、社会的評価・信頼が高まっていきました。
③介護DXの遅れ
一方、介護分野はどうでしょうか。
実践現場では、「寄り添う」「温かい関心」「尊厳」といった精神性と、「経験と勘」「(先輩の業務を)見て覚える」といった属人性などが優先されてきました。それぞれに重要なことであることは間違いありませんが、専門的技術として、データや根拠に基づいてサービス提供方法を標準化(専門職としての「判断」の基準や「介入」の方法が、科学的根拠に基づいて共通化されていること)する取り組みは大きく遅れています。
政府・自治体による行政施策も、介護需要の総量(給付費総額や要介護認定者数の増減など)や市民の要望に基づいた立案・計画・実施がされてはいるものの、地域ごとに異なる細やかな介護に関連するデータ(要介護状態に陥る原因、介護サービスを受けている間の心身機能の変化、介入やサービス投入量と利用者の状態の関係の変化など)を踏まえたものにはなっていません。
いずれをみても、公衆衛生・医療・看護とは格段の差があります。ただし、これらは、介護の実践現場が悪いわけでもなく、政府・自治体が悪いわけでもなく、そもそも「データが収集されていないこと」「存在するデータを多面的に利活用する体制とインセンティブが整備されていないこと」が問題の根源です。
したがって、これを見直そうと言うのが「介護情報基盤の整備」の趣旨と言えます。介護分野も公衆衛生や医療・看護のようにDX化を進めることで、介護専門職の実践を標準化させ、(私の造語ですが)EBLTC:Evidence-Based Long-Term Care =根拠に基づく介護が提供される体制を創り、その社会的評価・信頼を高めるような改革が必要です。
おそらく、政府も「介護情報基盤の整備」にこうした期待を込めているはずです。
(2)事業の概要
①これまでのデータ利活用
そうは言うものの、これまで介護分野において、データが収集・利活用されてこなかったわけではありません。
政府・自治体は、2013年度から「要介護認定情報データベース」と「介護レセプト等情報データベース」を保有しています。
前者は、要介護認定を受けた個々の高齢者の基本情報(性別・年齢階級・要介護度など)だけでなく、認定調査項目(いわゆる74項目)の調査結果も格納されています。さらには、主治医意見書の情報の一部(傷病名など)や認定の有効期間も含まれたデータベースです。
後者は、個々の高齢者が利用したサービスの種類と内容、利用したサービスの提供期間・回数、費用の情報(介護報酬の細かな単位数)などが格納されています。給付管理票のデータが個別に紐づけられて格納されている、と言ってよいでしょう。
この2つのデータベースは、10年以上にわたる縦断データ(経年的に個々の高齢者ごとに紐付けされた形式)として保存されており、政府・自治体の政策立案などに用いられてきました。
ここには介護実践現場や医療機関などでも利活用が望まれる情報も含まれています。これらのデータを利用者単位・事業所単位で活用すれば、自立支援・重度化防止に向けた介護サービスの質の向上にさらなる効果を出せるはずです。
一方、介護実践現場では標準化されたデータを収集してきていません(一部の先駆的な取り組みを行っている事業者を除く)。しかし、2018年度施行の制度改正で、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションでは介護報酬の加算に連動させる形でVISIT(monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care)の情報を収集し、厚生労働省が保有するデータベースにアップロードし、それを当該事業所でのサービスの質の改善のために利活用できるようになりました。
それに並行しつつ、厚生労働省老健局に設置された検討会で、そのVISITをバージョンアップする形でLIFE(Long-term care Information system For Evidence)が開発され、「科学的介護情報システムデータベース」が構築されました。
これは、2021年度施行の制度改正で、運営基準においてすべての介護サービス事業所・施設に利活用の努力義務が課せられるとともに、訪問系サービスを除くほぼすべてのサービス種別に対し、介護報酬の加算に紐づく形で利活用が推奨されている形となっています。
このLIFEはVISITと同様、厚生労働省が保有するデータベースにアップロードし、フィードバックなどを受けて、そのデータを当該事業所でのサービスの質の改善のために利活用できるようになっています。ただし、利活用できる範囲は当該事業者だけとなっています(オープンデータ化されており、匿名化されたうえで、研究目的などでの利活用は可能)。
このデータを政府や自治体が活用できれば、さらに細やかな施策立案ができ、たとえば日常生活圏域ごとの特徴を踏まえた自立支援・重度化防止の対応なども可能になるはずです。
つまり、これまでの介護分野でのデータ利活用は、要介護認定情報データベースと介護レセプト等情報データベースが利活用できるのは政府と自治体のみ、LIFEのデータベースが活用できるのは利用者に関するデータを提出した事業者のみにとどまっており、断片的にデータを利活用している実態にとどまっている、というわけです。
これでは介護DXが進むはずがありません。現状では、医療・公衆衛生分野のように「オール・ジャパン」で介護に関する施策やその効果を検討することはできず、自立支援・重度化防止のための介護サービスのあり方を詳細に検討することもできません。行政も介護実践現場も標準化されたEvidence-Basedな展開ができる体制にはないと言ってよいでしょう。
ましてや、その医療・公衆衛生分野などとデータの連携を図り、ヘルスケア・対人サービスを包括的に進めていく環境にはありません。
②「介護情報基盤の整備」事業でのデータ利活用の概要
a)概要
こうしたことを背景として、「介護情報基盤の整備」の仕組みは検討されてきました。
端的に言えば、政府・自治体が保有する要介護認定情報データベースと介護レセプト等情報データベース、介護事業者が保有する科学的介護情報システムデータベースを一体化させ、さらにそこに居宅介護支援事業所等からケアプランをデータ化して提出を求める新たな「ケアプランデータベース」なども加えて、「介護情報基盤」を構築するのです。
そのうえで、これらのデータを秘匿化したうえで、政府・自治体・介護サービス事業者、さらには利用者が相互に利活用できる体制を作り、介護DXを推進するプラットフォームを作ることになるのです。
この事業は前述した通り地域支援事業のひとつであり、市町村事業として位置付けられますが、実際には「オール・ジャパン」で介護DXを推進していく体制をとることになります。
b)段階的な施行
まず、2026年4月からは、市町村が現行の要介護認定情報データベースと介護レセプト等情報データベースを介護情報基盤に移行する作業を始めることになります。それに並行して、保険者ごとに稼働している介護保険事務システムの標準化を進め、要介護認定事務のICT化の準備などが始まります。
その間、政府でもLIFEデータベースを介護情報基盤に統合し、ケアプランデータベースなどの構築とケアプランの情報をアップロードする体制を整えていきます。
そのうえで、2028年4月から介護情報基盤の整備の事業が全面施行・本格稼働することになっています。実際に介護サービス事業者・利用者にその影響・効果が波及することになるのは、その時期からとなるはずです。
なお、この事業については、いわゆる「マイナ保険証」の推進と同時並行の事業となります。そして、健康保険法等の改正で「全国医療情報プラットフォーム」にその情報・データベースを連結させることが確定していることの理解も不可欠です。政府はこの全体を「医療・介護DX」の仕組みとしているのです。
3.介護サービス事業者・従事者はどう対峙すればよいか
①現時点での政府の説明
この事業の施行に際して、介護サービス事業者・従事者はどのように向き合えばよいのでしょうか。
これについて、現時点では政府は次のような説明をしています。
*想定されるメリット・活用イメージ
・要介護認定申請の進捗状況について、ケアマネジャーがWEBサービス画面上で随時確認可能となるため、市町村への電話等での問い合わせが不要となり、業務の効率化につながる。
・ケアプラン作成に必要な要介護認定情報をケアマネジャーがWEBサービス画面上で随時確認可能となるため、情報提供を市町村へ依頼する手続きや市町村窓口・郵送での受取が不要となり、迅速なケアプランの作成が可能となる。
・電子データによる資格情報の確認が可能となることで、サービス提供時の被保険者証の確認等にかかる業務負担が軽減される。
・介護情報基盤を活用することで、利用者の情報を事業所間や多職種間で共有・活用しやすくなり、本人の状態に合った適切なケアの提供が可能となるなど、提供する介護サービスの質の向上が期待できる。
*ご準備いただくこと
・介護WEBサービス(介護情報基盤)を利用するためには、現在インターネットに接続して使用しているパソコンやタブレットに、専用の電子証明書(クライアント証明書)のダウンロードが必要です。
・そのほか、マイナンバーカードで利用者の本人確認を行う際に用いるカードリーダーの導入や、介護WEBサービスを利用する端末への専用アプリケーションのダウンロード、介護WEBサービスの初期設定等の利用端末の環境設定等が必要です。
・医療機関が、電子カルテや文書作成ソフト等から、介護情報基盤経由で主治医意見書の作成・送信を行う場合は、電子カルテや文書作成ソフト等の改修が必要です。
これらはすべて重要なことばかりです。読者の皆さんにはしっかりと確認していただきたいと思います。ただし、極めて穏便に記載されているとも言えます。
そこで、これに付け加えて、私なりに厳しめに以下のような追記をしておきたいと思います。これを含めて、読者の皆さんには介護情報基盤の整備の事業にしっかりと向き合っていただきたいと思います。
②LIFEへの対応の強化・拡大
介護情報基盤の本格稼働に向けて、各事業者等では、利用者の心身機能などについて客観的なスケールやデータに基づいて判断し、その変化に応じてサービスの提供方法を見直すような実践を一層拡大していく必要があります。したがって、LIFEにデータをアップロードするだけでなく、フィードバックされたデータをみて、そこからサービスを見直すようなデータを読み取るスキルが必要となります。
こうしたスキルを「データ・リテラシー」と言いますが、それを実践者は涵養する必要があります。
現実的には、遅くともこの事業が全面施行される2028年4月までに、科学的介護推進体制加算などのLIFE関連加算は、上位の加算が漏れなく算定できる体制をとる必要があります。そこからアウトカム(心身機能の維持・改善)のデータを示すことができる体制づくりをすることも、必然的に求められます。
なぜなら、介護情報基盤では、介護実践現場からのデータはLIFEを最も重要視しており、将来的には、それに基いて、アウトカムに応じたインセンティブ措置を拡大することを想定しているものであるからです。
また、そうした体制を取ろうとすれば、現場のICT化が拡大していることが必須の条件です。この意味では、生産性向上推進体制加算も上位の加算を取得できる体制を取っておくことが不可欠です。
そして、政府・自治体としては、介護情報基盤をしっかりと機能させるために、そうした介護サービス事業者が増えることが重要となります。
したがって、次期(2027年度)介護報酬改定では、こうした加算のさらなる誘導策が拡大されるでしょうし、LIFE関連加算の「蚊帳の外」であった居宅介護支援(ケアマネジメント)や訪問介護・訪問看護にも同様の報酬体系が組み込まれることが確実視されます。
③ケアプランデータ連携システムの利用拡大
介護情報基盤には「ケアプランデータベース」も格納されることになっていると前述しました。これについて、居宅介護支援事業所等からのケアプランデータのアップロードは、既存の「ケアプランデータ連携システム」を用いることが決まっています。
しかし、デジタル庁が公表している「介護現場の生産性向上に関するダッシュボード」から「ケアプランデータ連携システムの複数事業者活用自治体割合(3割以上の事業者が利用している市区町村の割合)」を確認すると、今年9月末時点でわずか7.4%にとどまっています。惨憺たる実情と言ってよいでしょう。
介護情報基盤の整備の事業が全面施行される2028年4月以降、給付管理業務もサービス提供票の送付も、そして介護サービス事業所へのケアプランの交付も、すべてケアプランデータ連携システムを用いることになることが確定的ですので、このシステムの導入は不可欠となります。
むろん、介護情報基盤の本格稼働に向け、2027年度の制度改正や介護報酬改定の際、このシステムの利用についての誘導策が矢継ぎ早に示されることも間違いありません。
④医療・介護連携は「介護情報基盤」を媒介に
介護サービス事業者・従事者は、介護情報基盤に関連するデータの提出・利活用に消極的な姿勢をとるケースが多いようです。確かに、法令上はここへのデータ提出などは「任意」となります。
しかし、前述したように、この介護情報基盤はマイナ保険証や要介護認定事務と一体運用されることになります。介護情報基盤の事業に参画しない事業者は、遅くとも2028年4月には、利用者の被保険者情報の把握や要介護認定の通知などへの対応が不十分となり、自動的に不利益を被ることになるでしょう。
さらに、介護情報基盤は「全国医療情報プラットフォーム」に連結されることが決まっているということも前述しました。医療機関・訪問看護ステーション・調剤薬局、さらには保健行政がもつ膨大なデータは臨床的にも共同利用され、各機関の連携にも用いられ始めています。具体的には、既往歴・現病歴や薬剤の情報、さまざまな臨床データなどの共同利用はすでに軌道に乗りつつあります。
そこに介護情報基盤が連結されるということは、日常的な医療・介護連携も、この巨大なデータベース上で行われることを意味します。介護情報基盤に参画しない、LIFEもケアプランデータ連携システムも使わないという介護サービス事業者は、全国医療情報プラットフォームに接続できない事態は容易に想像できます。
そうなれば、入退院時の連携も、施設や在宅で介護サービスを利用している際の医療機関との連携も、現実的には困難になってしまいます。
このプラットフォーム全体が本格的に動き始めた時には、おそらく退院時カンファレンスや入退院時の情報連携は、対面や文書で行われることはなくなり、すべてデータ上で、あるいはオンライン上で行われることになるはずです。
この意味で、医療介護連携を「顔の見える関係」などといって模索してきた仕組みは過去のものとなり、「データで連携する関係」という仕組みに取って代わられることになるでしょう。
4.おわりに
介護情報基盤の整備の事業が施行されることは、介護実践現場にDXが求められ、前述したEBLTCが推奨されることに他なりません。そして、政府・自治体にも介護についてEBPM(Evidence-Based Policy Making:データや科学的根拠に基づいて政策を立案・実施・評価する手法)を求めることになります。このことをしっかりと理解しておくことが必要です。
一方で、介護DXなどの取り組みは「生産性向上」施策の一環としても位置付けられており、私は大変に気になっているポイントです。この一抹の懸念については、次回のこのリポートで解説したいと思います。