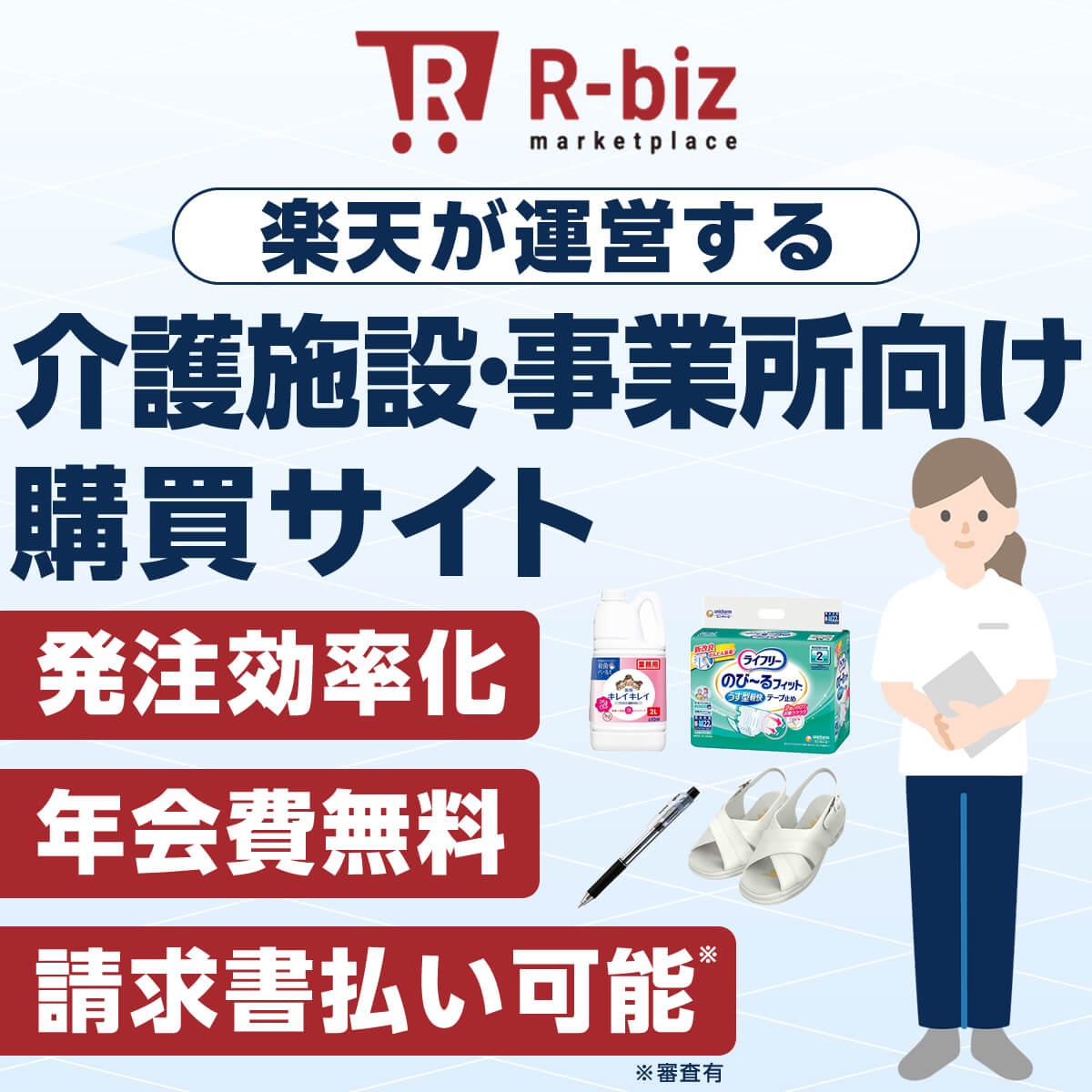毎年4月は、前年度に厚生労働省が行った研究事業の成果が報告される時期です。そこで今回は、4年間にわたって研究が続けられた「ケアプラン点検」に注目してみましょう。【石山麗子】
◆ ケアプラン点検の進化
既存のケアプラン点検支援マニュアルは、2008年に厚生労働省によって作成され、それ以降、各地域で使われてきました。
研究事業で分かったこととして、ケアプラン点検の実施方法は様々であり、多くの保険者が専門的な知識やスキルを持つ職員の確保に苦労していること、人材不足が課題であることがあげられます(2021年度調査結果)。
その結果、点検を受ける側にとっては、一定水準に達しない、または一貫性に欠ける点検が行われる場合があることが課題となっています。
そこで、ケアプラン点検の方法を統一するとともに、保険者の事務負担を軽減して効果的・効率的な点検を行うために、「ケアプラン点検項目」と「ケアプラン点検支援ツール」が策定されました。これらは、適切なケアマネジメント手法に基づくよう留意して作られました(2022年度)。
これらはさらに、厚生労働省が発表した新しいアセスメント項目「課題分析標準項目」に対応できるように改良されました。このツールは、複数のツールをパッケージとして活用できるよう工夫されており、保険者だけでなく、ケアマネジャーの自己チェックや育成の場面でも使えるようになりました(2023年度)。
そして2024年度には、これらのツールをさらに見直し、最終的には保険者に説明するための研修会も開催されました。
◆ 不満が残るようでは…
一連の研究事業は、ケアプラン点検を実施するかどうかを議論するものではありません。むしろ、点検の効果を高めるための工夫について話し合ってきました。
特に意識されたのは、保険者職員の業務負担の軽減だけでなく、ケアプラン点検の本来の目的を達成し、点検を受ける側の心理的負担も軽くすることです。
現場で働く人にしか分からないこともありますが、市町村には介護保険の保険者として点検をしっかりと行う責任があります。お互いが努力しているのに不満が残るようでは、本来の目的である「被保険者の支援」を実現するために不都合が生じる恐れがあります。そのため、点検項目だけでなく、点検の視点や判断基準までを事前に明示しました。
新しいケアプラン点検では、保険者がケアマネジャーに気付きを与えるという指導関係ではなく、「ケアマネジャーと保険者の両者が気付きを得て学び合う」ことを目的の1つとしました。お互いが対等な立場で学び合える関係であることが強調されています。