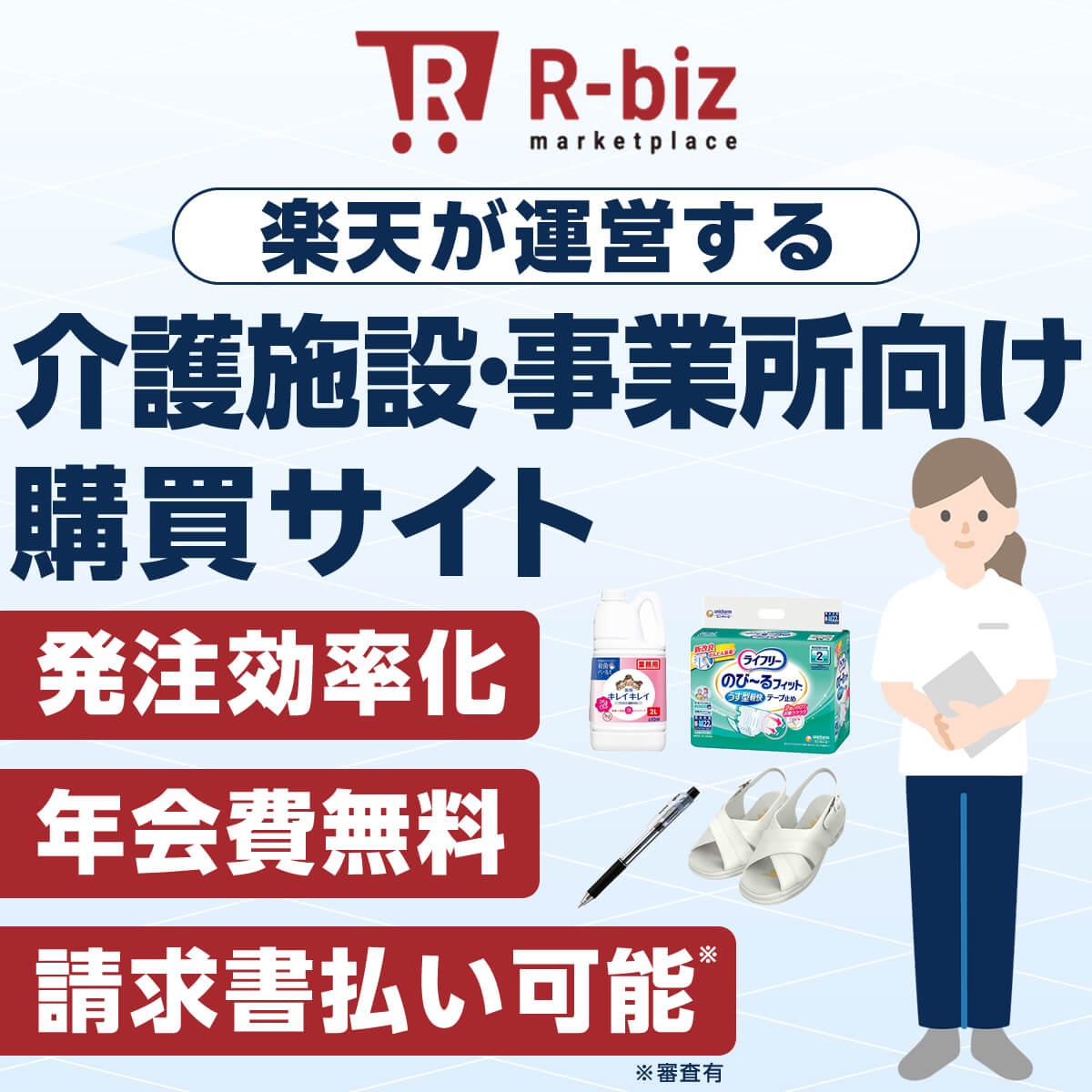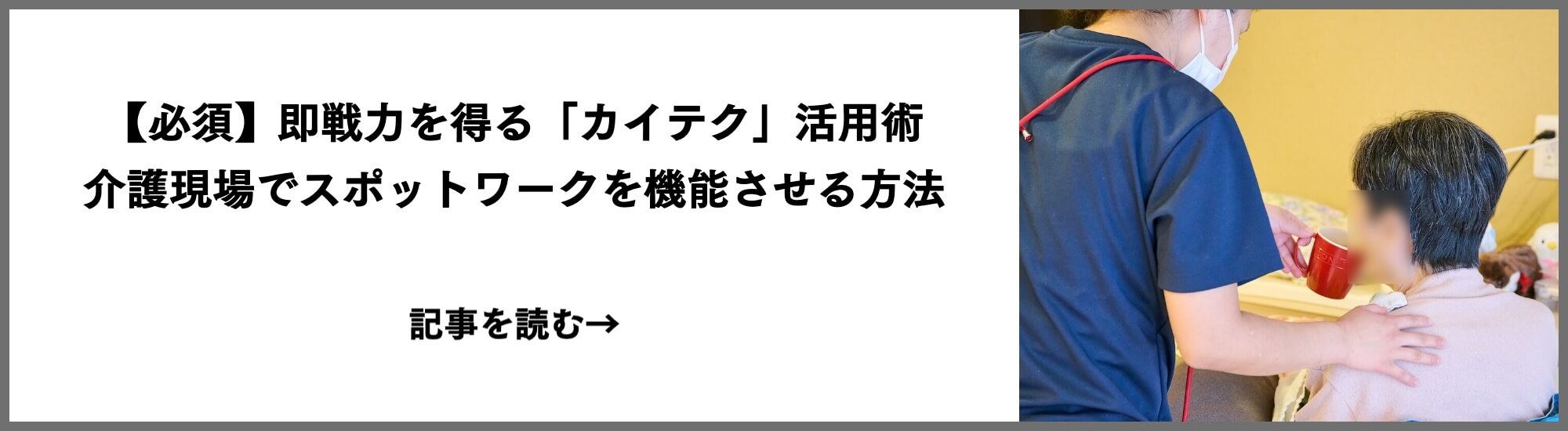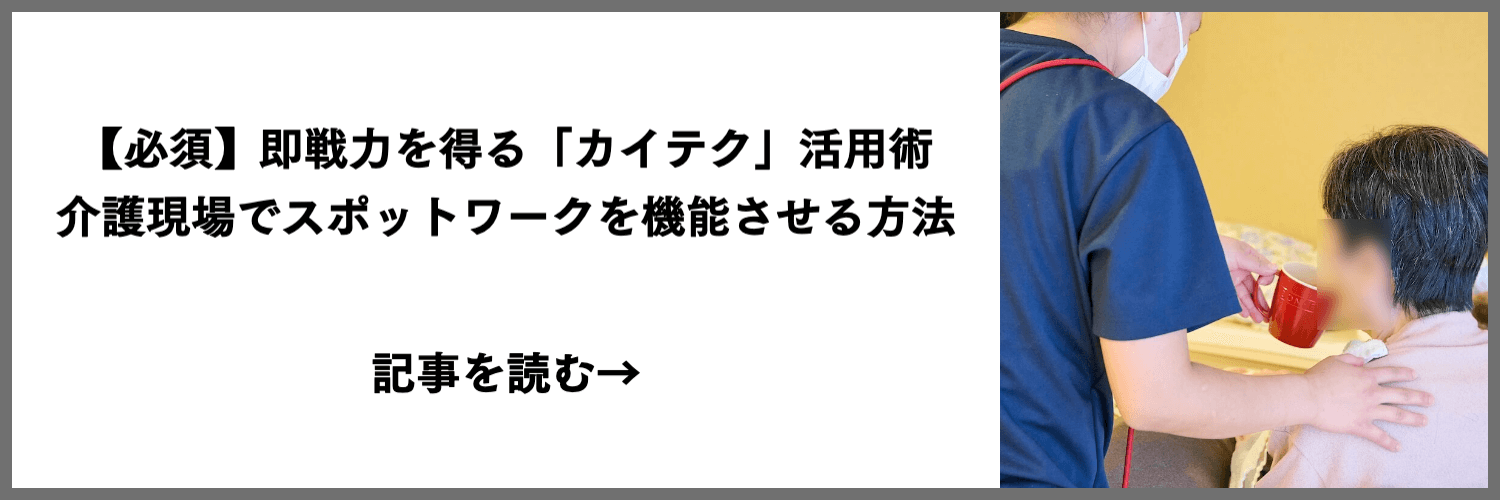【青柳直樹】老人ホームの過剰サービス、悪貨が良貨を駆逐しないために 最期を支えるホスピスの光と影


サービスが過剰に提供されているのではないか − 。こうした疑念が今、有料老人ホームをめぐって強く投げかけられています。【青柳直樹】
厚生労働省はこの問題を受けて、今月14日、新たに検討会を立ち上げました。議論の発端となったのは、訪問看護が何度も繰り返し提供され、その結果として高額の請求につながっていた一部の事例です。制度の濫用ではないかとの指摘が相次ぎ、適正化の行方に注目が集まっています。

青柳直樹|医師。2017年にドクターメイト株式会社を創設。日本ケアテック協会の理事も務める。介護施設が直面する医療課題に対応すべく、オンラインの医療相談や夜間のオンコール代行などのサービスを展開中。介護職の負担を減らすこと、利用者の不要な重症化、入院を減らすことなどに注力している。
一方で、現場の看護職が「やりがいを持って支えていた」「病院にも在宅にも受け皿がない人たちの最後の居場所だった」と語っているように、この仕組みが果たしてきた役割も決して小さくありません。問題の核心は、ホスピスケアという仕組みが持つ意義を認めながら、いかに不適切な運用を是正し、健全な形で未来につなげていくかという点にあります。
◆ 制度の信頼を揺るがす過剰サービス
国の現行の制度では、末期がんや特定の疾患がある方に対し、医師の指示があるなど一定の要件を満たしていれば、訪問看護を多く提供することが可能とされています。これ自体は、在宅での看取りなどを支える重要な仕組みです。しかし実際には、制度を恣意的に活用してサービス提供回数をできるだけ増やし、高額な報酬を得ていた施設があったとされます。
中には、記録上では30分以上のサービスを複数の職員で提供したとしながら、実際には数分程度しか訪問していなかったという内部告発も出ています。仮にこれが事実とするならば、「必要なサービス」を超えた過剰供給であり、制度への信頼を揺るがす問題と言わざるを得ません。
◆ 制度全体への逆風にならぬように
ただし、議論は冷静に進めるべきです。こうした問題が一部に見られたからといって、制度全体を否定することはできません。特にホスピスケアは、医療的ケアを必要とする方の「最後の暮らしの場」として、大きなニーズに支えられています。
例えば、末期がんの方を病院から在宅に戻すことは、多くのケースで困難を極めます。介護施設も医療対応が難しい場合があり、両者の間を橋渡しする場として、有料老人ホームによるホスピスケアが重要な役割を果たしてきました。実際に、看取りが今後さらに増加することが見込まれており、制度の根幹まで揺るがすような改革には慎重さが求められます。
◆ 見直すべきは「ラインの曖昧さ」
今回の問題の背景には、制度の「曖昧な基準」があると指摘されています。医師の指示などで頻回の訪問看護を認める仕組みは、本来は一時的・限定的な対応を想定したものです。しかしそれが、現場では「ここまでやっても構わない」という解釈にすり替わってしまっている場合もあります。
制度上明らかな違反とは言えなくても、実質的には不必要なサービスを繰り返しているとすれば、それは持続可能な制度運用とは言えません。今後は、訪問頻度や算定要件に一定の上限を設けるなど、現実に即したルール作りが求められるでしょう。
◆ 民間なしでは成り立たない
厚労省の検討会でも繰り返し指摘されたのが、「一部の悪質な事例が、真摯に取り組んでいる事業者の存在を脅かしてしまう」危うさです。理念を大切にしながら地域に根ざしたホスピスケアを提供している事業者にまで、過度な規制や報酬引き下げが及べば、結果的に「悪貨が良貨を駆逐する」事態にもなりかねません。
介護や医療の分野では、すでに民間の力なくして成り立たない領域が数多くあります。わずかでも利益を上げれば即座に規制対象とされるような風潮が強まれば、参入意欲を削ぎ、持続可能な基盤を壊すことにもつながります。
◆ 地道な是正で「信頼される仕組み」へ
ホスピスケアは、今後ますます必要とされるサービスです。その制度を守り、発展させていくには、不適切なサービス提供の温床となり得るルールのグレーゾーンを丁寧に埋めていく地道な改善が欠かせません。
議論の主軸は、単なる「規制強化」や「厳格な取り締まり」ではなく、「健全な制度運用をどう実現するか」であるべきです。すべては、安心して最期の時を迎えたいと願う利用者と、その支援を担う専門職のために − 。今後、きめ細かい丁寧な議論が進むことを望みます。