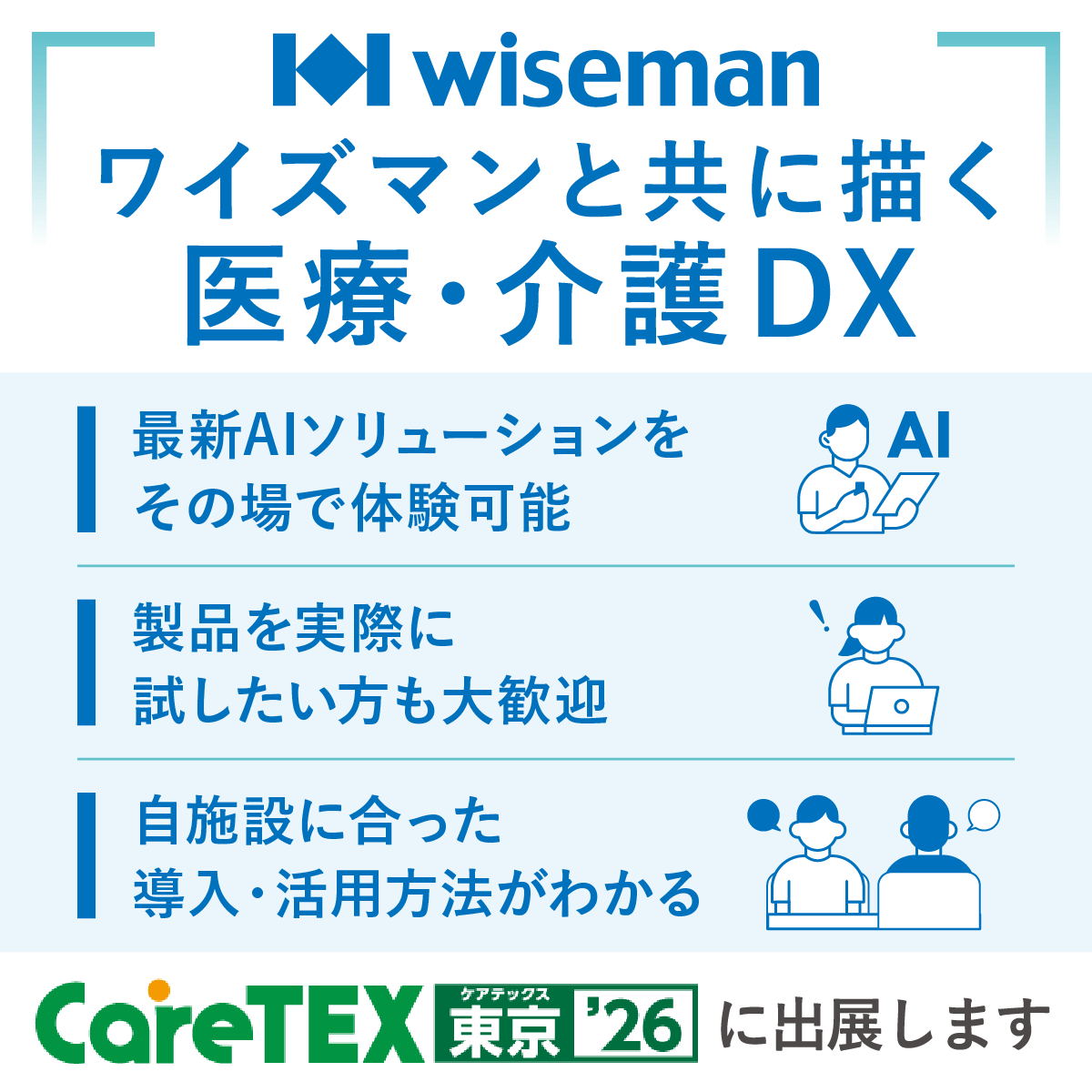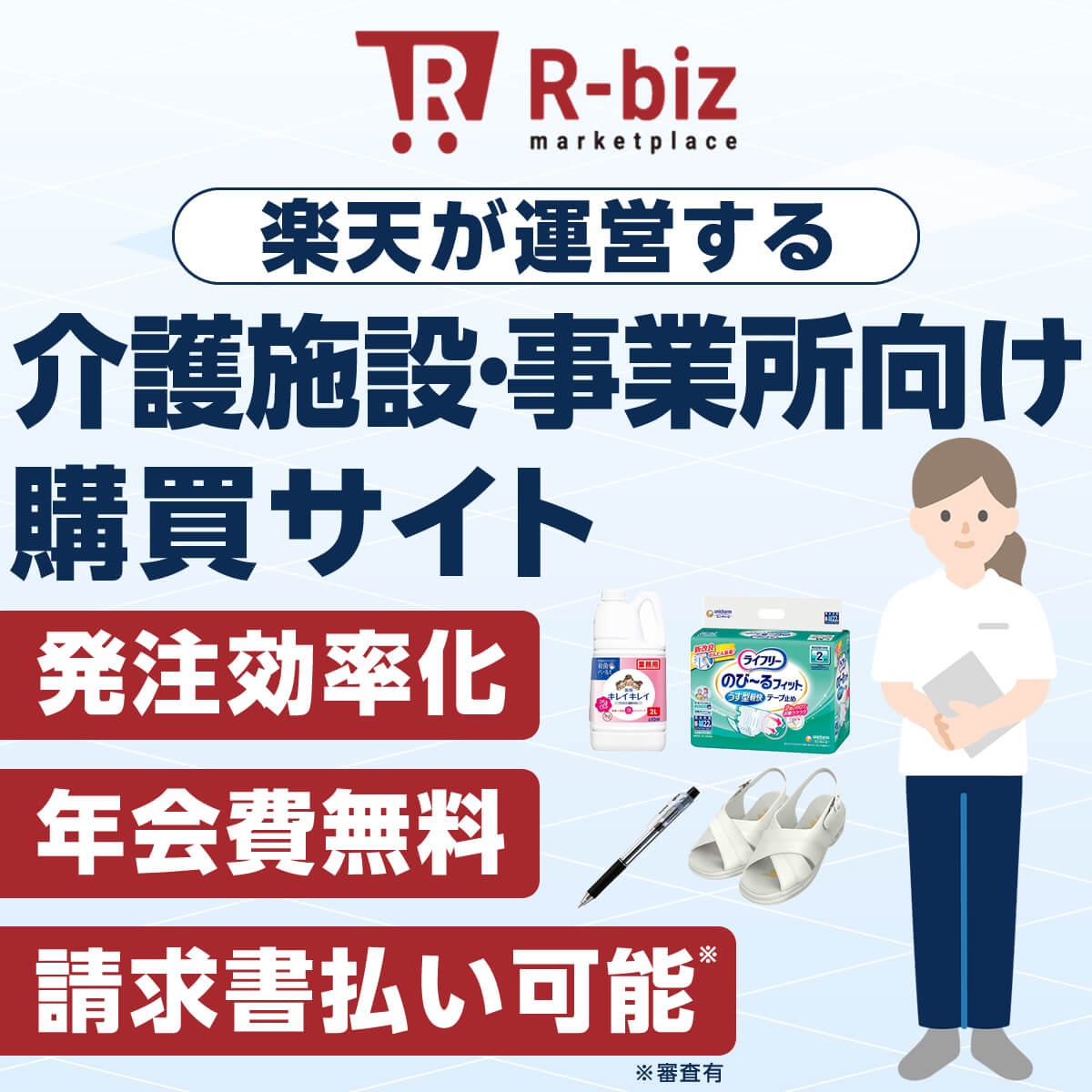【片岡眞一郎】在宅介護のテクノロジー活用はなぜ遅れているか 現場の“構造的な壁”と突破のヒント


2040年に向けた介護サービス提供体制のあり方を議論してきた厚生労働省の検討会が、4月10日に中間とりまとめを公表しました。【片岡眞一郎】
この中には、訪問系サービスや居宅介護支援といった在宅系サービスでもテクノロジーの有効活用を図り、職員の負担軽減やサービスの質の向上につなげる構想が盛り込まれています。しかしながら、在宅系サービスは施設系サービスと比べてテクノロジーの導入が進んでいない状況にあります。
本稿では主に在宅系サービスに焦点を当てます。現在、テクノロジーの導入が進んでいない理由はいくつか存在します。
◆ 簡単ではない導入促進
その1つは、施設系サービスと比べてサービス種別が多岐にわたり、それぞれに適したテクノロジーの開発が必要となることです。これはテクノロジーを開発する企業にとって、ビジネスマーケットが細分化されて投資判断を難しくします。
また、施設系サービスと異なり、複数の介護事業所が関与している点も普及を阻害する要因となっています。例えば、ケアプランデータ連携システムを自事業所で導入したとしても、地域で関与する他の事業所が導入していない場合は、その効果が出にくくなってしまいます。
また、訪問系サービスはサービス提供時間に応じて報酬が決まるため、「職員の業務効率化が収入減につながるのでは」という懸念が生じがちです。特に、直接的なサービス提供時間に関わる部分の効率化への抵抗感が生まれやすい側面も、普及を妨げる要因となっています。
◆ 先進的な事業所も
それでは、在宅系サービスでのテクノロジーの活用余地はどこにあるのでしょうか。
施設系サービスでは、見守り支援機器、インカム、記録システムなどを活用し、業務の効率化による利用者満足度の向上や職員の負担軽減、それに伴う離職率の低下など、成果を上げている好事例も増えてきています。他方、在宅系サービスでも少しずつ、その兆しとなるような取り組みが出始めています。
例えば、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを導入し、外出先でも各種記録などのデータにアクセスできる体制を整備することがあげられます。訪問の合間の時間、事務所に戻らなくても書類を作成できるようになり、業務の効率化が図れるためです。
また、職員同士の連絡にメールやビジネスチャットを活用することで、情報伝達を効率化することも1つの方法です。最近では、生成AIを活用したケアプランの作成支援、アセスメント情報の整理、申請書類の作成を実施するなど、先進的な事業所も出始めています。
◆ 重要な課題分析、業務の切り出し
一方で、すべての業務をデジタル化すればよいというわけではありません。
例えば居宅介護支援では、モニタリングなどを原則対面で実施することをルール化している事業所もあります。Web会議ツールなどを活用することも可能ではありますが、自宅や生活の状況など、実際に訪問しなければ把握できない情報もあると考えているためです。
こうした視点は非常に大切ですし、何よりも、タイムスタディなどを活用して事業所の業務の状況や課題を分析したうえで、テクノロジーに任せる業務を整理して切り出すことにより、相談援助業務や事務業務の適切な効率化を検討することが重要です。
なお現在、ケアプランデータ連携システムを活用したサービス計画表の送付、提供票(予定)の送付、提供票(実績)の受領などの電子化により、印刷や情報共有の時間を削減する事業所も増え始めています。
例えば、鳥取県米子市のように、自治体が積極的に導入を奨励し、事業所の申請率が30%を超えてくれば、改善効果がより顕著に現れるようになってきます。国も導入促進のため、今年6月から「ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン」といった支援策を講じるので、ぜひこの機会に活用していただくことをお勧めしたいです。
在宅系サービスでのテクノロジーの活用は、施設系サービスに比べて複雑な課題を抱えていますが、相談援助業務や事務業務を中心として効率化と質の向上につなげる兆しが見え始めています。
自事業所の業務を客観的に分析し、課題を明確にしながら、そのうえで、ケアプランデータ連携システムやビジネスチャットなど課題解決につながるテクノロジーの導入を、1つでも2つでも具体的に検討していくことが重要になるでしょう。
テクノロジーの導入にはオペレーションの変更が伴うこともあり、事業所・職員にとって負荷がかかる側面もあります。ただ、業務分析に基づく適切なテクノロジーの活用により、業務負担を軽減して職員が本来の専門性を発揮できる環境を整備することで、サービスの質を更に高めていけるようになりますので、やはり非常に重要です。
我々も事業所の皆様と一緒に、在宅介護の維持・充実のために取り組んでいきたいと思います。