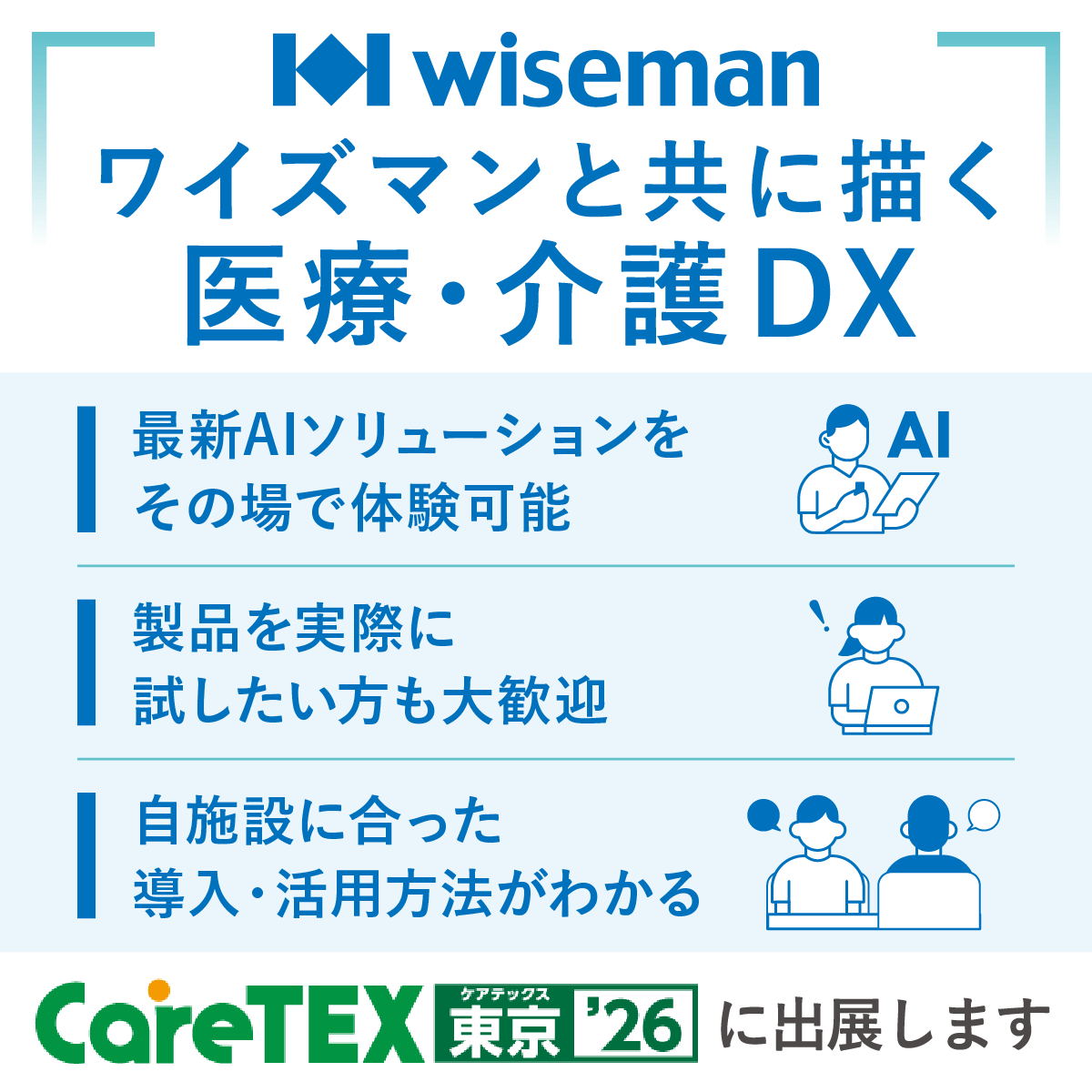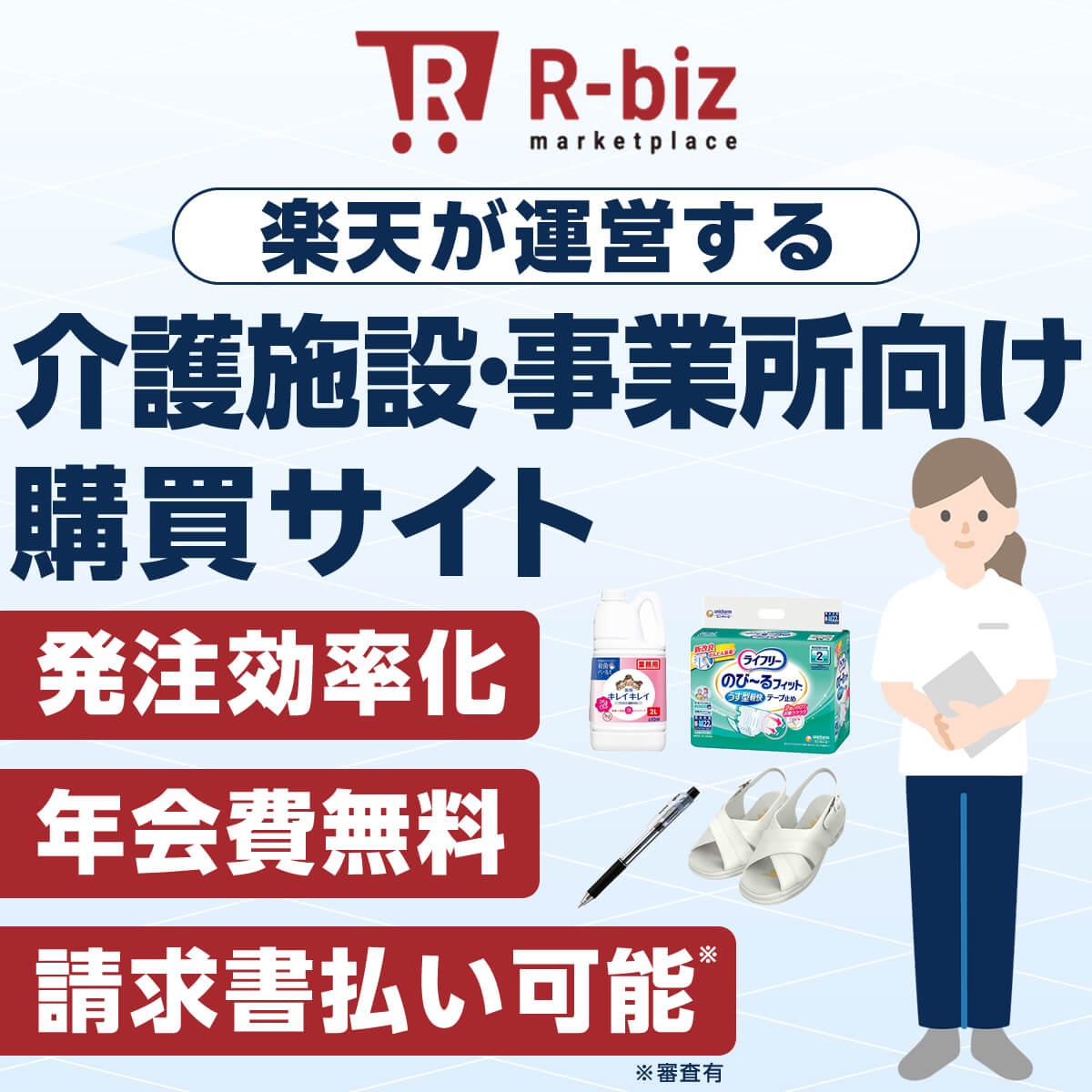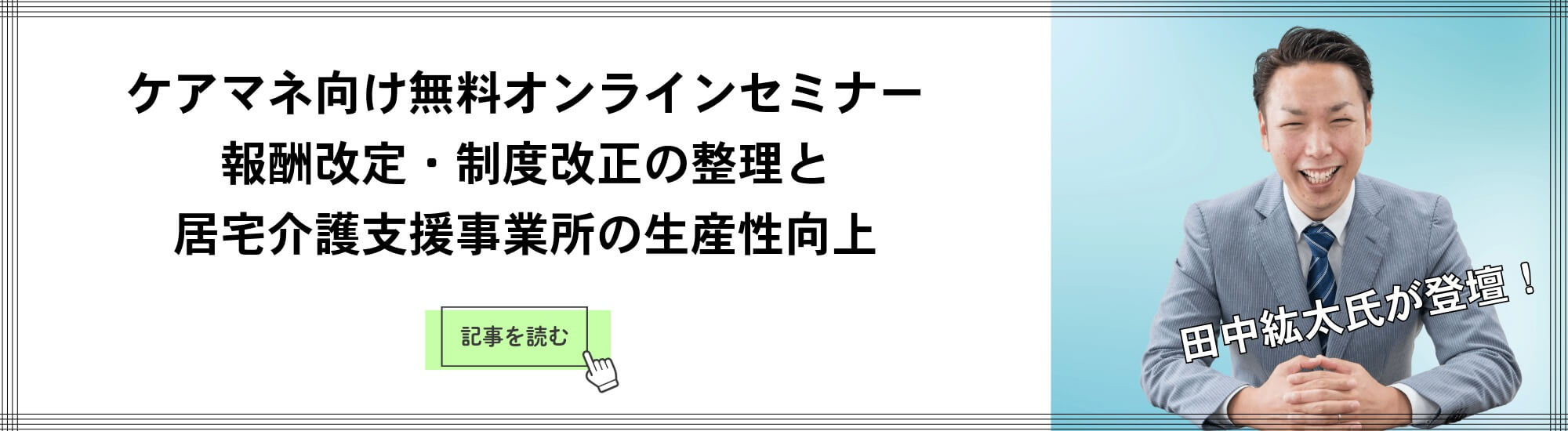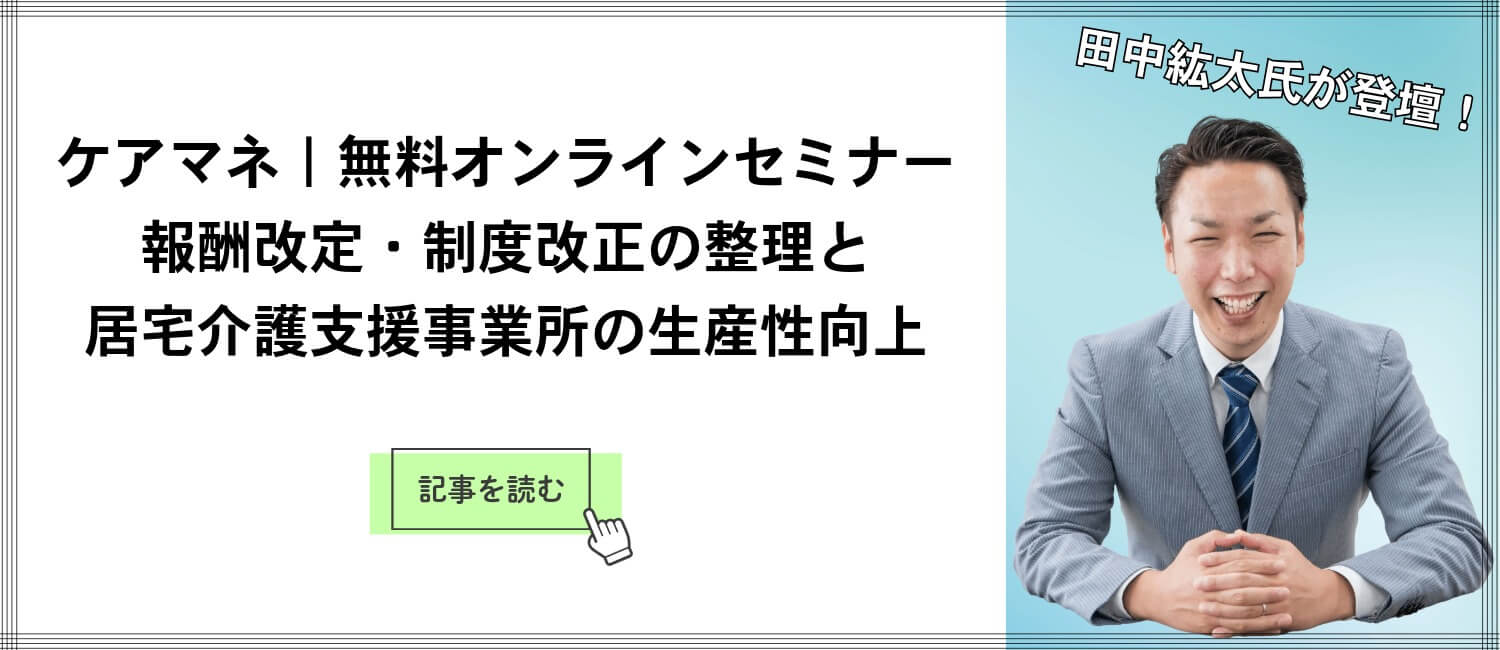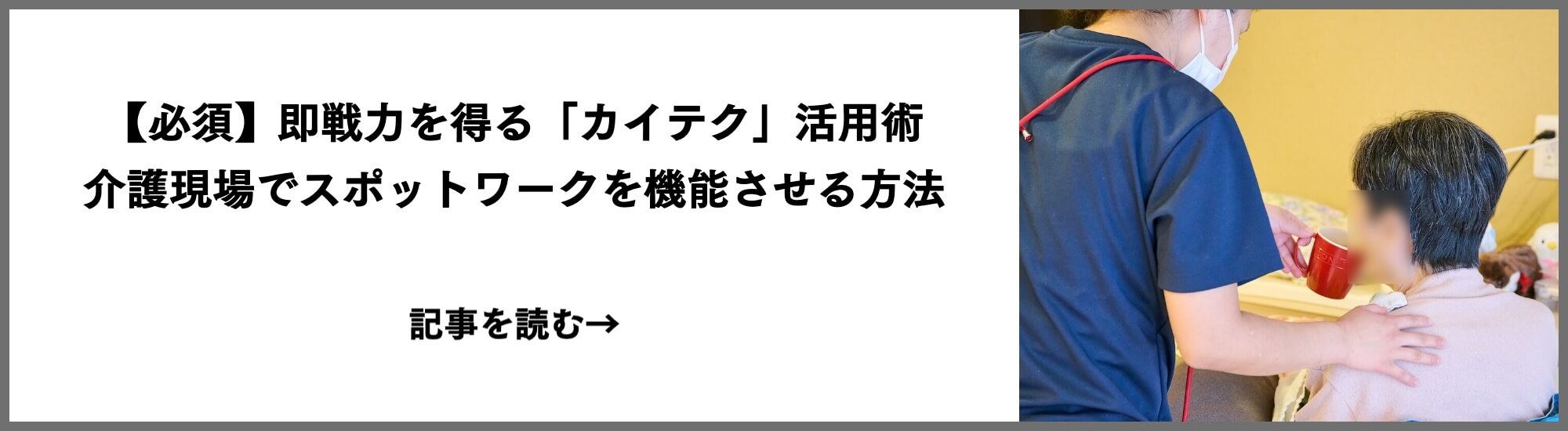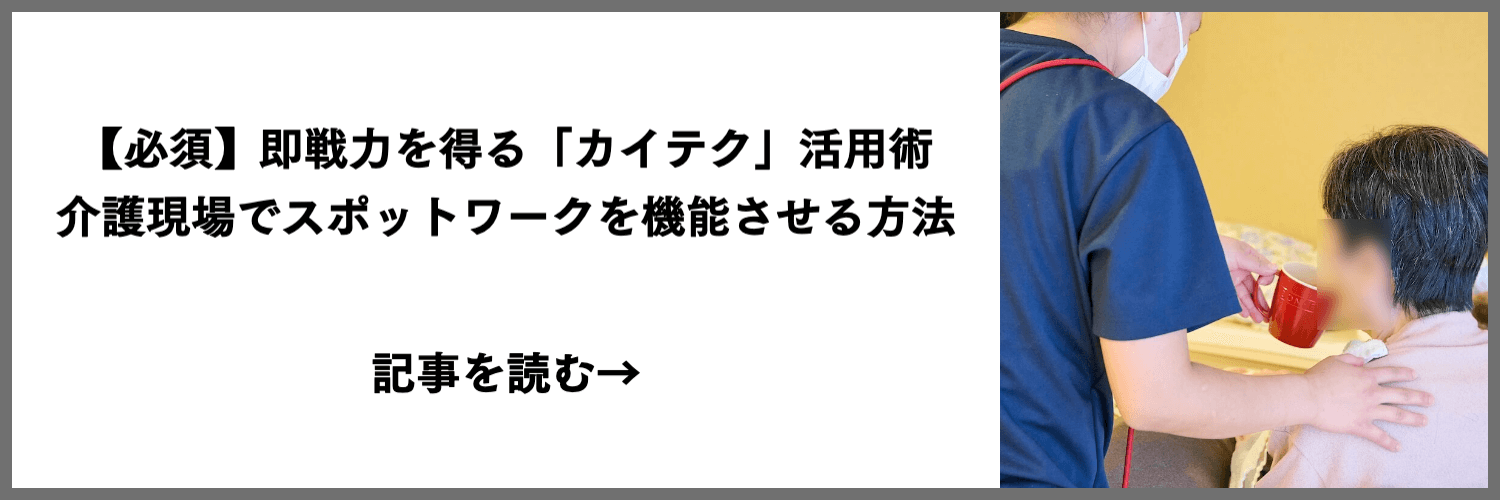【奈良夕貴】週休3日制は介護現場をどう変えるか 制度導入と“働き方再設計”の現在地


◆「週休3日制」は介護現場に馴染むのか?
柔軟な働き方の実現が政策的にも求められる中、介護業界でも「週休3日制」の導入が注目されています。【奈良夕貴】
国の「こども未来戦略」や第9期介護保険事業計画に基づく「総合的な介護人材確保対策」でも、週休3日制の推進が明記されており、育児・介護との両立、副業・兼業への対応などを背景に、柔軟な働き方のひとつとして全国的な機運が高まりつつあります。
すでに一部自治体ではモデル事業が展開されています。宮城県や福島県の介護事業者では、導入を契機に求人応募数が増加した、通勤回数が減って生活が安定したなど、一定の成果が報告されています。今年度から大阪府もモデル事業所を開始しました。
週休3日制は、特に、これまで介護職に関心のなかった若年層や異業種からの応募を呼び込む事例を生んでおり、新たな層へのアプローチ手段となっています。また、採用促進や離職防止に加え、職員のエンゲージメントや勤務満足度の向上、職場の一体感の醸成など、間接的な効果も指摘されています。働きやすい環境は、結果として介護の質を高めることにもつながります。
◆ 実は“全員がハッピー”とは限らない? 制度の落とし穴とヒント
ただ、週休3日制を導入すれば即効果が得られるわけではありません。たとえば、完全週休3日制を導入した法人では、採用効果が顕著であった一方、従来の勤務形態に慣れた中堅職員が新制度に適応できず、結果として退職に至ったケースもあります。
制度が新しいからこそ、こうした影響は長期的に検証していく必要があります。定着率や離職率などの実質的な効果は、時間をかけてこそ見えてくるものです。新たな制度を導入する際には、新規採用者だけでなく、今いる職員をいかに大切にするかという視点も欠かせません。
ここで注目されるのが、「選択的週休3日制」という考え方です。完全週休3日制しか選択肢がない場合、かえって働き方の自由度が狭まり、制度が逆効果になるおそれがあります。
一方で、シフト調整が複雑になることから、完全週休3日制の導入を希望する法人が多いのも事実です。解決策として、例えば、法人内に旧来通りの勤務が可能な部署を残す、短時間勤務制度と組み合わせるなど、多様な働き方の選択肢を確保することが求められます。
特に、新人職員や外国人職員にとって、入職初期はOJTやコミュニケーションが重要な時期であるため、まずは週休2日制で進め、段階的に移行するなど、柔軟な設計も考えられます。
現場の懸念や不安に丁寧に向き合い、試行期間を設けたうえで、段階的な導入を進めていくことが、制度定着の鍵になると考えられます。
◆「休みを増やす」だけではない、これは“働き方改革”そのもの
さらに重要なのは、週休3日制を「休日数の変更」ではなく、「働き方の再設計」として捉える視点です。業務の棚卸しや間接業務の標準化、ICTの活用、eラーニングの導入、スポット人材の活用など、複合的な取り組みを並行して行う必要があります。制度の持続的な運用には、管理職の負担軽減やマネジメント支援も不可欠です。
週休3日制は、ゴールではなくスタートです。制度の導入をきっかけに、職員一人ひとりのライフスタイルに合った働き方を実現し、より持続可能で魅力ある介護現場をつくる第一歩とすることが期待されます。