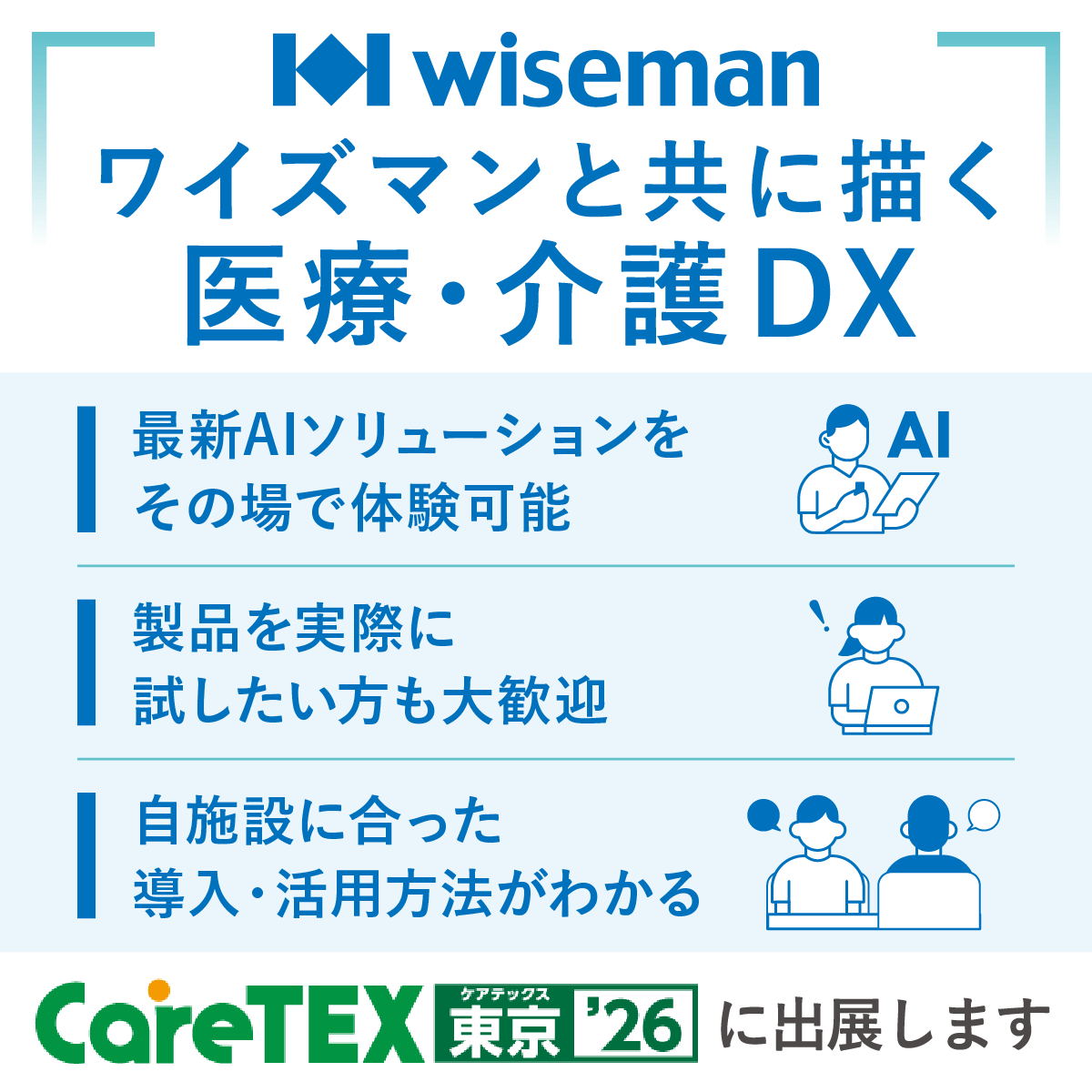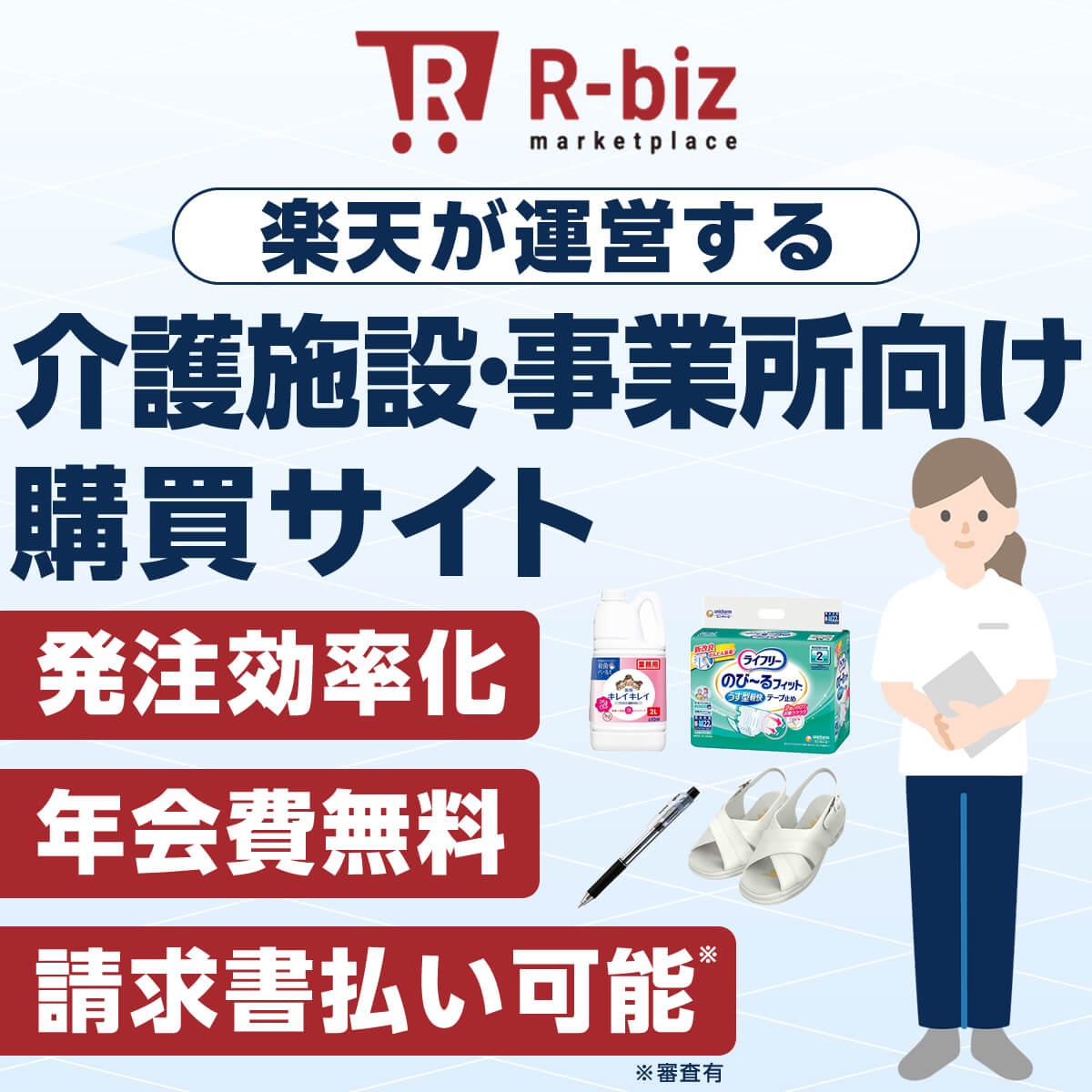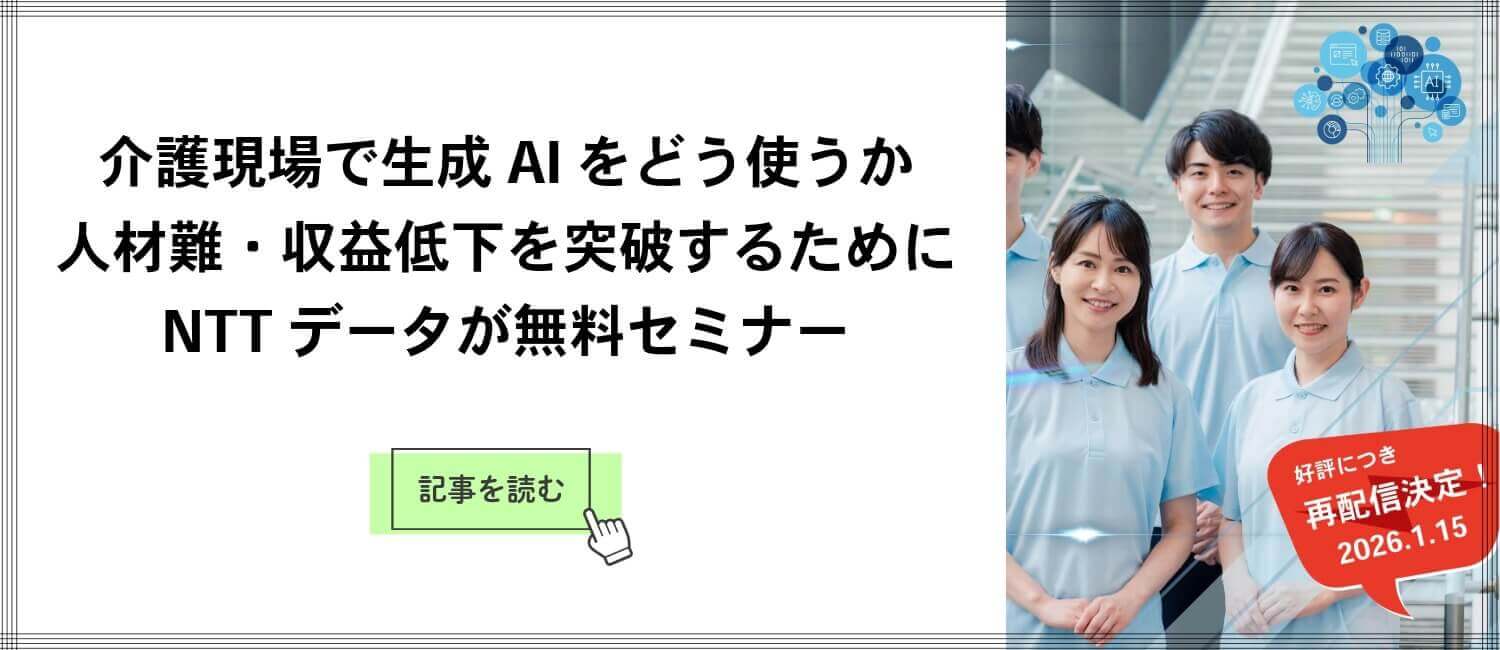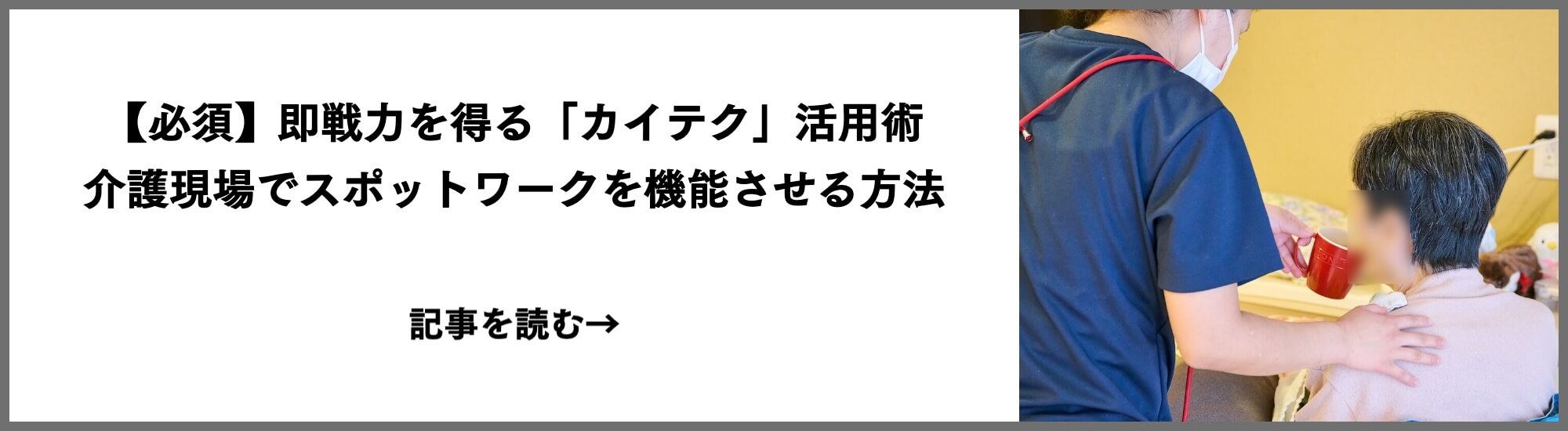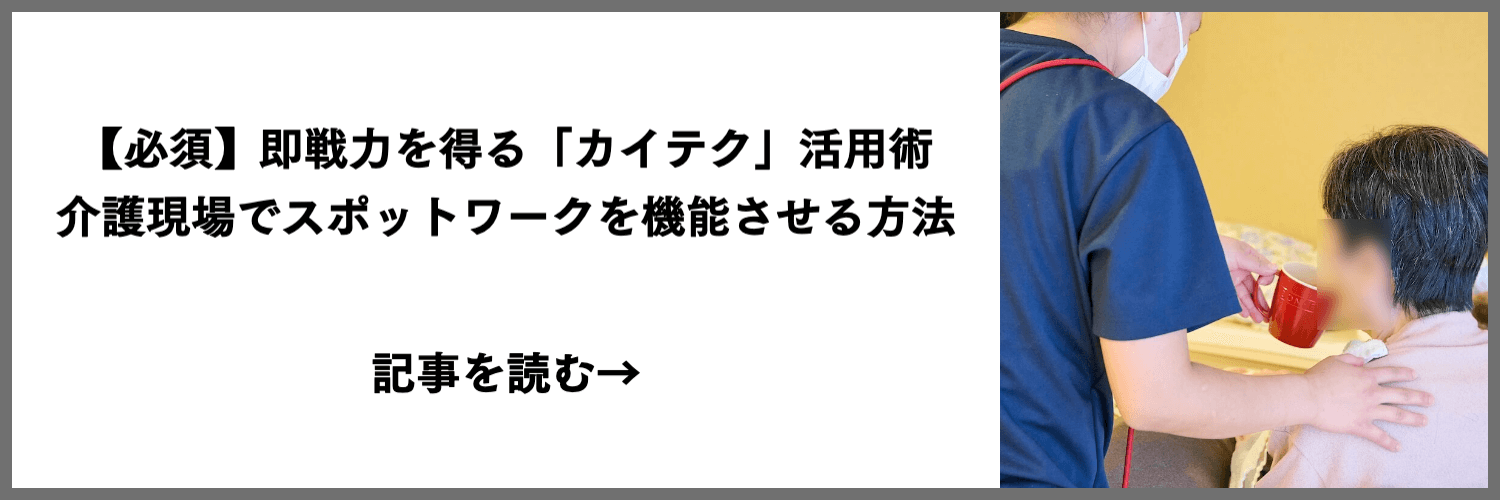【壷内令子】ケアマネのシャドウ・ワークがまた増える? 要介護認定の主治医意見書の事前入手、ルール明確化への期待と不安


◆ 全国に広がるか?
厚生労働省は先月末の審議会で、要介護認定のプロセスで不可欠な主治医意見書について、申請者が事前に自ら入手しても差し支えないことを、ルール上明確にすることを提案しました。これまで一部の自治体で運用されていた実情を踏まえ、今後はその位置付けを明確にする方向で検討を進めると報じられています。【壷内令子】
厚労省の調査によれば、92.3%の自治体では市町村が主治医に意見書の作成を依頼する方式を採用している一方で、2.9%では申請者が意見書を事前に取得する運用が行われています。実は、私が活動している地域もこの2.9%に該当しているのですが、現場の実感としては賛否の意見が混在しています。ケアマネジャーにとって、この主治医意見書の事前入手による影響は決して小さくありません。
◆ 早まる認定、深まる連携
当然、事前入手には相応のメリットがあります。まず、主治医意見書が早く提出されることで、要介護認定の流れがスムーズになり、結果の通知の遅れが改善されます。暫定ケアプランの作成を避けられるケースが増え、後から限度額やサービス内容を調整する必要も少なくなります。
特に、医療的ケアが必要な高齢者や在宅療養中の高齢者について、正式な認定結果に基づいた支援が早期に開始できるため、より適切なサービスの提供につなげることができます。これは、利用者に安心をもたらすだけでなく、ケアマネジャーにとっても負担軽減につながる大きなメリットと言えます。
また、申請段階からかかりつけ医との連携が始まることで、日常的な医療連携の促進にもつながります。顔を合わせて意見を交換する機会が増えれば、主治医からの助言や情報提供を得やすくなります。制度として明確化されることで、地域の医療・介護連携の質が高まると期待できるでしょう。
◆ 広がる役割、重なる業務
とはいえ、現場で実際にこの運用を担っている立場から見ると、課題も多くあります。
例えば主治医が遠方の場合。意見書を受け取りに行くだけでも時間と労力がかかります。加えて、作成の依頼や催促、作成状況の確認、期日の管理など、様々な調整業務が発生します。
制度上は明記されていないものの、主治医から意見書を得るまでのプロセスで、実質的にケアマネジャーが担うことになる業務は少なくありません。こうした中で増えていく調整や対応は、やはりシャドウ・ワークとして日常業務にのしかかってくることになります。
また、紙の主治医意見書の持ち運びは個人情報漏洩のリスクを伴い、セキュリティ面での不安も強まります。
◆「あるべき形」を地域で探る
将来的に介護情報基盤が整い、主治医意見書の電子化やオンライン提出が実現すれば、こうした負担やリスクは大幅に軽減されるはずです。しかし、その実現までの間に生じる現場の混乱やケアマネジャーの疲弊を防ぐため、丁寧な制度設計と運用が欠かせません。
大切なのは、地域で有効な協力体制をどう築くか、という視点です。一方に負担を押しつけるのではなく、行政も、ケアマネジャーも、利用者も、それぞれの立場が尊重されるような運用が求められます。誰もが納得できるかたちを地域全体で話し合い、それを支え合って築いていくことが必要ではないでしょうか。
私自身、25年間、主治医意見書の事前入手の運用が実際に行われている地域でケアマネジャーとして活動してきた立場から、制度を運用する側にも、ぜひ現場の声をしっかりと汲み取っていただきたいと強く願っています。