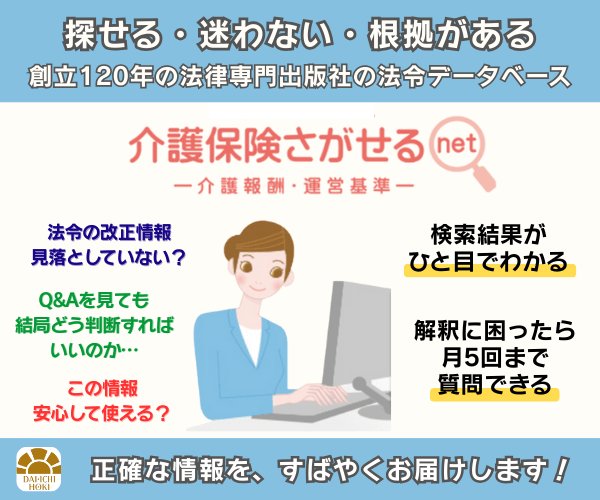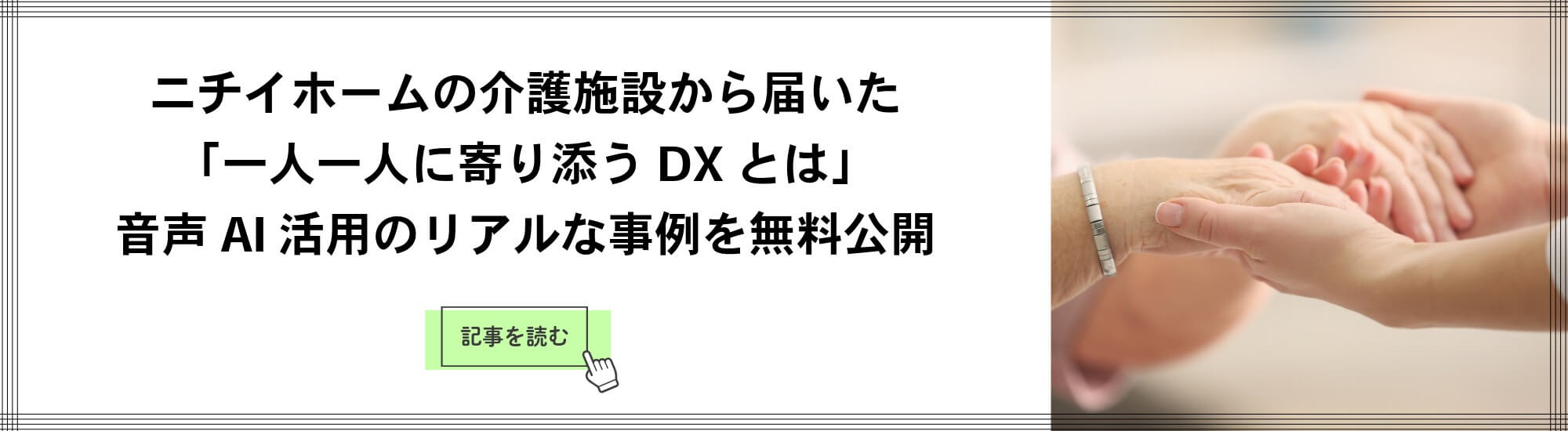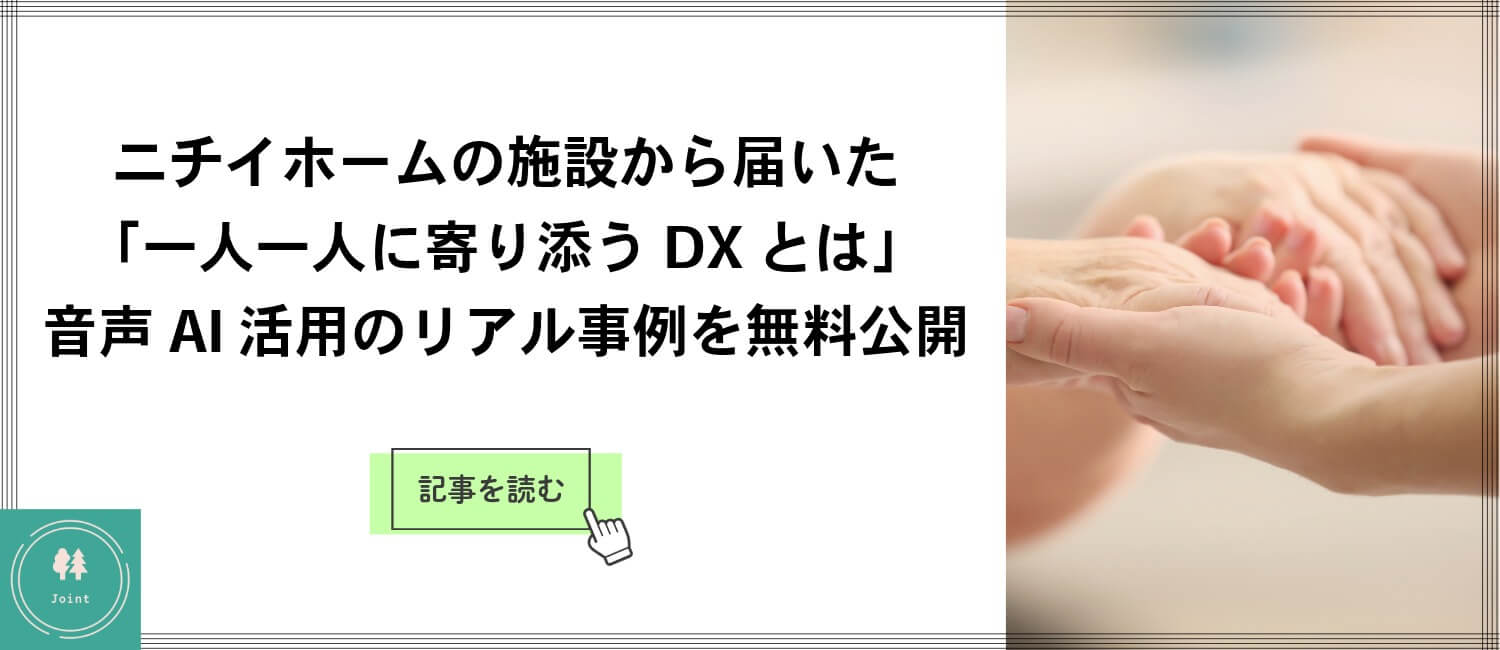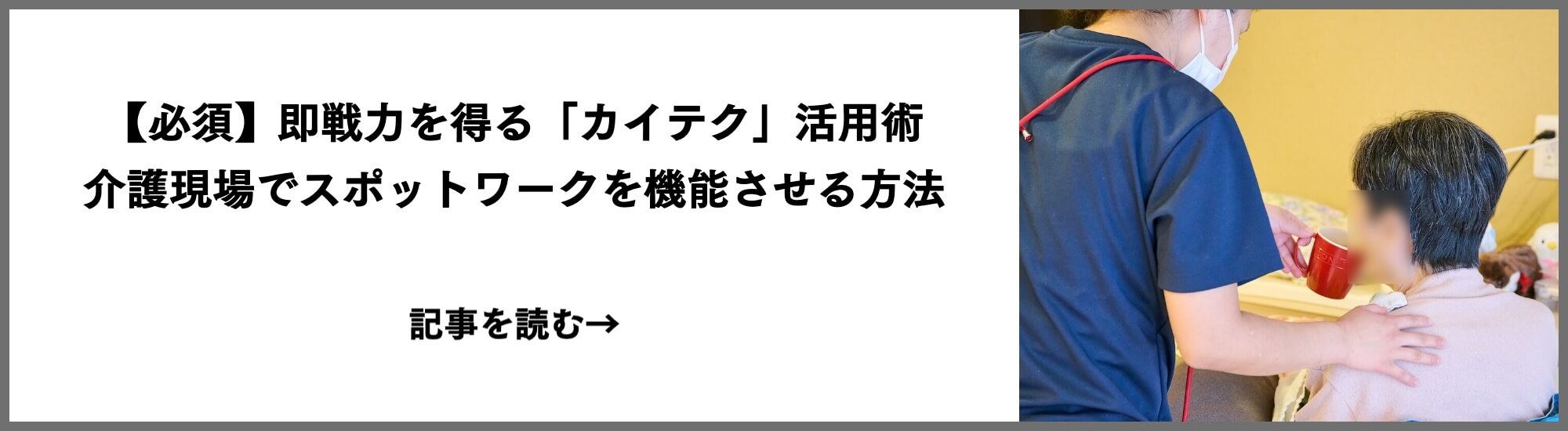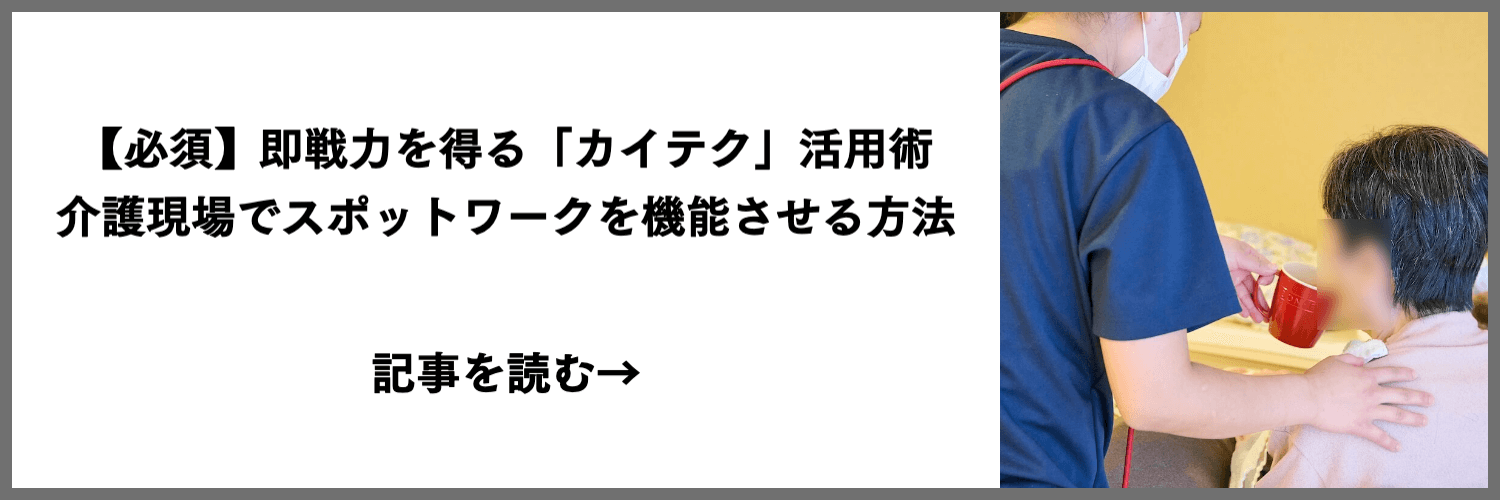有料老人ホームをめぐる様々な課題を議論している厚生労働省の検討会が、7月25日に「これまでの議論の整理」を公表しました。この中には、いわゆる「囲い込み」への対策として、例えば「ケアマネジャーの独立性・中立性の確保が必要」「適切なケアマネジメントが行われていることが重要」といった意見が記載されています。
今回はこれを出発点として、現在広がりつつある居宅介護支援の新たなビジネスモデルの問題点について考えたいと思います。【田中紘太】
◆ 集合住宅の事業者と結託
居宅介護支援の分野では近年、集合住宅の利用者を多く抱えつつ、テレワークを全面的に認めながら全国各地のケアマネジャーを組織化し、上位の「特定事業所加算」などを取得するという運営形態が、1つのビジネスモデルとして捉えられるようになってきました。
集合住宅の利用者が中心ならモニタリングなども効率的に回れるため、より楽に稼げる点を魅力に感じるケアマネジャーが存在するようです。しかし、これには問題点が多くあると言わざるを得ません。
例えば、一部の集合住宅の事業者と特定のケアマネジャーが結託し、介護保険給付の“売上”を最大化するような運営が行われています。訪問介護や通所介護など、自社もしくは関係の深い事業者によるサービスを限度額ぎりぎりまで組み込み、より高い介護報酬を得る。事業の効率性や収益性を重視し、こうした手法が横行している現状があります。
こうしたビジネスモデルを成立させる前提として、入居時にケアマネジャーの変更を暗黙の条件とする集合住宅も散見されます。もともと外部のケアマネジャーが作成していたケアプランは、入居を機に、集合住宅と結びつきの強いケアマネジャーに引き継がれ、事実上、施設側の意向を色濃く反映した内容に変わっていきます。こうした構造は、「ケアマネジャーの独立性・中立性の確保」という考え方と明らかに矛盾すると言わざるを得ません。
実際、集合住宅の入居者のケアプランをみると、併設の訪問介護や通所介護のセット提供で完結しているケースが多々あります。利用者にとって本当に必要なサービスが選ばれているか、利用者の選択の自由が真に担保されているかという視点が、後景に追いやられていると言わざるを得ません。果たしてそれが、利用者本位のケアマネジメントと呼べるのでしょうか。
問題なのは、こうした仕組みが1つのビジネスモデルとして認識・共有され、徐々に広がる動きがあることです。
テレワークで働くケアマネジャーを各地に配置し、集合住宅の入居者のケアプランを一手に担う。そして上位の加算を取得し、事業の効率の良さと高収益、働きやすさをうたって人材獲得競争でも優位に立つ。
これはケアマネジメント本来の機能・役割とかけ離れた営みであり、真面目に取り組んでいる事業所を苦境に追いやるリスクもはらんでいます。速やかに規制すべきではないでしょうか。
◆ 必要な制度的対応
では、どのような対策が必要なのでしょうか。
まず、居宅介護支援の「同一建物減算」を現行の5%から大幅に拡大すべきです。医療保険の訪問診療などはより大きな減算幅となっており、まずは最低でも10%から15%へ強化すべきではないでしょうか。
また、個々の居宅介護支援事業所が抱える集合住宅の利用者の割合などを、定期的に広く公表する仕組みも検討すべきです。透明性の向上は、事業者の不正や不適切な行為を抑制する効果があるはずです。
加えて、ケアプラン点検の強化も急務です。点検の実行力・強制力を高めるとともに、点検対象の基準もより実態に即したものへ改めていく必要があると考えます。
もちろん、事業運営の環境に地域差があることは理解できます。都市部では個人宅の利用者が中心でも成り立ちますが、地方では集合住宅の利用者を確保しなければ件数が伸びず、経営が厳しくなる事業所もあるでしょう。しかし、それを理由に本来のケアマネジメントの理念や趣旨をないがしろにしてよいはずがありません。
◆ 今こそ原点に立ち返るとき
ケアマネジャーは利用者の生活や尊厳を支える専門職です。その責任は、制度の抜け道を恣意的に通るようなビジネスモデルよりも、はるかに重いものであるべきです。
安易に利益追求の仕組みに加担するのではなく、基本に忠実に、制度本来の意義や価値を重視して、アセスメントに基づき過不足のないケアプランを作る。それこそが、ケアマネジャーに課された本質的な使命ではないでしょうか。
ルールに沿って誠実に取り組めば、居宅介護支援の事業は十分に成り立ちます。法令遵守でまっとうに運営しても、しっかりと堅実に経営すれば相応の利益を出すことができるんです。
制度の間隙を突くような事業者に手を貸したり、彼らの手法を真似したりする必要は全くありません。2025年の節目を迎えた今こそ原点に立ち返り、それぞれが職業倫理を胸にケアマネジメントに向き合っていくべきではないでしょうか。
繰り返しになりますが、現在広がりつつある集合住宅型のビジネスモデルは、制度の趣旨・理念から大きく逸脱したものです。早晩、規制の対象となるでしょう。ケアマネジャーの役割と価値を守るためにも、専門職としての自らの良心と責任をもって、制度の健全な発展に力を尽くしていくことが大切だと感じています。