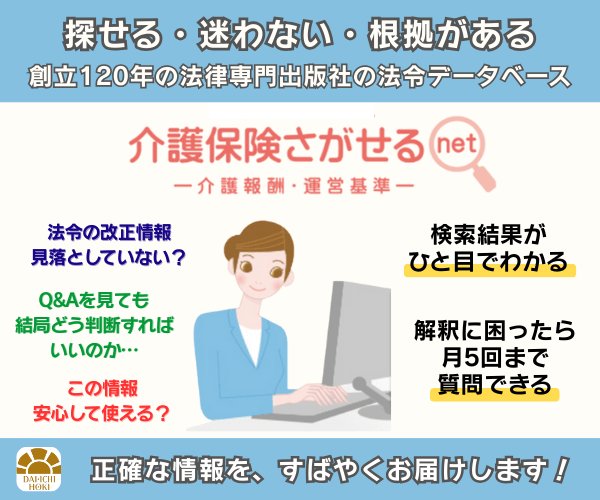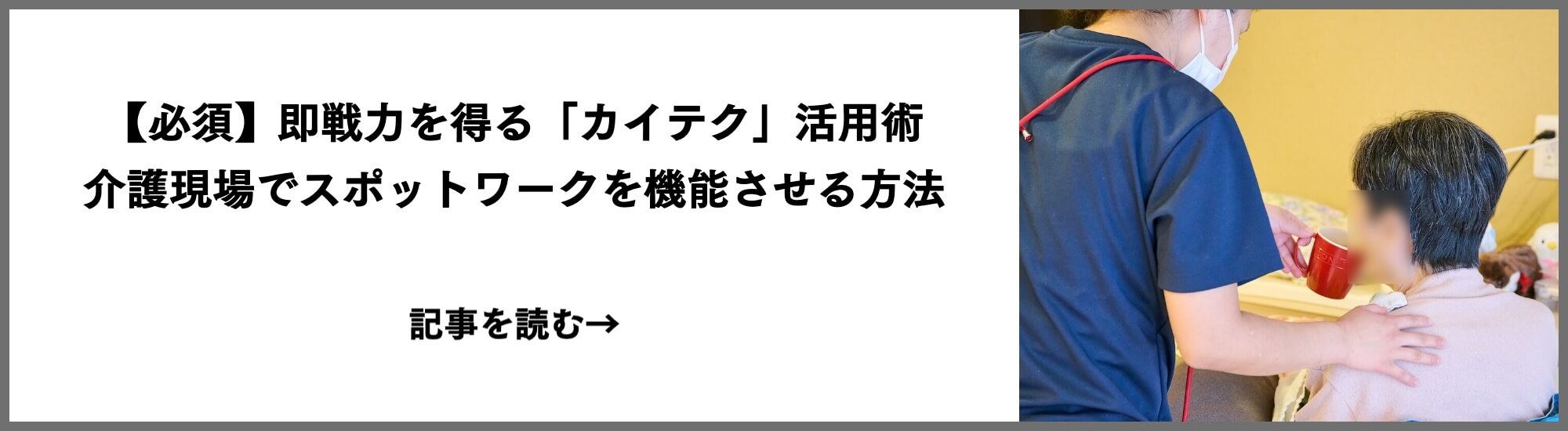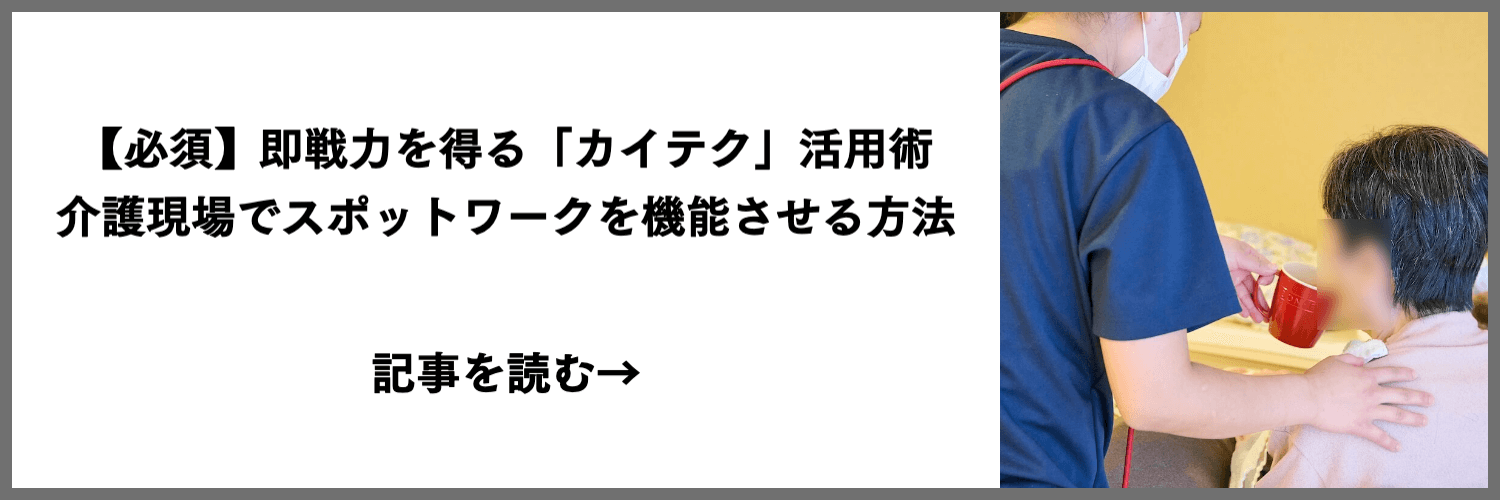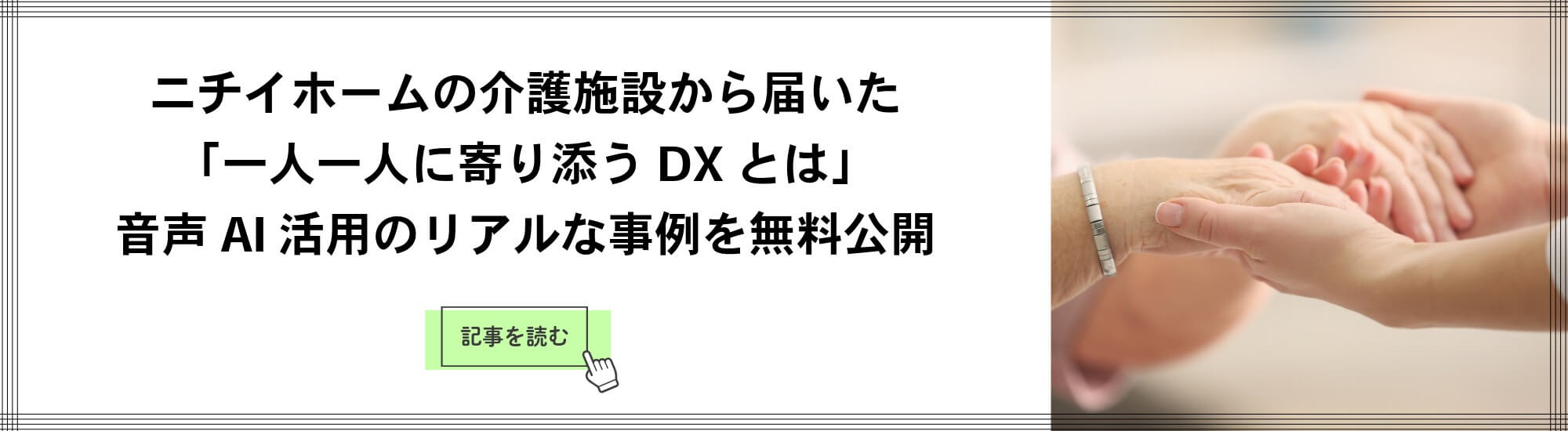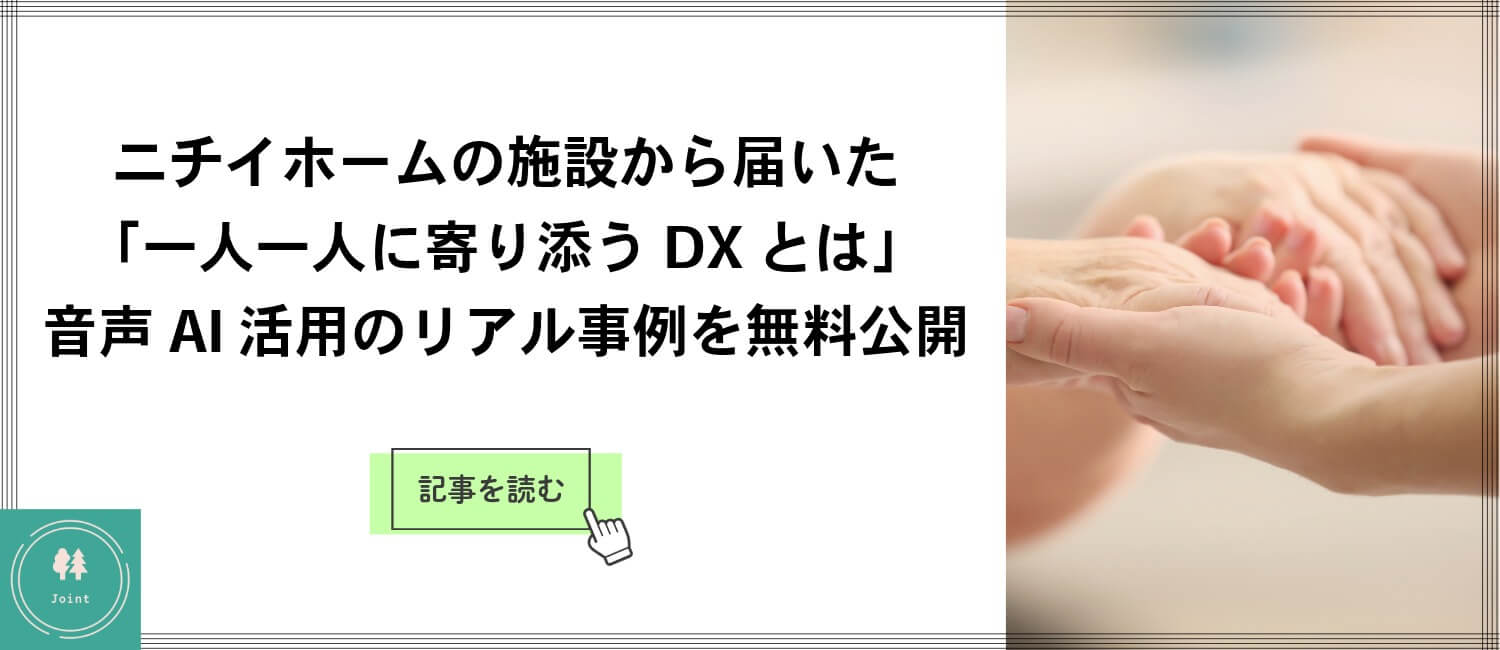【小濱道博】住宅問題の解消が共生の試金石 外国人介護人材の定着に向けた課題と希望の芽
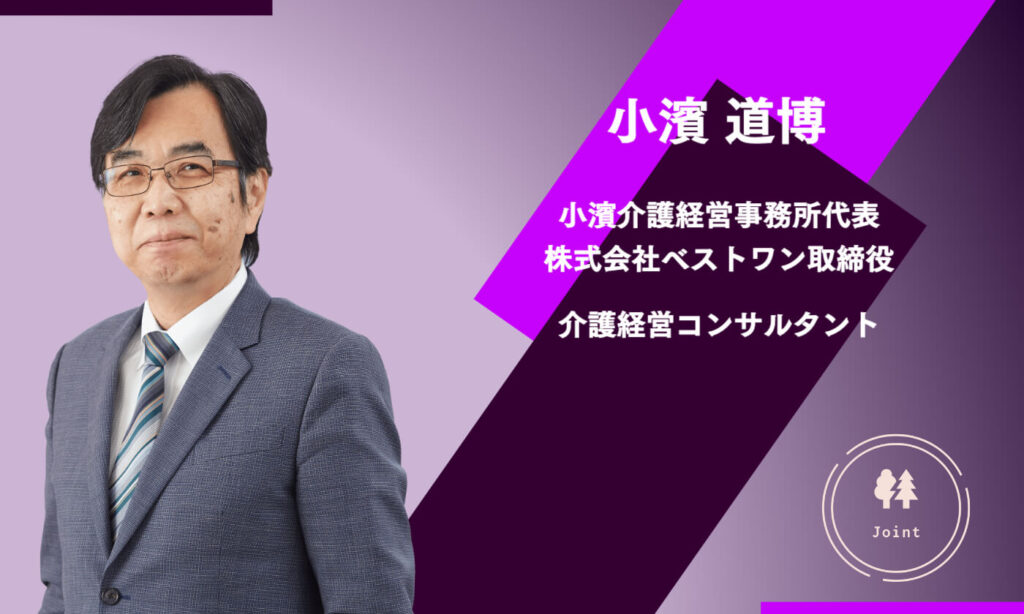
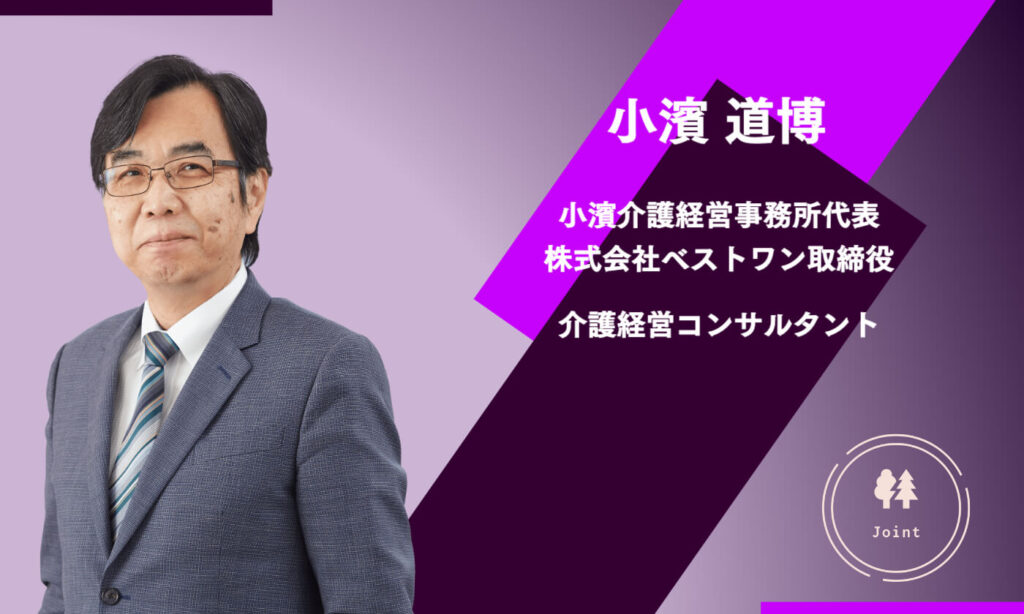
◆ 外国人材の戦略的位置付けと課題の顕在化
政府は6月に閣議決定した「骨太の方針2025」で、外国人材の活用を含む共生社会の実現を国家戦略と位置付けており、特に介護分野では「介護人材の処遇改善」「業務の効率化」「外国人材の活用」を包括的に進める構造的改革を進行中である。
その一環として、今年4月から訪問系サービスでの外国人材の受け入れが解禁され、その供給網は施設内にとどまらず地域サービス全体へと拡大しつつある。【小濱道博】
こうした人材政策の推進にあたって、受け入れ法人には生活面での支援が求められるが、中でも最も深刻かつ構造的な障壁となっているのが「住宅確保」の問題である。
例えば、技能実習生のほとんどは自ら賃貸契約を行わず、受け入れ先が法人契約で住宅を確保する形を取っているが、それでもなお「外国人が入居すること」を理由に家主から契約を拒否される事例が多発している。この拒否感の背景には、ゴミ出しルールや騒音といった生活習慣の違いへの懸念、そして文化や言語の違いへの不安がある。
日本語が堪能であっても国籍を理由に拒否されるケースが多発しており、これは根深い偏見の存在を示唆している。
◆ 地方での住宅確保の壁
特に地方部では住宅ストックそのものが限定的であり、公共交通機関の利便性も低いため、介護事業所から通勤可能な範囲に住居を確保することが難しい。都市部に比して外国人の受け入れ体制も整っていないため、家主による入居拒否の割合はさらに高くなる傾向にある。
こうした実態から、せっかく制度的に受け入れ枠が拡大されても、住宅の確保ができないという理由だけで受け入れを断念する介護事業所が少なくない。これは制度の有効性を損なう重大な要因である。
◆ 注目される香川県モデル
このような構造的問題に対し、香川県が今年度に創設した「海外人材確保強化事業」は、送り出しから定着までを包括的に支援するモデルとして注目を集めている。
同県は特にフィリピンを主たる送り出し国に選定。相手の政府機関であるDMW(Department of Migrant Workers)から認証を得た送り出し機関の連合体と、香川県の中小企業団体中央会とがMOUを締結し、県の監理団体や登録支援機関とのマッチングを進めている。
また、県が介護の専門学校と提携して日本語講座を開設、フィリピンの介護資格を持つ人材の更なる育成を進めている。
本事業ではフィリピン人材に特化したコンサルティング会社が香川県の公募事業を受託し、人材の育成・紹介・定着化を支援する枠組みが構築された。安定的な人材供給と地域への定着支援を同時に実現する枠組みを整備している。
香川県がフィリピンを選択した理由は、同国が長年にわたり介護分野の人材育成に注力してきており、介護士資格を取得する専門学校が多いこともあって、ホスピタリティや対人スキルに優れていることがあげられる。
また、日本との制度的な連携が最も進んでおり、EPAや技能実習制度、特定技能制度においても送出実績が多いほか、DMWを通じた信頼性の高い人材管理体制が構築されていることも大きい。宗教的・文化的な親和性の高さも、日本の高齢者との良好な関係構築を後押ししている。
◆ 環境整備の実効性と地域定着が鍵
同じく県が進める外国人介護人材受入促進事業では、「獲得強化事業」と「環境整備事業」の2つの柱がある。前者では現地合同説明会や人材マッチングを通じて質の高い候補者を確保し、後者では法人契約住宅に対する家賃補助、家具・家電・自転車などの整備補助、日本語研修費や生活ガイダンスなどの定着支援を一括で提供している。こうした包括的支援により、県内の中小介護事業者でも安心して外国人材を受け入れられるようになっている。
特筆すべきは、単なる住居提供に留まらず、地域との接点を重視している点である。地域交流イベントや自治会との連携によって、外国人材が地域に溶け込み、長期的に定着していく仕組みが設計されている。このような「生活支援を通じた雇用定着」という視点は、他自治体にとっても重要な示唆を含んでいる。
◆ 共生社会実現に向けた課題と展望
外国人材の住居問題は複雑であり、その解決には政府、受け入れ企業、NPO、不動産事業者、保証会社、地域社会といった多様な関係者間の緊密な連携が不可欠である。現在の取り組みは断片的なものが多く、より相乗効果を生む連携戦略が求められる。空き家ストックの戦略的活用やデジタル技術の最大限の導入も、住居支援の効率化とアクセス向上に貢献する。
技能実習制度が「育成就労制度」へと移行しようとしている今、単に人材を導入するだけでなく、その生活基盤を確保し、社会との橋渡しを担うインフラ整備が不可欠となる。住宅問題はその最前線であり、今後の多文化共生政策において避けて通れない課題である。
香川県のような先進事例を全国に展開し、国・自治体・民間・地域住民が連携した持続可能な受け入れ環境を構築していくことが、真の共生社会実現に向けた鍵となる。