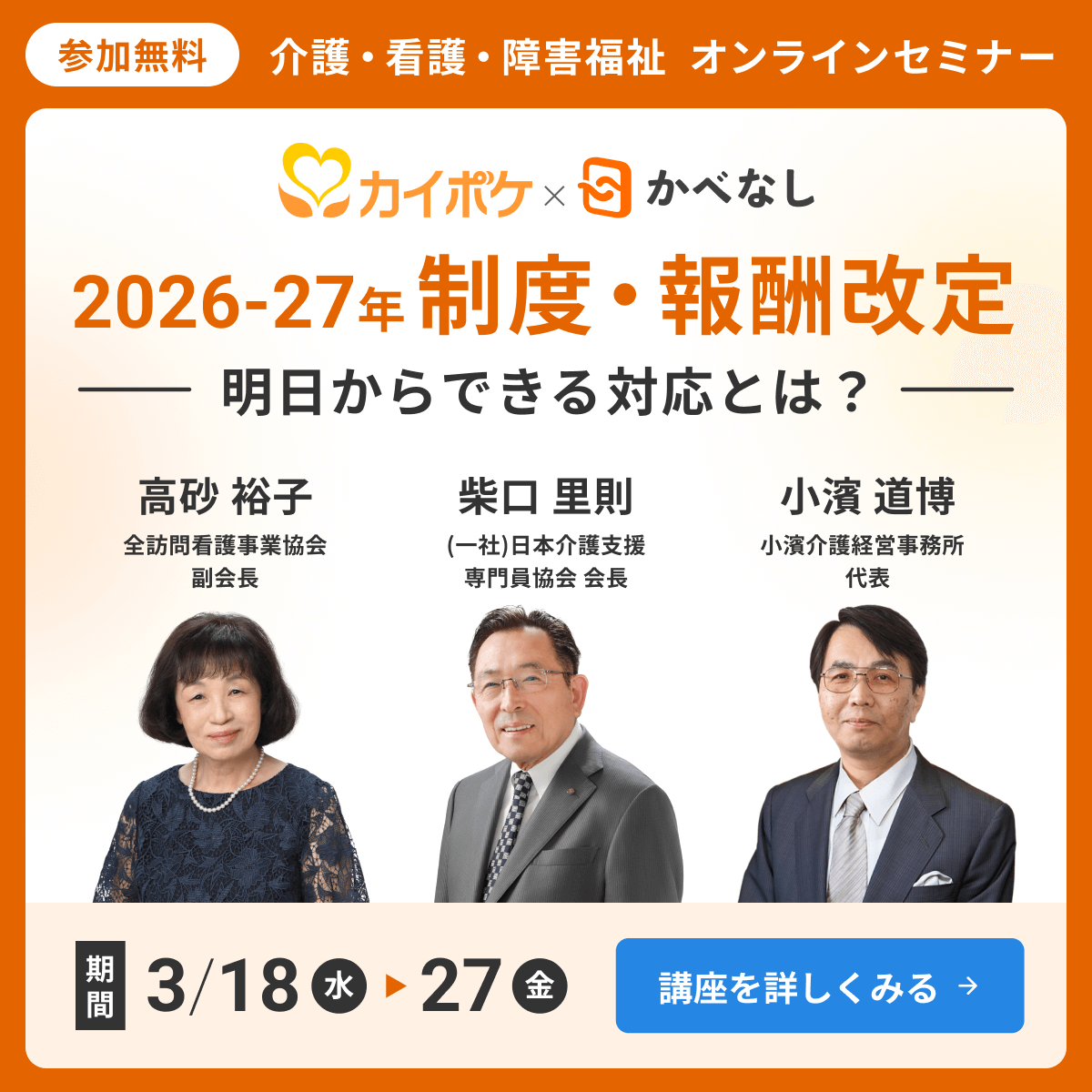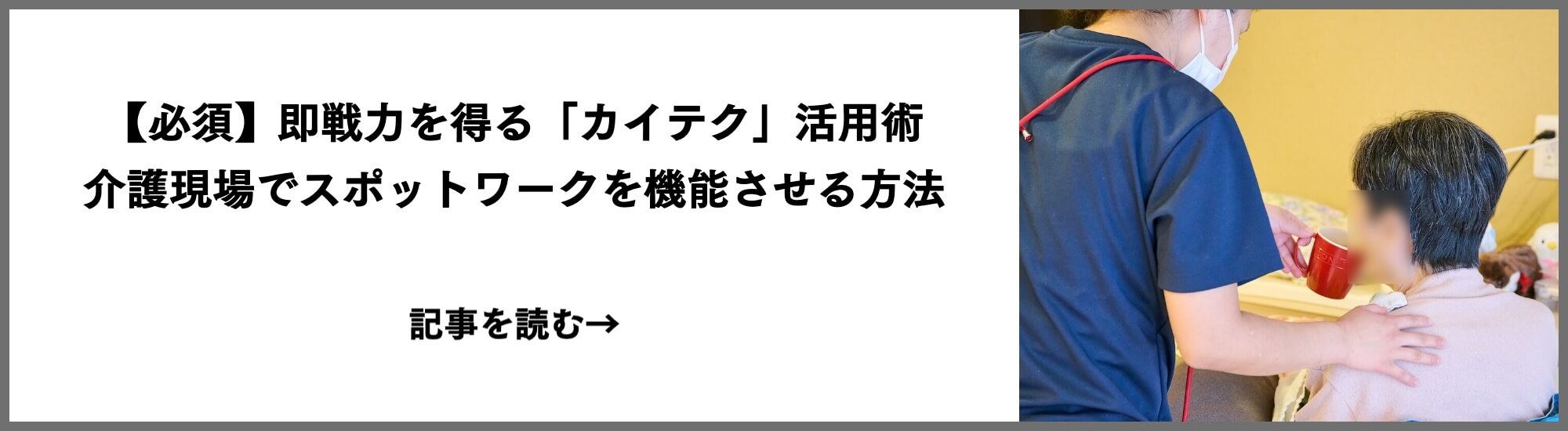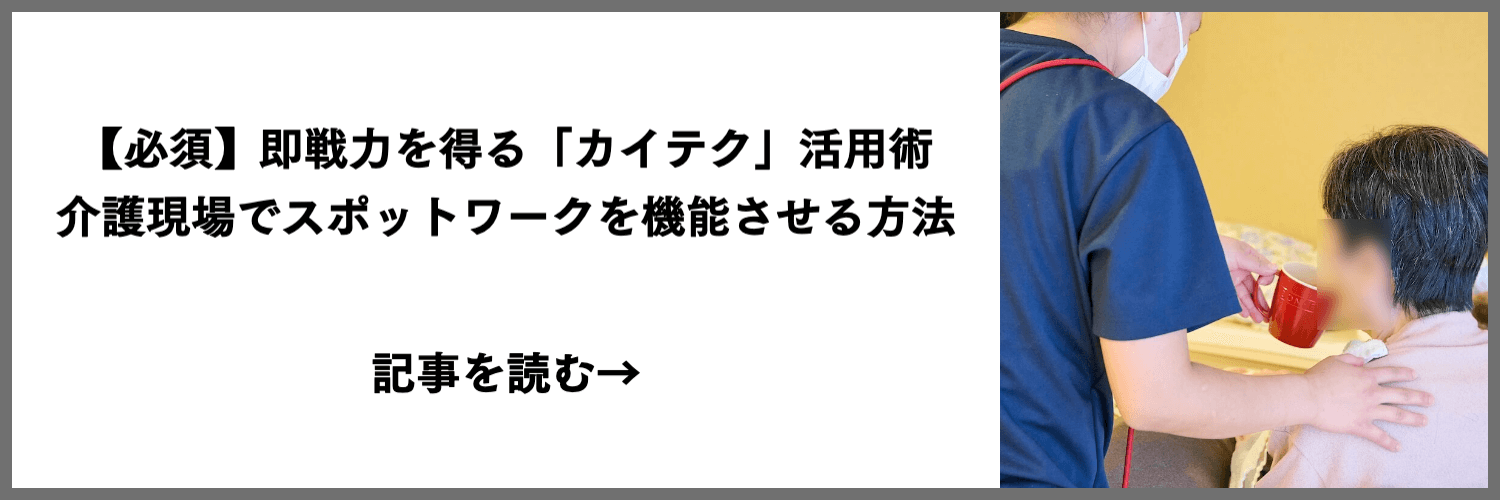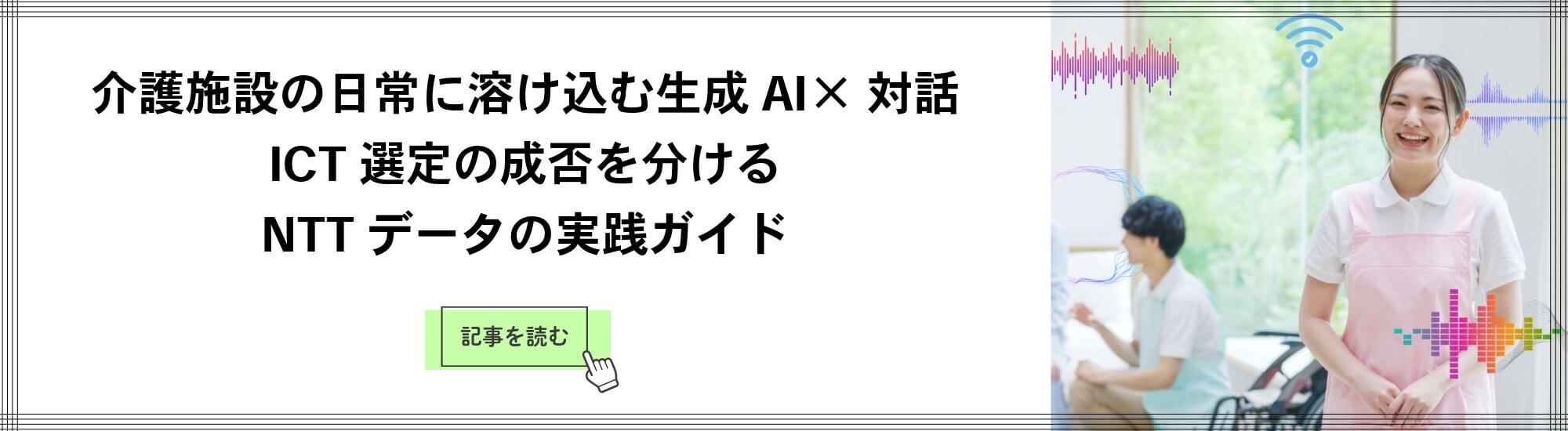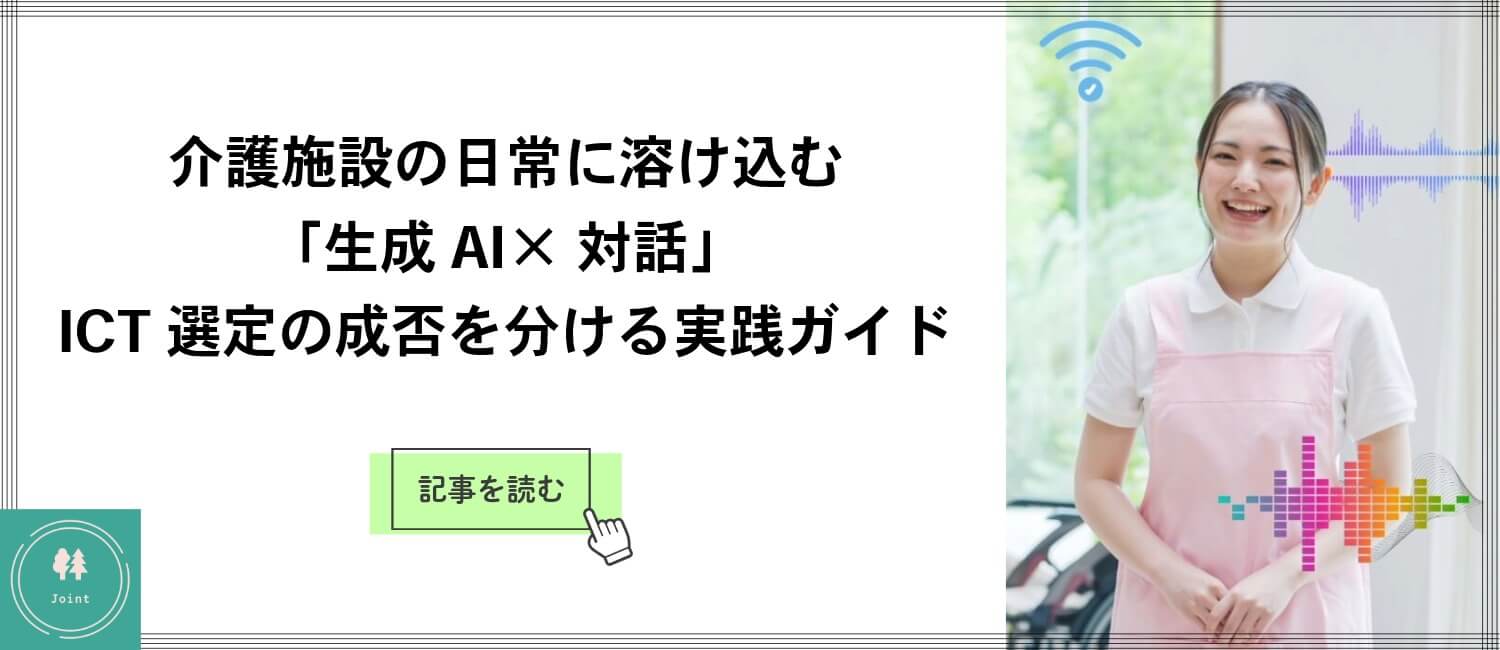【村上久美子】2040年を論じる前に… 問われる地域包括ケアの現在地 構想先行より現実直視の打開策を


地域包括ケアシステムはできあがったのか? 介護現場の関係者のほとんどが「No」と答えるのではないだろうか。【村上久美子】
遡ること2022年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが仕事と介護の両立に関する調査研究事業の報告書を発表した。
その中で目を引いたのが、それまでの仕事を辞めた285名のうち、「希望する介護保険サービスが地域で提供されておらず利用できなかった」ため離職した、との割合が34.7%にのぼったことである。
◆ 節目の2025年の厳しい状況
当時はまだ、厚生労働省が「2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築を実現していく」としていた過程にあったわけだが、その2025年を迎えた現在、要介護者が必要とするサービスを全国どこでも利用できるようになったのだろうか。
先月に公表された厚労省の統計によると、「中重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で在宅生活を継続する可能性を高める」として創設された定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能、看護小規模多機能について、今年4月現在の事業所数はそれぞれ1397、5361、1108ヵ所となっている。サービス提供範囲である中学校区(現在全国で9033校)に1つ、という設定には程遠い数だ。
また、特別養護老人ホームの入所待機者も、以前より減少したとはいえ、いまだ全国的には25万人超の方々が希望しても入所できない状態が続いている。
さらに、地域に根付いてサービスを提供している訪問介護事業所の多くが、昨年度の基本報酬の引き下げにより窮地に追いやられており、倒産件数は過去最多、人材不足によりサービス提供を断らざるを得ない状況も多発している。
◆ 経営の健全化、人材確保に力点を
一方で厚労省は、このような現状を十分に評価・検証することなく、新たな動きを見せている。地域包括ケアシステムを深化させるという従来の方向性のもと、今年1月に「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会を設置。その「とりまとめ」を7月25日に公表した。
主な内容としては、全国を3つの地域に分類してそれぞれの状況に応じた新体制を構築していくこと、喫緊の課題となっている人材の確保に向けてテクノロジーの導入や事業者の経営改善を支援していくこと、などがあげられる。
しかし、前述した通り地域包括ケアシステムが構築されたとは言い難いのが実情だ。2025年の遥か先の2040年に向けて重点的に行うべき施策など、現状を正確に把握・検証せずして見出すことは困難である。
確かに、検討会で示された様々な視点と対応策を具体化していくことは必要かもしれない。ただ、その前提として「経営の健全化」、それを通した処遇の改善による「人材確保」に最も重きを置いて、効果の出る対策を講じていかなくてはいけない。
そうでないと、状況は一段と深刻になる。介護保険料を納めていてもサービスを受けられない、という事態がますます広がってしまうだろう。
早急に手を打つべきではないか。業界では「もはや手遅れ」といった悲観的な見方をする人も増えてきた。もっと危機感を持って対応を検討していただきたい。