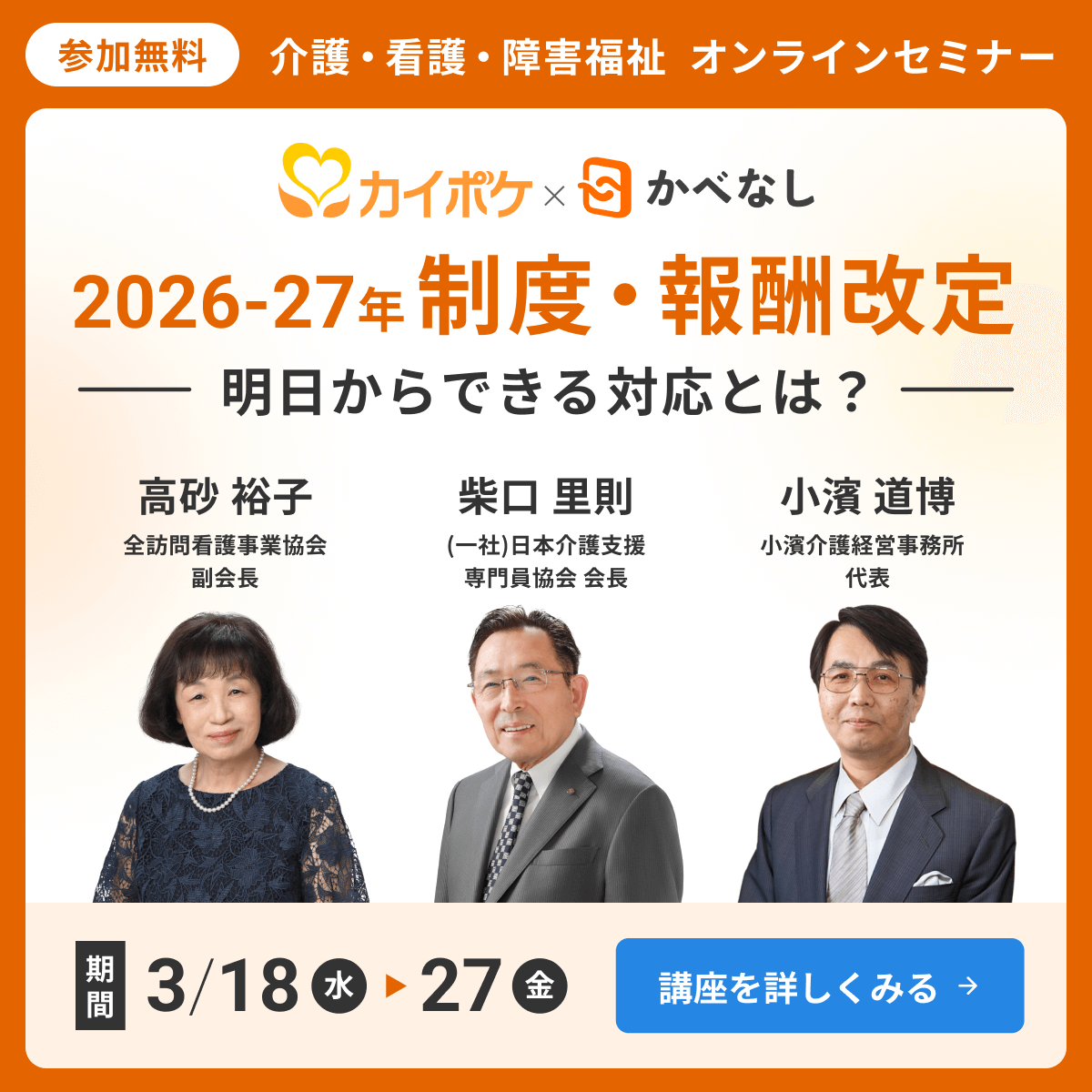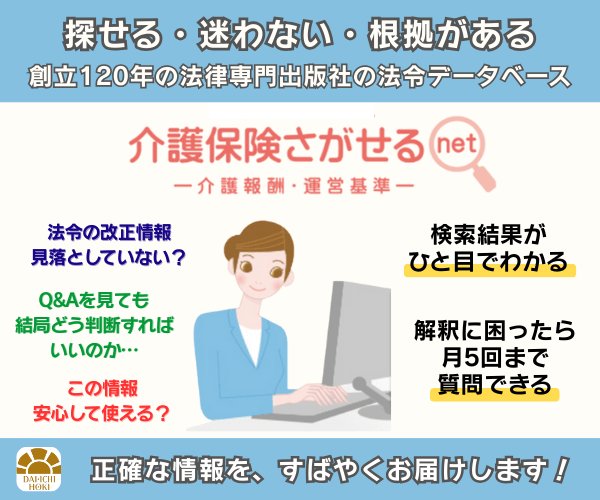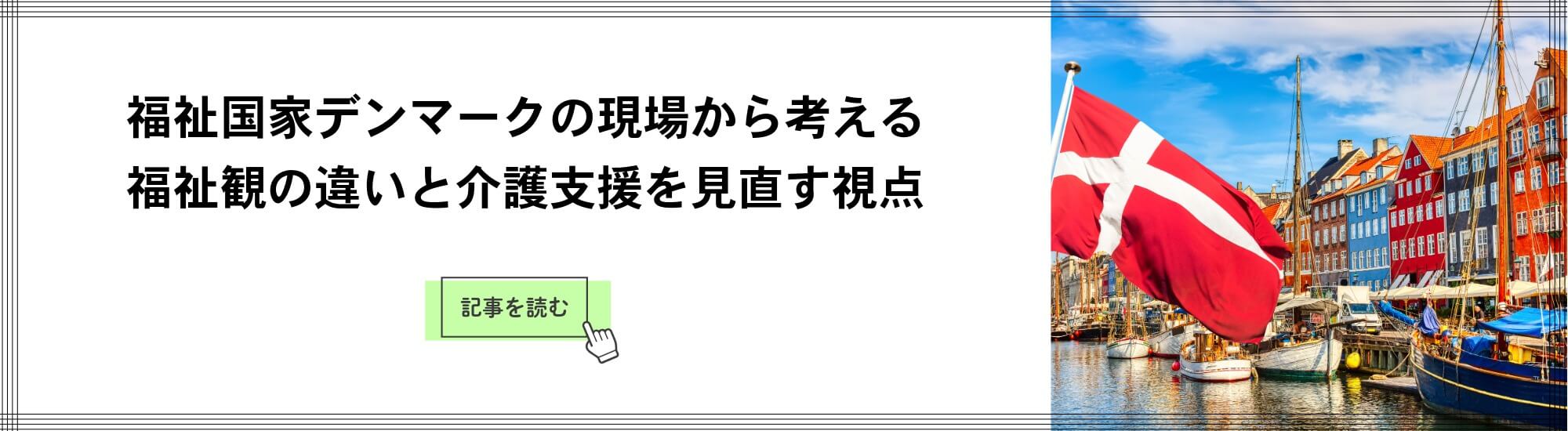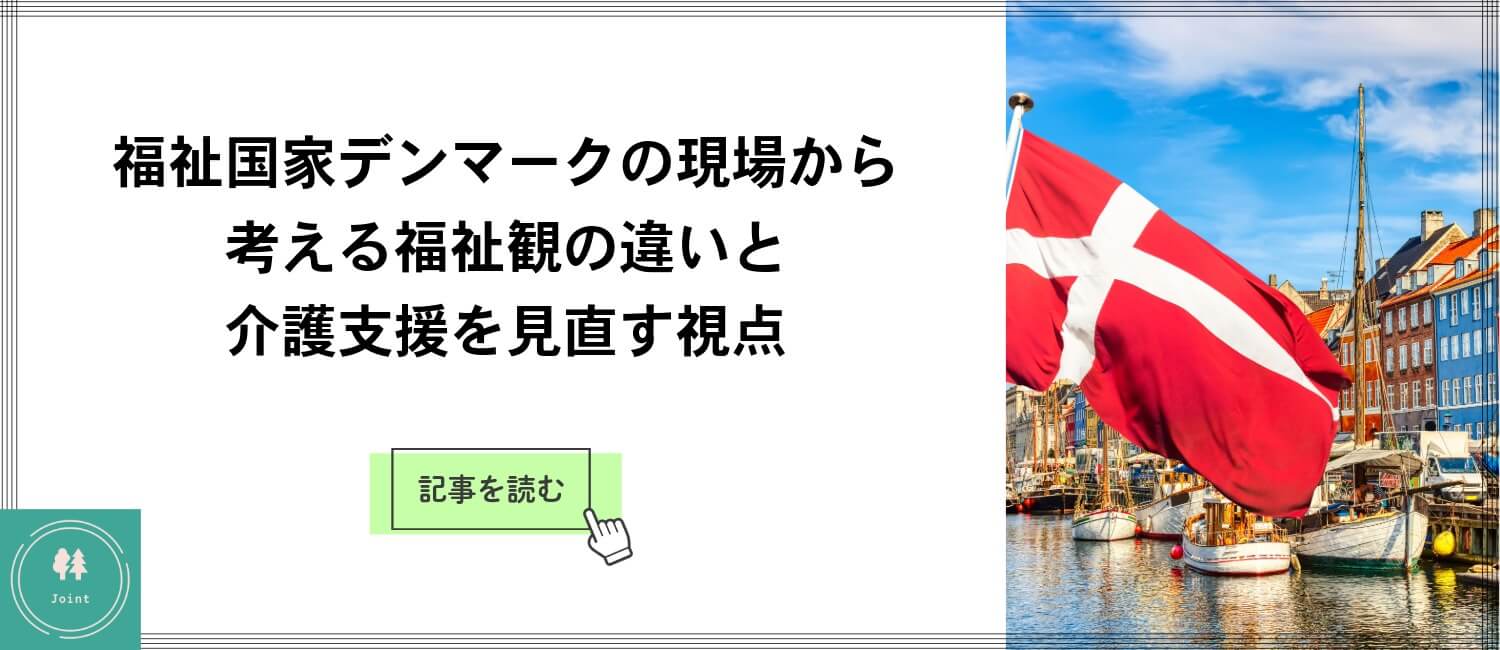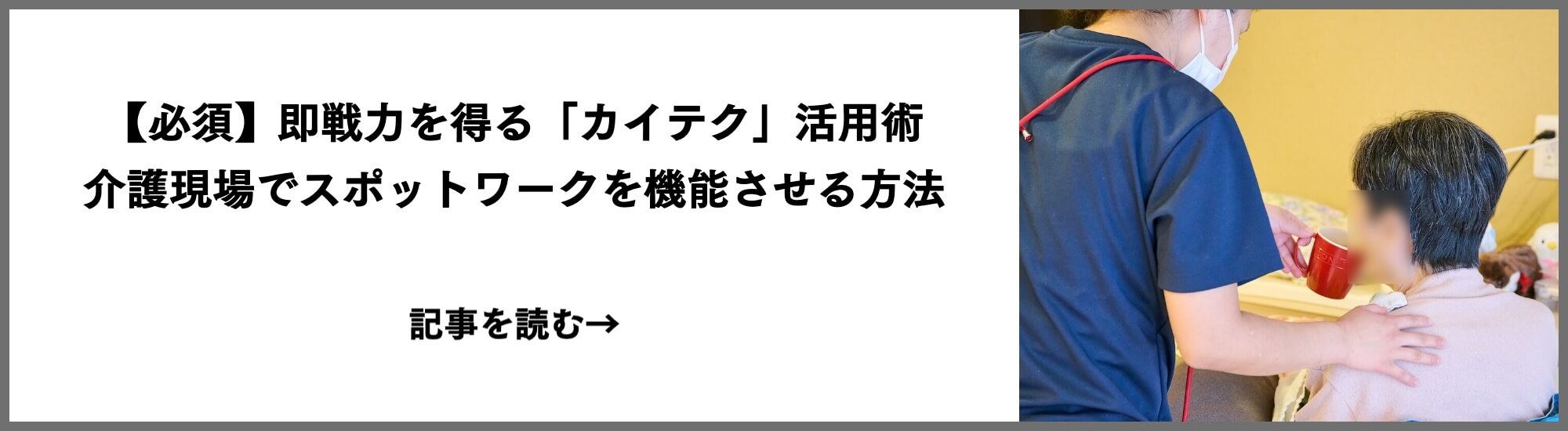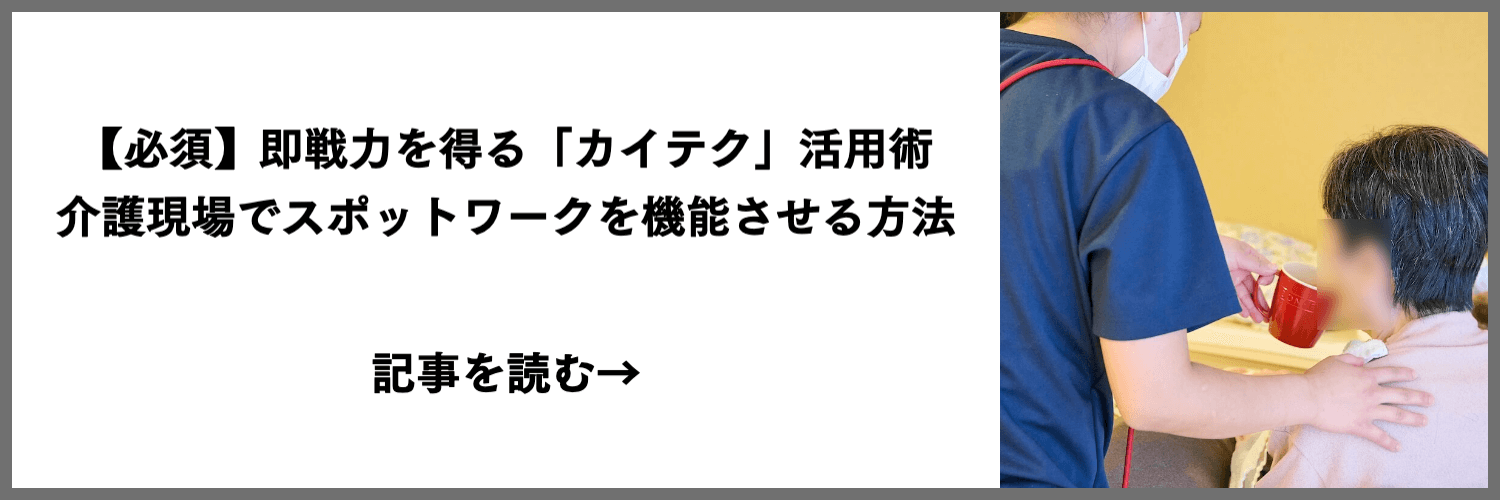【高野龍昭】処遇改善加算は来年度から新体系へ 想定される方向性と介護現場への影響、政治判断の行方


1.はじめに
2024年度の介護報酬改定における処遇改善加算、すなわち現行の処遇改善加算の加算率や算定要件などは、政府が「2年(2024年度・2025年度)分」と決めており、2026年度分については新たな体系が示されます。【高野龍昭】
おそらく、来月あたりから社会保障審議会・介護給付費分科会での議論が始まり、年末頃にその意見の取りまとめが示され、来年の年明け頃には2026年度分の処遇改善加算の概要が示されるはずです。
そして、具体的な政省令・算定基準などは2026年度の当初から施行されることになるでしょう。
このことは、対象となる介護サービス事業所・施設にとっては、新たな加算の体系に合わせた手続きや内部の体制整備に備える必要があることを意味します。そして、行政(保険者)にとっては、2026年度の介護保険特別会計の予算策定に際し、歳出の増加分として一定額を見込む必要があることを意味します。
2.処遇改善加算の期中改定
(1)期中改定の経緯
この期中改定は、2024年度の介護報酬改定の改定率などを最終的に決めた財務大臣と厚生労働大臣の「大臣折衝事項(2023年12月20日)」に、下記のように示されていることに根拠があります。それに併せ、同日の会見で武見敬三厚生労働大臣(当時)が同様のコメントも出しています。
今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置し、3年目の対応については、(中略)処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討する。
この異例の決定については、当時の岸田政権における政策全体の最重要課題のひとつが「物価上昇局面における賃上げ」であったことが大きく影響しています。物価の上昇と他産業での賃上げが進むなか、介護従事者の賃金の原資のひとつである処遇改善加算を2026年度末までの3年の間据え置くことは、介護人材確保に大きな足枷となることを懸念し、異例の「2年分の措置」という政治判断をしたと考えられます。
(2)2026年度の処遇改善加算の方向性
これから検討される2026年度の処遇改善加算の見直しの方向性は、今年6月に閣議決定されたいわゆる「骨太方針2025(経済財政運営と改革の基本方針2025)」で概要を読み取ることができます。
この骨太方針では、まず「減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要」と総論的に掲げたうえで、介護・医療分野の各論として以下のように処遇改善に言及しています。
* 人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引き上げを始めとする処遇改善を進める。
* 処遇改善について、過去の報酬改定等における取り組みの効果を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。
* 医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかりと図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。
* 介護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、事業者の経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する。
※「骨太方針2025」より筆者にて抜粋
処遇改善の前向きな見直しに向け、相当程度踏み込んだ文言が並んでいると言って良いと思います。このことから考えると、2026年度の処遇改善加算の見直しは、実践現場のみなさんにとっては一定の期待ができるものになると推測されます。
ただし、期待できるのは加算の「加算率」についてです。加算率そのものの上積みは期待して良く、それはその後の2027年度の定期の改定にも好影響を及ぼすと考えられます。
一方で、「加算の要件」については、これまで以上に「生産性向上」や「データヘルス改革」と「給与水準の改善」に向けた対応力を事業者に問うものになるだろうと考えられます。
その根拠は、「骨太方針2025」そのものが分野・業種を問わず、生産年齢人口の減少を見込んで、生産性向上やDXの推進を求めていることにあります。それに加え、前述の「骨太方針2025」の抜粋箇所にあるように「賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られる」ことを求めている点も見逃せません。
したがって、月額賃金改善要件・職場環境等要件・キャリアパス要件といった現行の要件が、さらにしっかりとしたものに見直されることになると予測されます。
最も注目されるのは、「骨太方針2025」で「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」という新しい用語を使って介護・医療などの人材確保策が論じられている点です。これは「デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー」と説明されています。
ここから解釈をすれば、今後の処遇改善加算は「デジタル技術を活用して生産性向上のアウトカムを生み出せる体制の事業者に勤務する介護従事者について、より高い賃金を得ることができる仕組み」とすることを示唆しているように思われます。この意味で、「加算の要件(特に職場環境等要件)」は一定のハードルの高さが設けられるはずです。
また、2026年度からは、介護保険法改正による「介護情報基盤の整備」の事業が施行され、行政・事業者ともに一層のICT/DX化が求められることになります。新たな処遇改善加算も、その事業の施行・推進を後押しするため、アドバンスト・エッセンシャルワーカーの存在を評価する傾向が強まると考えて良さそうです。
3.報酬本体の「期中改定」は行われるのか
多くの事業者・介護従事者にとっては、処遇改善加算の見直し以上に、介護報酬本体(基本報酬や各種加算など)の期中改定を期待しているところだと思います。
2024年度の介護報酬改定時の改定幅の薄さに加え、その後も続伸する物価水準などにより、経営そのものが揺らいでいる事業者も少なくない状況にあり、基本報酬などの上積みは、客観的にみて必要な状況だと言って良いでしょう。
しかし、現実的には「介護報酬本体の期中改定」が実施される可能性は、極めて低いと考えられます。
その根拠のひとつは、前述の「骨太方針2025」に、それに関する記載がまったく見当たらないということにあります。そしてそれ以上に、「処遇改善加算以外の介護報酬の期中改定を実施する」という政策は、「行政の無謬性」に抗うことになるという点に根拠があります。
この「行政の無謬性」は、地域や国・時代を問わず、政府や行政機関が「間違いを犯してはならない」「間違った施策を実施することはない」「現行の施策は間違っているはずはない」というある種の「神話」に支配されていることを指すもので、政治・行政・社会保障の分野で古くから用いられている概念です。
この「神話」のもとで考えると、わが国の政府が「2024年度の介護報酬改定は『失策』だった」として、それを是正するためのイレギュラーな「期中改定」を行うことは、通常はあり得ないということになります。
これを覆すことができるのは、過去の政策をみる限り、最高裁レベルの裁判による判決か政治判断(立法府による決定や圧力)しかありません。
振り返ると、現行の処遇改善加算の源流は、2009年度の年度初めに補正予算を組んで創設された「介護職員処遇改善交付金」という政治判断による施策にあります。
これは、2009年8月の総選挙で民主党政権に代わる直前の自民党・公明党政権において、リーマン・ショックへの対応として「経済危機対策」という施策が講じられる中で実施されたものです。それを民主党政権が引き継ぎ、2012年度の介護報酬改定の際に現行の処遇改善加算に続く姿になったという経緯があります。
当時からわが国の財政方針は「財政均衡主義」(※)であり、それは今後も続きます。これを一時的・部分的にせよ覆し、「無謬性」のもとにある行政府が施策を見直すことは困難です。それは、立法府による政治判断に期待するほかないと言えます。
※ 財政緊縮の政策方針のもと、歳出を増やすのであればその分の歳入を何らかの形で確保すること。新たな施策を講じるときは、他の施策を見直して、その分の財源を確保すること。
この意味で、さらなる処遇改善や事業者の経営支援について、野党による法案提出を期待する声もあります。今夏の参議院選挙の結果を受けて、議席の多数を占めた野党勢力に政治判断を求めることは期待をして良いかも知れません。
しかし、今夏の参議院選挙で勢力を伸ばした野党の大部分は「社会保険料の伸びの抑制」「現役世代の『手取り』を増やす」といった公約を掲げています。したがって、介護報酬をアップさせる政策や高齢者介護・医療に財源を費やす施策は、介護保険料をアップさせ、現役世代の「手取り」を減らすことに直結するため、野党勢力に介護報酬の期中改定の動きを期待することは、簡単なことはないでしょう。
このように私が思いを巡らせてみる範囲では、どう考えても介護報酬の期中改定はおろか2027年度の介護報酬改定についても、明るい見通しを抱くことはできません。