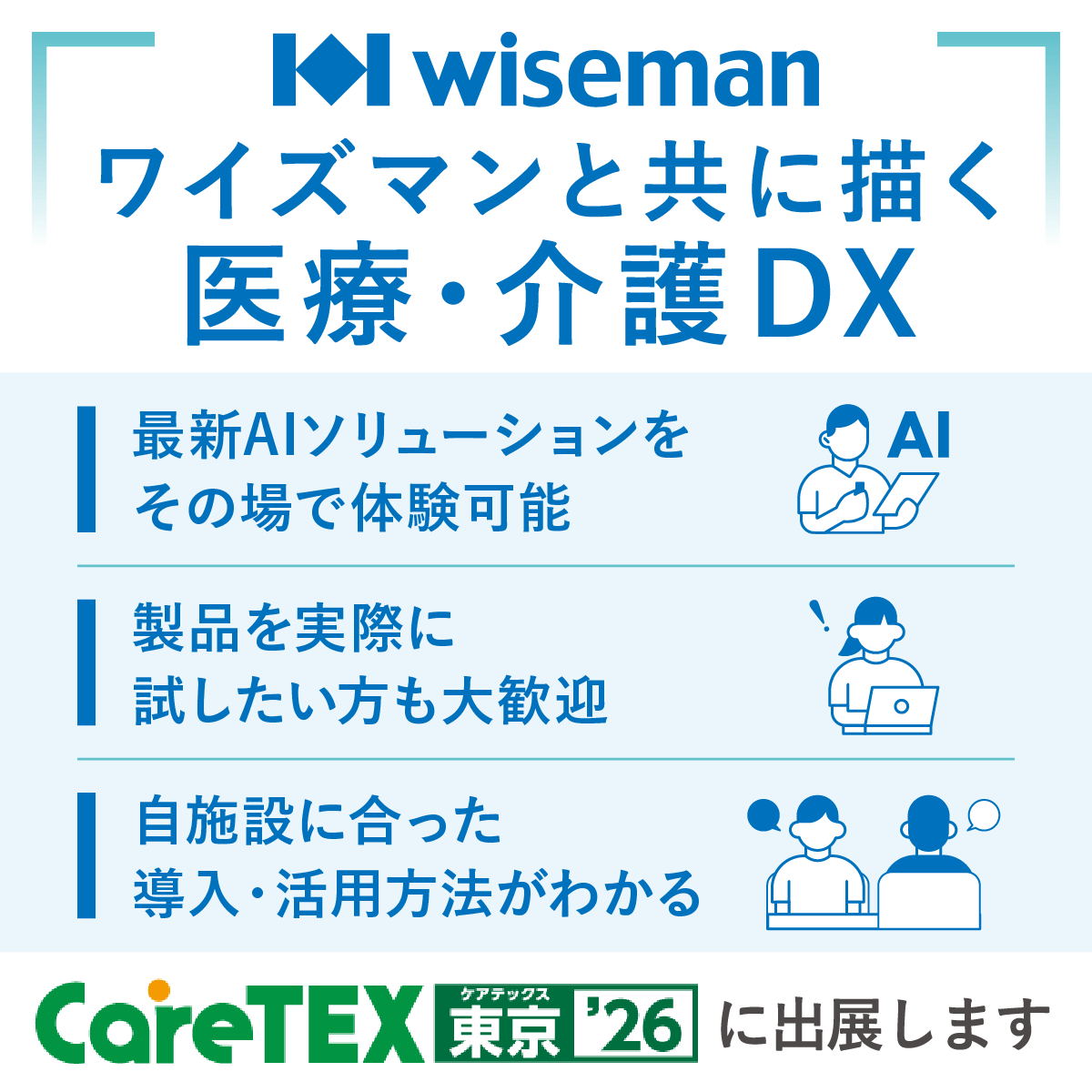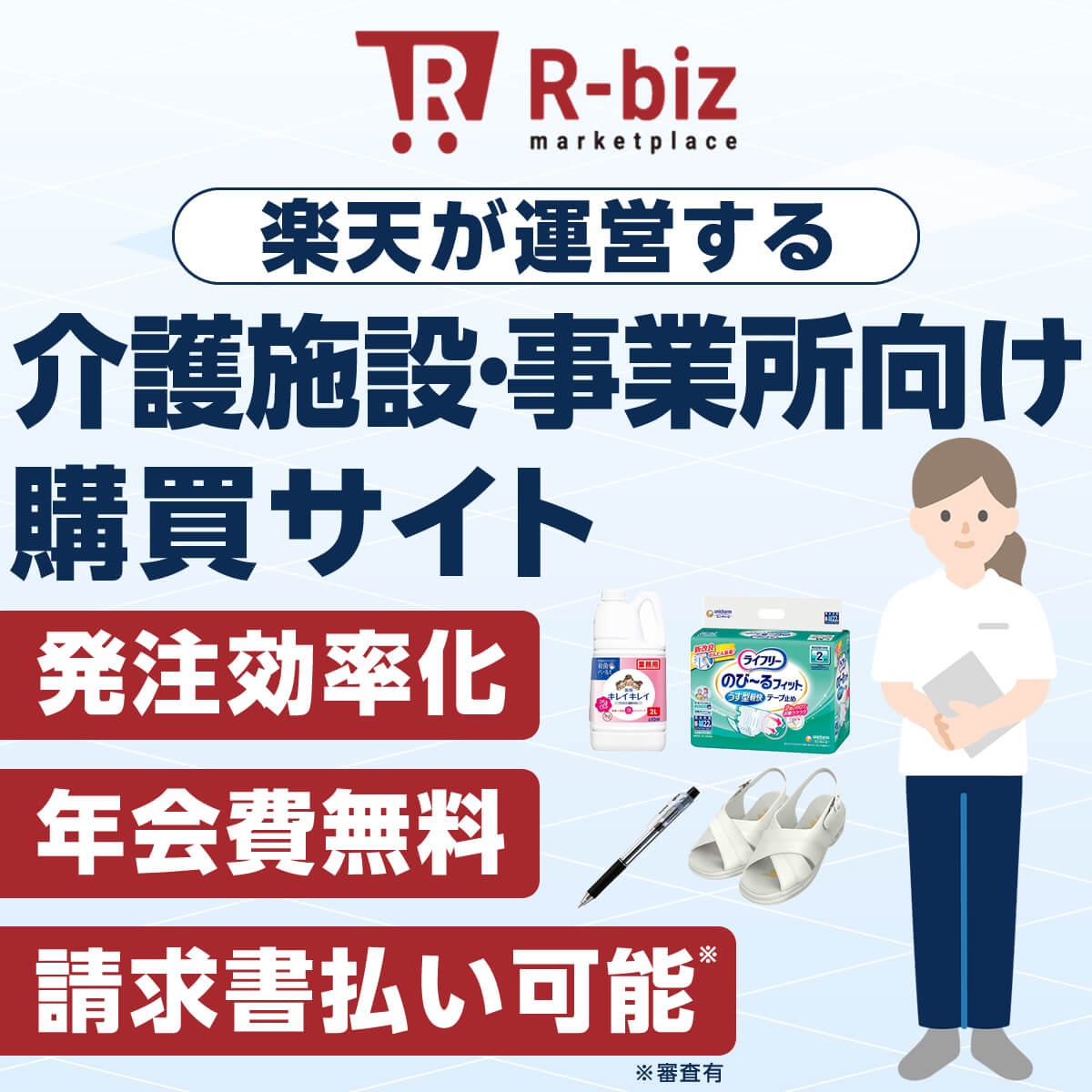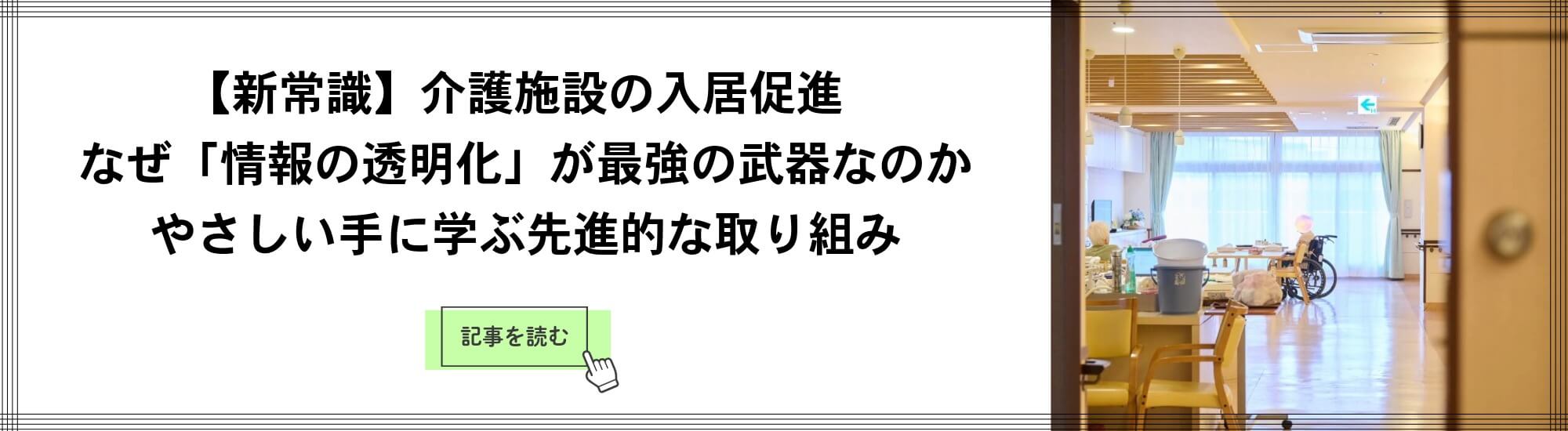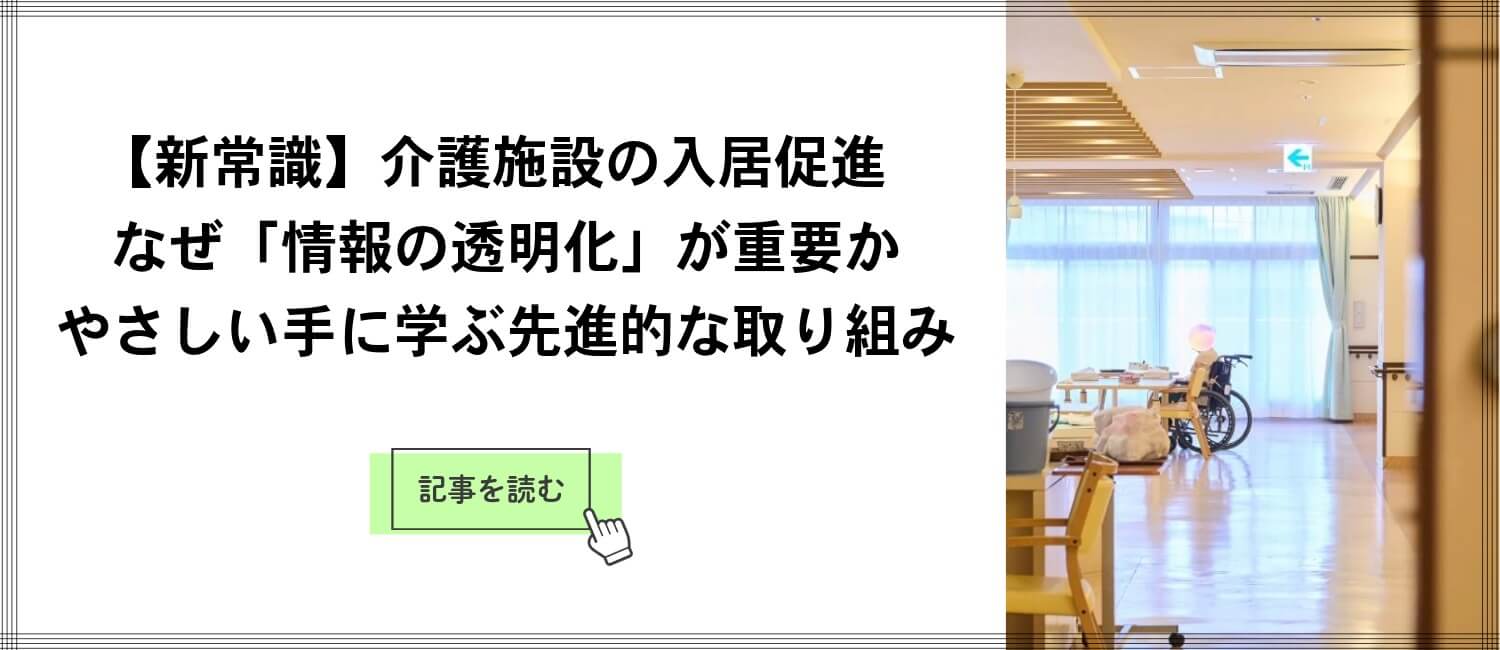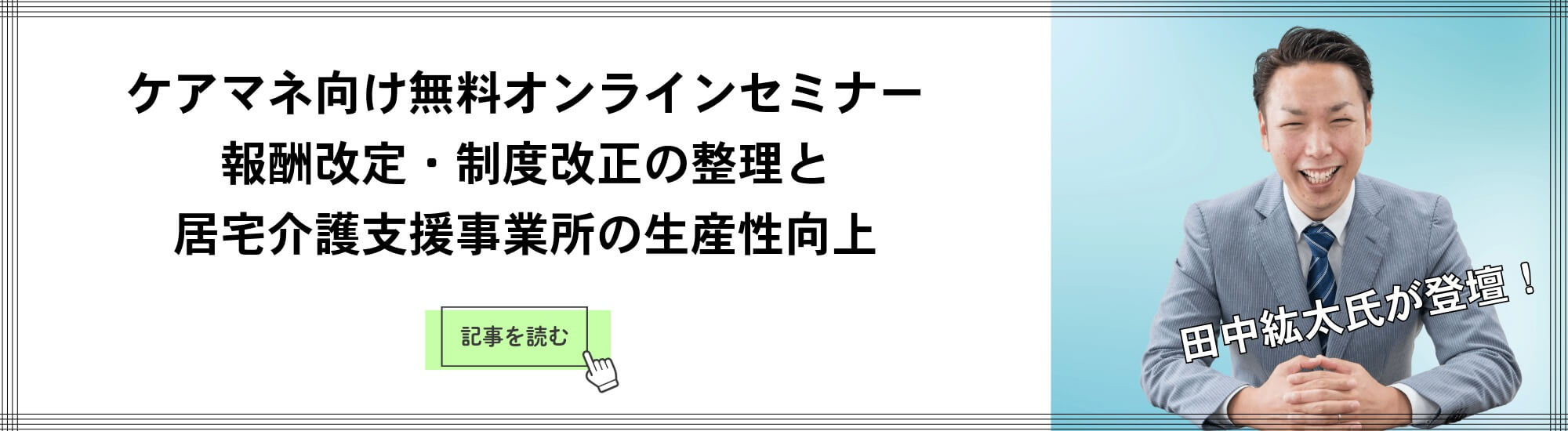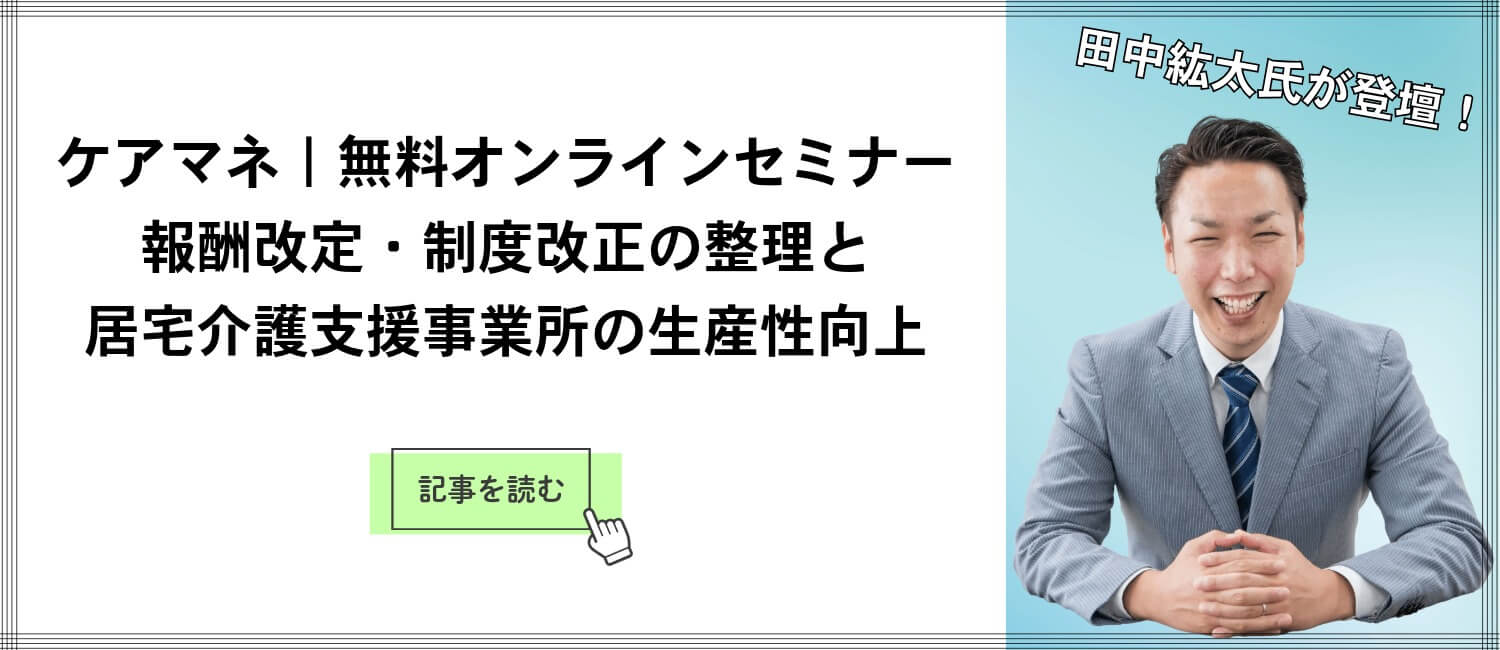【小濱道博】訪問介護の外国人材解禁の現在地 課題を乗り越えて地域のケア体制を整備するカギは?
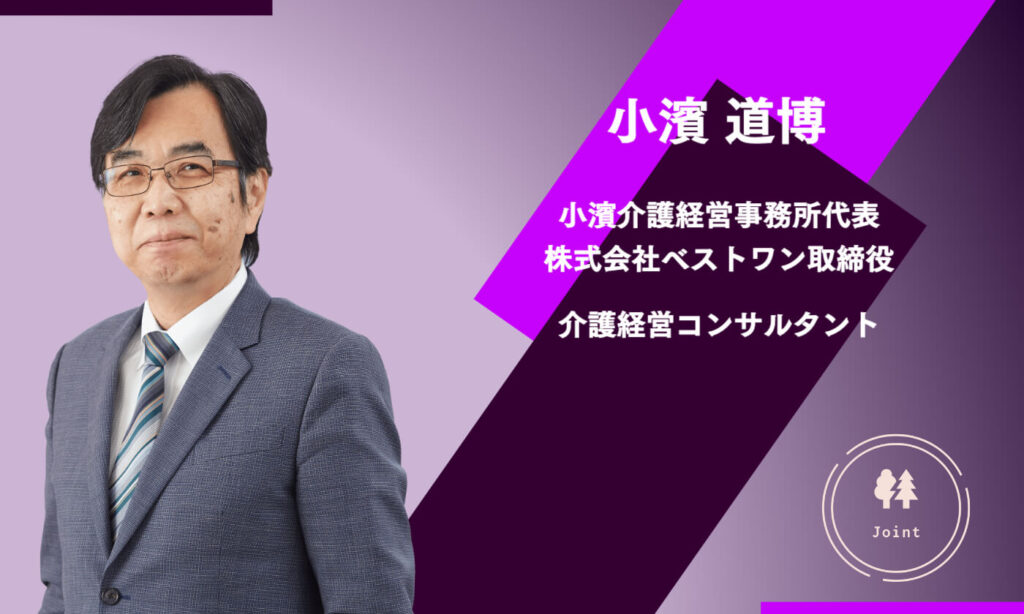
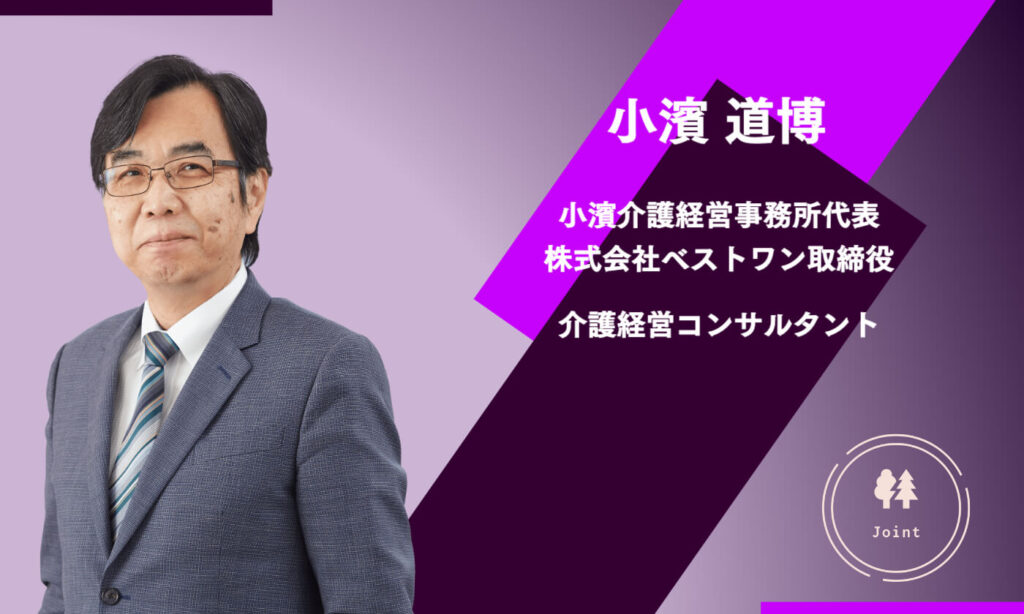
◆ 制度解禁の意義と背景
今年4月、それまで規制されていた外国人材の訪問介護への従事が正式に解禁された。【小濱道博】
技能実習生は4月1日から、特定技能人材は4月21日から従事が可能となった。訪問介護にとって大きな制度的転換点である。
厚生労働省の推計によれば、2040年度には介護職員が約57万人不足すると見込まれており、その中でも訪問介護の担い手不足は特に深刻である。これまで施設系に限られていた外国人材の受け入れが訪問介護に広がったことは、地域包括ケアを支えるうえで重要な意味を持つ。
しかし、訪問介護で外国人材が業務に就くには、介護職員初任者研修の修了と1年以上の実務経験が必須とされた。さらに、訪問介護に従事させる前には国際厚生事業団に適合確認申請を行い、適合確認書の発行を受けなければならない。制度的な要件は高く、即戦力としての配置は現実的に難しいのが実情である。
日本語力や生活習慣の違い、調理や生活援助といった細やかなスキルの習得も不可欠であり、小規模な事業者にとっては負担が重い。ICTによる補助が広がっているとはいえ、制度が解禁されたからといって導入が容易に進むわけではない。
◆ 移動手段という現実的制約
訪問介護は移動が業務の前提である。地方部では自動車が必須であり、都市部でも電動自転車や原付バイクなどが欠かせない。
ところが、外国人材の多くは来日時に運転免許を持たず、日本の法制度上、原付免許を取得することが難しい人もいる。この制約は、訪問介護の業務遂行に直結する大きな問題であり、受け入れにあたって無視できない要素となっている。
◆ 配置転換という現実的解決策
こうした条件を踏まえると、外国人材をいきなり訪問介護に投入するのではなく、まずは介護施設や高齢者向け住宅に併設されたデイサービスなどで受け入れ、研修と経験を積ませたうえで配置転換する方法が現実的である。
例えば、私の知る沖縄の事業者では、デイサービスに受け入れた外国人材4人のうち2人を訪問介護に移行させた。千葉の事業者でも、法人内のデイサービスで1年間受け入れた後に訪問介護へ転換する仕組みを整えている。関西の訪問サービス事業所では、在留資格「介護」を持つ人材を中心に配置を進める事例も見られる。
ただし、技能実習制度では転職が認められていないため、別法人への転換は不可能であり、同一法人内での配置換えに限られる。
小規模な訪問介護事業所が受け入れを進める場合、併設のデイサービスなどで育成し、その後訪問介護に移す方法が現実的である。単独型の事業所では、受け入れ人材を特定技能外国人に絞り込んだうえで、社会福祉連携推進法人や地域内の事業者グループに参加し、共同で育成システムを構築することが不可欠である。
◆ 送り出し国の特性と住宅問題
送り出し国の選定も重要である。
インドネシアは制度の安定性や勤勉さが評価されるが、イスラム教に基づく宗教的配慮が必要である。ミャンマーは給与の一部を国に送金する制度があり、仕送りと併せて生活が厳しくなる傾向にある。ベトナムは日本語力が比較的高い一方で、多額の借金を抱えて来日する人材が多く、心理的負担が大きい。
これらを総合すると、もちろん一概には言えないものの、訪問介護分野ではフィリピン人材が最も適していると考えられる。フィリピンは英語力が高く、ホスピタリティ文化を持ち、ICTの翻訳機器との親和性も高い。費用負担も比較的低く、調理や生活援助に早く適応できる点も強みである。
また、忘れてはならないのが住宅問題である。都市部では外国人であることを理由に賃貸契約を断られる事例が残り、地方部では受け入れ可能な住宅そのものが不足している。
結果として、事業者が寮を設けたり、自治体と連携して空き家を活用する事例が見られるが、十分な住環境が整備されなければ定着は望めない。住宅の確保は外国人材の受け入れにおける最大の課題の1つであり、今後の対策が強く求められている。
◆ 併設型での活用の有効性
当面の最適解として考えられるのは、高齢者向け住宅に併設された訪問介護事業所での活用である。
ここでは一般の利用者に対する広域的なサービス提供を伴わず、同一建物や徒歩圏内でのサービス提供が中心となるため、移動手段の制約を最小限に抑えられる。さらに、住宅併設型であれば生活習慣や調理支援についても画一的な研修が行いやすく、外国人材にとって学習環境が整いやすい。
小規模事業所や単独の訪問介護事業所にとっては導入ハードルが高い中で、この形態が最も制度に適合しやすく、現場での混乱を防ぐ最適な活用方法と考えられる。
訪問介護事業所が存在しない自治体はすでに100を超えており、外国人材の受け入れは地域ケアの持続に直結する課題である。
制度が解禁された今こそ、教育、移動、住宅、法的手続きを含む包括的な支援体制を地域社会全体で整備することが求められる。育成やシステム構築を外部にアウトソーシングするという判断も必要である。
当面は高齢者向け住宅に併設された事業所での活用を足がかりに、将来的には地域全体で外国人材を育成・活用する仕組みを築くことが、訪問介護の未来を切り開くカギとなるのである。