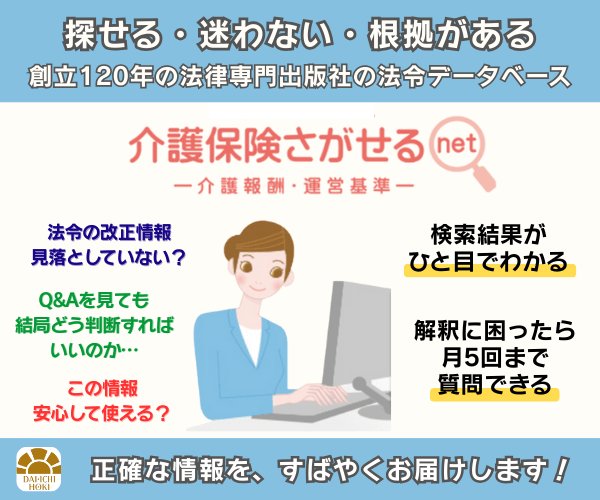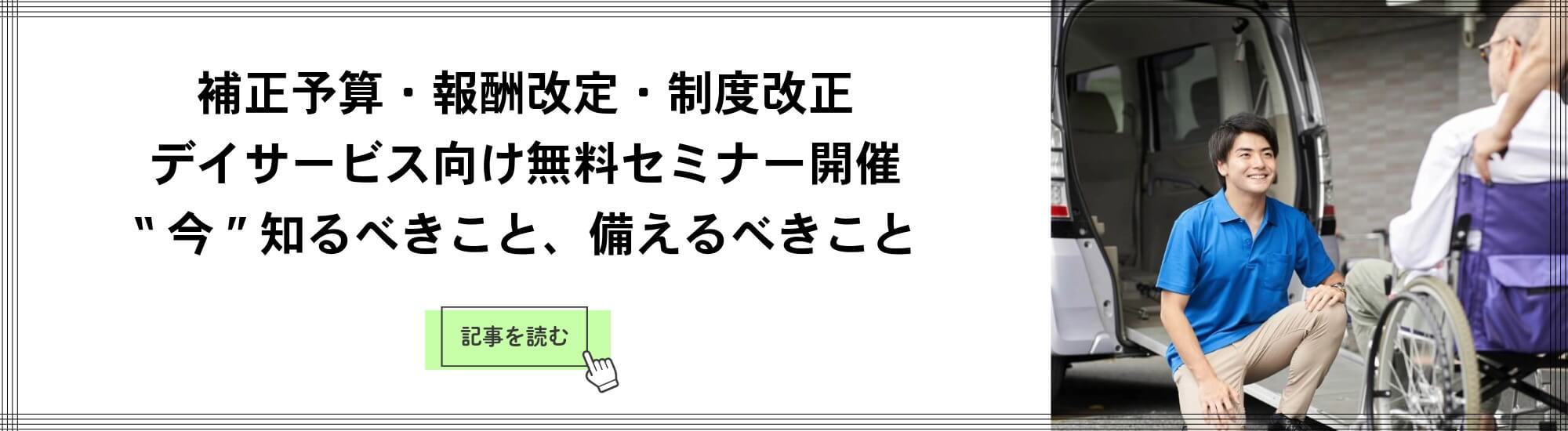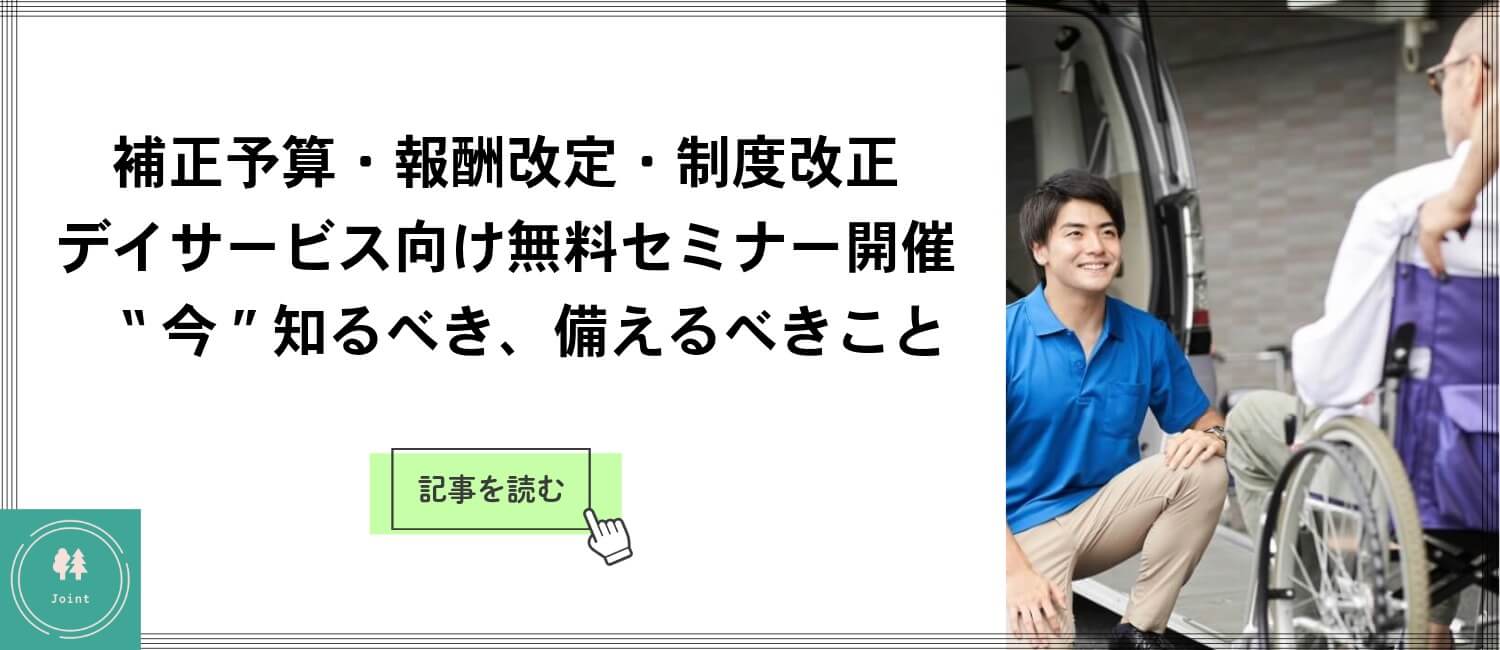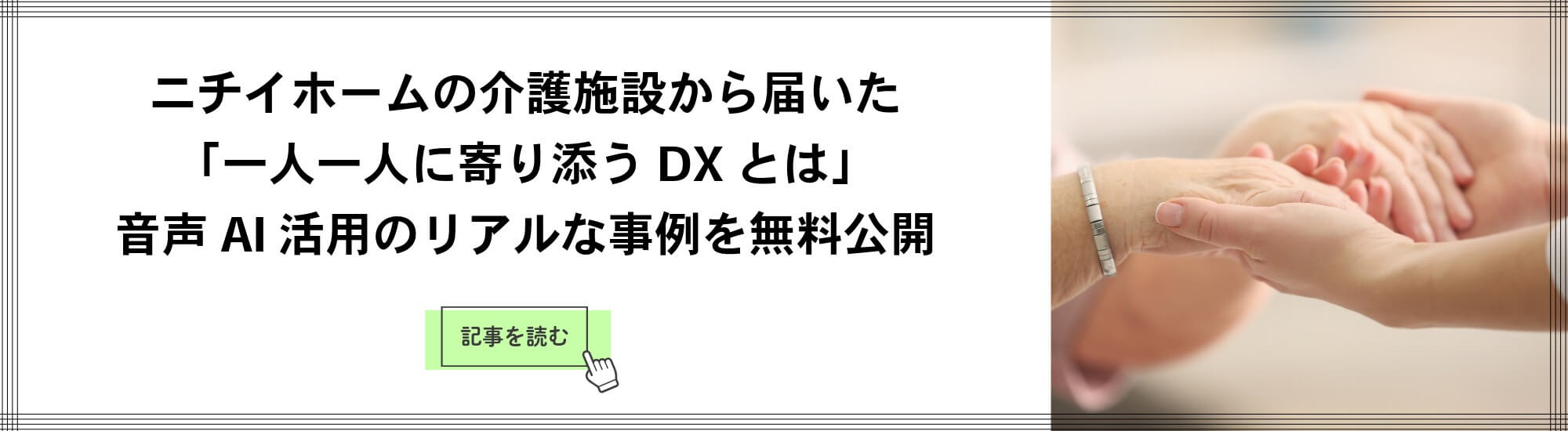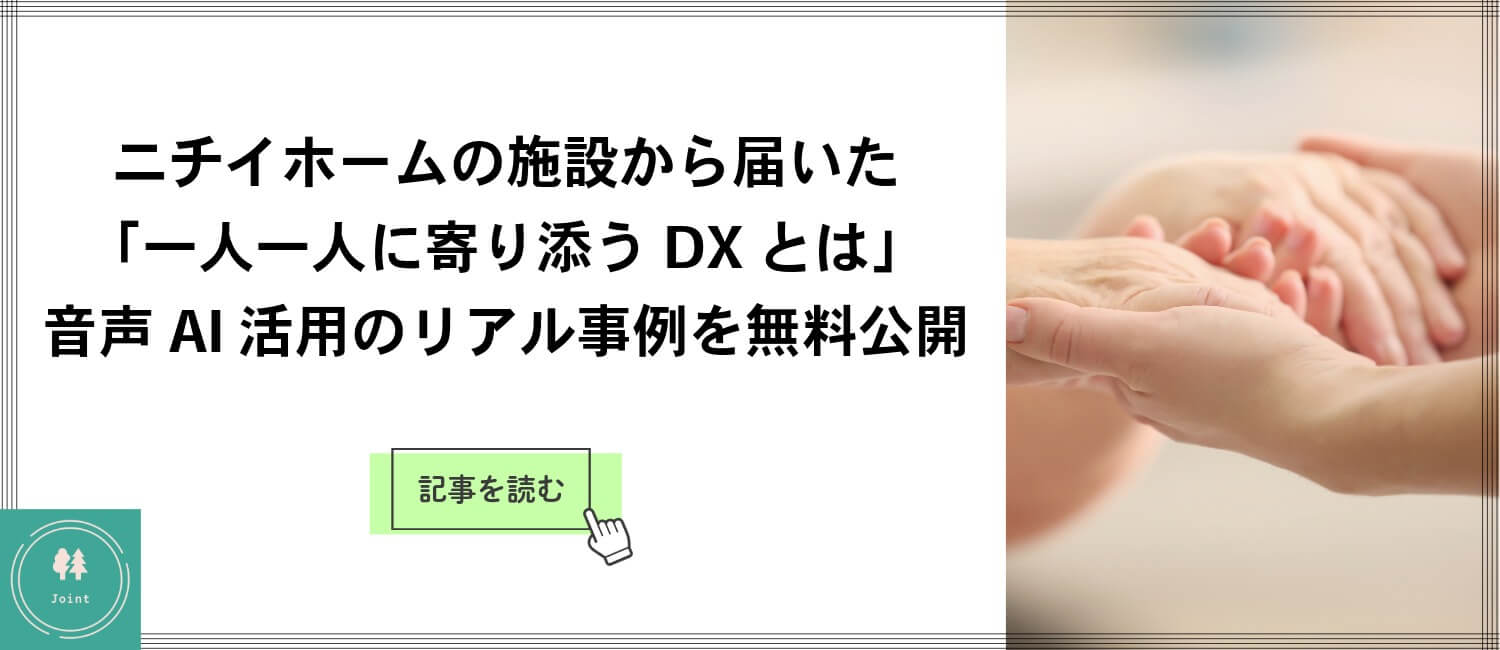外国人介護人材、片道切符から循環へ 帰国者の再来日を支援 東大発ベンチャーの挑戦


日本の介護現場と東南アジアをつなぎ、経験を持った外国人材の循環を実現しようとする企業がある。ベトナムやインドネシアに拠点を持つメドリング株式会社だ。【Joint編集部】
同社が手がける「MEDRiNG KAIGO」では、母国へ帰った外国人材の再教育と日本での再就労を支援する。また、外国人材が日本でも母国でも活躍できるような仕組みづくりを進めている。
◆「ぐるぐる回る循環を」
メドリングは、帰国後の外国人材に現地の医療機関・介護施設などでの就労機会を用意しつつ、オンラインとオフラインを組み合わせた教育プログラムを提供し、介護福祉士国家試験の再挑戦も後押しする。
日本の介護事業者と契約し、教育費・渡航費などの支援を受けつつ有望な人材を紹介する。また、帰国した外国人材をリモートのキャリアアドバイザーとして起用し、現役の外国人材と介護施設とのマッチングの精度を高めている点もユニークだ。
このほか、インドネシア、ベトナム、日本をまたぐ常時更新型のデータベースを構築し、日本語力や人柄、スキルなどの評価軸で外国人材を可視化する。現地での“つなぎ雇用”を確保しながら、学び直し→介護福祉士国試→再就労までを一筋の流れで設計している。
安部一真CEOは取材に対し、「面接と再教育を通じて『即戦力かつ再来日の意思が強い人材』に絞り込み、日本の介護現場が負担を抑えつつ受け入れられる仕組みを作っている」と語る。「これまでのような片道切符ではなく、日本と東南アジアのあいだで外国人材がぐるぐる回る循環を生み出したい」。
◆ 貴重な人材の散逸を防げ
背景にあるのは、人材需給の構造的なギャップだ。2040年には日本で約57万人の介護人材が不足する見通し。昨年度末時点で約7.4万人の外国人材が介護現場で働いており、2030年までにさらに多くの受け入れが計画されている。
一方で、「特定技能」の介護は就労期間が5年に限られており、介護福祉士国試に合格できなければ、原則として帰国を余儀なくされる。コロナ禍後の来日組が期限を迎える2027年以降、帰国者は万単位に達する可能性が高い。このままでは“日本式介護”を学んだ貴重な外国人材が散逸し、アジア市場で他資本に取り込まれる懸念が強い。
そこでメドリングは、帰国直後から就労と学び直しの場を用意し、再挑戦で日本に戻る道と、母国で日本式介護を広げる道のデュアル戦略を構想する。
「一度母国に戻っても、浪人して再チャレンジできる環境を作らねばならない」。
安部CEOは外国人材の循環がもたらす効果を、日本の人手不足の緩和と東南アジアの介護の発展を同時に進める“双方益”と位置づけ、それが最良の道だと睨む。既に複数の介護事業者と契約を結んでおり、当面は年間で数千人規模の“再来日パス”の確立を目指す構えだ。
◆「国益にも資する循環を」
この取り組みは、経済産業省の「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」に採択された。インドネシア、ベトナム、日本でのフィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)を2026年8月末までに終え、その成果も踏まえてより本格的な事業化を目指す。安部CEOは、「日本で育った介護の力を他資本に奪われないよう、国益にも資する循環を実装したい」と意気込む。
メドリングは東京大学発のスタートアップだ。東南アジアで医療DXを展開し、現地の医療機関向け電子カルテシステム「MEDi」を100超の施設に導入。MRTグループに参画し、東大病院など日本の医療機関とのネットワークも強みとしている。
人材の流れを一方通行にしない。キャリアに行き止まりを作らない。現地での就労と学び、日本での再挑戦、将来のアジアでの活躍までを見据えた循環モデルは、慢性的な人手不足に悩む日本の介護現場に、持続可能な補給線を引く。課題先進国・日本発の意欲的なチャレンジに期待が集まる。