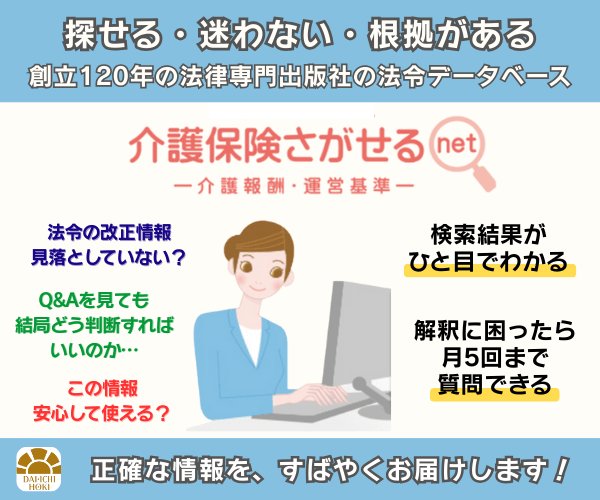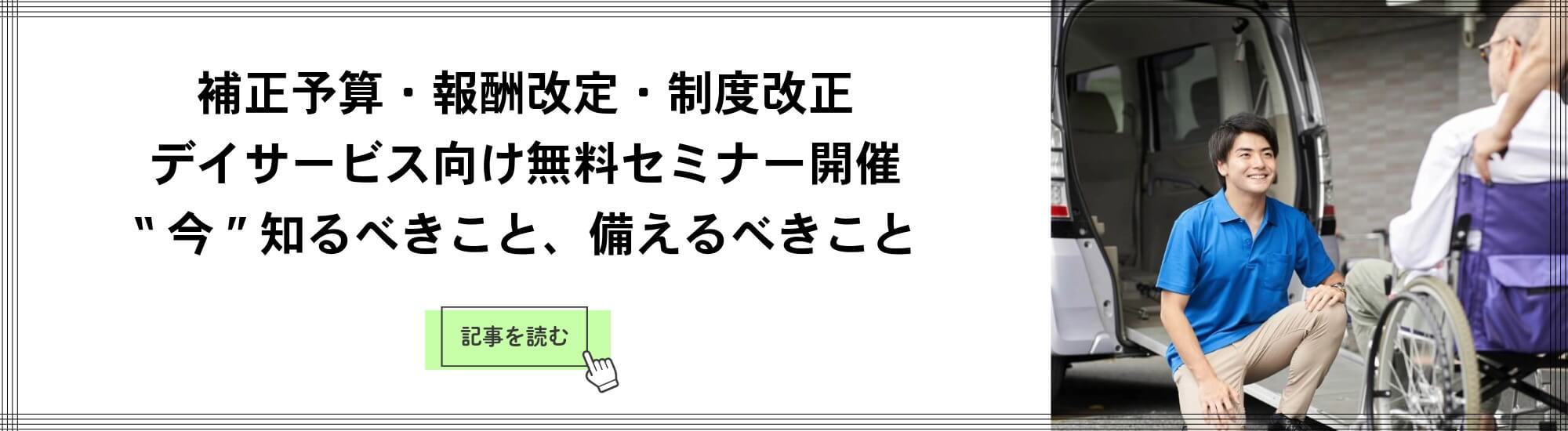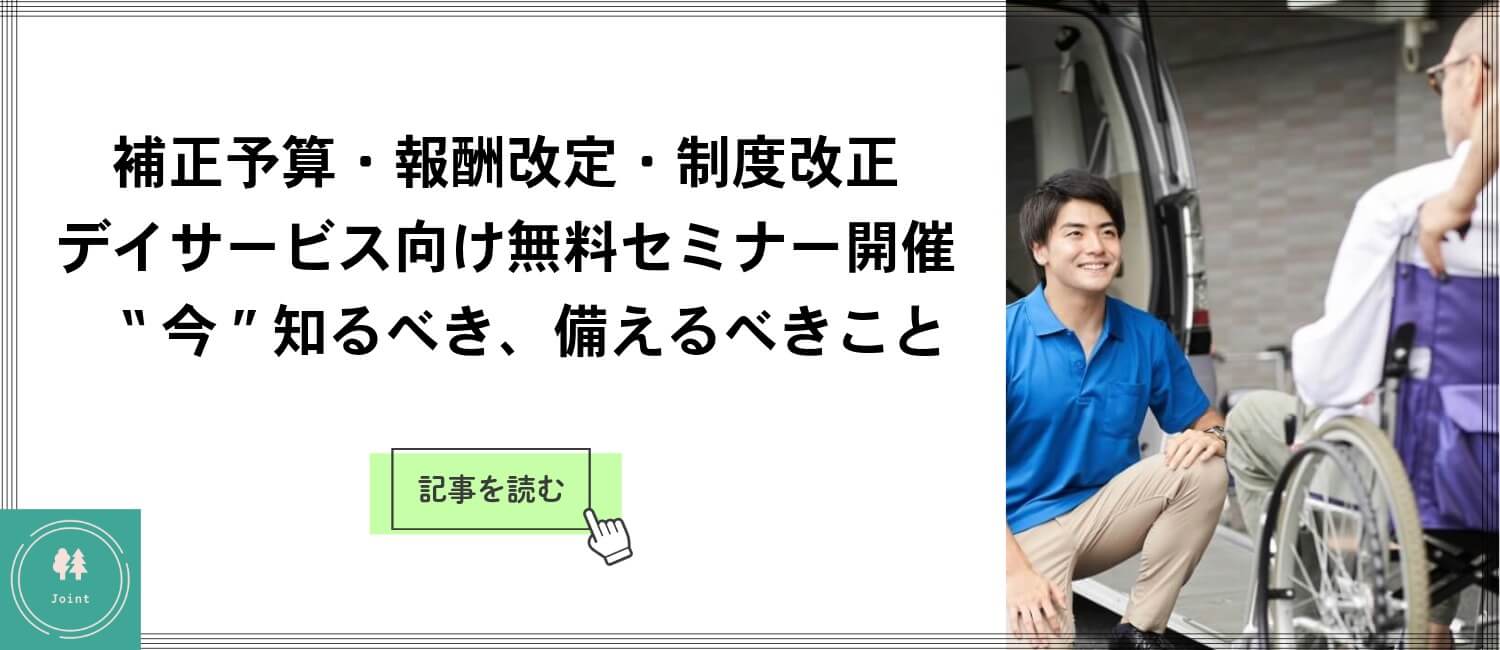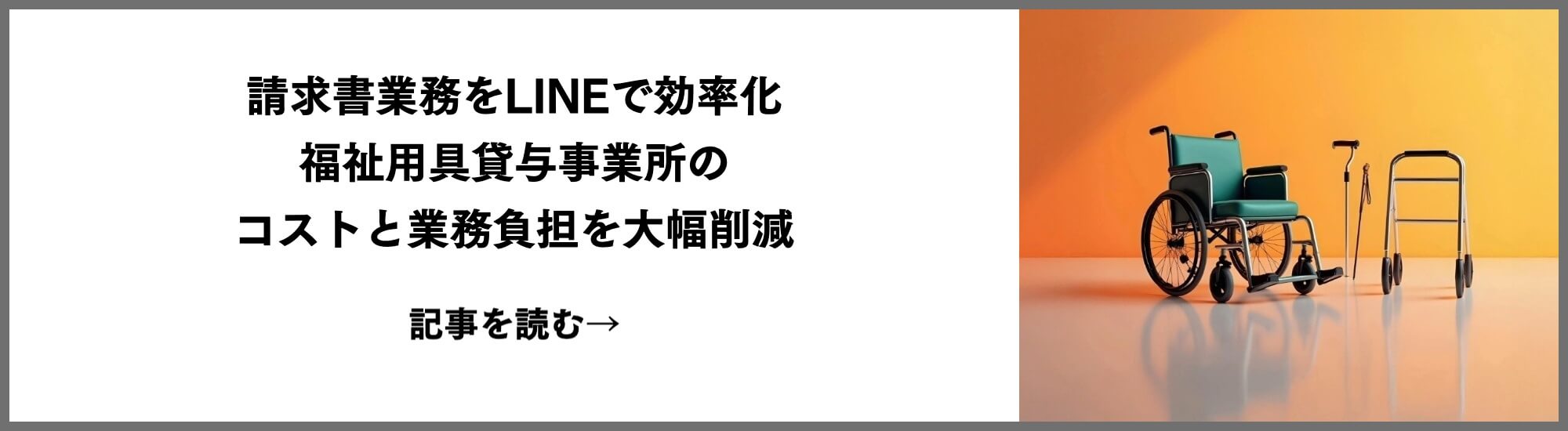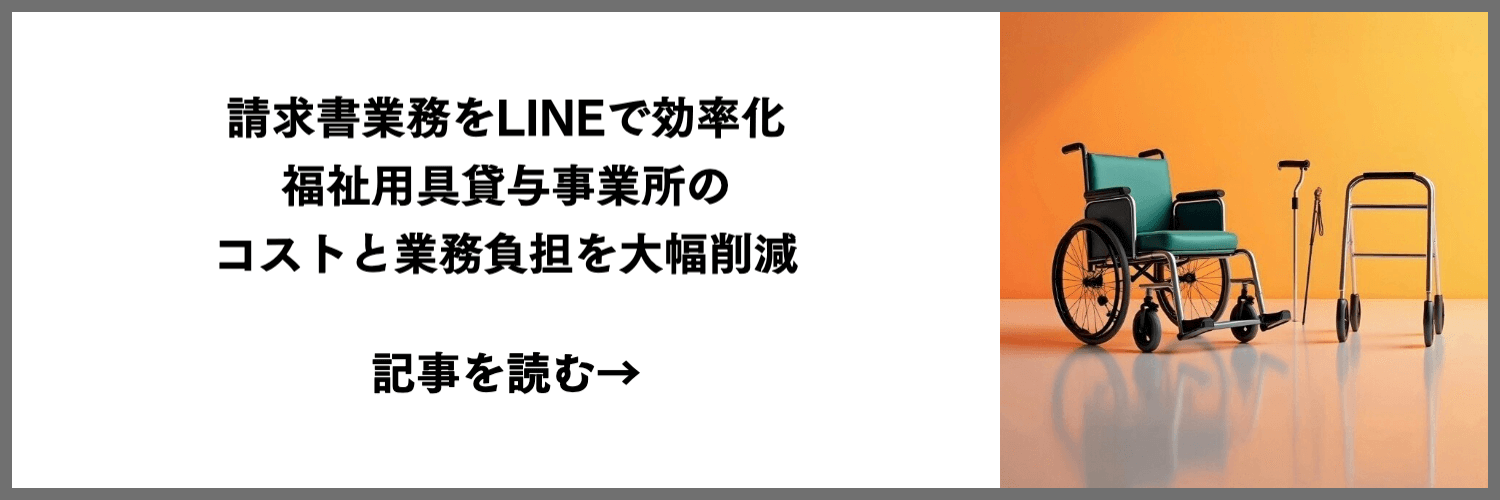訪問介護・通所介護の軽度者外し、現場の関係者が猛反発 次期制度改正へ年末に結論


少子高齢化が急速に進むなか、介護保険制度の持続可能性をどう確保していけばいいのか − 。厚生労働省は9月29日の審議会で、こうした「給付と負担のあり方」を俎上に載せた。【Joint編集部】
2027年度に控える次の制度改正に向けた論点として、軽度者に対する給付の見直しをあげた。要介護1、2の高齢者への訪問介護と通所介護、特にホームヘルパーの生活援助について、市町村がそれぞれ運営する地域支援事業に移すことの是非が、これから年末にかけて検討されていく。
財務省がこれまで繰り返し、「介護の人材や財源には限りがある」「給付を重度者に重点化していく必要がある」などと主張し、厚労省に具体化を促してきた経緯がある。サービスの運営基準の緩和やボランティアの活用などでコストを下げ、かかる費用の抑制につなげる狙いがある。
◆「これ以上先送りできない」との声も
この日の会合では、現場の関係者が反対の論陣を張った。
全国老人福祉施設協議会の山田淳子副会長は、「要介護度1、2の高齢者への適切なケアは、在宅生活を継続するために必須。地域支援事業への移管を実施すれば、専門性の乏しいサービスで対応することになり、自立支援のケアを劣化させる」と問題を提起。「サービスの質・量を確実に低下させ、長年築いてきた在宅ケアは著しく後退してしまう」と警鐘を鳴らした。
認知症の人と家族の会の和田誠代表理事は、「認知症の場合、要介護1、2など身体的に元気な人ほど家族の負担が重くなるという現実がある。認知症の人や家族のために、訪問介護や通所介護などの重要なサービスは給付として必ず死守してほしい」と訴えた。
また、全国町村会を代表する茨城県美浦村の中島栄村長は、「要介護1、2の高齢者の状態は要支援の高齢者と大きく異なる。各自治体の地域支援事業の実施状況も一様ではなく、移管は難しいのではないか」と述べた。
一方で、日本商工会議所・社会保障専門委員会の幸本智彦委員は、「これ以上の先送りはできない状況。現役世代の負担を抑制しつつ、介護保険制度の持続可能性を確保するために、スピード感を持って議論を進めてほしい」と注文。日本経団連の井上隆専務理事は、「現役世代の負担が重くなり、それが成長を阻害している。何ができるのかよく考えなければいけない」と呼びかけた。
厚労省は引き続き関係者と議論を深める構え。最終的な判断は、今秋に誕生する新たな政権の枠組みが年内に下すことになる。