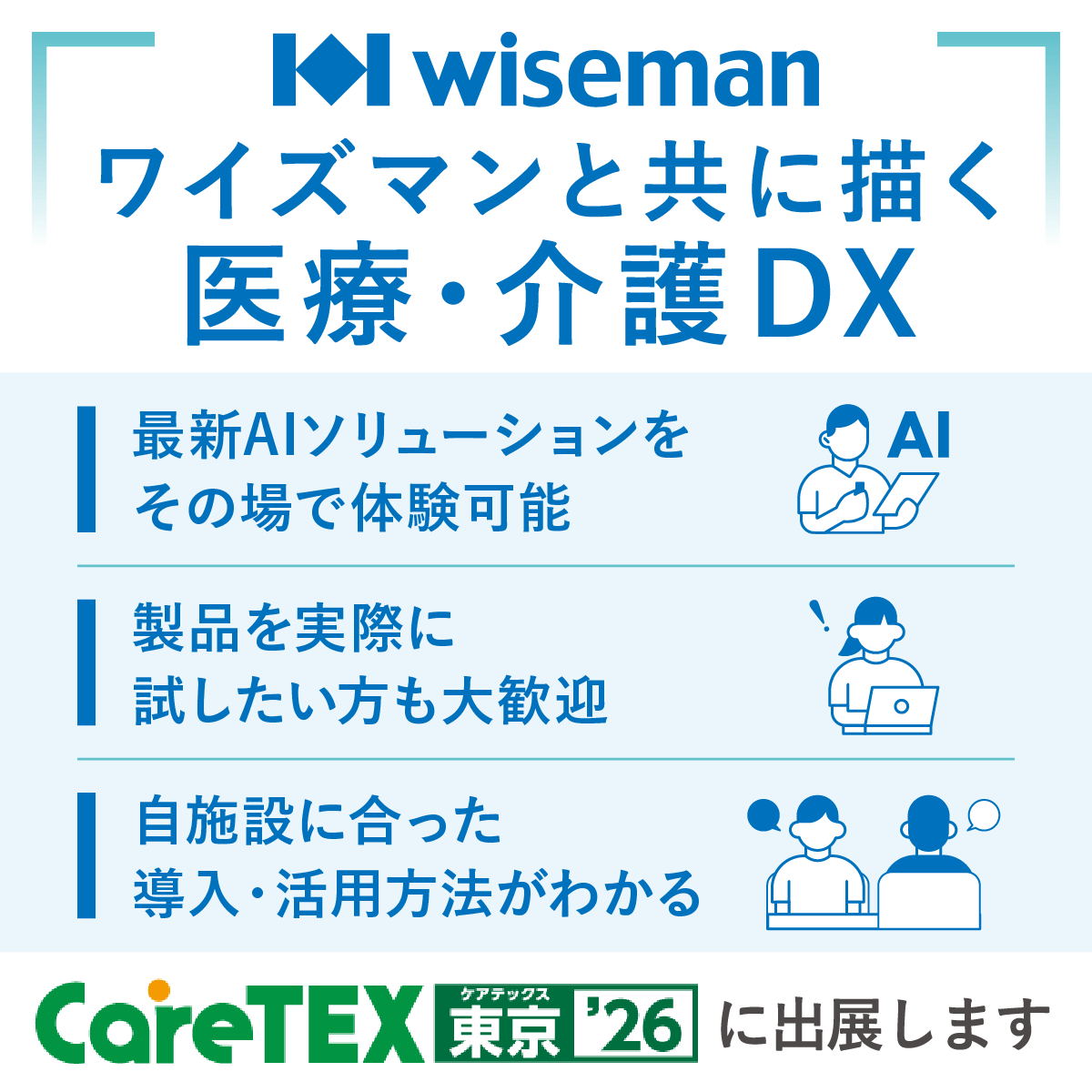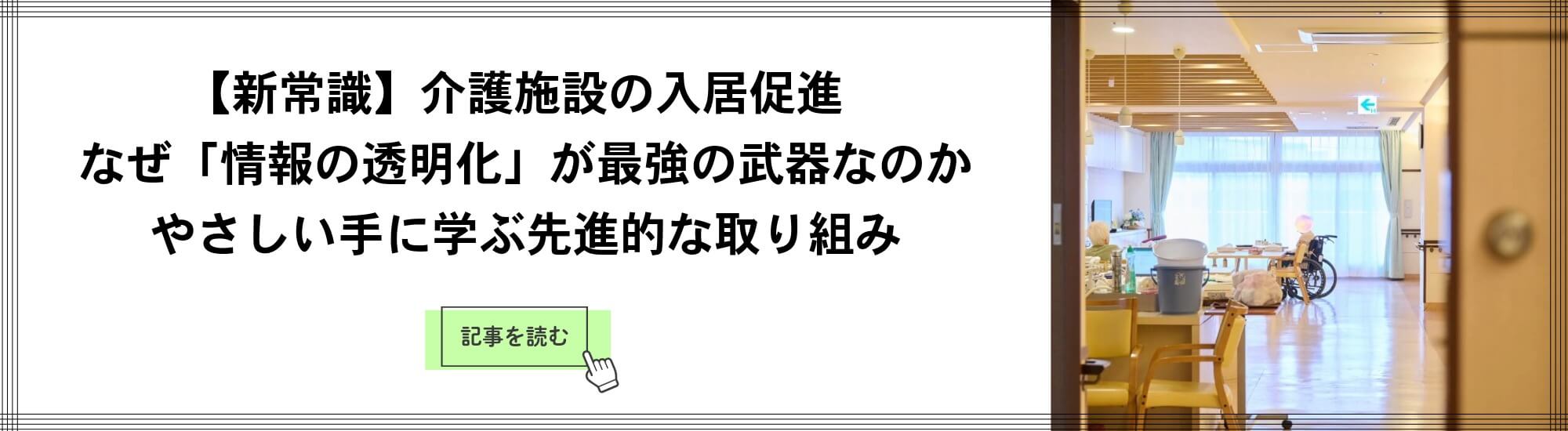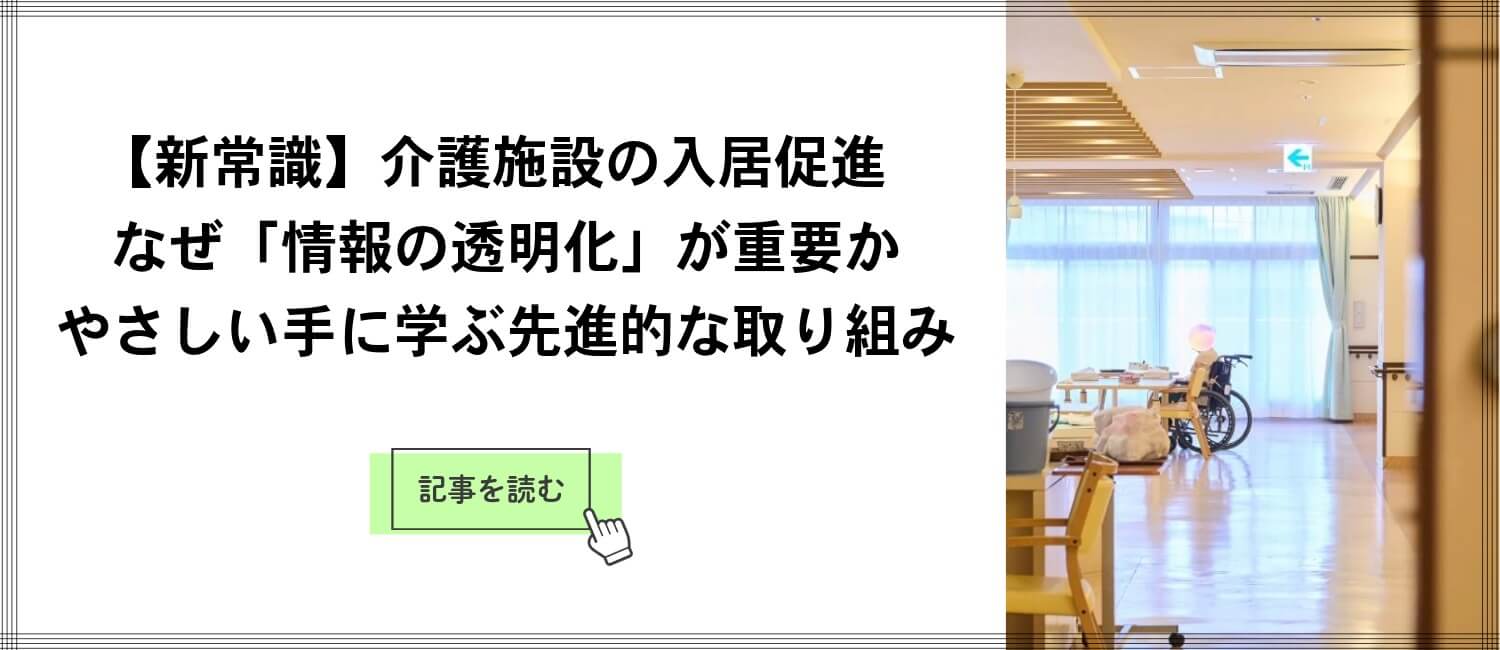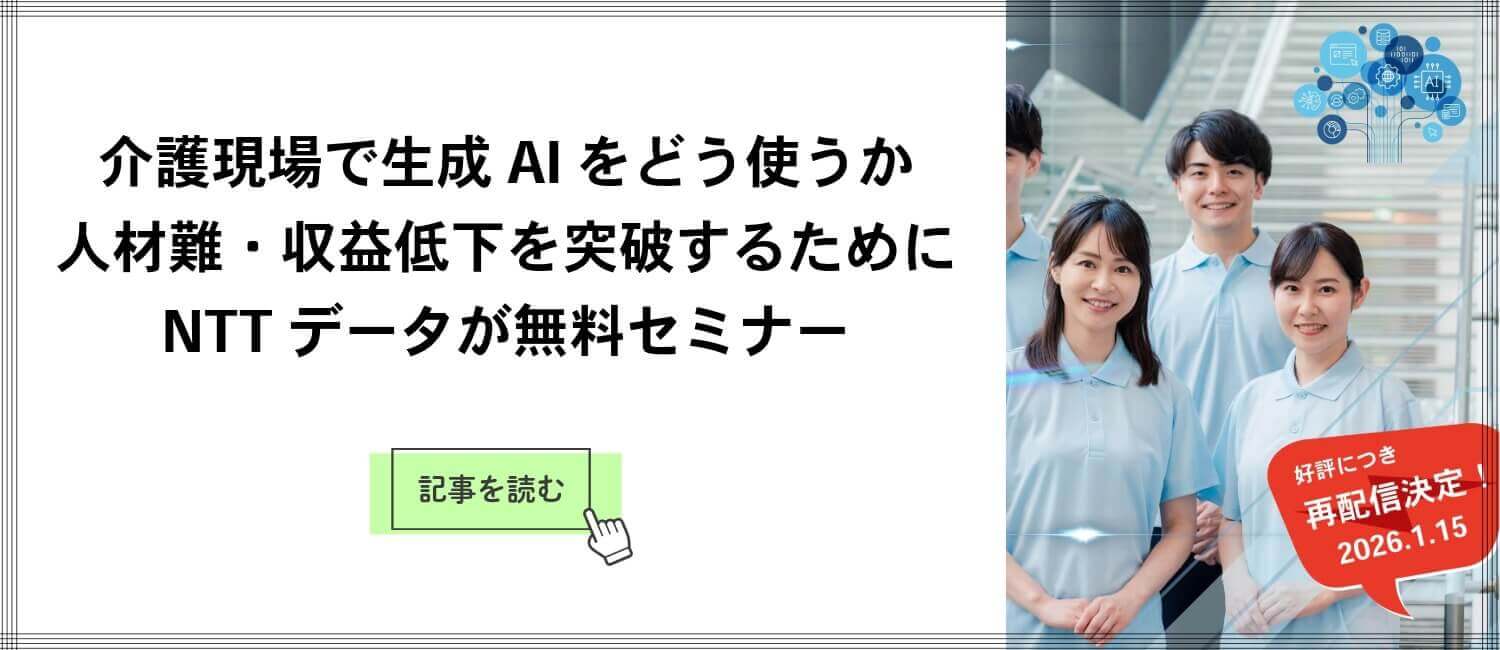自然災害の激甚化・頻発化により、専門職の災害支援が以前にも増して重要となっています。今回は、これまで日本介護支援専門員協会の支援活動を通して学んできた経験から、災害時の介護支援専門員の役割と平時からの備えについて、心得ておきたいことなどを述べたいと思います。【山口浩志】
◆ 介護支援専門員の役割
「平常時」がある瞬間に「災害時」へと劇的に変化します。近年は、台風や水害、豪雪、山林火災、竜巻など想定外の事態が発生しやすく、全国どの地域でも大きな災害が起きる可能性があります。
日本介護支援専門員協会は、大規模災害時、全国から速やかに災害支援ケアマネジャーを募集すると同時に、災害支援コーディネーターを確保・派遣するなど、様々な役割を担うことになります。また平時には、都道府県支部で防災・減災活動の研修会や災害対策訓練を実施するほか、行政や他団体との連携体制の構築に努めています。
さて、災害発生時の介護支援専門員の役割は何でしょうか。
まず、要援護者になる恐れのある利用者の把握に努めることが大切です。例えば、既往歴や症状といった健康状態、基本的な日常生活動作や精神面の留意点、居住環境、服薬内容、緊急連絡先などが、有事には極めて重要な情報となります。
◆ 重要な平時からの備え
事業所としての平時からの備えも欠かせません。まず地域住民との連携は、要援護者の命を守る基盤となります。災害発生時の近隣の方からの支援活動は、日頃からのつながりがあってこそ実現されるものです。そのためにも、町内会や民生委員などとの連携が重要となります。
また、利用者が暮らす地域の防災情報を確認しておくことも大切です。地域の避難場所がどこにあるか、重度の要介護者であれば、指定福祉避難所の情報を確認しておくことも求められます。
また、災害発生時に優先的に安否確認を要する利用者の情報をまとめた利用者台帳などを整理しておくことも重要です。ライフラインが遮断されることも想定し、安全に避難できる方法・場所の選定をしておかねばなりません。そのためにも、担当ケースの住宅地図や緊急連絡先、医療処置などの基本情報をまとめておくことは、平時からの大切な備えのひとつです。
これらのことを含め、介護支援専門員が定期的に開催するサービス担当者会議などの場で、日頃から災害時に関しても関係者間で話し合い、リスクアセスメントを作成することで、お互いに情報を共有できるように努めることが、介護支援専門員の大切な役割と言えるでしょう。また、各種制度の情報について事前に把握しておくことも大切な備えとなります。
◆ 協会の今後の取り組み
大規模災害時にどういった法令が適用され、どこにどのような避難所が設置されるのか。そうした情報を迅速に知ることも、森を見て木を見る支援に結びつく大切な要素となります。
日本介護支援専門員協会では、こうした取り組みを災害支援ケアマネジャー養成研修・フォローアップ研修などを通じて更にブラッシュアップし、今後の実践に活かしていきます。
「災害は平等、被害は不平等」「見落とさない、見逃さない、見過ごさない」。これを心得として、これからも災害支援の強化に積極的に臨みたいと考えています。