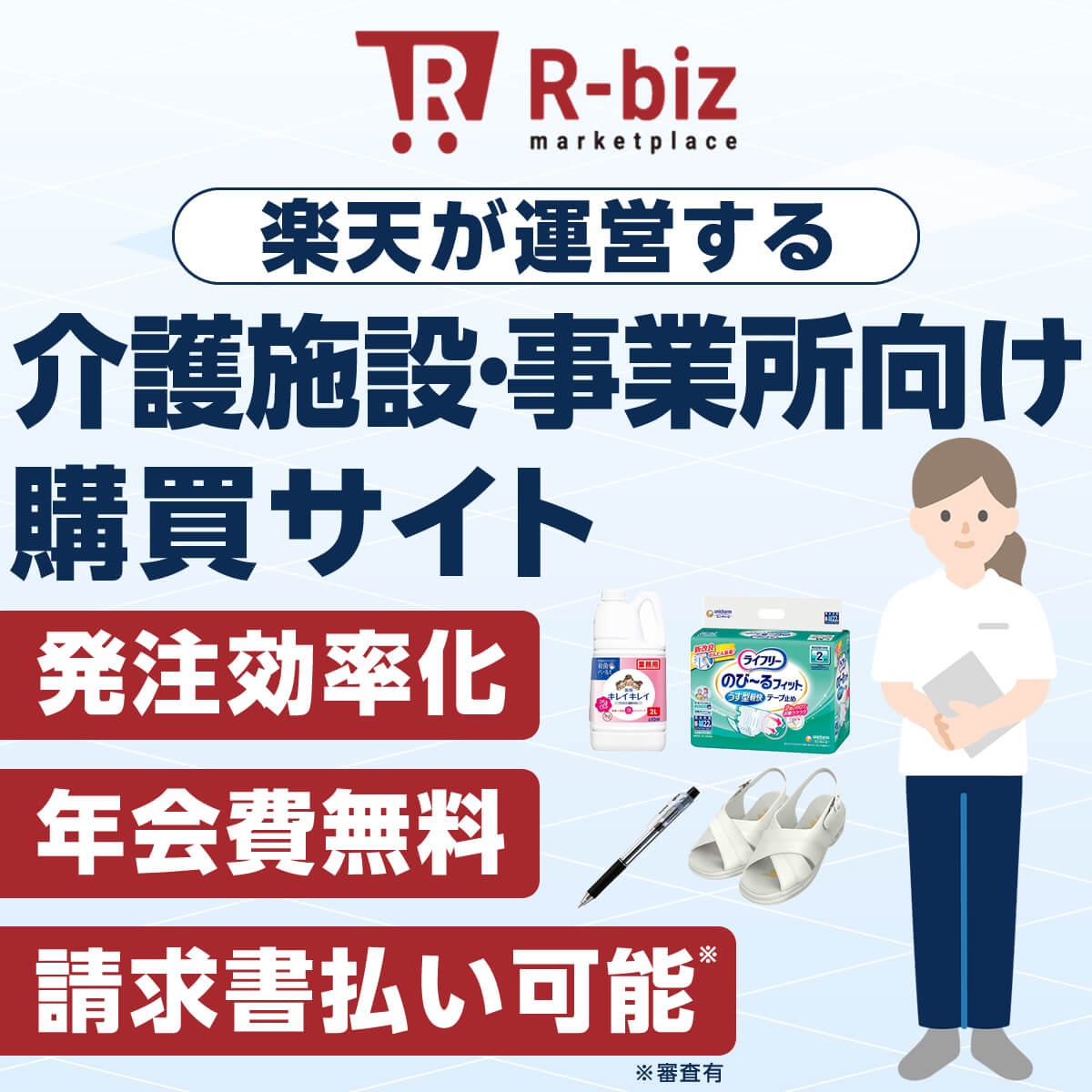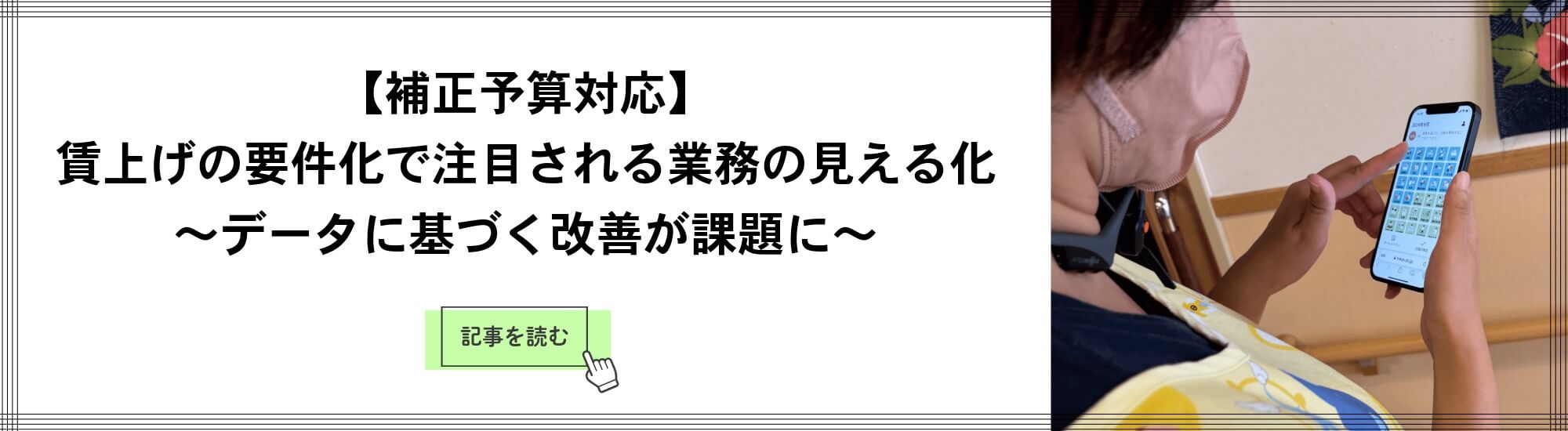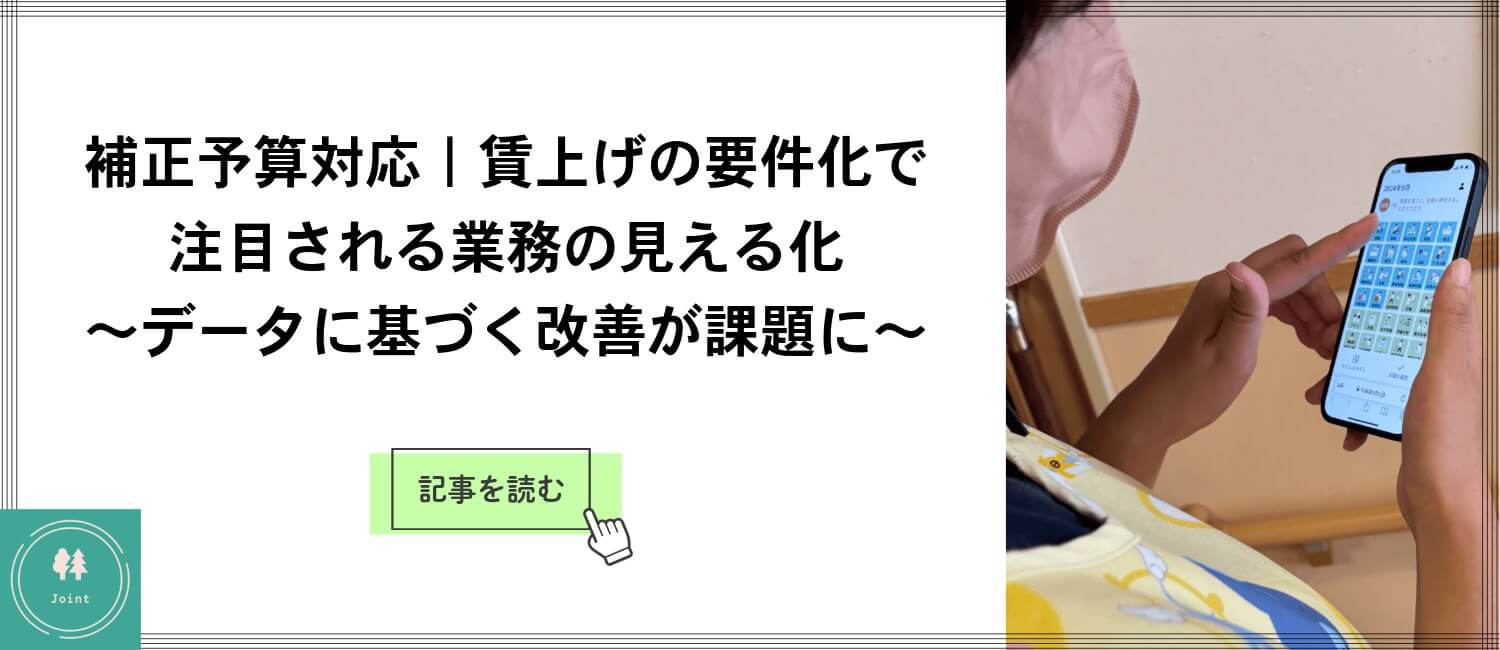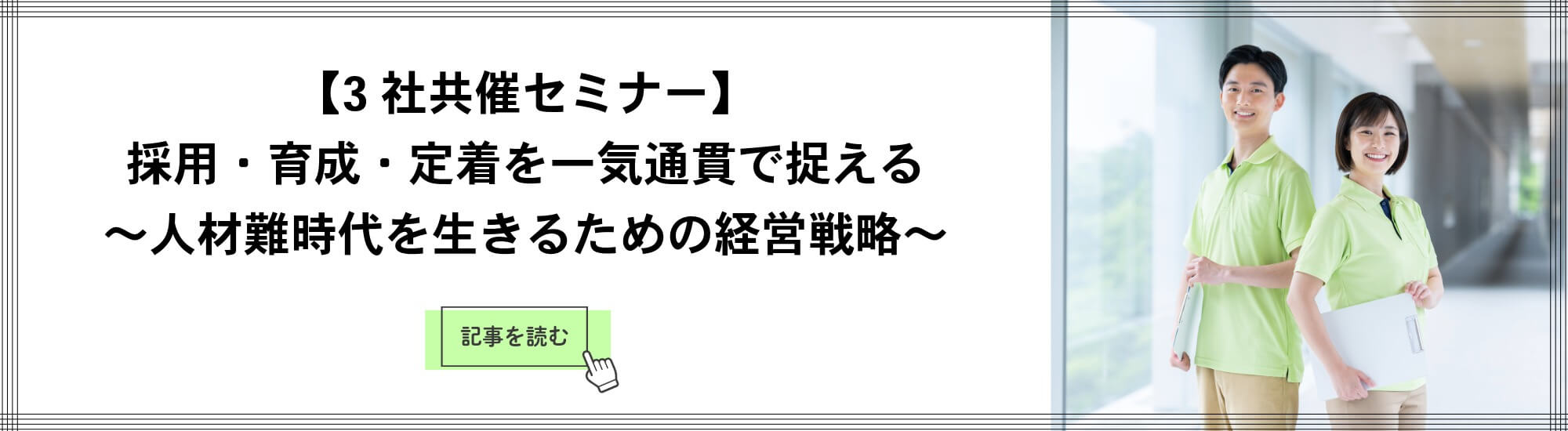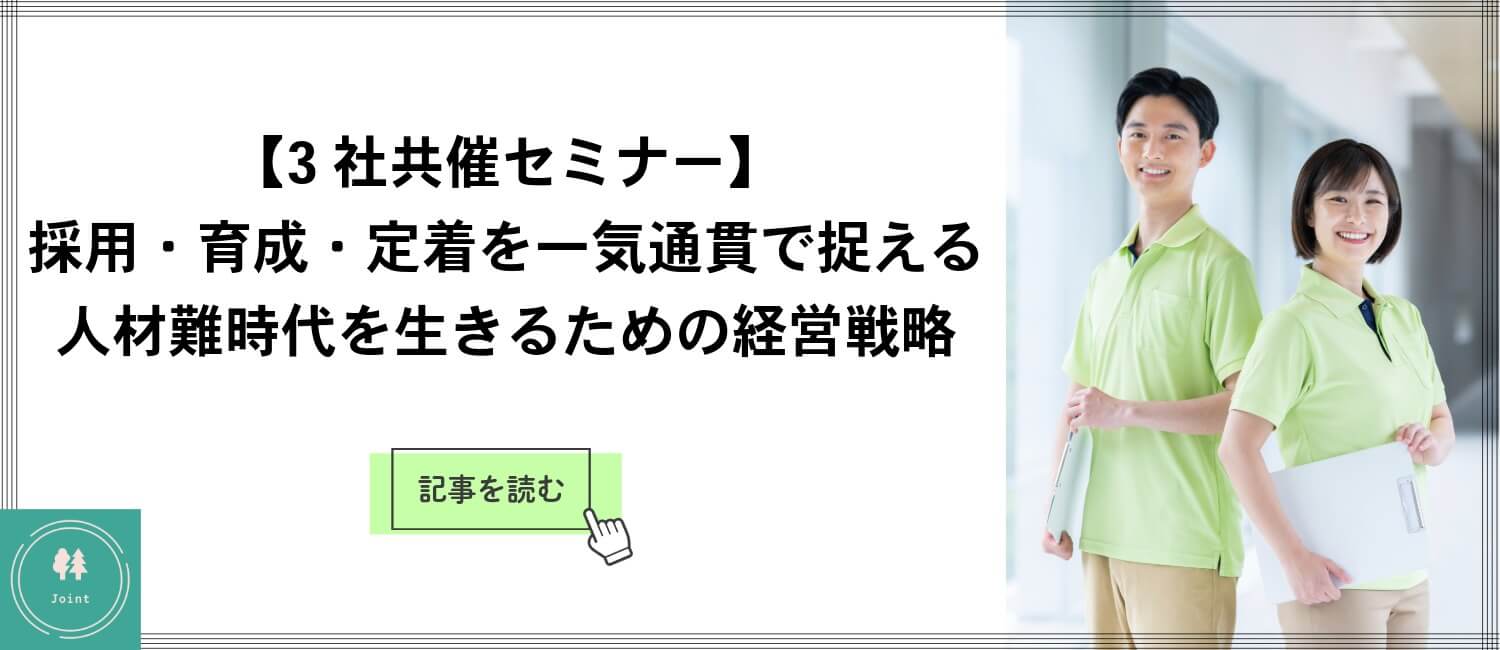【大転換】ケアマネ更新制の廃止はゴールではない 学び続けられる現場づくりのスタートライン=田中紘太


多くのケアマネジャーの負担軽減につながるでしょう。厚生労働省は思い切った判断をしたと思います。水面下で調整が進んでいたものの、想定より早く進んだと前向きに受け止めた方も少なくないようです。【田中紘太】
今月27日の審議会で、厚労省はケアマネジャーの資格の更新制を廃止する方針を固めました。会合で確認された重要なポイントは、次のように整理することができます。
◯ 資格の更新という概念がなくなる=資格者証の有効期限の印字がなくなり、更新手続きそのものが不要になる。
◯ 研修の受講は続く=専門職としての資質向上のため、一定の研修の受講が引き続き求められる。
◯ 研修の負担は軽くなる=時間数の縮減やオンデマンド化などで、より柔軟に受講できるようになる。
◯ 雇い主にも責任が生じる=ケアマネジャーが必要な研修を受けられるよう、事業者にも十分な対応が求められる。
◆ 小さくない人材確保の効果
現在は受講機会の制約もあり、1日でも研修を受けられないと資格を失効しかねない厳しい状況です。この“ヒヤリ”がなくなるだけでも大きい。今回のニュースを朗報と捉える人が多いことも頷けます。
また、ベテランのケアマネジャーらが更新を機に離職を決めるケースが少なくないことも、皆さんご存じの通りです。これが解消されることは、深刻な人材不足と向き合う事業者の1人として、とてもありがたいことだと感じます。
資格の更新という“関所”をなくし、ケアマネジャーがそれぞれのペースで継続的に学んでいける制度に変えることは、きっと人材の裾野の維持・拡大にも寄与するはずです。
現任者はもちろん、いわゆる「潜在ケアマネジャー」にとってもインパクトは大きいでしょう。復職の際に一定の研修が必要とはいえ、介護現場に戻るハードルはぐっと下がります。人材確保の効果は決して小さくありません。
◆ 変わらない研修の重要性
更新制を廃止する一方で、ケアマネジャーには一定の研修の受講を引き続き求めていく − 。
厚労省はこうした考え方を示していますが、私はこれにも賛成です。非常に重要なことだと捉えています。
我々は専門職であり、その仕事を続けるためには継続的な学び、自己研鑽が欠かせません。ケアマネジャーが少ない小規模な事業所では、独学の知識・技術が固定化していくリスクもあるでしょう。定期的な研修、外部からの良い刺激は、利用者の保護や専門性の維持などに不可欠です。
研修をオンデマンド化し、かかる負担を分散させながら受講していける仕組みを整備することは、現実的で妥当な方向ではないでしょうか。
◆ 事業者の責任の明確化を
事業者にはどんな対応が求められるのでしょうか。厚労省はまだ詳細を明らかにしていません。私は、一定の厳格なルールを設けることが必要だと考えます。
まずは居宅介護支援の運営基準。現行でも、事業者にはケアマネジャーの資質向上に努める責務がありますが、ここをよりしっかりと加筆すべきではないかと思います。
特定事業所加算の要件も見直すべきです。運営基準との二段構えにより、ケアマネジャーが無理なく継続的に学んでいける環境を確実に担保すべきです。
要するに、事業者の研修支援の責任を明確化して十分な対応を求めるべきです。厚労省には、次の2027年度の介護報酬改定に向けてしっかりと検討を進めていただきたい。
加えて言うと、原則として研修費は法人負担、研修受講は勤務扱いとすべきです。
資格は個人に帰属するものですが、研修の受講はケアマネジャーとして働き続けるために不可欠で、事業所にとってもサービスの質や信用などの面でメリットが生じます。研修のために有給休暇を消化させる運用は、ケアマネジャーにとってあまりにも酷ですし、人的投資の観点から筋が悪いと言わざるを得ません。
研修費も捻出できるはずです。今は昔と違い、多くの自治体が研修費の助成を用意しています。私が運営する事業所では10年以上、研修は業務時間内、自己負担ゼロを続けてきました。
ケアマネジャーの皆さんはぜひ、求職・転職の際に「研修は勤務扱いか」「研修費は法人負担か」を確認して下さい。それが当たり前の法人がありますので、答えが悪ければ他を探して下さい。十分な体制を整えない法人を選ばない文化が広がれば、業界全体の水準の向上につながるはずです。
◆ この転換を好機に
5年ごとに重い負担を強いる更新制を廃止し、自由度の高い継続的な学びと事業者の研修支援で質を担保していく − 。こうした国の方向性に私は賛成します。
今回の厚労省の判断を高く評価する声も多いようですが、これはゴールではなくスタートです。
更新制がなくなれば、実質的に学び続けていくかどうかは私たち自身の意思と行動にかかってきます。自由度が広がる分、専門職としての自律がこれまで以上に問われることになるでしょう。
更新制の廃止で生まれる“余白”を、実効性のある豊かな学びに振り向ける。事業者はケアマネジャーの研修の受講を支える責任を果たす。国は運営基準や加算の見直し、処遇の改善で制度に背骨を通す。
ケアマネジャーの価値は、学び続ける営みの積み重ねで更に磨かれていくでしょう。今回の大きな転換を、現場の力を底上げする好機にしていきたいと考えます。