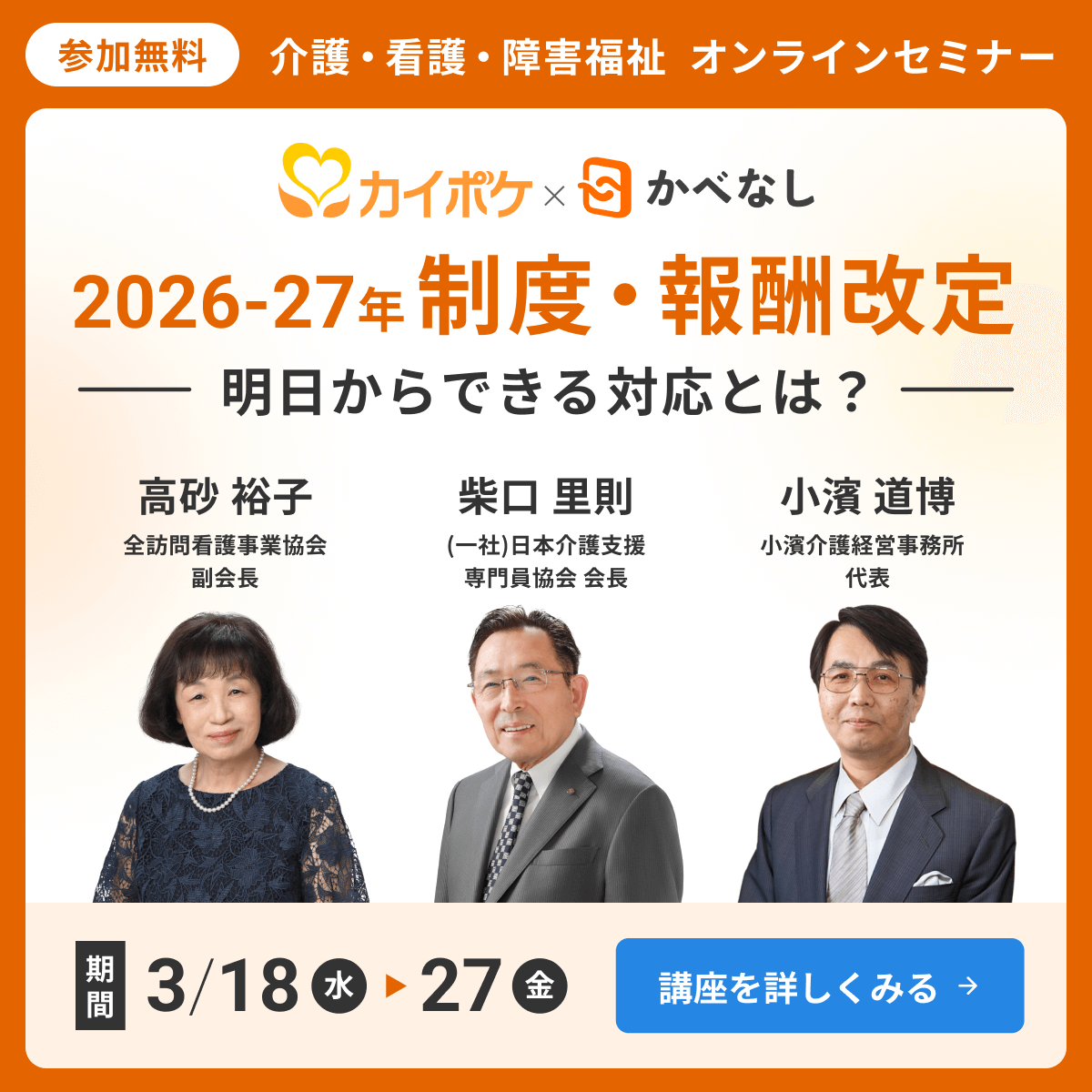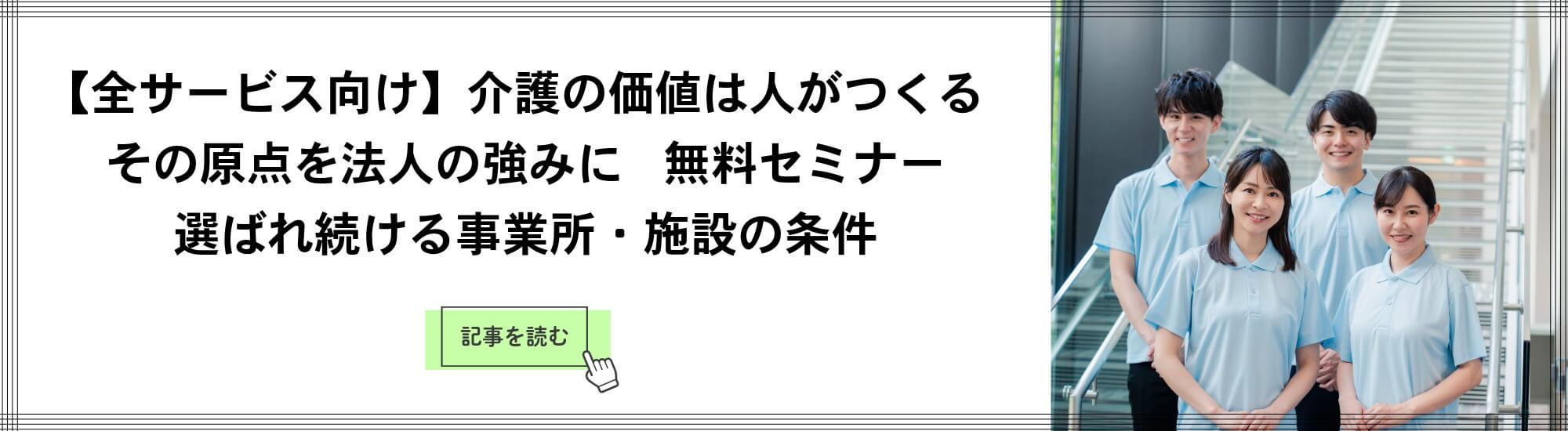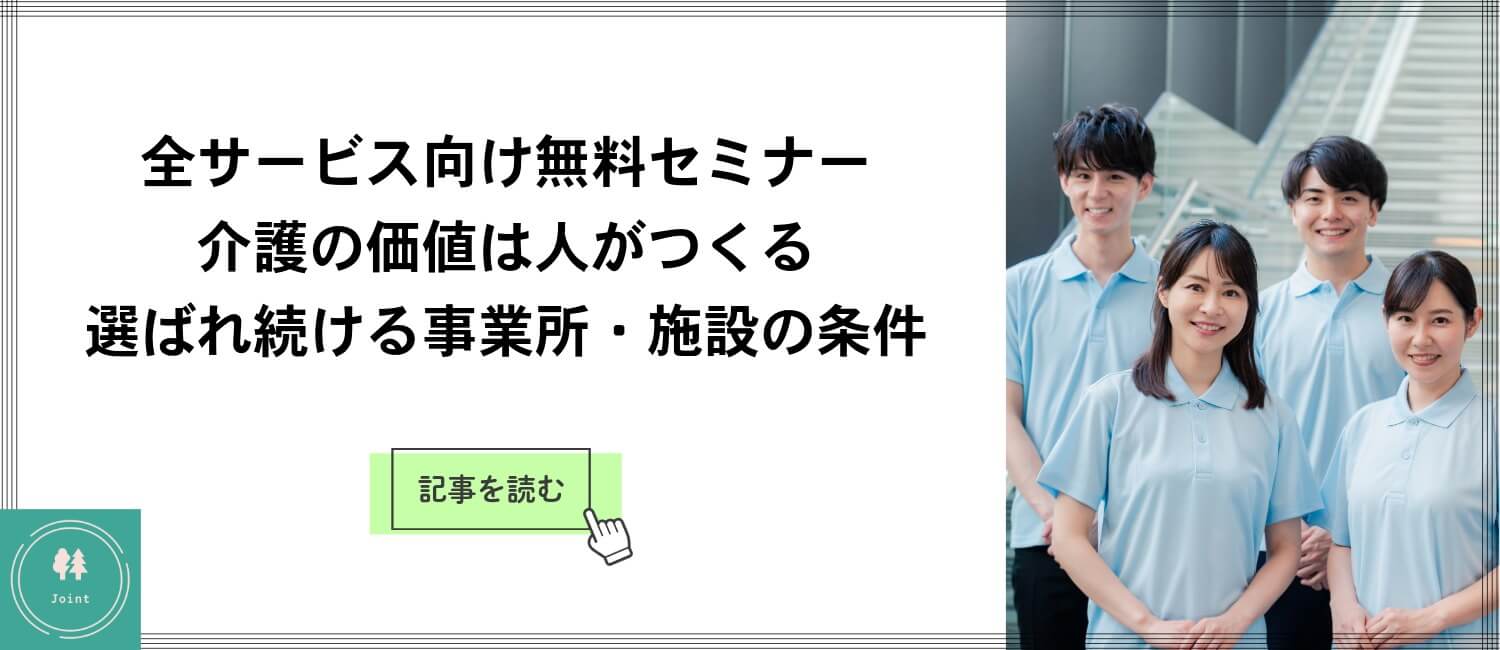介護支援専門員の不足は、現在の課題としても、近い将来の課題としても深刻です。その解決のためには、ケアマネジャーが働きやすい環境づくりが大切ですが、具体策の1つに処遇の改善があります。【石山麗子】
◆ なぜ「改定前倒し」なのか
11月21日、高市総理は約21兆3000億円にのぼる「強い経済を実現する総合経済対策」を行うことを発表しました。
この総合経済対策は3つの柱から構成されており、医療・介護などは「第1の柱:生活の安全保障・物価高への対応」に該当します。
政府はこの中で、国民の生活に不可欠な医療・介護分野に対し、緊急的な支援措置を行う方針を打ち出しました。赤字の医療機関や介護施設を中心に、通常の報酬改定の時期を待たずに、補助金を活用した「医療・介護等支援パッケージ」を展開する意向を示しています。
最初に着目すべきは、来年度に介護報酬改定を行う方針が明示された点です。
順当にいけば、次の介護報酬改定は令和9年度に行われる予定でした。介護報酬改定は基本的に3年に1度。ただこれは、経済や物価が安定していることを前提としたサイクルです。
今回の“前倒し改定”の背景には、物価高・人材不足・賃金上昇という介護現場の「三重苦」があります。本来の改定時期を待っていては、国民のニーズには到底応えられない ー 。政府はそう判断したのだと思います。
次に着目すべき点は、総合経済対策の具体的な対応の内容や額です。政府は処遇改善について、医療機関の従事者にはプラス3%を、介護従事者全般には月1万円を、どちらも半年分措置する方針を示しました。
現在、居宅介護支援には処遇改善加算がありません。いったいどのような取り扱いとなるのでしょうか。介護職員との差がまた開くのか、心配されるところです。
◆ 明記された「ケアマネジメント」
今回の政府の総合経済対策には、「訪問介護・ケアマネジメントの提供体制の確保に向けた取り組みを支援する」とも明記されています。
この対策が発表された11月21日には、介護報酬改定などを議論する審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)が開催されました。同日開催は決して偶然ではないでしょう。議題はたった1点で、「介護人材確保に向けた処遇改善などの課題」に絞られていました。つまり、政府が示した「第1の柱:生活の安全保障・物価高への対応」について、来年4月に向けていち早く対応するという行動の表れと言えるでしょう。
審議会の資料によれば、ケアマネジャーの離職率は他職種より低いものの、採用率も「訪問介護員」や「介護職員(施設等)」より低い状況です。賞与込み給与の比較をみると、ケアマネジャーは看護師やリハビリテーション職より低く、准看護師と同等でした(34.5万円)。
このような事務局の資料説明の後には、議論に参加している委員が意見を述べましたが、大半の委員はケアマネジャーの処遇改善について、「必要」との考えを示しました。
こうした流れを踏まえれば、来年度の介護報酬改定において、ケアマネジャーも対象とした処遇改善が実現することが、十分に期待できる状況になってきたと言えるでしょう。