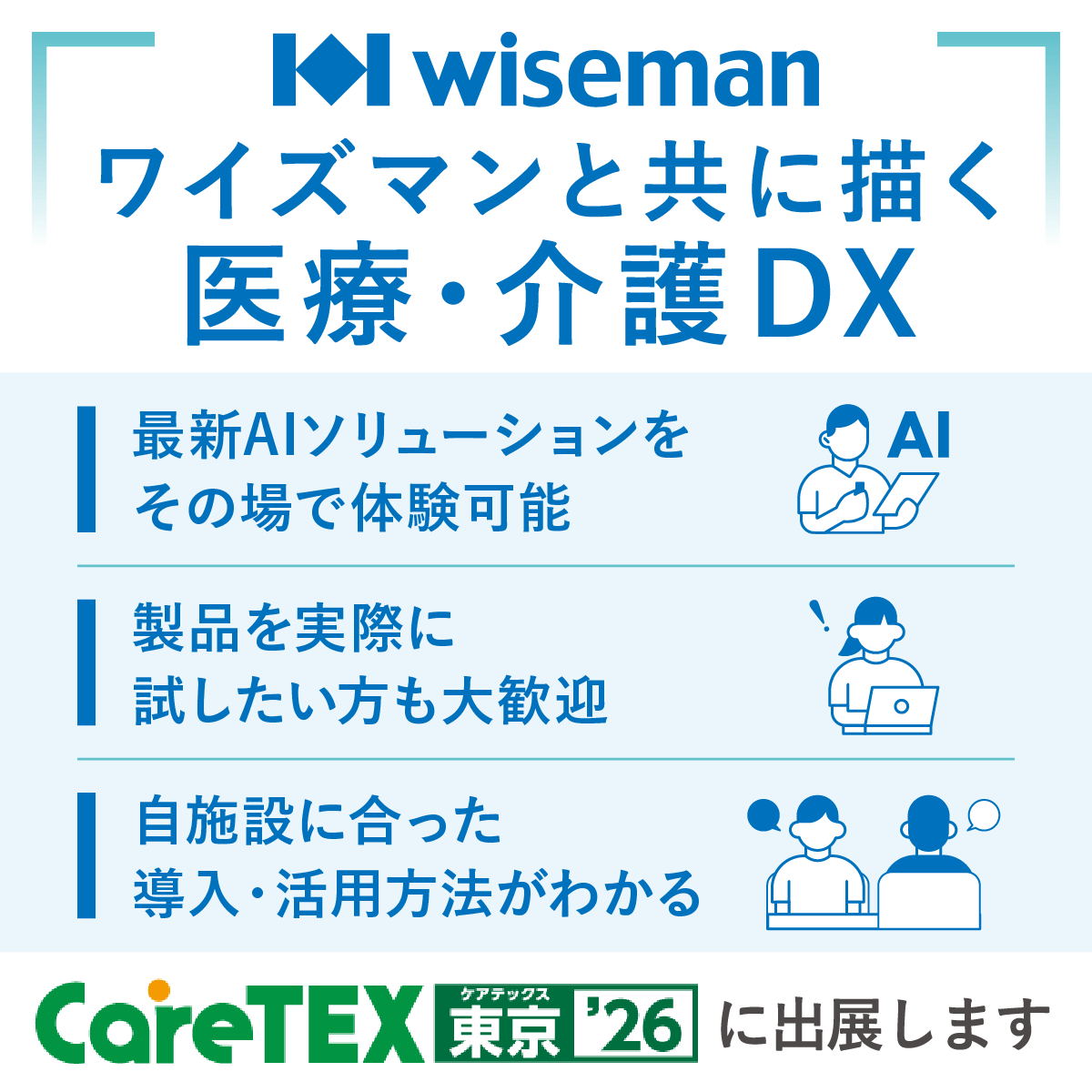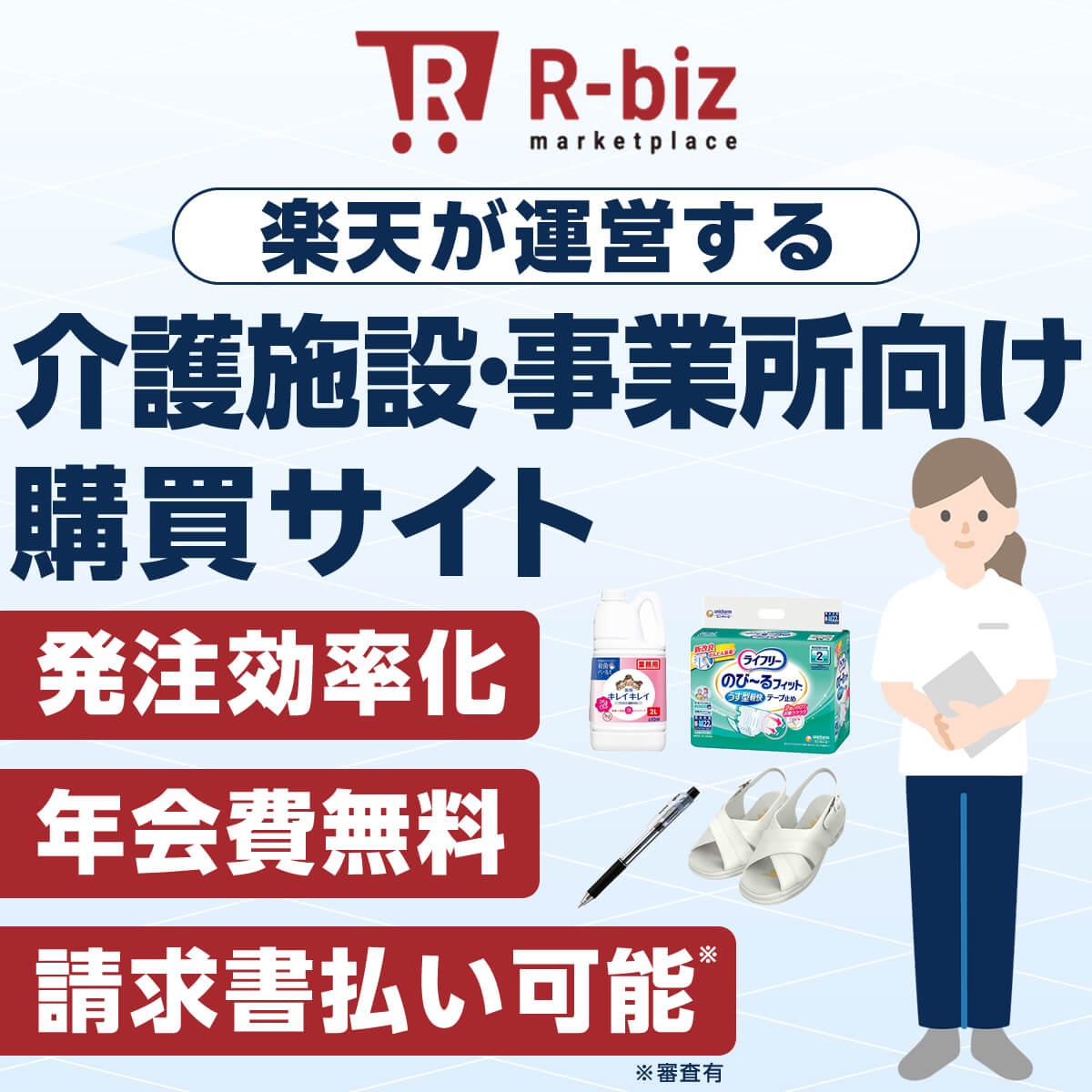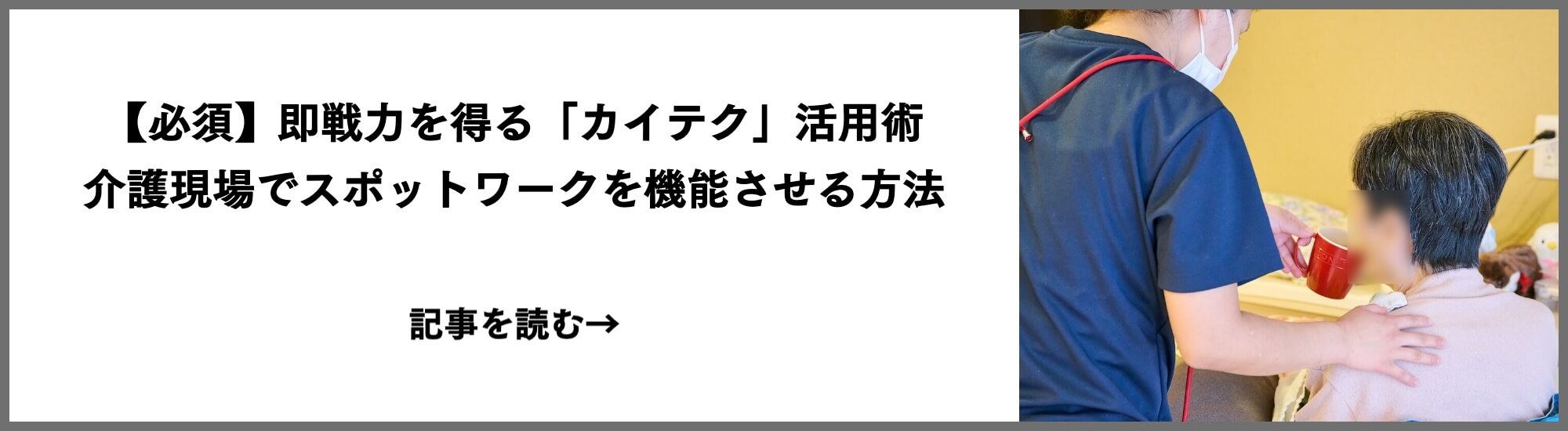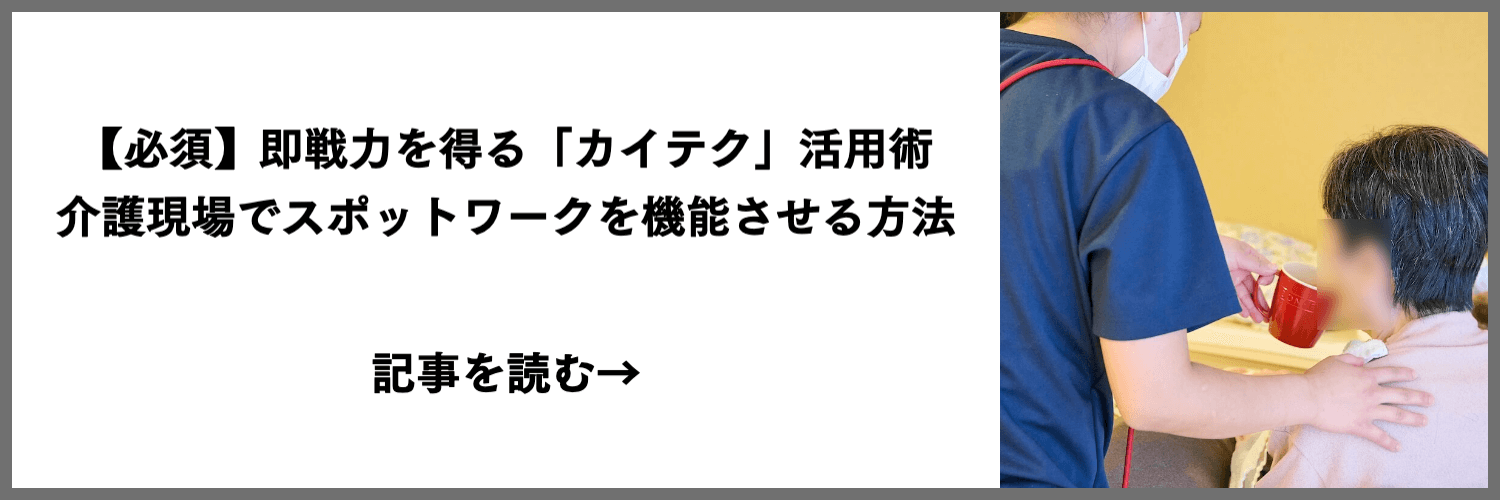【壷内令子】ケアマネにもケアプランを 疲れた心に寄り添う価値 自分をいたわり、支え合える職場へ


最近、ケアマネジャーのモチベーションがどんどん下がっていると感じます。【壷内令子】
現場で働く仲間たちから「もう疲れた」「しんどい」といった声を耳にします。そのたびに胸が痛みます。日々の悩みや苦しさを聴くだけでなく、どうにか支える方法はないかといつも考えています。それが仲間を守ること、ひいては地域の介護サービスを守ることにもつながるのではないでしょうか。
◆ 忙しさが心を奪い、未来を描けない現実
あるとき、私が活動する地域のケアマネジャーにこんな問いかけをしてみました。
「あなた自身の目標ってありますか?」「どんな働き方がしたいですか?」「仕事をしながら、どんな生活を送りたいですか?」
返ってきたのは、「忙しすぎてそんなこと考える余裕はない」「疲れすぎて未来のことを考えたこともない」といった言葉でした。
私はもっと現実的な要望が返ってくると思っていました。たとえば、「給与が上がれば生活にゆとりができるから、趣味を楽しみたい」「書類業務が減れば、余裕をもって利用者や家族の話を聞くことができる」などです。
でも、実際には“何も考えられないほど疲れている”という現実があったのです。これはなんとかしなければ、と感じました。
◆ 利用者には目標を、でも自分には…
私たちケアマネジャーは、利用者さんに目標を設定し、そこへ向けた支援を行う存在です。ところが、自分自身には目標がないことが少なくありません。それは、心も体も疲弊して、希望を持つことすら難しい状況にあるからだと思います。
だからこそ、まずは「自分の目標を持てるようになること」から始めてみてはどうかと考えました。「考える余裕がない」と感じている今だからこそ、より基本的なことを目標に掲げてみるのはどうでしょうか。最初の一歩として、「自分のことを少し考えてみる」ことからスタートすればいいと思うのです。
◆ 経営者・管理者に求められること
では、経営者や管理者に求められることは何でしょうか。
まず大切なのは、事業所のケアマネジャーが「今、何に悩み、どこに困っているのか」をできるだけ具体的に把握することです。
たとえば、「書類が多くて大変」と言われたとき、それは支援経過のことなのか、ケアプランのことなのか。あるいは、アセスメントやモニタリングの記録について、内容のまとめ方や言葉選びに迷っているのかもしれません。同じような内容を何度も繰り返し書いていて、時間ばかりかかってしまっているケースもあります。
そういったひとつひとつの「困りごと」に丁寧に目を向けて、どの部分に負担を感じているのかを具体的に見つけ出してあげてほしいのです。
また、中には利用者や家族への対応に心をすり減らしているケアマネジャーもいます。理不尽な要求を受け、振り回されて困っているような場面も少なくありません。
けれど、そうした苦しさはなかなか口に出しづらいものです。だからこそ、しっかりと耳を傾け、実態をつかみ、必要なサポートや具体的な対応策を一緒に考えていくことが大切だと考えます。
◆ “職員向けケアプラン”も必要
私たちは利用者さんにケアプランを立てて支援しています。それと同じように、ケアマネジャーひとりひとりにも“職員向けケアプラン”があっていいのではないでしょうか。
ケアマネジャーは皆、それぞれ違う背景や悩みを抱えています。給与を引き上げることは重要ですが、それですべて済むという話ではありません。その人に合った支援を考え、実行していく仕組みが必要です。
もちろん、口で言うのは簡単で、実際にやるのは本当に難しいことです。私自身、現場で日々実践しているからこそ、それはよく分かります。
それでも、少しずつでもいい。皆が自分らしく働き、笑顔でいられるように。同じ目線で寄り添い、応援していく姿勢が、厳しい状況の今こそ大切なのではないでしょうか。そうして職員を大切にしていくことが、自分たちの事業にとっても、地域にとっても重要なのだと思います。