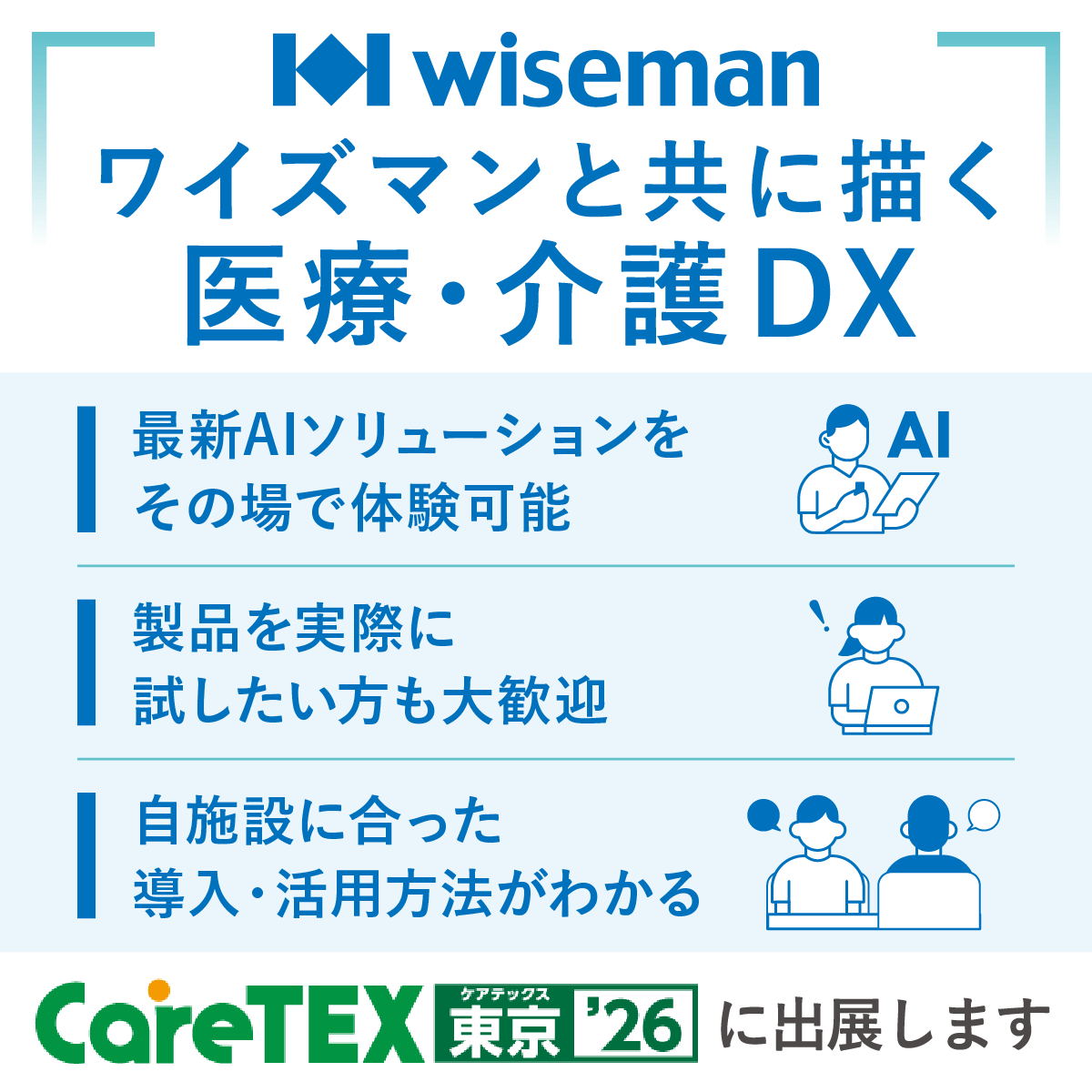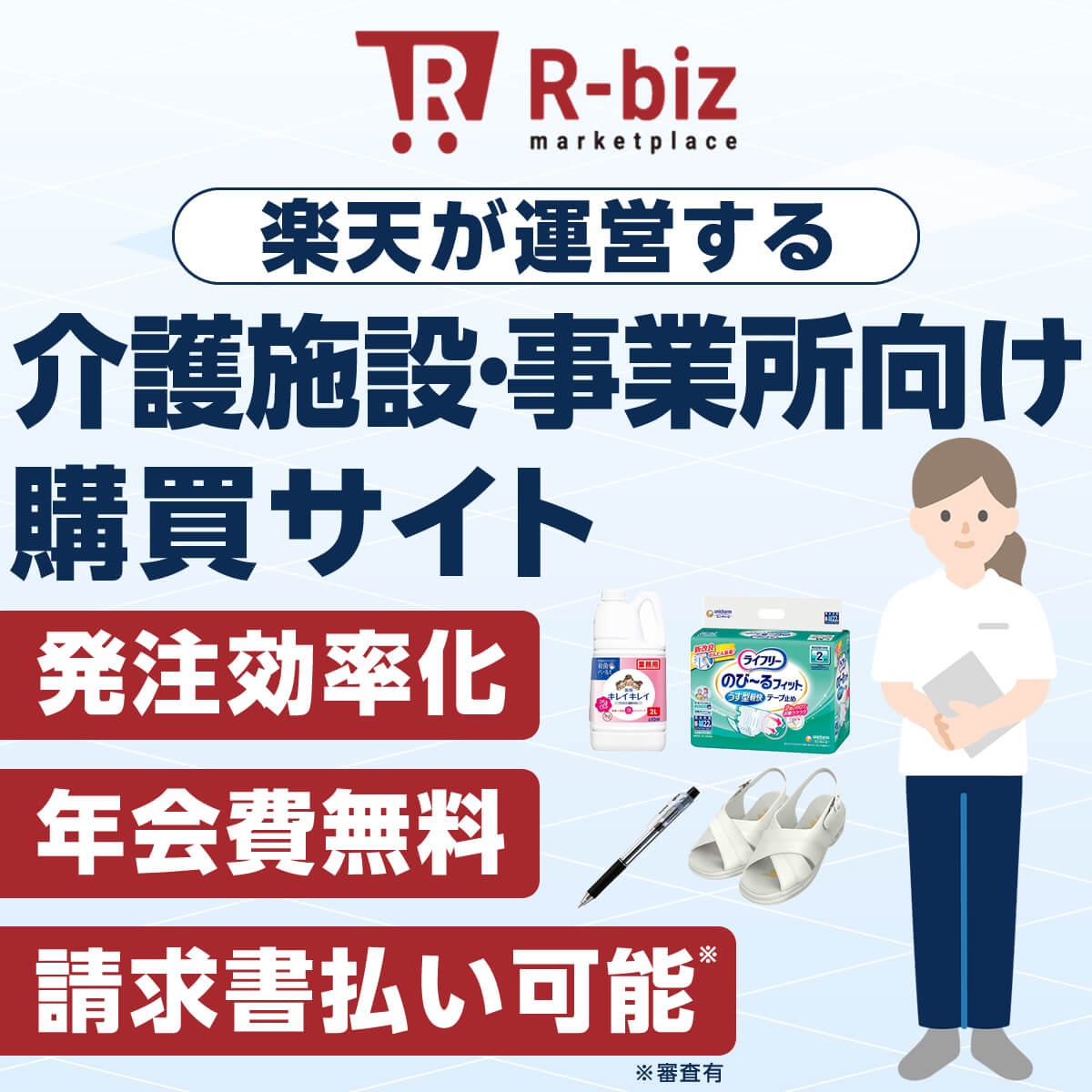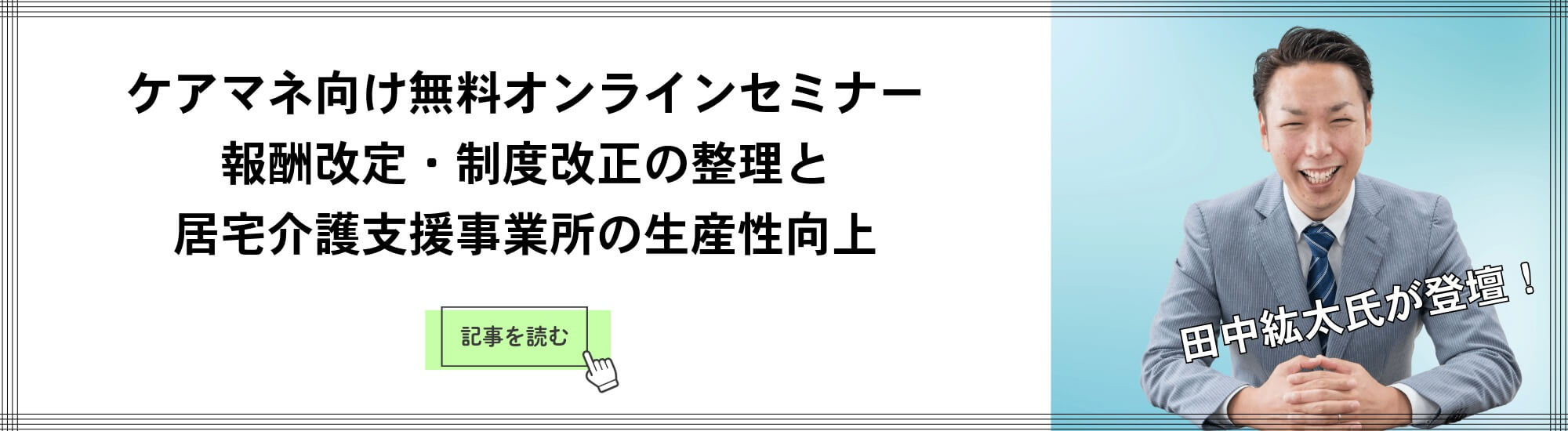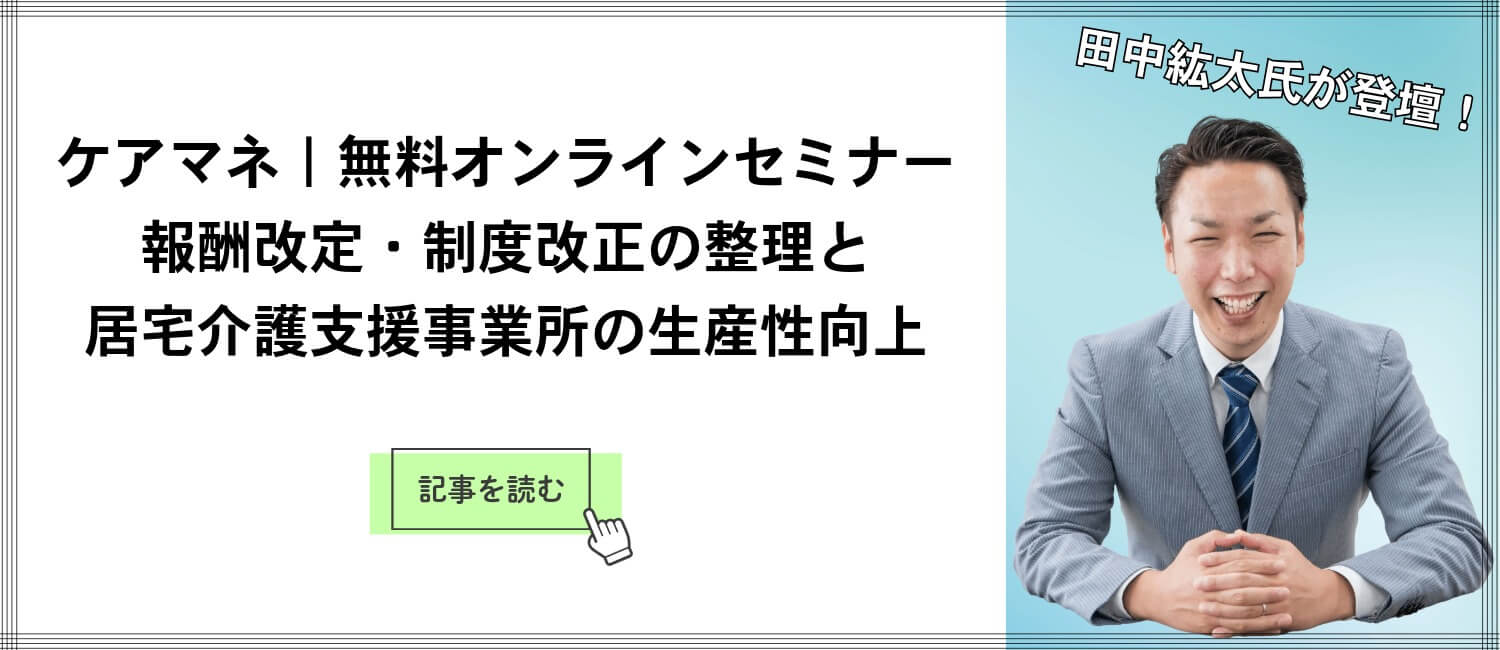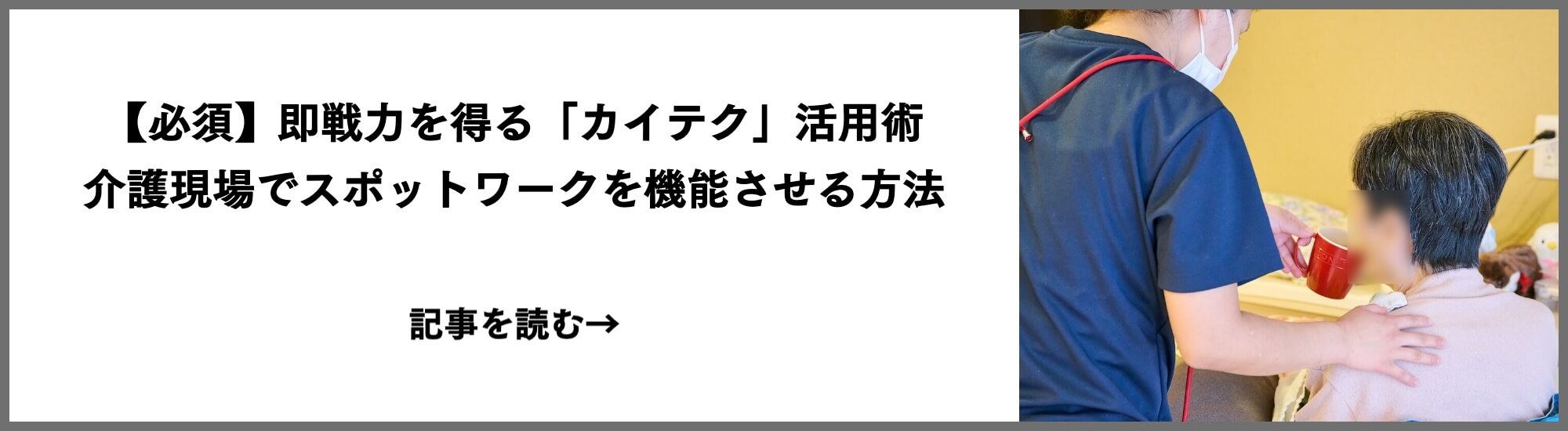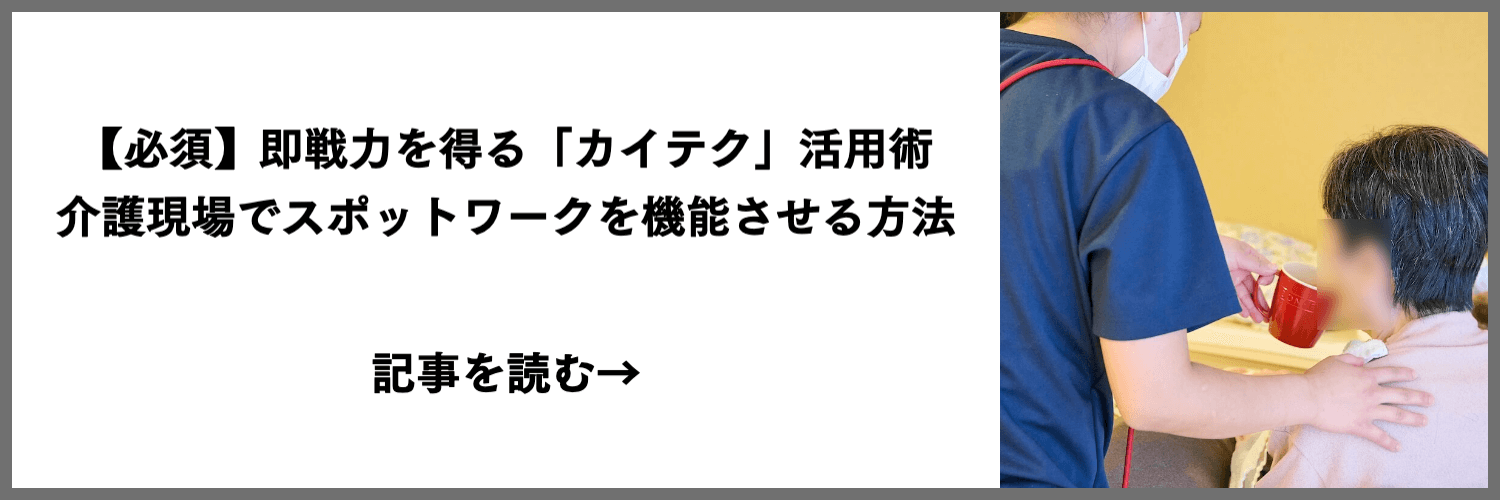【天野尊明】劇的な参院選で変わることと変わらないこと 介護業界から与野党を巻き込む「それぞれの発信」を


7月20日に投開票された参院選は、与党が大きく議席を減らし、昨年の衆院選に続き過半数を割り込む劇的な結果となりました。【天野尊明】
◆ 明暗が分かれた医療と介護
以前のコラムで筆者は、常識的には選挙前のタイミングで石破茂首相を交代させるのではないかと書きましたが、そうした看板の架け替えさえなく、与党は2万円の給付金だけを片手に国民の不満が渦巻く選挙戦に突入しました。野党がこぞって争点を提示する中で、与党はテンプレートの演説に終始する様子も見られ、選対の機能不全が目立った戦いだったように思います。
その余波は介護分野にも大いに影響を与えました。
選挙区では、前厚生労働大臣の武見敬三氏や、元職で全国老人福祉施設協議会の精神的支柱とも言える園田修光氏がまさかの落選。全国比例でも、全国介護事業者連盟の斉藤正行理事長、全国社会福祉法人経営者協議会が推していた和田政宗氏らが、6万票前後という厳しい結果で涙をのみました。
一方で、日本医師会(釜萢敏氏)、日本看護協会(石田昌宏氏)、日本薬剤師会(本田顕子氏)などは底堅い組織力を見せ、比例12議席という狭き門を突破しています。
異例の選挙戦だっただけに、こうした状況を簡単に分析することはできませんが、確実に言えることは、介護関係団体の集票力の減退です。前述した候補者の会合や街頭演説には多くの聴衆が動員されていましたが、これが必ずしも得票につながっていない。SNS上で、「介護は経営者と現場の分断がある」という指摘がされていた通り、「事業者(経営者)団体」によるグリップが非常に効きづらくなってきていることが窺えました。
一方で、当選した釜萢・石田・本田の3候補は、あくまで医師や看護師、薬剤師といった個々人による組織を背景にしています。その点、かねてから問題意識の共有がしやすいと指摘されてきたところであり、与党への逆風が吹きすさぶ中でも、それが一定の機能を果たしたと言えるのかもしれません。
こうした事実は多かれ少なかれ、政治の場において「評価」されてしまうことが避けられません。当選が叶わなかった候補者の関係団体においては、当面の間、影響力の回復が課題になるでしょう。
◆ 押さえておきたい前提
さて、これらの結果を受けて、今後の介護業界への影響についても少し触れたいと思います。まず、前提として考えておかなければならないことは以下の3つです。
まずは、与党は少数であってもやはり与党であること。
例えば厚生労働大臣は、余程のことがない限り、引き続き自民党議員が担うことになります。そのため、影響力の弱くなった業界団体が、やはり力を落としている与党に相変わらず要望などを行う状況は変わらないでしょう。ただ、「誰に話を通せば物事が進むのか」が一段と見えにくくなりますから、従来通りの単純なプロセスでは上手くいかなくなることも確実です。
次に、野党が一丸となって政権交代を図る事態は起こりにくいこと。
今回の選挙で衆参ともに過半数となった野党ですが、その主義主張は右から左まで相当なウイングの幅で分布しています。それらが結束することは我々が考える以上に難しく、実際にはこれまで同様、(連立が組み直されるのでなければ)イシューごとに各党が自公に着いたり離れたりしながら、自身の政策を実現していく展開となる可能性が高いものと考えられます。
最後は、財務省が消費税率を維持するために自公と一層結びつくであろうこと。もちろん過半数である野党にも気を配りつつではありますが、やはり自公中心の政権運営を望むであろうと想像できます。
◆ 介護問題の議論の喚起を
これらのことを踏まえて想定できるのは、「財務省が一定のルールを維持しつつ、様々なイシューが飛び交う政権運営になる」という姿です。ひと言でいえば、これまでの路線に、野党の利害関係が差し挟まれていく。そのこと自体の是非はともかく、介護業界としては、やはりここに狙いを定めていくべきだと考えます。
例えば処遇改善についてであれば、政党ごとにスキームの違いはあれど、概ね与野党ともに方向性は一致しています。しかし、与党だけではそもそも少数であることに加え、財源論などに重きを置くことから、それほど踏み込みが大きくなりません。そこへの対策としては、世論の高まりを背景に野党各党も巻き込んでいくというアクションが、これまで以上に効果的になるでしょう。
かねてから筆者のコラムでは、「それぞれがそれぞれのできるアクションを」と繰り返しお伝えしてきました。立場によって良し悪しは違うと思いますが、今回の参院選は、「それぞれのアクション」が大きな影響をもたらしたものだと感じています。
ひとつの業界で、誰もがひとつの価値観に縛られる必要はありません。ぜひ、皆さまそれぞれが感じるところをなお闊達に、この介護の業界から発信し、世論を喚起していただきたいと願ってやみません。