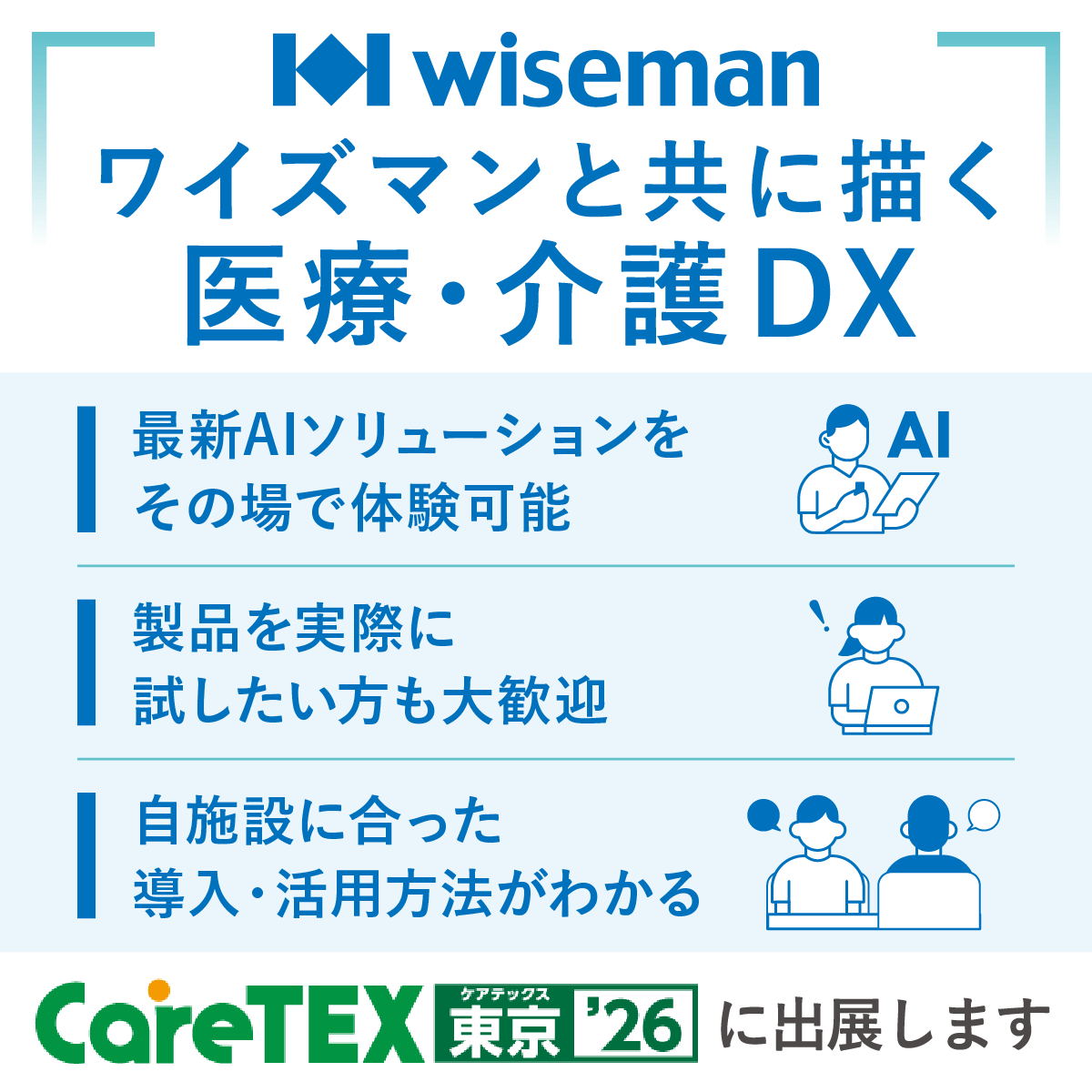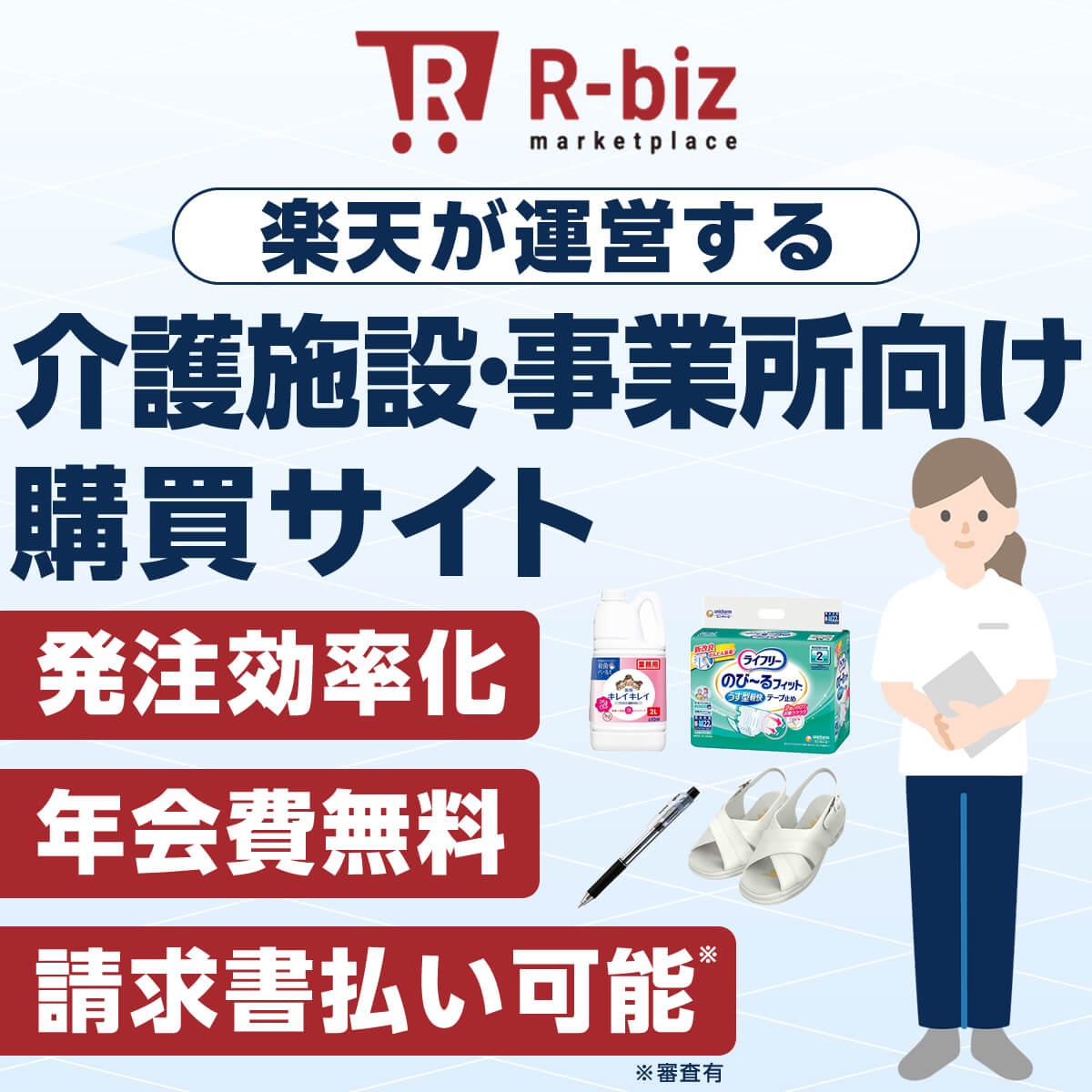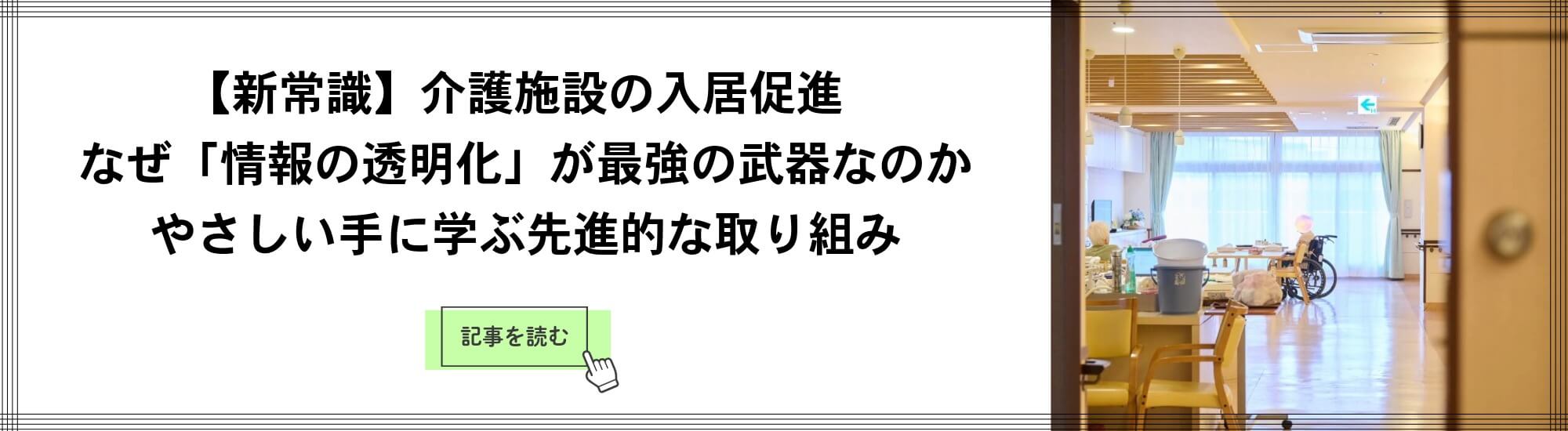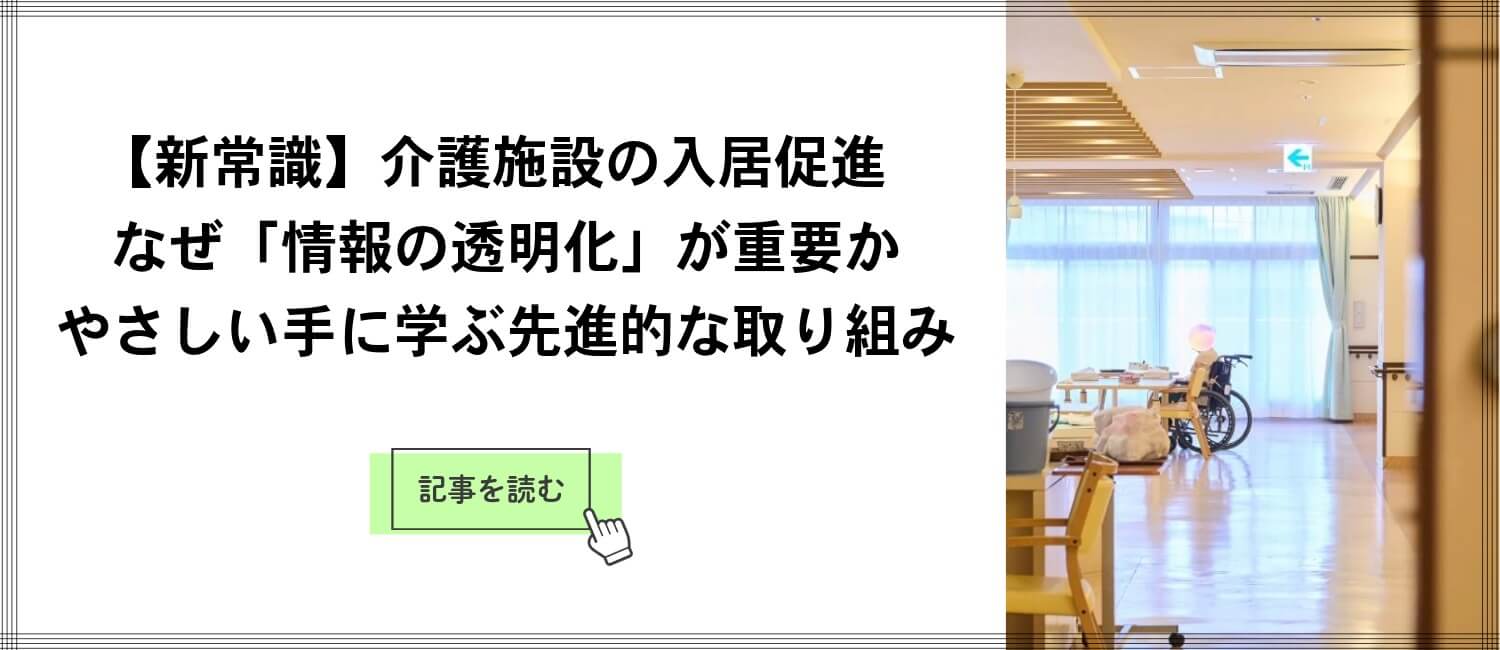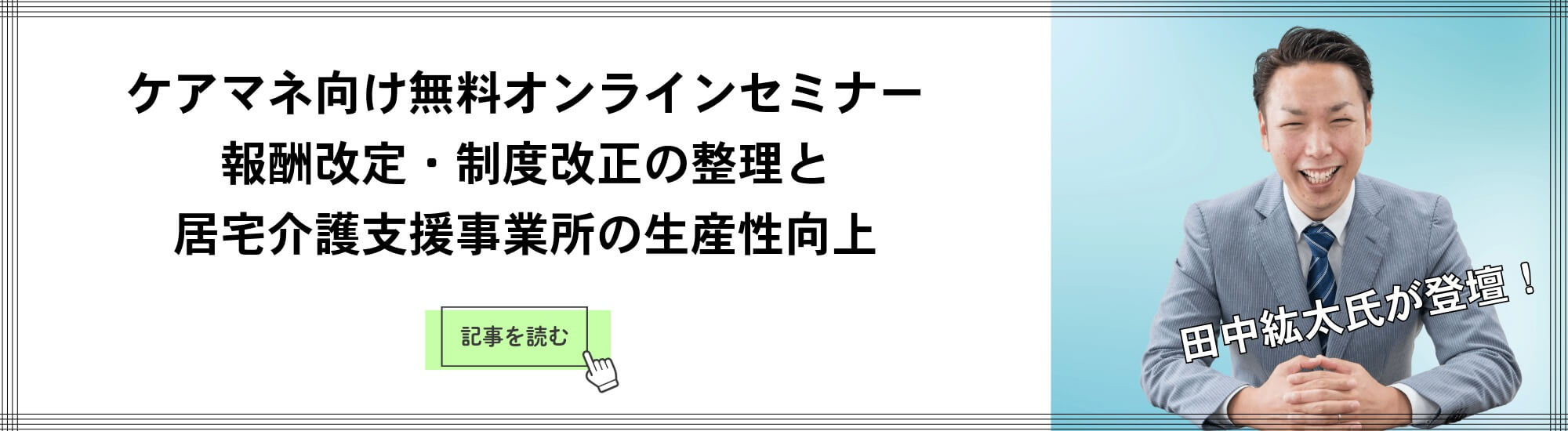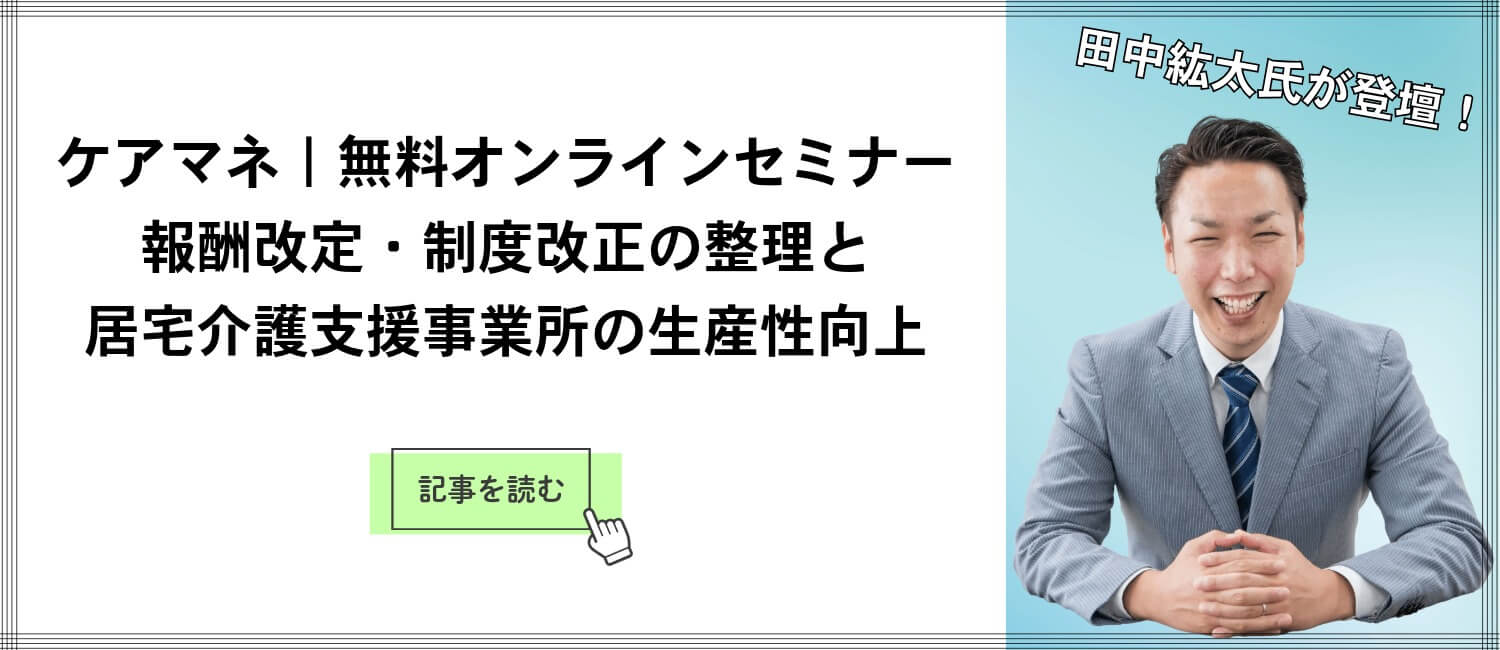【結城康博】中途半端な有料老人ホームの「囲い込み」対策案 介護報酬の減算の強化や総量規制の検討を


今月3日、有料老人ホームのあり方を話し合う厚生労働省の検討会で、これまでの議論を整理した報告書の素案が提示された。【結城康博】
この中には、一部の住宅型有料老人ホームによるいわゆる「囲い込み」の対策も盛り込まれた。しかし、その内容は中途半端。これでは抜本的な問題解決には至らないだろう。
◆ 同一建物減算を最大30%にすべき
今回の素案で不十分だった点として、介護サービス事業所に対する介護報酬の大幅な減算が明記されていないことがある。この検討会が介護報酬を扱っていないことは理解しているが、次期改定に向けた布石を打っておいてほしかった。
例えば、現行の訪問介護の「同一建物減算」は、状況に応じて10%、12%、15%となっている。しかし、もう少し減算幅を大きくすべきではないだろうか。20%から30%を念頭に検討すべきと考える。
あわせて、新たな例外規定も設けるべきではないか。集合住宅ではなく、地域の一般的な住宅で暮らす利用者に一定割合以上のサービスを提供している場合は、減算をまったく適用しないことが有効だろう。
いわば、集合住宅に併設・隣接されている事業所に地域の高齢者を支える役割をしっかり担ってもらうことで、実質的に「囲い込み」を是正させていくのである。介護報酬による十分な対策を講じなければ、いたちごっこのルールが変わるだけで、問題解決の十分な実効性・即効性は期待できないのではないだろうか。
◆「総量規制」の対象に
また、今回の素案では、住宅型有料老人ホームが居宅介護支援事業所、介護サービス事業所と提携する場合に、その提携状況を前もって行政に報告・公表するよう求める方針が示されている。
確かに、このような報告・公表の義務付けには一定の意味がある。行政が指導・監督をスムーズに行いやすくなり、「囲い込み」の実態が顕在化する効果が期待できる。給付費の「使い切り」などの実態も把握しやすくなるだろう。
また、住宅型有料老人ホームが利用者・家族と契約を交わす際に、系列の居宅介護支援事業所などの利用を強要することを禁止するルールの新設も、一定の評価をすべき施策だと言える。
ただ、それでも不十分と言わざるを得ない。やはり抜本的な「囲い込み」の対策は、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などを総量規制の対象に位置付け、行政がサービス量を調整できる仕組みを作ることではないか。条件を満たして申請すれば開設できる仕組みを改め、思い切った規制強化に乗り出すべきである。
今回の素案には、中重度の要介護者らを受け入れる住宅型有料老人ホームを対象とした登録制の導入が盛り込まれたが、さらに踏み込んだ対応が求められると考える。
◆ 給付費の適正化に向けて
もちろん、事業を健全に展開している有料老人ホームが大半であることは言うまでもない。しかし、収益の拡大に偏った事業者が一部に存在することも事実で、競争原理(疑似的市場)を導入している介護保険制度自体に問題がある。そのことは、厚労省も十分に承知しておくべきである。
また、生活保護の受給者らを対象とした「囲い込み」の“貧困ビジネスモデル”も、いまだに一部の事業者で見られる。このような実態を放置させている現状も、総量規制がなされていないことに起因する面が大きいのではないか。
介護保険制度は、税金や保険料といった公的な財源で賄われている。総量規制を強め、いわば「計画経済」の考え方をもう少し浸透させるべきだ。「囲い込み」のように無駄な給付費を生む仕組みを放置していてはいけない。地域で奮闘する介護事業所・施設は速やかな支援を求めている。彼らに必要な介護報酬の大幅な引き上げを要求することも、このままでは一段と難しくなってしまうのではないだろうか。