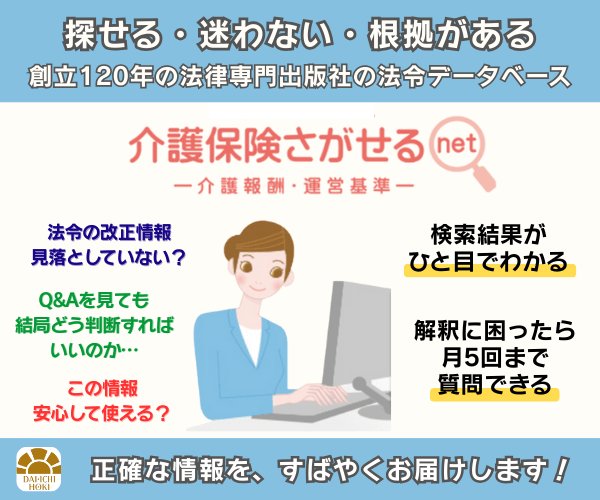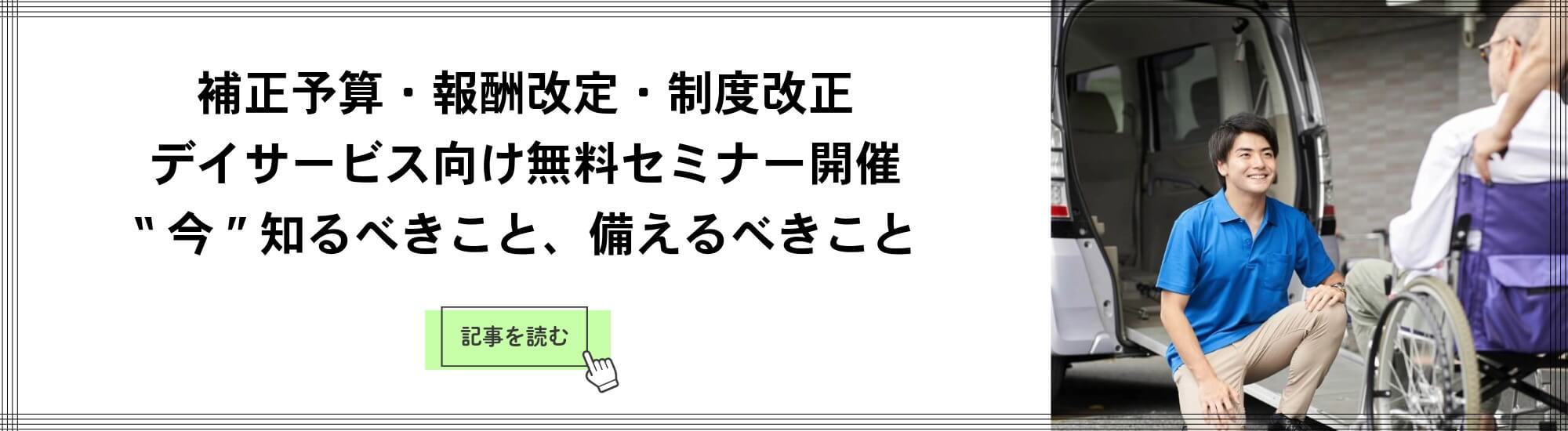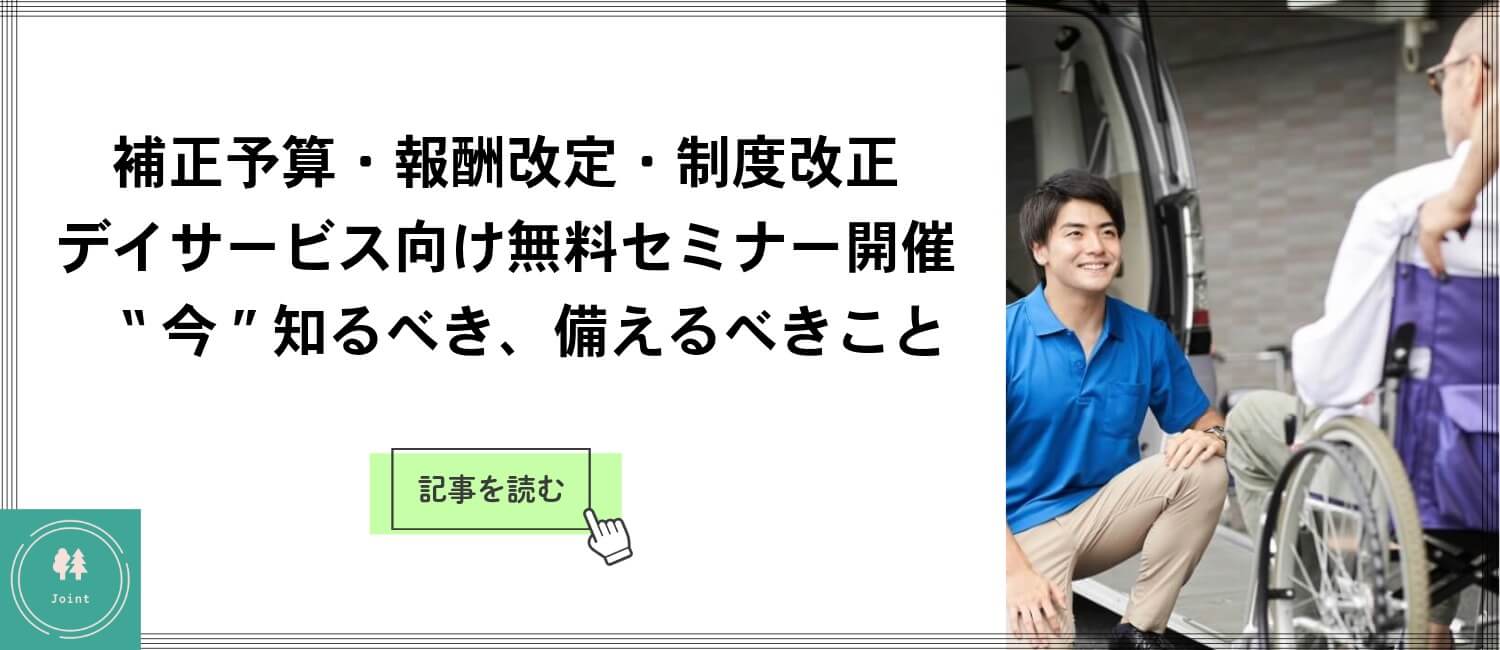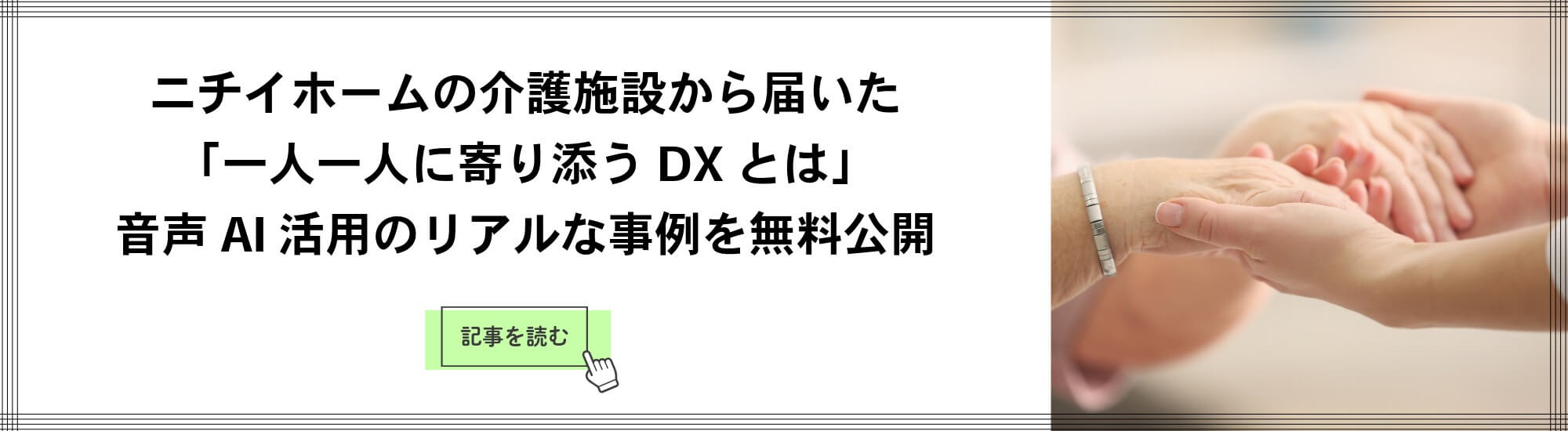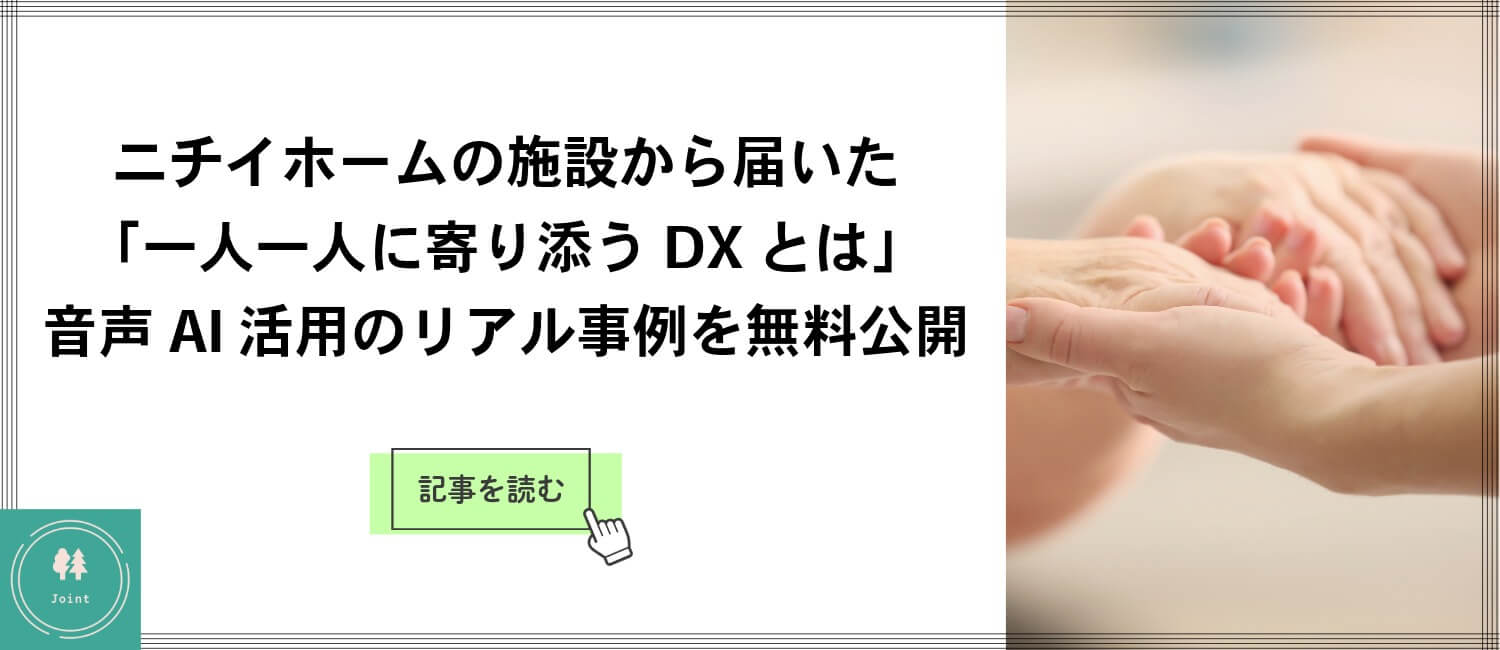介護の生産性向上、小規模事業所を主役に 生成AI × 行政簡素化が拓く地域の未来=小濱道博
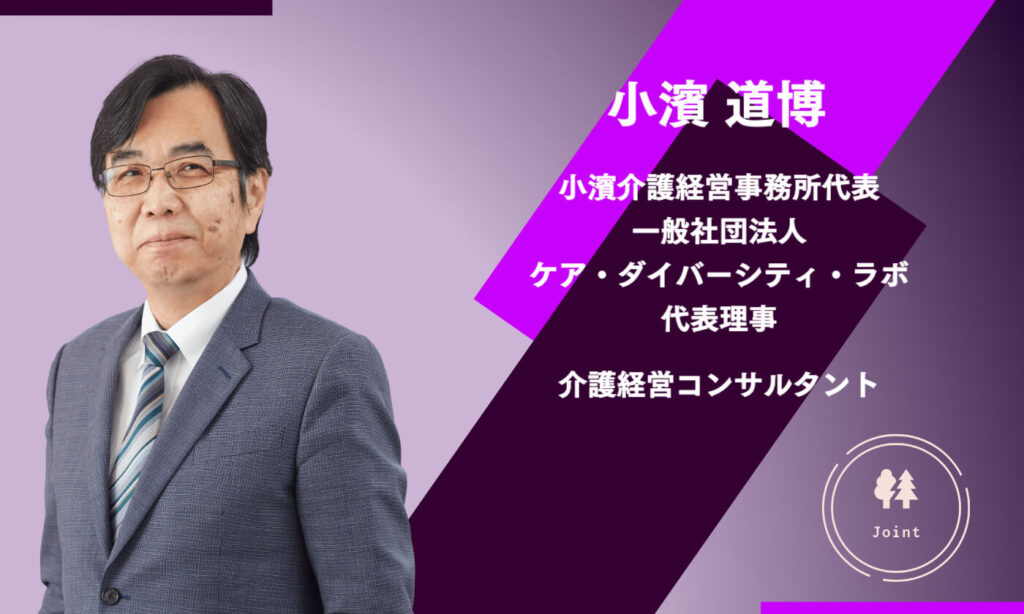
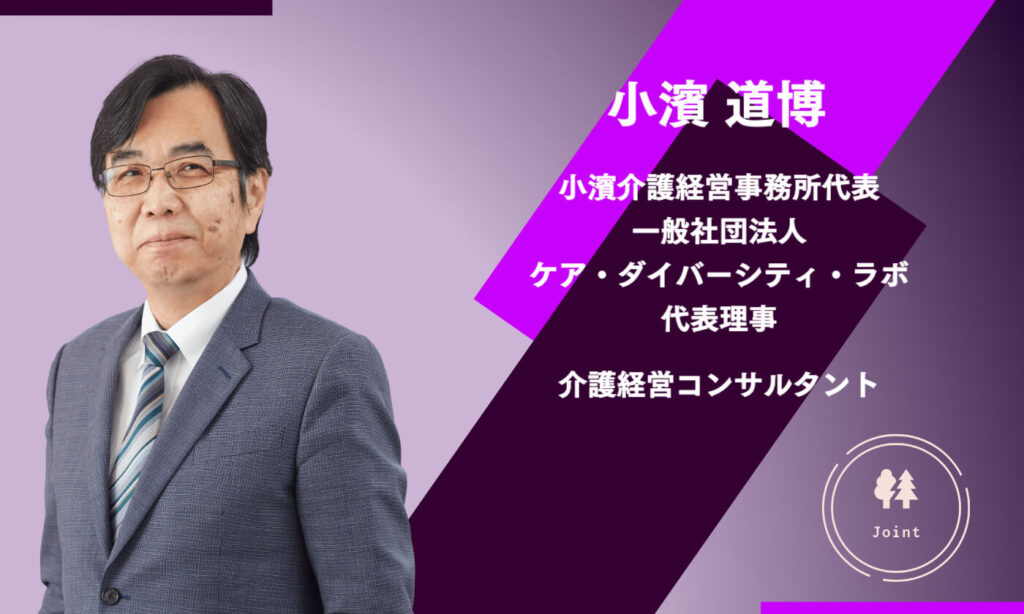
1,国策が抱える構造的な問題点
現在、国が推進している介護分野の生産性向上策は、その取り組みが介護施設や中規模以上の法人に偏りがちであるという構造的な問題を抱えている。日本の介護業界の半数以上を占める小規模事業所は、経営者自身が現場に出ているため、業務改善のための時間的・精神的な余裕が乏しいのが実情である。【小濱道博】
現行の生産性向上の推進プロセスは、現場サイドでは手探りの状態である。すでに生産性向上委員会を設置している施設でも、「毎月の評価だけやって終わっている」「成果が出ない」という相談が多い。
その原因は、いまのシステム上で求められる、最初の原因分析や課題分析を十分に実施していないことにある。スタート地点が定まっていないため、ただ活動しているだけで終わってしまうという形骸化が全国で生じている。そもそも、今の推進プロセスは、現場の業務改善とともに、行政側のデータ収集の目的が強く、その点が現場に過度な負担を求めている。
また、現状の生産性向上は、ICTや介護ロボット、センサーといった機械的なツールに固執する傾向が強い。ICTは機械であり、ロボットやセンサーに代表されるが、これらは在宅サービスなど小規模事業所の大部分にはほとんど関係のない話である。このような旧来の手法にこだわるスパンでは、真の生産性向上は厳しいと言わざるを得ない。
2,生成AIの威力
小規模事業所の職員が日常的に多大な時間を費やしているのは、行政側が求める計画書、記録、議事録、集計、シフト表といったアナログな事務作業である。例えば、担当者会議の議事録作成には1件あたり20分から30分を要し、月平均10回から15回の会議を開催する場合、この記録作成だけで月に約300分もの時間を奪われている。
この煩雑な記録業務の効率化に、高額なロボットやセンサーは不要である。2万円程度のICレコーダーと付属アプリを活用すれば、音声を録音し、同時に文字起こしを行い、数分で議事録のドラフトを作成することが可能だ。
これにより、1件30分かかっていた作業が5分から6分で終わるようになり、ケアマネジャーは月に200分以上の時間を捻出できる。この時間は、担当件数の増加や利用者と向き合う質の高い時間へと転換できる。
3,ベンダーの協力も不可避
また、AIが作成した記録を外部データとして取り込めない記録ソフトが多いため、職員がコピペや手打ちで再度入力する手間が生じている。この点、利用者情報の機密性を守るセキュリティ強化が大きな目的であることは理解できる。
しかし、これは高度な技術的対応によって、外部データ連携とセキュリティ確保を両立させることも可能であろう。今こそ介護記録ソフトのベンダーは、AIが作成したデータと記録ソフトがクロスオーバーに活用できるよう、AI業界との提携を積極的に進め、オープンなシステムへと大きく舵を切るべきだ。これができると、LIFEの活用もAIによって飛躍的に改善される。
4,外国人材の活用とAI推進の必然性
AIの推進は、外国人材の受け入れ拡大においても重要である。小規模事業所における業務マニュアル、申し送り、記録のほとんどが日本語であることは、外国人職員にとって大きな障壁となり、ミスや事故につながる危険性がある。
AIを活用すれば、これらの日本語情報をスピーディに翻訳し、インカムなどを用いたリアルタイムの通訳や、マニュアル対応のためのチャットボットシステムを構築できる。若い外国人職員はデジタルネイティブ世代であることが多く、彼らがAIの活用を率先して行うことで、事業所全体のテクノロジー導入を牽引していく可能性も期待される。
5,行政の簡素化とAI推進で圧倒的に進展する
介護崩壊を防ぎ、職員が本来のケアに集中できる環境を整備するためには、特に小規模事業所に焦点を当てたパラダイムシフトが求められる。そのためには、現在の生産性向上推進策の限界を超える、2つの施策の断行が欠かせない。
すなわち、行政が求めるプロセスや書類を簡素化し、加算の算定要件も簡略にして現場の負担を減らすこと、そしてそこに生成AIの活用を強力に進めることである。
真の業務効率化に必要なのは、報酬算定プロセスと必要書類の簡素化、AIによる自動化・知能化であり、成果を生まない原因分析や課題分析、因果関係図の作成に時間を費やすことではない。
行政側の簡素化の断行と、現場へのAI導入を推進することで、煩雑な事務作業からの解放は一気に実現する。これに伴い、因果関係図や生産性向上委員会の活動、第三者の伴走支援といった既存の枠組みも必要なくなるだろう。