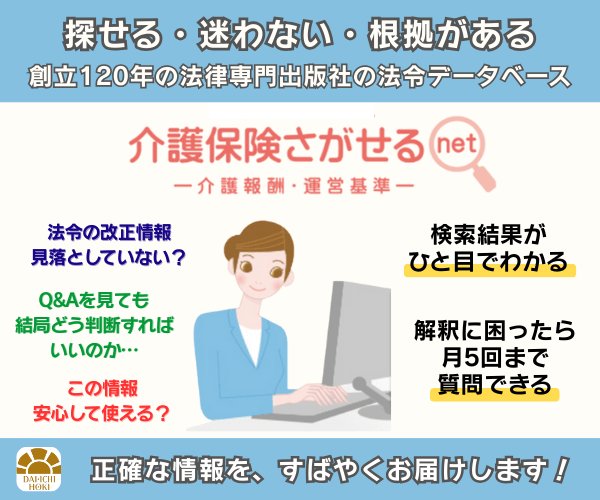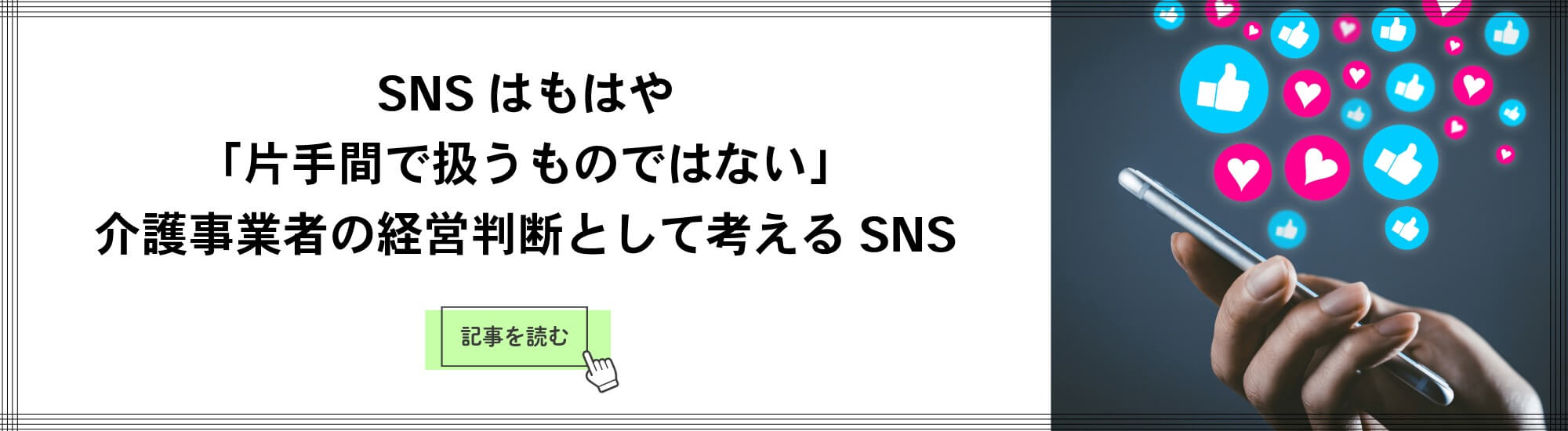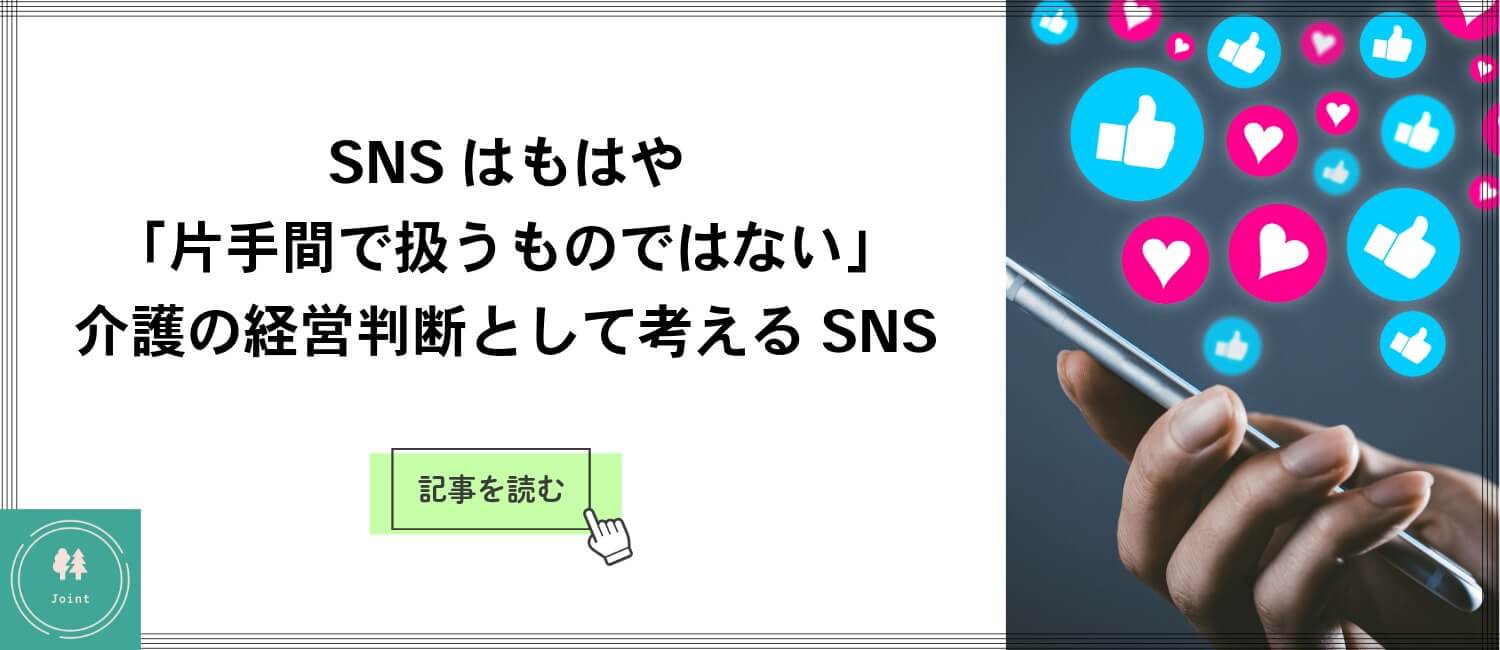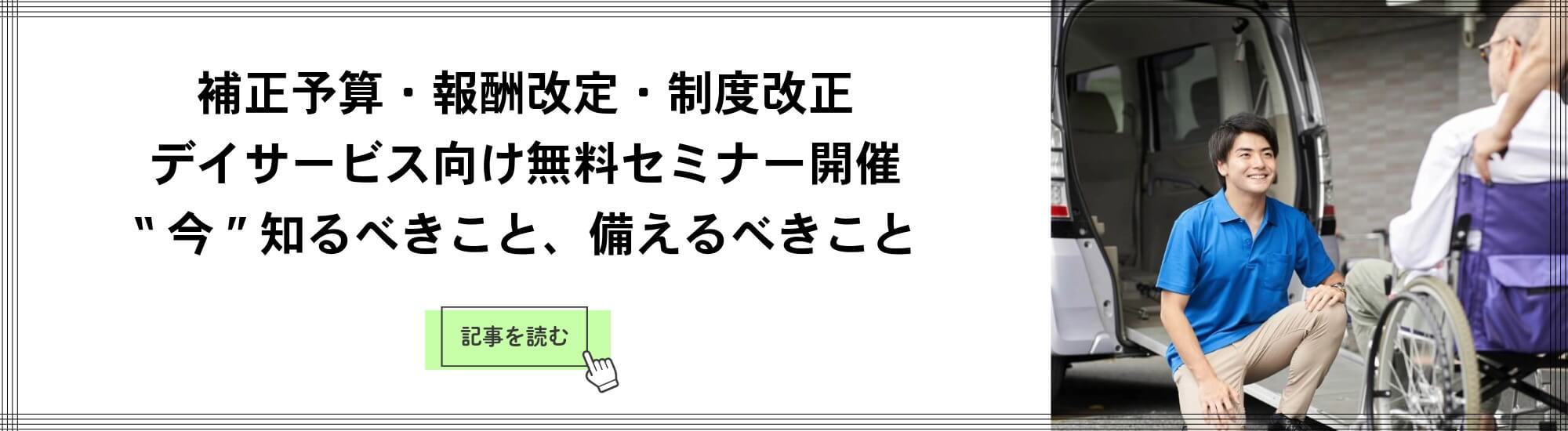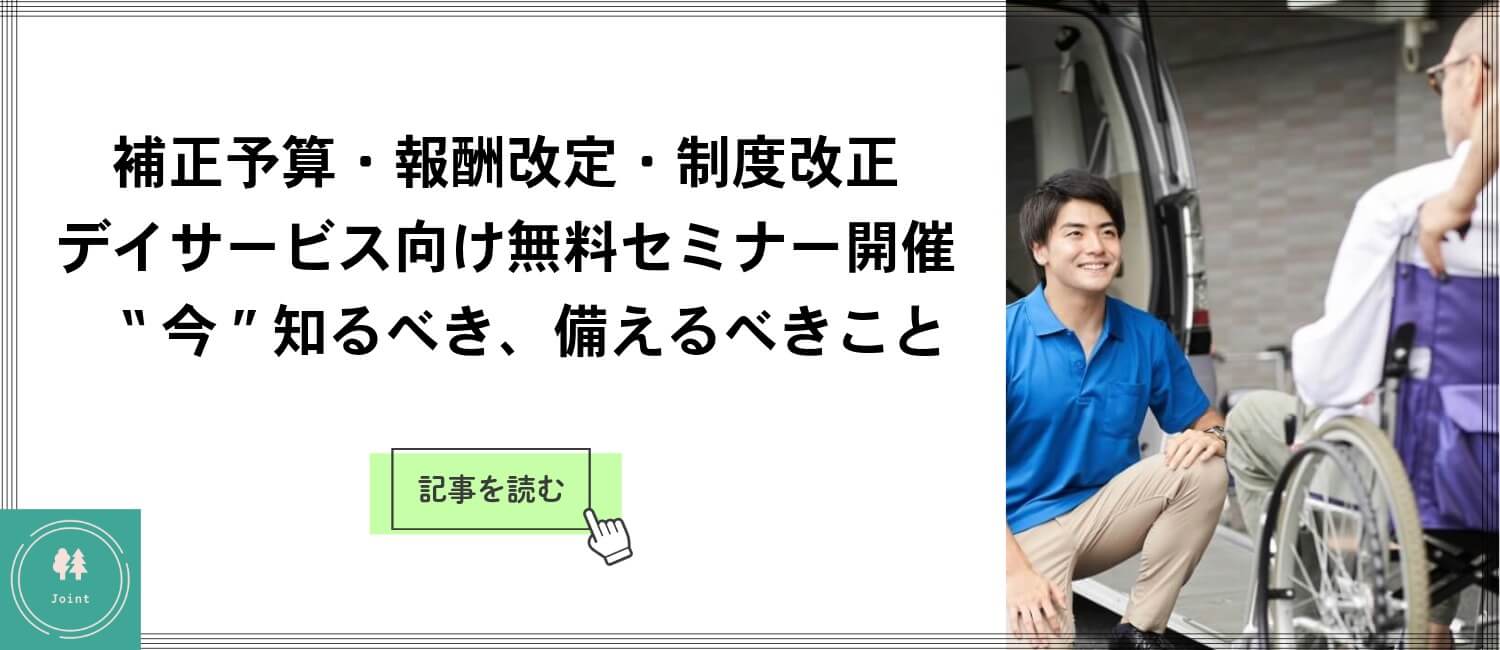10月27日の審議会で、厚生労働省はケアマネジャーの資格の更新制を廃止する方針を打ち出した。一瞬、多くの介護関係者が喜んだに違いない。現場の切実な声が届き、ついに国を動かすことができたんだと…。【結城康博】
しかし、厚労省の改革案をよくよく見てほしい。資格の更新制が廃止される一方で、ケアマネジャーが研修を受ける義務は残るようだ。
これでは意味がない。実質的な更新研修の存続と言うほかない。細部が決まるのはこれからのようだが、少なくとも現状では全く喜べないと理解すべきではないか。
結論を先に書いておく。研修は必要だがその義務付けは不要。
◆ これではますます落胆
厚労省の改革案が公表されてから、私は複数のケアマネジャーにインタビューを行った。「更新制の廃止といっても、研修の義務付けが残されるのはがっかりだ」。そんな声が多かった。
私も正直、厚労省は「更新制を廃止する」と謳ったものの、実質的な仕組みは大きく変わっていないと認識している。
確かに、これからケアマネジャーに義務付けられる新たな研修は、5年間など長い期間をかけて、それぞれ自由なタイミングで、負担を分散させながら受講していけるようだ(*)。現行の更新研修と比べて、多少、時間的な調整幅が拡がることは間違いない。しかし、研修の受講が義務付けられていることに変わりはない。
* 現行の更新研修の時間数でみると、1年あたり6~7時間程度
◆ 研修の義務付けこそが問題
誰もが認識していることだと思うが、そもそも問題は資格の更新制ではなく、研修の義務付けにあったのではないか。
自動車の運転免許のようにごく短時間の更新の仕組みであれば、多少の負担があっても問題とならないだろう。しかし、ケアマネジャーの資格は違う。30時間を超えるような研修の義務付けが、もともと多忙な専門職に重い負担を強いてきたのだ。
今後も研修の義務付けが存続する限り、少なからぬ割合を占める60歳代を過ぎたケアマネジャーらを中心として、研修の受講が離職の理由、定着の障害となり続けるだろう。
また、子育てなど何らかの事情で介護の現場から離れた後、再びケアマネジャーの仕事に戻ろうと考えている人にとって、研修の受講は復帰のハードルとなるだろう。「潜在ケアマネ」の活用を難しくする施策は、人材確保の観点から大きな痛手となる。
医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士などの専門職には、いずれも研修の義務が課せられていない。唯一、ケアマネジャーのみが研修を義務付けられている資格である。
全国的にケアマネジャー不足は顕著で、その対策は喫緊の課題である。だからこそ、まずは既に従事しているケアマネジャーの離職率を軽減して、高齢になっても働き続けられる環境の整備が急がれるはずだ。その具体策が更新制の廃止、研修の義務付けの解消ではなかったか。
しかし、現時点では更新制を廃止するものの、研修の義務付けを存続させるようなので、状況はこれまでと大きく変わらない。現場で奮闘するケアマネジャーの気持ちを汲み取らないと、モチベーションをますます低下させてしまうのではないかと心配でならない。
地域の中の大変な仕事、シャドウ・ワークをさんざん押し付けておいて、「唯一あなたたちだけは質が至らないから研修は義務ね」というお上のスタンスが、多くの人材の離反を招いてきたのではないか 。
◆ とるべき施策
ここで改めて強調しておくが、私は「研修はまったく不要」と言っているのではない。専門職にとって研修の受講、学びの継続が必要不可欠であることは言うまでもない。
しかし、上から目線で義務付けられた研修をこなすとなると成果は限定的にとどまる。厚労省は直ちに、ケアマネジャーが自ら主体的に研修を受講していく仕組みを考えるべきではないか。研修の受講を義務付ける「北風」の施策ではなく、後押しする「太陽」の施策を考えるべきだ。
例えば、研修を受けたケアマネジャーが多く在籍している居宅介護支援事業所が、一定の加算を算定できる介護報酬の体系とするのはどうか。研修を受けられる環境を事業者に整えてもらい、その加算分は「特別手当」としてケアマネジャーに還元する仕組みにすべきだ。
たとえ研修の受講が法令で義務付けられても、ぜひ前向きな姿勢で学ぼうというケアマネジャーが増えなければ、資質の向上という目的は達成されない。このままでは、大変残念な骨抜きの更新制の廃止に落胆せざるを得ない。
今はまだ最終的な方針は決まっていないと聞く。審議会が報告書をまとめる年末に向けて、厚労省の英断に期待したい。