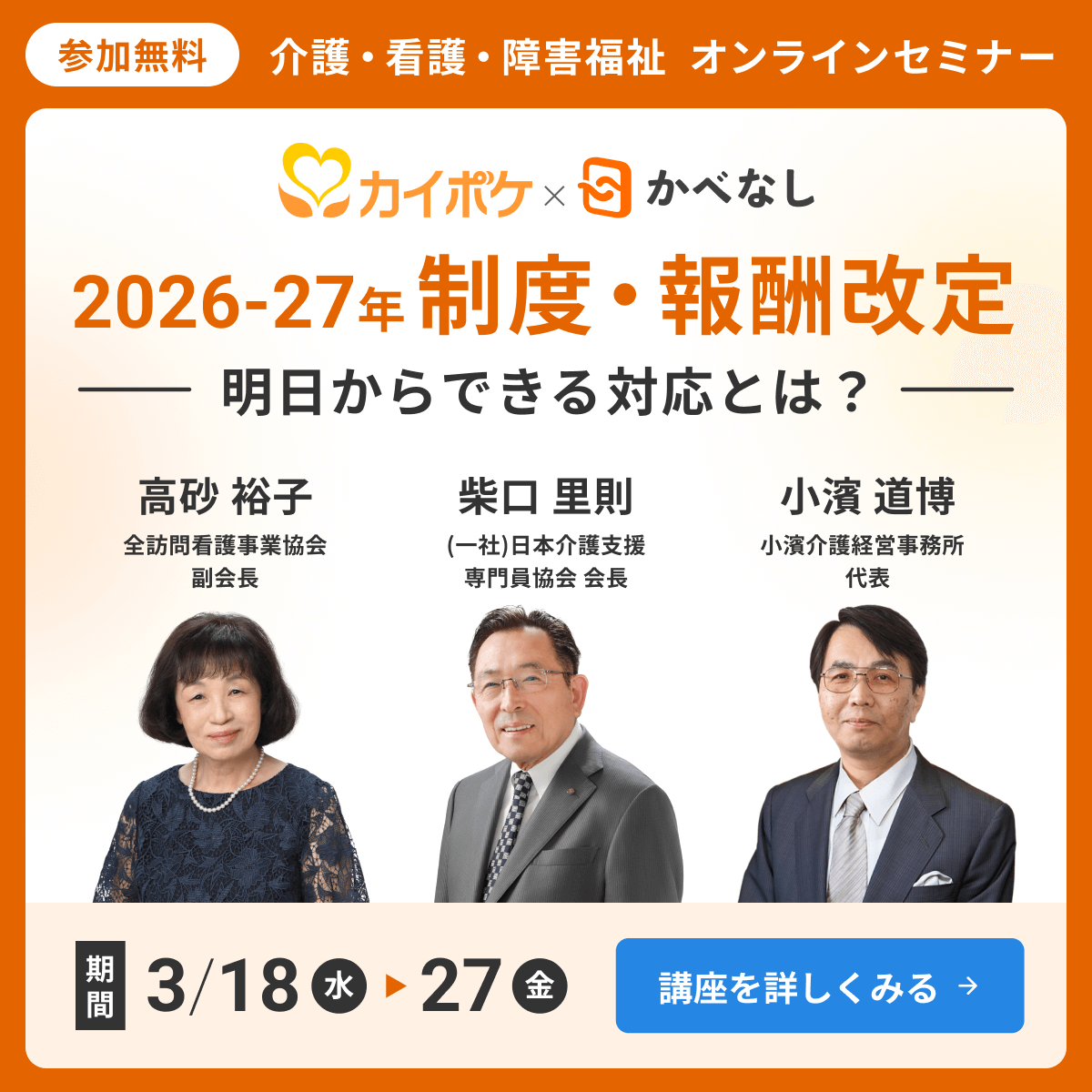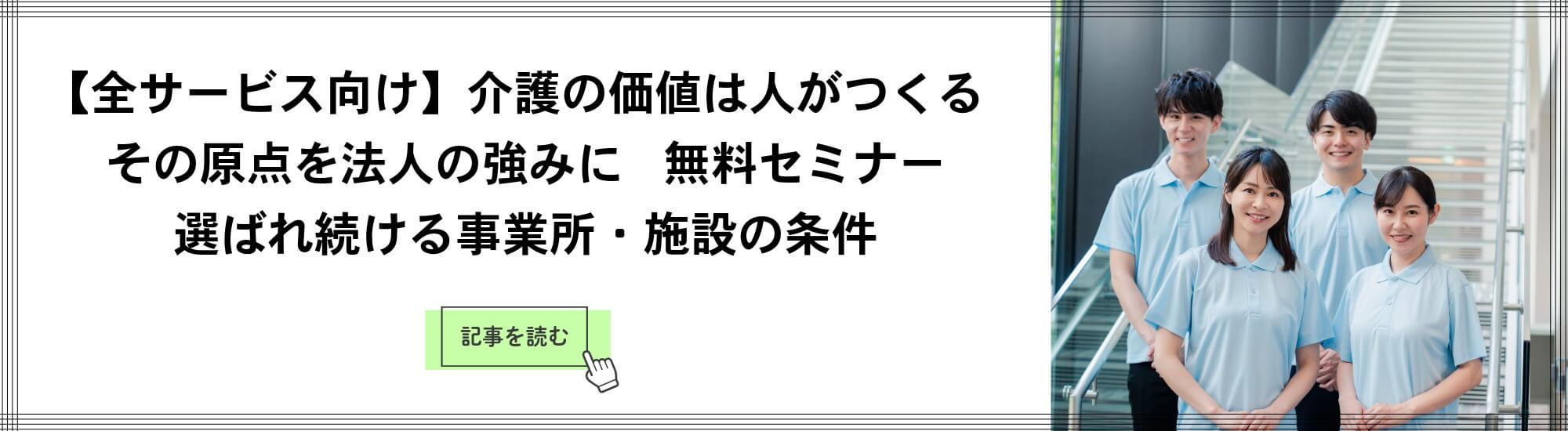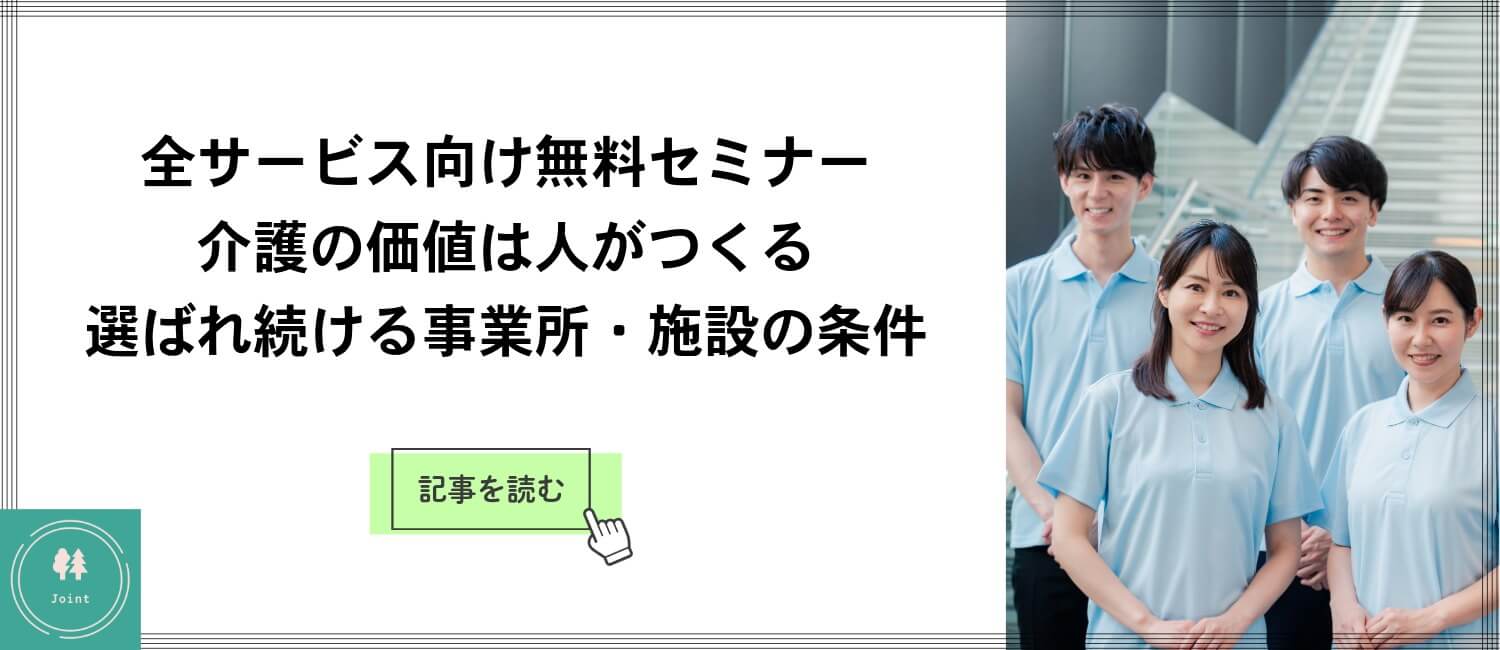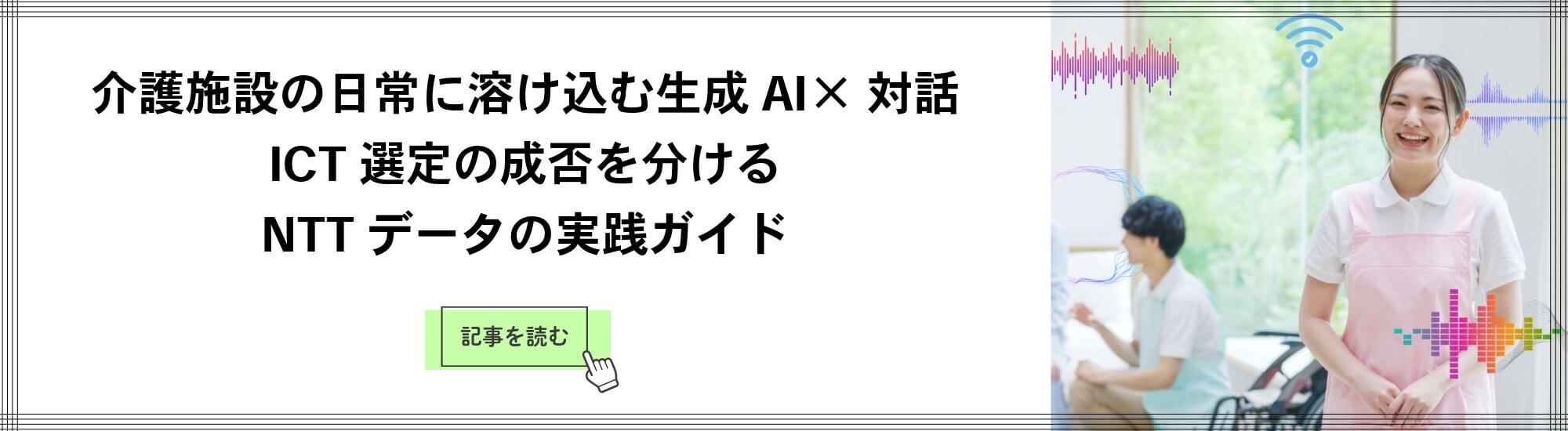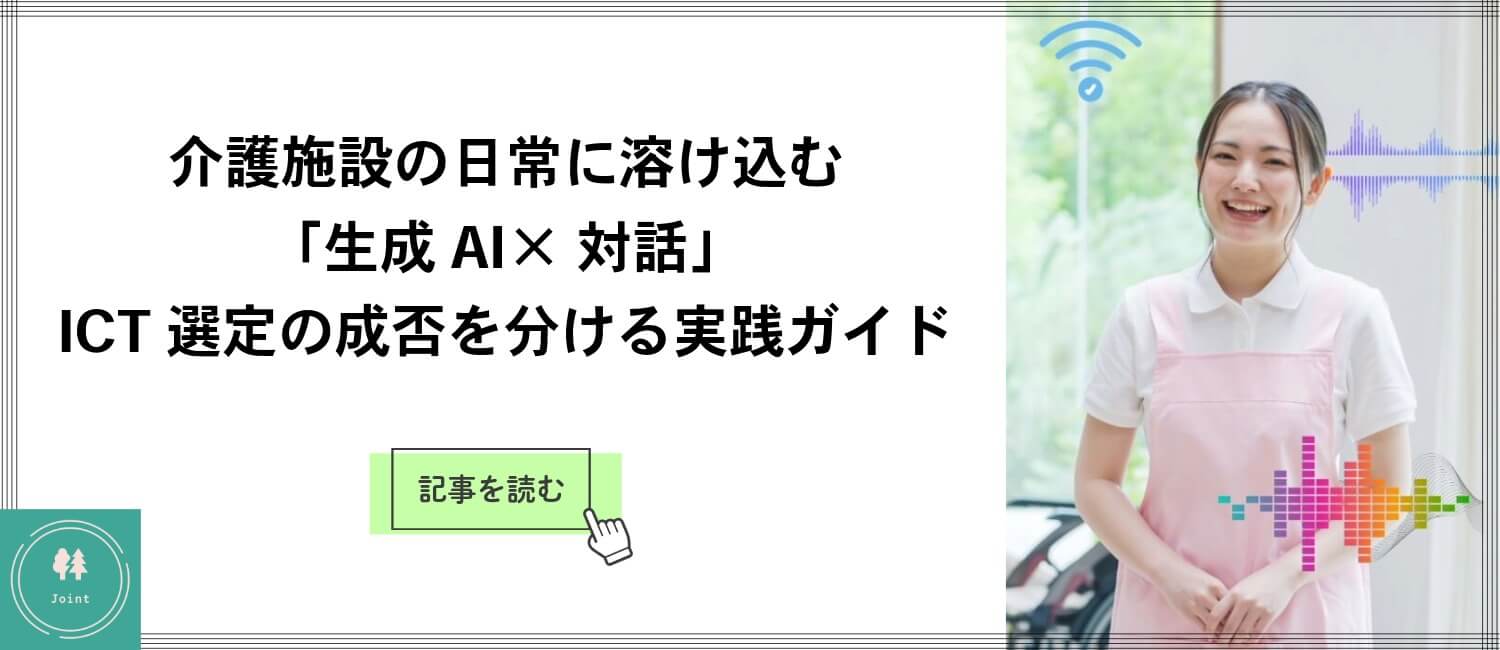【壷内令子】居宅介護支援の10割給付を守るべき理由 利用者負担の導入は「パンドラの箱」


ケアマネジャーの処遇改善について、ようやく本格的な議論が進み始めています。【壷内令子】
長年、介護報酬の「処遇改善加算」など国の施策の対象から外され、責任と業務量ばかりが増え続けてきた私たち。そのような状況下で、賃上げの話が具体的になってきたこと自体は、1つの前進だと感じています。処遇改善は当然必要なことであり、そこに異論の余地はありません。
◆ 財源議論への「大きな違和感」
一方で、その財源として「居宅介護支援への利用者負担の導入」があげられていることには、大きな違和感を覚えます。
ケアマネジメントは、利用者個人のためだけのものではありません。地域の暮らしや社会保障制度そのものを支える、非常に重要で幅広い役割を担っています。
そこに利用者負担を持ち込むことは、必要な支援から遠ざかってしまう人々をさらに生み出しかねません。結果として、制度全体の安定性にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
仮に、最初はごく少額の定額負担からのスタートだとしても、その後への懸念は拭えません。「これまでなかった負担を求める」という判断を一度下してしまえば、その後は「1から2へ」「2から3へ」と、段階的に負担が拡大していく未来は容易に想像できます。
それはまさに、開けてはいけない「パンドラの箱」を開けてしまうことに等しいのではないでしょうか。
◆ 賃上げだけでは解決しない
そもそも、賃金が少し上がる程度では、ケアマネジャーという仕事の魅力が劇的に回復するとは思えません。
人材不足の背景には、賃金面の問題だけでなく、膨大な業務量や精神的な重圧があります。さらには、「なんでも屋」のような存在として扱われてきた現実も無視できません。
日々の業務は多岐にわたります。書類作成、サービス調整、モニタリング、家族対応、多職種連携、緊急時対応、そして行政対応……。その中には、本来の役割とは言い難い業務までもが含まれているのです。
こうした「シャドーワーク」が山積みのままではどうでしょうか。たとえ処遇がわずかに改善されたとしても、「この仕事を続けたい」「新たに目指したい」と思える魅力ある職業になるのは難しいはずです。
居宅介護支援への利用者負担の導入については、こうした現場の負担を一段と増やすという観点からも、強い危機感を覚えています。
利用者負担が発生すれば、集金業務や未納対応といった全く質の異なる負担が、ケアマネジャーに新たにのしかかります。場合によっては、利用者・家族との金銭トラブルやカスタマーハラスメントにつながるリスクも高まるでしょう。本来、信頼関係の上に成り立っているはずの支援の場に、「お金をめぐる緊張関係」が持ち込まれてしまうのです。
◆ 本質は「環境の整備」にある
そもそもこの問題は、過去に幾度となく議論されてきました。そのたびに「導入すべきでない」という判断が下され、10割給付の仕組みが守られてきた経緯があります。
これは決して問題の先送りではありません。現場や利用者への影響を真剣に考えた結果です。私はそう受け止めています。
だからこそ、処遇改善を進める今このタイミングで、同じ議論を再び持ち出すことには、極めて慎重であるべきです。何度でも申し上げたい。現行の10割給付は、このまま維持すべきです。
ケアマネジャーの処遇改善は、間違いなく必要です。しかし、それは賃金の引き上げだけで完結するものではありません。働き方や業務のあり方と一体となって進めてこそ、本当の意味での改善につながります。
業務内容の整理、役割の明確化、シャドーワークの削減、ICTの活用、そして多職種や行政との適切な連携・役割分担。こうした土台を整えることこそが、ケアマネジャーという仕事の魅力を取り戻す本筋ではないでしょうか。
そして、そのための適切なアプローチは、利用者に新たな負担を求めることではありません。ケアマネジャーが本来の役割を安心して果たせる環境を整えることにこそ、問題の解決の鍵があると考えます。