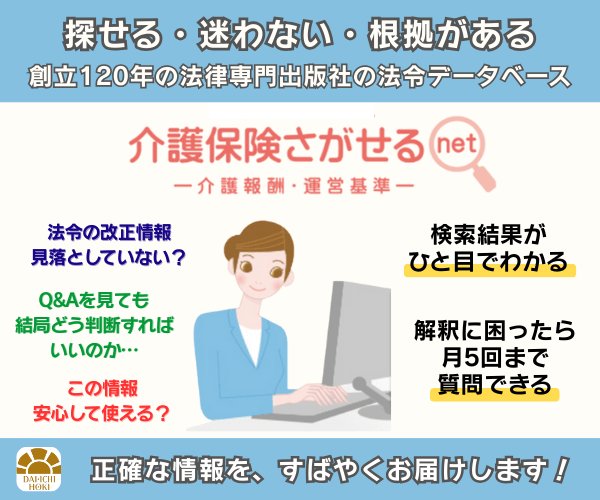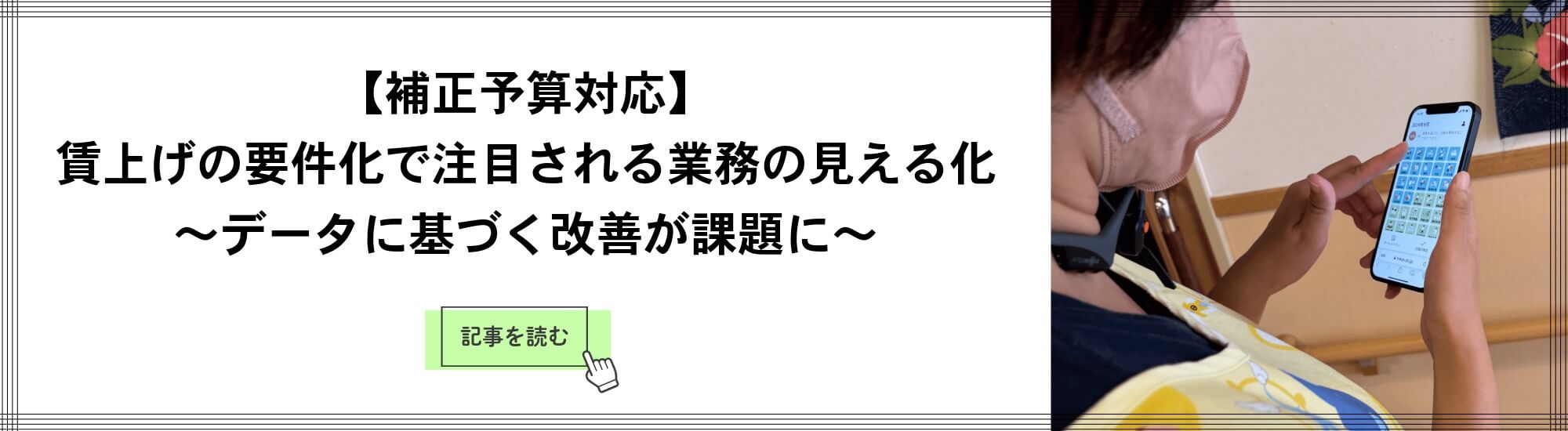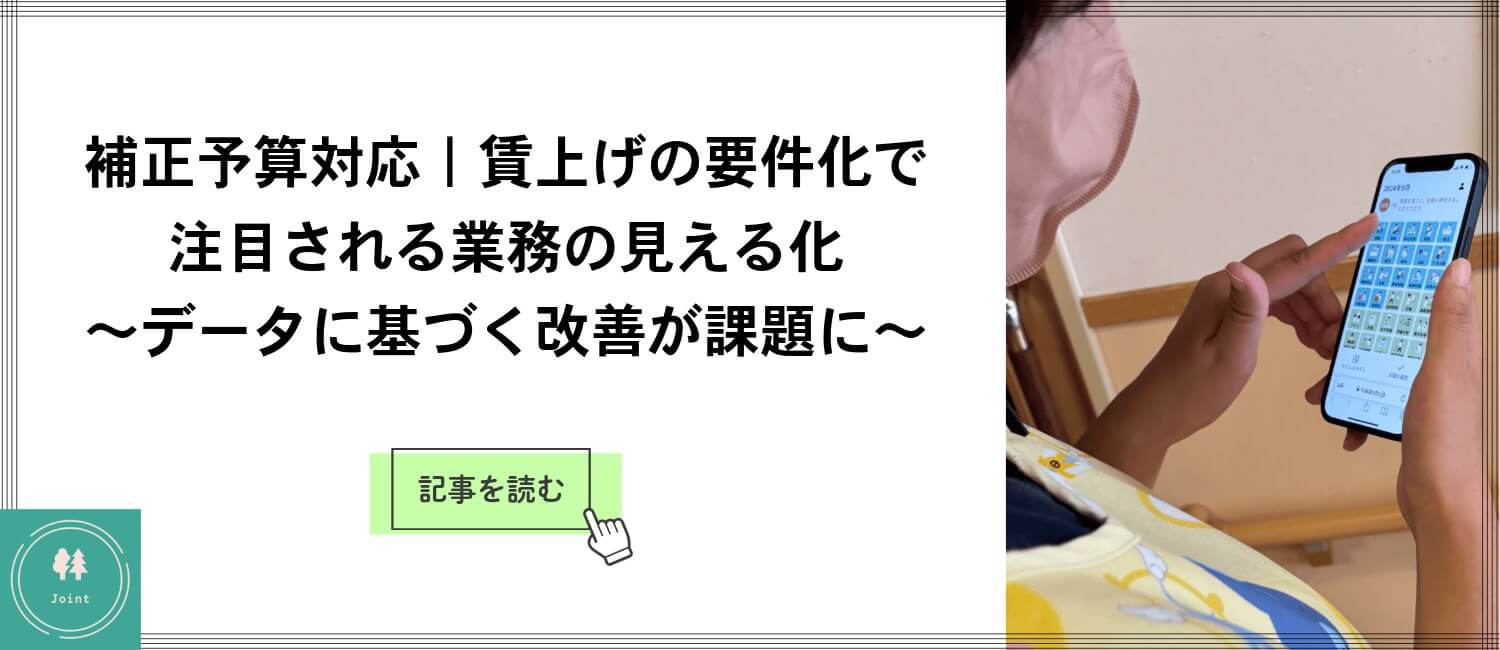【石山麗子】なぜ制度が必要か 専門職として、次世代を担う若者に説明できるか


今後の制度改正を話し合う介護保険部会では、過去のスケジュールに照らし合わせると、おおむね今の時期、3年ごとの事業計画期間2年目の9月から具体的な論点に沿った議論が進められてきました。
9月8日の介護保険部会では、今後、具体的な議論を行ううえで重要な視点が示されました。その時間軸の射程は「2040年」です。15年後、読者の皆さまご自身、大切なご家族の年齢はそれぞれ何歳でしょうか。【石山麗子】
◆ 若者に向けられた異例の白書
日本は人類に経験のない少子・高齢化と、それゆえ生じる人口減少に起因する社会課題に見舞われています。特に、これからを生きていく若者には、その課題は切実です。そうした若者へのメッセージともとれる白書が、このたび報告されました。
“厚生労働白書”です。この文字を見た瞬間に「堅苦しそう」、「興味がない」、「専門家や行政が読むもの」という印象を抱かれたかもしれません。確かに、今まではそうだったかもしれません。元来、白書は中央官庁の年次報告書で、閣議に報告されるものですから致し方ありませんでした。
ところが、今回はその様相が一変しました。白書のタイトルは、まるでちょっと固めの手紙、内容は高校生のテキストのようです。
令和7年版厚生労働白書(令和6年度厚生労働行政年次報告)「次世代の主役となる若者の皆さんへ -変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」
主なメッセージの対象は“若者の皆さん”で、具体的には高校生、大学生、社会人になったばかりの方です。
若者にはこれから長い人生が待っています。健康や労働にかかわる政策は厚生労働省の所管です。もし若者が困難に直面したとき、本当は制度(サポート)が存在しているのに、それを知らなければ孤立したり、その後の人生を左右する状況に陥るかもしれません。
今年の厚生労働白書には「こんな制度がある」、「困ったら助けを求めることができる」という緩やかな認識を持ってもらいたい、というメッセージが込められています。
日本には、年金、医療、介護、労働など幅広いセーフティネットが張られています。つまり制度は“存在”しています。
しかし、ここからが重要です。人口減少社会では、今ある制度がこの先は「存在しない」恐れがあることも否定できません。言葉を選ばずに言うなら、仮に誰かが制度に無関心でいるとするならば、今は制度が存在していて困らずに済んでいるから、という理由も1つにあるかもしれません。
◆ 先を見据える視点と制度の持続可能性
私たちが次の介護保険制度改正を考えるとき、大きく問われることの1つは先の未来を想定できているかです。ですから、2040年(15年後)をリアルに想像してみることが欠かせないのです。
介護保険制度は、「国民の共同連帯の理念」に基づき設けられています。制度の連帯は、財源と、考えや意識の両方に支えられています。
今の若者が社会保障に対してどのような印象を抱くかは極めて重要です。「高齢者ばかり手厚い」という印象を持つことがあるなら、やがて連帯は成立しなくなります。これは介護保険だけではありません。
これまでの厚生労働白書では“つながり”、“支えあい”という言葉が継続して使われてきました。令和7年版で初めて使用された言葉があります。それは“社会の分断”、“世代間(の)対立”です。
中央官庁の年次報告である厚生労働白書が、まるで手紙かと見まがうようなタイトルとなったのは、若者自身がこれからの人生で社会保障を知り、活用し、幸福な人生を送ってほしいというメッセージで、日本が迎えている状況を一緒に考えていこうという呼びかけでもあります。その背景にあるのは、厚生労働省が将来に抱く制度の持続可能性への危機感であると筆者は解釈しました。
最後に、厚生労働白書には“若者以外の皆さん”へのメッセージもあります。今日の日本を形成することに参加してきた大人としてどう読むのか。いわんや、社会保障制度に携わる専門職としてどう読むのか。そのことを考えさせられる、過去に類を見ない白書となっています。